
川合正倫 Masanori Kawai
パートナー
東京

NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター
中国では2021年11月1日より個人情報保護法が施行された。これにより、ネットワーク安全法(2017年施行)、データ安全法(2021年9月1日施行)を加えた中国における情報規制の基幹三法が施行されたことになる。
これらの法令における「越境移転」に関する下位規範であるデータ越境移転安全評価弁法のパブリックコメント版(以下、「本弁法」)が2021年10月29日に公表され、11月28日までコメントを受け付けている。データの越境移転は、日本企業を含む外国企業の関心が高い事項であるため、本稿において同弁法の内容を紹介する。
本弁法は、ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法等に基づいて制定される旨が規定されており(1条)、情報規制の基幹三法に従うデータの越境移転に関する統一的な規定と評価できる。
本弁法に従う安全評価の対象は、データ処理者による、中国域内の運営において収集及び発生した重要なデータ並びに法律に従い安全評価を求められる個人情報の域外提供とされ(2条)、2021年に施行されたデータ安全法及び個人情報保護法の規定内容に概ね沿う内容といえる。
安全評価は、当局(国家ネットワーク情報通信部門。但し、企業所在地の省級のネットワーク情報通信部門を通じて申告を行う。)による評価が求められる場合と自己評価で完結することが許容される場合があるが、このうち当局評価が強制される要件が明確にされた(4条)。以下のうち(1)(3)はデータ処理者の属性を基準とし、(2)(4)は対象となるデータの内容を基準としている。個人情報保護法において「国家ネットワーク情報通信部門の規定する数量」とされていたところ、取り扱う個人情報が100万人を超える取扱者であるか、又は、移転する個人情報が累計で10万人(センシティブ個人情報の場合は1万人)を超えるかが基準とされている。
当局によるデータの越境安全評価においては、申告書、データ越境リスク自己評価レポート、データ処理者と域外受領者との間で締結する契約等を提出する(6条)。当局審査が必要な場合も自己評価を行うことが前提とされている。国家ネットワーク情報通信部門は、申告資料の受領日から7営業日以内に受理の有無を決定し、書面で回答する(7条)。申告が受理された場合、国家ネットワーク情報通信部門は、業界主管部門、国務院関係部門、省級のネットワーク情報通信部門、専門機構等を組織して安全評価を行うことになる(10条)。
データの越境安全評価は、国家安全、公共利益、個人又は組織の権益へのリスクを重点的評価事項として、以下の内容を含むものとされ、移転元の事情のみならず移転先所在国の法環境や移転先のデータ保護レベルについても審査の対象とされている。
国家ネットワーク通信部門は、受理通知書の発行日から45営業日内にデータ越境安全評価を完了させるが、状況が複雑又は補充資料を必要とする場合には当該期間を原則60営業日を超えない期間まで延長することができる。評価結果は、データ処理者に書面で通知される(11条)。なお、データ越境評価結果の有効期間は2年とされ、有効期間内に審査重点事項に変更がある場合等には、データ処理者は再申告しなければならず、再申告がない場合にはデータの越境活動を停止しなければならない(12条)。
データ処理者は当局による審査の有無にかかわらず、データの越境移転前に、越境リスクに関し自己評価をすることが求められる。自己評価の重点事項は以下のとおりであり、その大部分は当局による審査事項と重複する内容となっている(5条)。
データ処理者は、域外受領者のデータ安全保護責任義務を規定する契約を域外受領者と締結することが求められており、この点については、越境移転に関する当局審査及び自己評価の対象とされている。データ処理者と域外受領者との契約の内容についても規定されるべき項目が明確化されている(9条)。
個人情報保護法において、国家ネットワーク通信部門が制定する標準契約を締結することが、域外提供における当局審査を回避するための要件とされているが、上記内容を含む標準契約のフォーマットは別途公表されるものと考えられる。
データ処理者が本弁法に基づく評価を行わずにデータの越境移転を行う場合に、いかなる組織及び個人もネットワーク情報通信部門への苦情又は通報を行うことができる旨が規定されている(15条)。
また、本弁法の規定に違反する場合には、ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法等の規定に基づき処分する旨も明確化されている(17条)。
本弁法は、中国国内外の企業の関心が高い越境移転における安全評価について包括的な内容を規定するものであり、重要性が高い。情報規制の基幹三法への具体的な対応策の検討にあたっては、法執行の状況も踏まえた判断が求められる側面もあり、本弁法の立法のみならず今後の実務動向も注目される。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)


東崎賢治、羽鳥貴広、近藤正篤(共著)
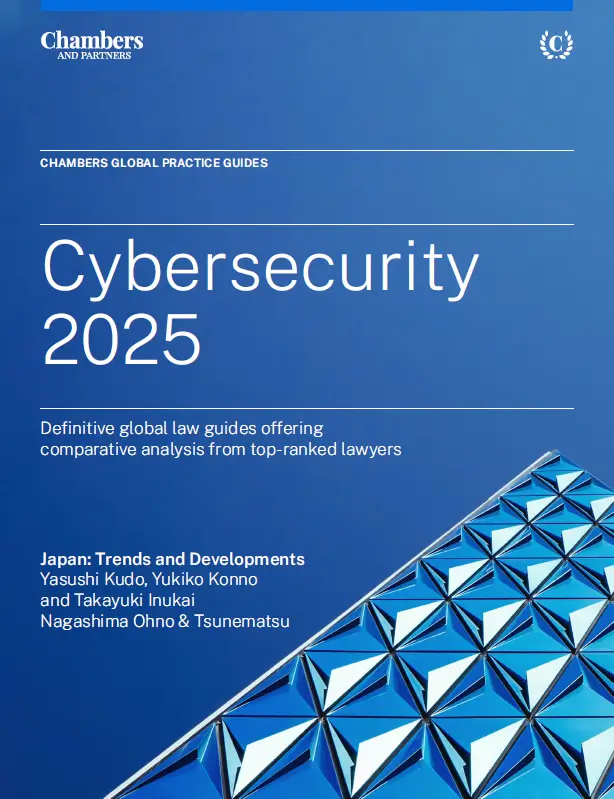
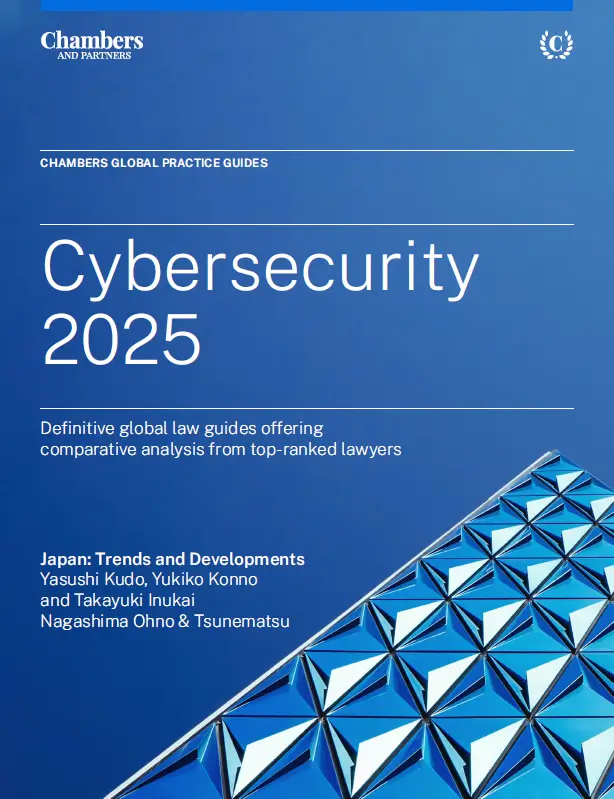
(2025年3月)
工藤靖、今野由紀子、犬飼貴之(共著)


(2025年3月)
鈴木明美、松宮優貴(共著)


(2025年2月)
殿村桂司、小松諒、今野由紀子、松宮優貴(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)


長谷川良和


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


井上皓子


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


井上皓子


長谷川良和


(2025年6月)
佐々木将平


德地屋圭治、李辛夷(共著)


(2025年5月)
川合正倫、艾蘇(共著)


(2025年5月)
鹿はせる


(2025年4月)
若江悠