
松尾博憲 Hironori Matsuo
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
昨今、様々な業界でNFT(Non-Fungible Token)その他のトークン(以下「NFT等」と総称します。)を活用した新たなビジネスやサービスが生まれています。その中でも、スポーツは、NFTの持つ希少性などの特徴と親和性の高いコンテンツビジネスの代表的なものとして、NFT等の活用が特に進んでいる業界の一つです。
NFTは、代替性のないデータという単なる「商品」ではなく、メタバース、Web3.0といった新たなフェーズにおけるITインフラともなりうる「技術」です。そのため、スポーツ業界においても、今後さらに幅広い活用方法が生まれていくと思われますが、現時点で、スポーツビジネスにおいて既にNFT等が活用され、又は活用が期待されている主なものとしては、以下があげられます。
① デジタルコレクティブル(Digital Collectibles)
② ファントークン(Fan Token)
③ NFTチケット
NFT等を利用したビジネスやサービスにおける一般的な法的留意点は、既に様々な議論がなされています※1が、NFT等自体の法的性質やNFT等の取引をめぐる法律関係が現在の法令上はなお自明ではないことから、プラットフォームの利用規約等による権利関係の整理なども実務上は非常に重要なポイントです。それらは上記①~③の活用例においても同様ですが、加えて、各活用例に特有の法的論点の検討も必要です。本稿では、それぞれの活用例において留意すべき法的なポイントを具体的に取り上げます。
デジタルコレクティブルは、従来は主に紙ベースで販売・流通していたトレーディングカードなどのコレクティブル(収集品)のデジタル版といえるものです。2020年にいち早くサービスが開始されて大きな話題となったNBA Top Shotをはじめ、既に多くのリーグ・チームや選手個人が画像や動画などのデータをNFTとして販売しており、最近では、Candy Digital社が取り扱うMLBの大谷選手のトレーディングカードのNFTが野球カテゴリー史上最高額の10万ドルで購入されたことなども話題になりました※2。
従来の紙ベースのカードやサイン入りアイテムなどに比べて、NFT化したデジタルコレクティブルには、物理的な制約なく、世界中の製作者・コレクター間で容易かつ即時に販売・譲渡が可能というメリットがあります。チェーン上で取引記録を確認できるNFTの特徴を活かして転売時に発行者(制作者)に利益の一部が還元される仕組みを構築可能な点も製作者にとって魅力的となりえます。また、現物と違って劣化しないのも利点の一つですし、発行者やプラットフォームの信頼性やセキュリティ次第では、現物よりも偽造や盗難のリスクが低いというメリットもありうるでしょう。
スポーツ業界におけるデジタルコレクティブルについては、その発行者、購入者、そして選手やチーム・リーグ等の関係者間の権利関係に留意する必要があります。例えば、MLBのトレーディングカードを長年販売してきたことで知られるTopps社が2021年に発売した「Topps Series 1 NFT Collection」のように、選手の画像等をNFTとして販売する場合、発行者は、選手の肖像・パブリシティ権についてライセンスを受ける必要があります。選手の肖像・パブリシティ権は本来、選手個人に帰属するものですが、選手契約や大会・リーグのルールなどにおいて、選手以外がライセンス権限を持っていたり、(選手がライセンスするにはチームの承諾を要するなど)選手によるライセンスに制限が課されていたりする場合がありますので、留意が必要です。例えば、日本プロ野球では、統一契約書16条において、選手はチームの指示による撮影を承諾し、撮影された写真等に関する肖像権、著作権等はチームに帰属することが定められており、これに基づき、選手の肖像権の利用は基本的にチームが一括管理しています。他方で、米国のMLBでは、労働協約(Collective Bargaining Agreement)により、選手の肖像の使用についてはチームやリーグではなく選手会に権利が与えられています。
また、選手の肖像・パブリシティ権とは別途、画像や映像自体の著作権の帰属も問題となります。発行者が自ら撮影するなどして著作権を有する画像等であればよいですが、そうでない場合、発行者は、著作権者から著作権の譲渡やライセンスを受ける必要があります。さらに、チームやリーグのロゴやユニフォーム等を使用するのであれば、それらについてはチームやリーグからライセンスを受ける必要があります。
発行者におけるこれらの権利関係の整理を経て販売されたデジタルコレクティブルについて、購入者がいかなる権利を取得するのかという点も、NFTの場合には特に重要なポイントとなります。購入者は、デジタルコレクティブルの「譲渡」を受け、その「保有者」となったとしても、選手の肖像・パブリシティ権を取得しないことは当然として、通常、そのデジタルコレクティブルに使用された画像等の著作権も取得しません。これらの権利は、購入者に譲渡されることなく、元の権利者のもとに留まります。それでは購入者が何の権利を取得するのかというと、プラットフォームの利用規約等にもよりますが、通常は、「NFTが表章する画像や映像などのデータを一定の範囲で利用する権利」を取得すると考えることができます。例えば、NBA Top Shotの利用規約では、購入者には私的利用等の一定の限定的な目的での使用、複製及び表示のライセンスが与えられる一方、コンテンツの著作権は譲渡されない旨や、コンテンツを加工したり、広告等その他商用的に利用したりはできない旨が明記されています(Terms of Use Section 4)。
以上のポイントは、実は、伝統的な紙ベースのトレーディングカードの場合と基本的には大きく異ならないともいえます。これは購入者の権利についても同様で、紙ベースのトレーディングカードを買ったことで、その写真の著作権も取得して自由に複製販売や商用利用してよいと考える人はいないと思います。しかし、NFT等の場合、その取引の意味が未だ十分に理解されておらず、法律上も権利関係が自明とはいえないことからも、誤解が生じやすいのではないかと思われます。また、紙ベースのカードに比して、NFTが発行される画像や映像等を悪用されるリスクも高いため、権利関係を明確化しておく必要性が高いということも指摘することができます。そのため、デジタルコレクティブルを取り扱う場合には、特に購入者との権利関係について、プラットフォームの利用規約等において明確にするなどの手当が重要となります。言い換えれば、NFT等が無形の財産かつ新しい技術・取引であるがゆえに、関係者間での理解や認識に齟齬が生じてしまう可能性が高く、当事者の意思の合理的解釈だけでは必ずしもカバーできない法律関係について、利用規約等を通じて補完する必要があるためともいえます。
また、紙ベースのトレーディングカードと異なり、NFT等が表章する画像や映像等のデータへの具体的なアクセス方法はプラットフォームのシステムに依存しうることから、何らかの理由でプラットフォームの運営が終了してしまったような場合には、そのアクセスが不可能となり、NFT等の実質的な価値が損なわれるおそれがある点も留意が必要です。
ファントークンは、スポーツクラブやチーム(以下「クラブ等」といいます。)が特定のプラットフォームを通じて発行する、ブロックチェーンを活用した代替性のあるトークンです。トークンの保有者には、トークンの保有数に応じてクラブ等が主催するイベント(投票等)に参加する資格が与えられたり、グッズ等の特典が与えられたりします。従前のファンクラブの仕組みをベースに会員登録をしたファンにトークンを発行するもので、トークンを発行することにより、①「ファン」であることの価値を表示し、その価値を明確化するとともに、②トークンの売買により「ファン」であることの価値の取引を可能にしたものともいえるでしょう。また、別の見方をすれば、寄付型/購入型のクラウドファンディングと同じような、プラットフォームを通じて魅力のある事業に対して金銭を支払うことにより一定の特典/サービスを受ける仕組みをベースとして、事業者が購入者にトークンを発行することによる資金調達を可能とし、また、トークンの保有を通じて、事業者(クラブ等)と購入者(ファン)の継続的な関係を構築したものといえます。そして、このような新たな手法によって、新規のファンを獲得しやすくなるという利点もあると思われます。
外国の例としてはChilizが運営するSocios.comというプラットフォームなどでFCバルセロナやパリ・サンジェルマンFCなどの著名なクラブ等がファントークンを発行しています。また、国内では株式会社フィナンシェが運営するプラットフォームFiNANCiEにおいて、湘南ベルマーレやアビスパ福岡などサッカーやバスケットチームがファントークンを発行しています。
現状国内でのファントークンの対価は、クラブ等の投票企画への参加や特典の付与といったものに限られているようですが、クラブ等の事業収益などからの金銭的なリターンを受け取ることができる仕組みになると、金融商品取引法上の電子記録移転権利などに該当し、有価証券として取り扱われる可能性があります。その場合には、ファントークンの発行が開示規制の対象になったり、発行者であるクラブ等やプラットフォームが金融商品取引法上の業規制の対象となりますので留意が必要です。
また、電子記録移転権利などに該当しない場合であっても、物品やサービスの対価として使用することができる場合や他の暗号資産と相互に交換可能な場合には、資金決済法上の暗号資産に該当することになります。
ファントークンの購入者は、当初、プラットフォームを通じてクラブ等から直接ファントークンを購入することになると考えられます。そのため、法的には、①購入者(利用者)とプラットフォームとの間の利用契約、②購入者(利用者)とクラブ等との間のトークンの購入契約、③プラットフォームとクラブ等の間の利用契約が存在すると考えられます。①の利用契約は、プラットフォームの利用規約に同意し、利用登録を行うことによって成立します。②の購入契約は、購入者(利用者)がプラットフォームを通じてファントークンを購入することにより成立します。③の利用契約は、クラブ等がプラットフォームにおいてファントークンを発行することを合意することにより成立します。それぞれの契約について、プラットフォームが作成する利用規約やプラットフォームで表示される内容に従って内容が決まることになると考えられますので、プラットフォームが作成する利用規約の内容が重要になります。
従来型のファンクラブにはないファントークン特有の問題としては、ファントークンが取引の対象となることを前提とし、その経済的価値に着目した取引が行われる可能性がある場合には、価値の変動に関するクラブ等の責任について会員との契約において明確にしておくことが検討課題になると考えられます。基本的には、ファントークンの経済的な価値についてクラブ等は保証しないということを原則とし、その他、価値の変動リスク(ファントークンの追加発行やファントークンに関する事業の停止等)についてあらかじめ説明することによって、トラブルの発生を未然に防ぐような工夫が考えられます。
また、プラットフォームを離れて取引を行ったり、ファントークンに基づく権利を行使することができないこととされている場合、プラットフォームの倒産や事業の廃止によりファントークンに係る権利を確保することができなくなる可能性もあります。
NFTの活用が進んでいる欧米では、スポーツなどのイベントのチケットをNFTとして販売することも検討されています。NBAのダラス・マーベリックスのオーナーであるMark Cuban氏がその旨を発言したことでも話題となりました※3。アメリカでは、チケットの再販(転売)が一般的に許容されており、StubHubやSeatGeek等のプラットフォームで活発に取引が行われています。チケットがプレミアム化して高額で再販が行われることも珍しくなく、全米最大のスポーツイベントであるNFLのSuper Bowlの2022年のチケットは、試合前日時点のStubHubにおいて最も安いものでも約3,900ドル、平均取引価格は約6,700ドルなどの史上最高額で取引されました※4。
チケットをNFTとして販売することにより、興行主が転売をトラックしてマーケット情報を収集したり、転売時に興行主に利益の一部が還元される仕組みを構築したりできる点などにメリットがありえます。また、NFTを用いることで、チケットの保有者が何者かを把握しやすくなり、会場のセキュリティの観点からもメリットがありうるという指摘もなされています。他方で、取引にかかるネットワーク手数料(いわゆるガス代)の問題のほか、スタジアム入場時を含む大量の取引にブロックチェーンシステムの処理スピードが追いつかないおそれがあることや、支払手段が暗号資産に限定されている場合には暗号資産による支払が必要となる等の大衆にとってのハードルを含め、NFT自体がまだまだファン一般には馴染みがないことなどが、実現・普及に当たっての課題といえます。
チケットをNFTとして販売する場合の法律関係について、日本ではまだほとんど議論がされていませんが、その場合のNFTは、基本的に、興行主と観客の間の観戦契約上の観客の債権(興行主に対して、スタジアムに入場させ、試合を観戦させることなどを請求できる権利)を表章するものと考えられるでしょう。この場合もプラットフォームの利用規約等において明確化する必要はありますが、NFTの転売が行われる場合には、そのような興行主に対する債権が譲渡されると考えることができます。
チケットの転売一般に関して、日本においては、チケット不正転売禁止法※5による規制があります。いわゆる転売ヤーによる高額転売などが社会問題となったことを背景として2019年に施行された法律であり、チケットの券面や表示画面に転売禁止の旨や購入者情報を確認済みの旨が記載されるなどの所定の条件を充たした「特定興行入場券」については、販売価格を超える価格で営業として転売し、又は転売目的で譲り受ける行為が禁止されています。チケットをNFTとして販売する場合には、興行主としては、転売時に一定の利益を収受するシステムを構築しうることもあり、転売を完全には禁止しないことが通常となるのではと思われます。
その他に、各都道府県の迷惑防止条例によって、公共の場所でのダフ屋行為が規制されている場合がありますが、ネット上での転売は基本的には対象外と考えられています。
チケットの転売が基本的に許容されているアメリカとは異なり、日本では、チケットの転売は基本的に好ましくないものと捉える傾向が強く、転売を制限するための対策がとられているのが実情です。その背景は様々ですが、例えば、高額転売により悪質なブローカーのみが不労所得を得て興行主に一切還元されないという問題には、NFT化により興行主が転売時に一定の利益を収受できるシステムを構築することで対処できるかもしれません。また、NFTとして転々流通時の取引記録が残ることで、大量のチケットを一手に購入して転売している悪質なブローカーを容易に特定したり、反社会的勢力による転売を阻止したりもできる可能性があるように思われます。これらにより、日本においても、チケットの適正な再販市場の発展につながるかもしれません。
※1
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会「NFTビジネスに関するガイドライン」(2021年4月26日)
※2
「大谷翔平にまた偉業 NFTで史上最高額、タティスJr.の5倍の1150万円」Full Count(2022年1月28日)
<https://full-count.jp/2022/01/28/post1179901/>
※3
Taylor Locke “Mark Cuban: The Dallas Mavericks are thinking about ‘turning our tickets into NFTs’” CNBC(2021年3月26日)
<https://www.cnbc.com/2021/03/26/mark-cuban-dallas-mavericks-may-use-nfts-for-ticketing.html>。但し、その後、マーベリックスは、来場した観戦者に無料で選手のキャラクター画像等のNFTを交付するサービスを行っていますが、チケット自体のNFT化はまだ実現していません。
※4
Steven Taranto “2022 Super Bowl tickets: Prices on rise prior to Rams-Bengals showdown at SoFi Stadium in California” CBS Sports(2022年2月13日)
<https://www.cbssports.com/nfl/news/2022-super-bowl-tickets-prices-on-rise-prior-to-rams-bengals-showdown-at-sofi-stadium-in-california/>
※5
正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(平成30年法律第103号)。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
関口朋宏(共著)


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年6月)
近藤正篤(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
今野庸介


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年3月)
殿村桂司、小松諒、加藤志郎(共著)


(2024年10月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ(共著)
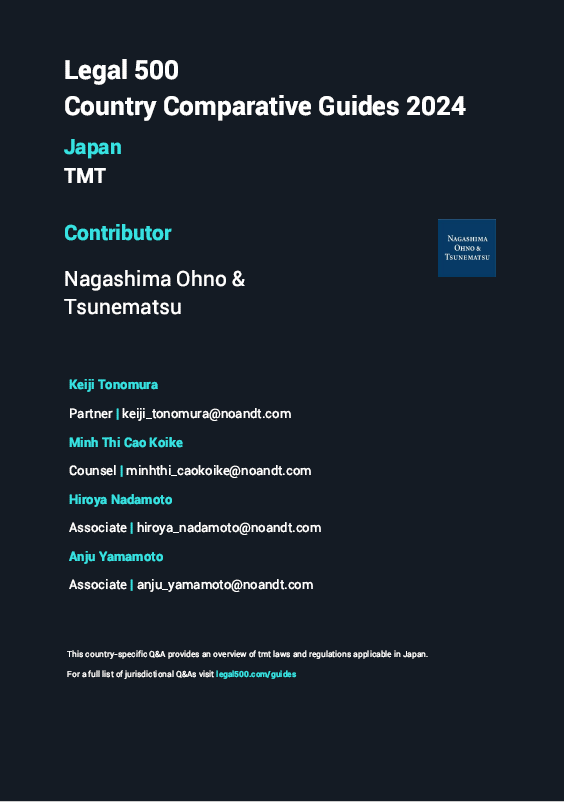
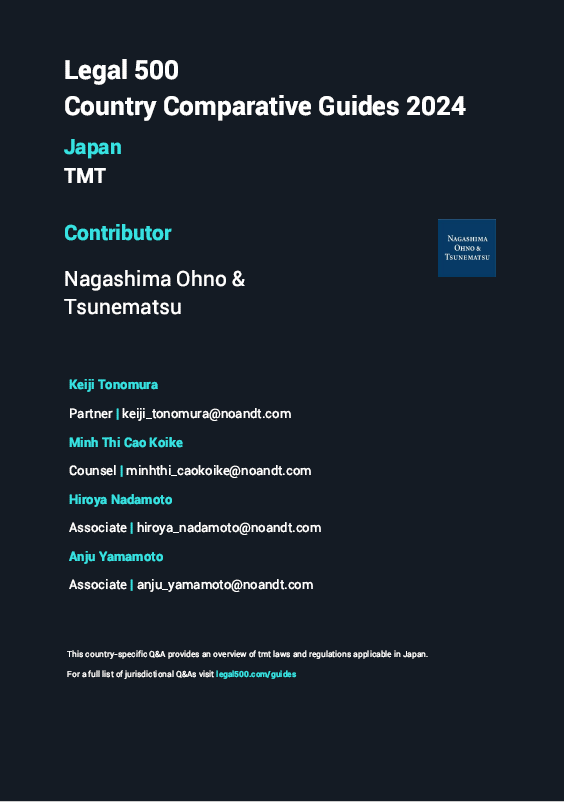
(2024年8月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、灘本宥也、山本安珠(共著)


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年6月)
近藤正篤(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
今野庸介