
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
2022年1月28日、知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会は、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」(略称:知財・無形資産ガバナンスガイドライン)Ver 1.0(以下「本ガイドライン」といいます。)を策定・公表しました※1。
本ガイドラインは、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした上場会社以外の会社、さらには投資家・金融機関にも活用されることが期待されています。また、本ガイドラインは、特許権・商標権・意匠権・著作権といった「知的財産権」のみならず、技術、ブランド、デザイン、コンテンツ、データ、ノウハウ、顧客ネットワーク、信頼・レピュテーション、バリューチェーン、サプライチェーン、これらを生み出す組織能力・プロセス等の「無形資産」も対象とするものであり、多くの会社に関係する重要なものと考えられます。
本ニュースレターでは、本ガイドラインの概要及び各社において今後求められるアクションの内容について解説いたします。
近年、知財・無形資産が競争力の源泉として重要性を増している一方で、日本企業においては無形資産よりも有形資産への投資が重視され、また、企業価値に占める無形資産価値の割合も有形資産価値に比して低い傾向にあるという指摘がなされています。この原因としては、知財・無形資産の投資・活用については、有形資産のように統一的な指標が乏しく、特に短期的には費用対効果が見えにくいこと、企業内部において知財・無形資産全体を統括する部門が存在しないことが多く、知財・無形資産の投資・活用戦略が経営戦略・事業戦略として必ずしも位置づけられてこなかったこと等が挙げられています。
このような現状を踏まえ、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード(以下「改訂コーポレートガバナンス・コード」といいます。)では、知的財産への投資等について、適切な情報開示(補充原則3-1③)、取締役会による実効的な監督(補充原則4-2②)が盛り込まれました。本ガイドラインは、この改訂コーポレートガバナンス・コードを受けて、どのように企業の知財・無形資産の投資・活用戦略の開示や社内におけるガバナンスの構築に取り組めば、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて分かりやすく示すガイドラインとして策定されました。本ガイドラインでは、各企業が知財・無形資産の投資・活用を促進することで、資本市場からの理解・サポートが得られ、金融市場からの資金調達力が強化されることを通じて、更なる知財・無形資産の活用・投資に向けた好循環を促すことが意図されています。
前記(1)のとおり、本ガイドラインは改訂コーポレートガバナンス・コードを受けて策定・公表されたものであるため、上場会社における経営戦略・事業戦略の構築・実行及び投資家との対話等のために活用することが想定されています。上場会社は、定時株主総会終了後遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を更新する必要がありますが、今後は本ガイドラインに示された考え方を参考に、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスを実践していくことが想定されています。
また、本ガイドラインの利用は上場会社のみに限られるものではなく、中小・スタートアップを始めとした上場会社以外の会社においても、本ガイドラインにおける考え方を踏まえた自身の知財・無形資産の投資・活用戦略の明確化を通じて金融機関からの資金調達につなげていく等、本ガイドラインを活用することが想定されています。
さらに、本ガイドラインは企業における知財・無形資産の投資・活用戦略に関する理解を深めるために、投資家や金融機関の側でも活用することが想定されています。
本ガイドラインは、企業に対し、自社の現状の姿(As Is)を正確に把握するとともに、目指すべき将来の姿(To Be)を描き出し、これらを照合することで、知財・無形資産の維持・強化に向けた投資・活用戦略を構築することを求めています。本ガイドラインは、この取組を進めるにあたって企業に求められるプリンシプル(原則)として、次の5つを挙げています(なお、5つ目のプリンシプル(原則)は投資家に求められる内容となっています。)。これらのプリンシプル(原則)は、4.で掲げる7つの具体的なアクションを進める際の重要な視点となります。
本ガイドラインでは、企業がどのように知財・無形資産の投資・活用戦略を開示・発信すれば、それが投資家や金融機関に適切に伝わり、適切な評価・分析につながるかといった観点から、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示・発信と、社内における体制確立の在り方について整理しており、企業がとるべきアクションとして次の7つが示されています。
企業はまず、経営における知財・無形資産の重要性を踏まえ、自らのビジネスモデルを検証し、自社の経営にとってなぜ知財・無形資産が必要であるのか、どのような知財・無形資産が自社の競争力や差別化の源泉としての強みとなっており、それがどのように現在及び将来の価値創造やキャッシュフローの創出につながっているのかについて、しっかり把握・分析し、自社の現状の姿(As Is)を正確に把握することが重要であるとされています。
分析に際しては、IPランドスケープ※2の活用等により、自社の知財・無形資産が他社と比べて相対的にどのような位置づけにあるかについても把握・分析し、自社の知財・無形資産の強みを客観的に捉えること、強みとなる知財・無形資産の把握・分析に当たっては、創出された社会価値・経済価値から逆算して(バックキャスト)、自社のどの知財・無形資産が強みであるかを特定していく視点が重要であるとされています。
技術革新・環境・社会を巡るメガトレンドのうち自社にとっての重要課題(マテリアリティ)を特定したうえで、注力すべき知財・無形資産の投資・活用戦略の位置づけを明確化することが求められています。特に近年ESG投資の要請が高まっていることを踏まえ、企業は、自社のESGへの取組内容にメリハリをつける観点からマテリアリティを特定することが推奨されています。知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行は、ESG課題の解決に向けた技術解決手段の社会実装の実現を長期的にプラスの価値評価につなげることを可能とするものであることから、マテリアリティを特定したうえで、その対応に向けて、知財・無形資産の投資・活用戦略の位置づけを明確化することが重要であるとされています。
自社の知財・無形資産の価値化が、どのような時間軸(短期・中期・長期)でサステナブルな価値創造に貢献していくかについて、達成への道筋を描き共有化することが求められています。具体的には、目指すべき将来の姿(To Be)を描き、強みとなる知財・無形資産を、事業化を通じて、製品・サービスの提供や社会価値・経済価値にいかに結びつけるかという因果関係を明らかにした価値創造ストーリーを構築することとされています。
ストーリー構築にあたっては、KPI等により定性的・定量的に説明することにより、その取組の進捗を把握できるようにすることが重要であるとされています※3。また、ビジネスを進めていく中で、経営を巡る環境変化等を踏まえつつ、目指すべき将来の姿(To Be)を必要に応じて見直していくという柔軟性を持つことも重要であるとされています。
知財・無形資産の把握・分析から明らかとなった自社の現状の姿(As Is)と目指すべき将来の姿(To Be)を照合し、そのギャップを解消し、知財・無形資産を維持・強化していくための投資や経営資源配分等の戦略を構築し、その進捗をKPI等の定量的な指標によって適切に把握することが求められています。
具体的には、今後どのような知財・無形資産の投資を行う必要があるのか(顧客ネットワークやサプライチェーンの維持・強化、研究開発による自社創造、アライアンスやM&Aによる外部からの調達・オープンイノベーションの活用など)、自社の知財・無形資産が支えるビジネスモデルを守るためにどのような方策をとるべきか(他社による侵害、価値棄損への対応、自社権利の維持管理や、秘密保持体制の構築運営など)について検討することが重要であるとされています。
知財・無形資産のスコープの広さに鑑みれば、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行に向け、社内で横串を刺すような体制は不可欠です。具体的には、例えば、取締役会に知財・無形資産の戦略的投資・活用に関し諮問する委員会を設置することや、執行側にナレッジを集約する目的でサステナビリティ委員会を活用することなどにより、社内の幅広い部署(経営企画、総務(IR、ESGなど)、事業、知財、研究開発、マーケティング、営業など)が連携することができる体制の構築が求められています。また、このような体制が実効的に機能するよう、知財・無形資産に関する知見を取締役のスキルマトリックスを構成する一つの要素として位置づけることや、取締役へのトレーニングの機会等を活用しつつ、取締役会以外の場において取締役が知財・無形資産に関する知見や認識を深める機会を設けることも有効であるとされています。
法定開示資料の充実のみならず、統合報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、IR資料、経営デザインシート等の既存の任意の開示媒体、さらには、広報活動や工場見学といった機会等も効果的に活用し、知財・無形資産の投資・活用戦略を開示・発信することが求められています。
投資家や金融機関その他の主要なステークホルダーとの対話・エンゲージメントを通じて、それらの声や意見に真摯に耳を傾けながら、知財・無形資産の投資・活用戦略を磨き高める不断の取組を進めることが求められています。
改訂コーポレートガバナンス・コードでは知的財産への投資等に関する具体的な情報開示が求められ(補充原則3-1③)、本ガイドラインでも知財・無形資産の投資・活用戦略の開示・発信が求められています(上記4.(6))。もっとも、情報開示はあくまでも改訂コーポレートガバナンス・コード及び本ガイドラインの一部分にすぎず、その実質は、各企業の経営・事業戦略の中に知的・無形資産をどのように関連づけるかという点に対する積極的な検討を求めるものですので、単なる開示の問題として捉えるのでは不十分であると考えられます。
そのため、まずは知財・無形資産の投資・活用戦略に関する社内における検討が不可欠であり、これを踏まえて、当該検討の過程・結果のうち、何をどのような粒度で、また、どのような方法で、対外的に開示し、アピールするかを考える必要があります。
なお、補充原則3-1③、4-2②の開示は、開示内容の性質上、コーポレート・ガバナンス報告書の提出の直前に開示内容を検討しては、対応が不十分となる可能性が高い上、その内容は、株主総会における株主の質問事項にも関連し得るものであるため、その対応については、遅くとも株主総会における想定問答の作成の段階で検討しておく必要があります。上場会社にとってもその他の会社にとっても、本ガイドラインが求める知財・無形資産の投資・活用戦略の検討は、可能な限り速やかに着手する必要性が高いものであるといえます。
本ガイドラインの示すゴールは「強みとなる知財・無形資産を活用した持続可能なビジネスモデルを検討し、将来の競争優位を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略を構築すること」です。そこでは、出発点として現状強みとなる知財・無形資産(As Is)を把握することは重要ですが、その現状の問題点の検討・分析からあるべき姿(To Be)を導く(いわゆるフォアキャストの視点)だけでは、必ずしも持続可能なビジネスモデルを検討したことにはならず、開示内容として十二分とも言い難いと考えられます。
本ガイドラインが重視しているのは、社会や市場のニーズ、外部環境及びその変化を踏まえ、経営陣が企業・事業の目標とする姿(To Be)を検討し、これを実現するためのビジネスモデルを策定するという一連の(通常の)経営判断のプロセスにおいて、これに並行・連動する形で、(これまで不十分であったと考えられる)会社の強みとなる知財・無形資産(As Is)の活用にどのような変化を加えていくべきかを検討すること(いわゆるバックキャストの視点)です。その際には、例えば、以下の観点からの検討が重要となると考えられます。
もっとも、現状(As Is)の正しい認識がなければ、あるべき姿(To Be)に向けた変化を検討することはできません。自社の強みがどこにあるのかは、まずは経営陣の認識のみならず、各事業部門における現場の情報や認識を吸い上げ、それらが、どの程度確立されたものといえるか(競合他社等の第三者からどの程度侵奪され得るものなのか/排除可能なものなのか)を、知財法制・データ保護法制や契約による保護といった観点も踏まえて検討・確認し直す必要があります。今後は、知的財産権による保護の対象ではない無形資産や、知的財産権による保護を検討してこなかった知財の保護(特に不正競争防止法による利益保護)についても、改めて意識する必要があります。この点は、会社の法務部門・知財部門の通常業務との並行が難しい場合や判断に困難が伴う場合も想定されることから、外部専門家と共同して行うことで、知財・無形資産の法的位置づけを正しく理解しておく必要があります。
また、これまでに知財・無形資産の議論にそこまで携わってこなかった経営陣への説明に際して、知財担当者と共に必要な限度で外部専門家を同席させ、議論の必要性を説明させる、また、知財・無形資産の活用戦略に当たって生ずる疑問・質問に即時に対応させること等も、スピード感のある事業戦略の決定に有用と思われます。
本ガイドラインにおいて頻繁に言及されるIPランドスケープ(前掲脚注2参照)は、バックキャストの視点における現状(As Is)とあるべき姿(To Be)の比較においても有用であるため、積極的な活用が期待されます。その際、各事業部門における現場の情報や認識をあらかじめ吸い上げる作業が必要になるため、知財部門・法務部門と各事業部門の連携が取りやすい状況を日頃から形成しておくことが重要です。
また、本ガイドラインでは、前記4.(5)のとおり、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行に向けて社内で横串を刺すような体制が不可欠であるとされており、実際にも経営陣や事業部門との対話も必要であると考えられることから、本ガイドラインの求める内容につき未対応であった企業については、場合によっては、知財部門の役割が更に増すことが予想されます。コロナ禍も相まって社内のコミュニケーションが従来どおりとはいかないケースも多々見受けられるため、現状の知財部門の果たすべき役割を今一度整理し直し、それを各事業部門にも周知することで、知財部門と事業部門との間の円滑なコミュニケーションのための土壌を形成することも重要と考えられます。
東証の公表資料※4によれば、コーポレート・ガバナンス報告書における改訂コーポレートガバナンス・コード補充原則3-1③、4-2②のコンプライ率は2021年12月時点で6~7割とされていますが、この中でも全ての企業が知的財産の投資に言及している訳ではないことが窺われます※5。もっとも、次回以降のコーポレート・ガバナンス報告書における開示は、本ガイドラインの内容を踏まえたものとなることが期待されるため、補充原則3-1③、4-2②の対応(comply、explainの内容)につき、各企業における取組の実質的な差異がわかりやすい状況となる可能性があるため留意が必要です。
知財・無形資産の戦略に関する開示については、あくまでも実質を伴った開示が求められているものであり、社内での検討や開示が不十分であるにもかかわらず、実施(comply)として対応することまでを求めるものではなく、知財・無形資産の開示や監督をどのように進めるのかや、知財・無形資産の投資・活用の現状を整理した上で今後の検討方針等を説明(explain)することも考えられます。仮に開示内容が不十分であるにもかかわらず実施(comply)として対応すると、かえって投資家からのネガティブな評価に繋がりかねないことに留意する必要があります。
なお、開示に当たっては、秘匿すべき会社の機微情報が明らかにならないよう留意する必要があります。検討対象となる知財・無形資産については発明の新規性、営業秘密の非公知性に影響のないよう留意する必要がありますし、社内の組織体制から会社が保有する情報を推察される可能性があるため、場合によっては、具体的な情報がprivilegeの対象となっているか等も検討する必要があります。
上記のとおり、本ガイドラインは、これまで十分に活用されてこなかったと言われる知財・無形資産を積極的に活用するための視点・考え方を示すものであり、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした全ての会社にとって参考になる重要なものです。もっとも、具体的にどのようなアクションを取るべきか、また、その内容をどこまで、どのような形で開示するかは会社ごとに異なっており、まさに各社におけるクリエイティブな発想に基づく工夫が期待されるところです。我々も、これまで知財・無形資産の投資・活用戦略の策定や社内体制の構築に関して依頼者の皆様と検討してきた経験を踏まえ、本ガイドラインを受けて実務がどのように進化していくか注視していきたいと思います。
※2
「IPランドスケープ」とは、令和2年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究報告書」(令和3年3月)では、「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有すること」と定義されています。本ガイドラインにおいて、IPランドスケープは、知財・無形資産を可視化することにより、知財・無形資産の投資・活用が自社の経営や事業にどの程度役立っているかを経営陣に理解してもらう上で有効なツールであり、また、知財部と他部門との対話を進める上で効果的であるとされています。
※3
ビジネスモデルを説得的に説明する上でどのような指標を用いるのが効果的かについては、各企業の試行錯誤を通じた蓄積が積み上げられていくことが期待されるとともに、引き続き学術的な研究が進められることが期待されるとされています。この点に関しては、東京大学未来ビジョン研究センター・研究フォーラム「知的財産と投資」が、知的財産に関するKPI等の設定に関して中間報告(「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関するKPI 等の設定(中間報告)」)を発表しています(https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/12017/)。
※4
「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果(2021年12月時点)」(https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu0000064ydu.pdf)
※5
なお、補充原則3-1③は、知財投資のみならずサステナビリティの取組についても言及していますが、両者は独立した内容であり、一方を開示すれば他方を開示する必要はないという関係にはありません。また、知財投資についてサステナビリティの文脈で説明・開示しなければならない訳ではなく、独立した内容として説明・開示すれば足りると考えられています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
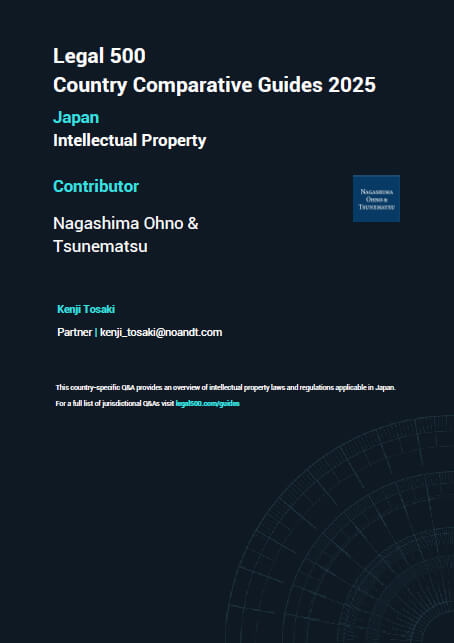
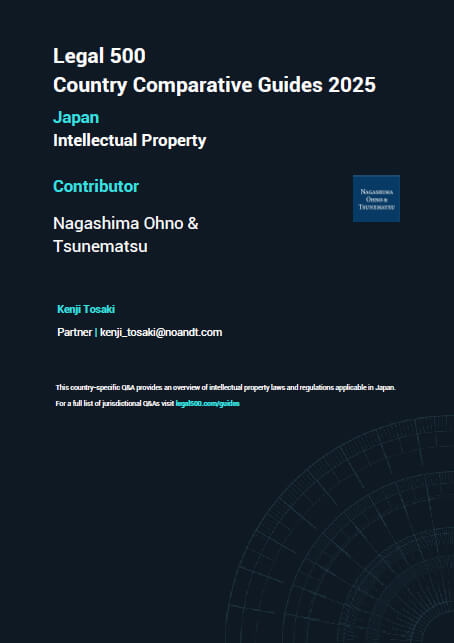
(2025年9月)
東崎賢治


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年10月)
三笘裕、濱口耕輔、奥野晟史(共著)


対木和夫、半谷駿介(共著)