
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
ニュースレター
<CASE/モビリティ Update> 「道路交通法の一部を改正する法律案」の概要(2022年4月)
本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。
2024年3月29日、国土交通省は、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(以下「自家用車活用事業」といいます。)を創設し、道路運送法に基づく許可に関する取扱いについて通達(以下「本通達」といいます。)を発出しました※1。これは、2023年12月に決定された「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」※2において、タクシー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法78条3号に基づく制度の創設)が決定されたことを受け、2024年2月から3月にかけて実施されたパブリックコメントにおける意見も踏まえて策定されたものです。今後、本通達に従って、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態が認められる場合に、地域の自家用車・一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする許可が行われることが予定されています。
自家用車活用事業は、日本におけるライドシェアを一部解禁するものと言われており、地域住民や観光客の利便性向上に資するだけでなく、タクシー事業者やタクシー事業者向け配車アプリケーションの提供事業者等による事業機会の拡大・創出、一般ドライバーによる所得獲得機会の創出にもつながります。
本ニュースレターでは、自家用車活用事業の制度、許可基準及び許可の条件について、その概要をご紹介いたします。
道路運送法は、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車)による有償での運送を原則として禁止しており、例外的に自家用自動車による有償運送が認められるのは、①災害のため緊急を要するとき、②市町村、NPO法人等が、国土交通大臣の登録を受けて、地域住民や観光客等の運送を行うとき、③公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送を行うときに限られます(道路運送法78条)。
本通達は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を上記「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」に該当するものとして、国土交通大臣の許可により自家用自動車による有償での運送事業を認めるものです。自家用車活用事業は、あくまでタクシー事業者が事業の実施主体となって一般ドライバーの管理や指導監督を行うことが前提とされていること、また、特定の地域・時期・時間帯において一定数の車両の範囲内で認められるにとどまることから、いわゆるライドシェアを一般的に認めるものではありません。なお、タクシー事業者以外の事業者がライドシェアを行うことを位置付ける法律制度については、「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」において、2024年6月に向けて議論を進めることとされています。
自家用車活用事業を実施するためには、法人タクシー事業者が管轄の運輸支局長に対して許可申請を行う必要があります。許可申請がなされた場合、以下の基準に適合するかどうかが審査され、適合する場合には許可されることになります。
| 基準 | 内容 | |
|---|---|---|
| (1) | 対象地域、時期、時間帯、不足車両数 | タクシーが不足する地域、時期及び時間帯、並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が指定していること。 |
| (2) | 資格要件 | 道路運送法に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること(いわゆるタクシー事業者であること)。 |
| (3) | 管理運営体制 |
|
| (4) | 損害賠償能力 | 自家用車活用事業について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険・共済に加入していること、又は運行業務開始までに加入する具体的な計画があること。 |
上記(1)については、2024年3月13日に、特別区・武蔵野市・三鷹市、京浜(横浜市、川崎市、横須賀市等)、名古屋(名古屋市、瀬戸市、日進市等)及び京都市域(京都市、宇治市、長岡京市等)の4地域について、曜日・時間帯毎の不足車両数が公表されています※3。また、2024年4月中に、札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、神戸、広島及び福岡の各地域についても不足車両数が公表されることが予定されており、自家用車活用事業を実施できる地域が拡大していく見込みです。
上記(3)において自家用車ドライバーの「他業での勤務時間を把握すること」が要求されているとおり、自家用車ドライバーは自家用車による運送を専業で行う必要はありません。もっとも、後記のとおり、自家用車活用事業の許可条件には、タクシー事業者による運行管理の一環として過労防止等のための措置を採ることが含まれており、タクシー事業者は、他業の勤務時間も踏まえ、自家用車ドライバーの適切な労務管理を行う必要があると考えられます。
自家用車活用事業の許可にあたっては、以下の条件が付されるものとされ、許可期間は2年間とされています。許可に付された条件に違反した場合には、事業の停止や許可の取消し等の行政処分が課される可能性があります。
| 条件 | 内容 | |
|---|---|---|
| (1) | 使用する自家用車 |
|
| (2) | 自家用車ドライバー |
|
| (3) | 運行管理・車両整備管理 | 事業者は、関連通達に基づき、運行管理及び車両の整備管理を行うこと。 |
| (4) | 運送形態・態様 |
|
| (5) | 稼働状況の報告 | 事業者は、使用可能な自家用車の稼働状況について記録し、運輸支局からの求めに応じて報告すること。 |
これらの条件には、タクシー事業者がその雇用するタクシードライバーに対して行う管理や指導監督と同様の対応を自家用車ドライバーに対しても行うことが求められる事項だけでなく、自家用車が使用されることによる追加的な管理や対応が必要になる事項が含まれており、タクシー事業者においては、許可条件を適切に遵守するための制度設計や体制構築、関連するシステムの開発・導入等が必要になると考えられます。
また、上記(4)の条件のとおり、自家用車活用事業においては配車アプリケーションの利用が想定されており、許可申請書においても「配車及び運賃の算出に用いるアプリ等の名称」を記載することになっています。
自家用車活用事業は道路運送法78条3号に基づく制度ですが、同条2号に基づく自家用有償旅客運送制度についても、より使いやすい制度へと改善するための措置が実施・検討されています。具体的には、2023年末に、①「交通空白地」の目安を提示するとともに夜間などの「時間帯による空白」概念を取り込む、②自家用有償旅客運送の実施主体からの受託により株式会社が参画できることを明確化する、③観光地において宿泊施設が共同で車両を活用することを促進する、④自家用有償旅客運送の「対価」の目安をタクシー運賃の「約8割」とすること、の4点について通達の改正等の措置が講じられた上、今後、新たにダイナミックプライシングの導入やタクシーとの共同運営の仕組みの構築等が検討されています。
今後、自家用車活用事業や自家用有償旅客運送制度に基づき、自家用車により有償で人を運送する場面が増えてくるものと思われます。諸外国と比較すると日本におけるライドシェア事業の解禁には様々な議論がありますが、上記の施策の実施効果を検証するとともに、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、2024年6月に向けて議論が進められていくこととされているため、議論の状況や方向性、立法動向を引き続き注視する必要があります。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(監修)、水越政輝、松﨑由晃(共著)


犬島伸能、中村彰男(共著)
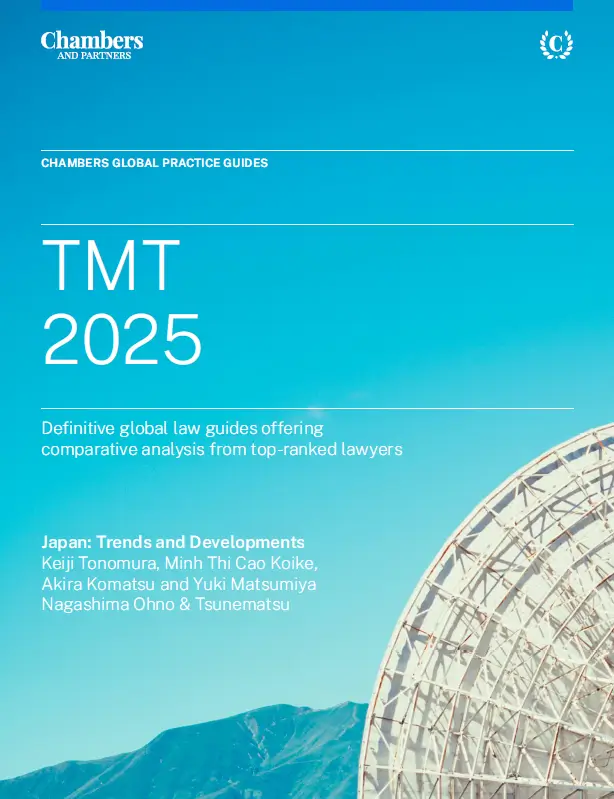
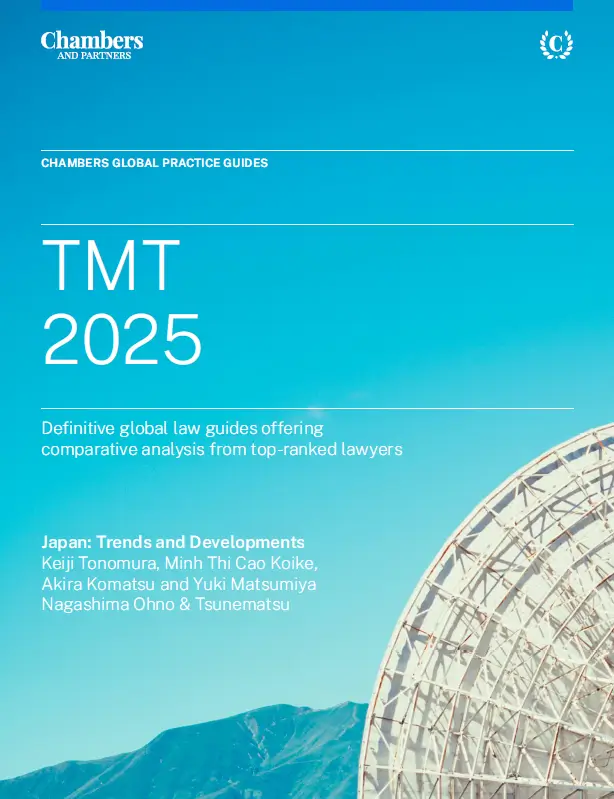
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


(2024年5月)
水越政輝、小松諒(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年9月)
関口朋宏(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
関口朋宏(共著)