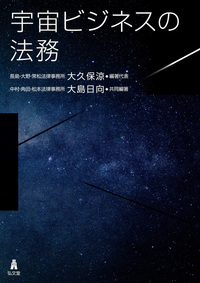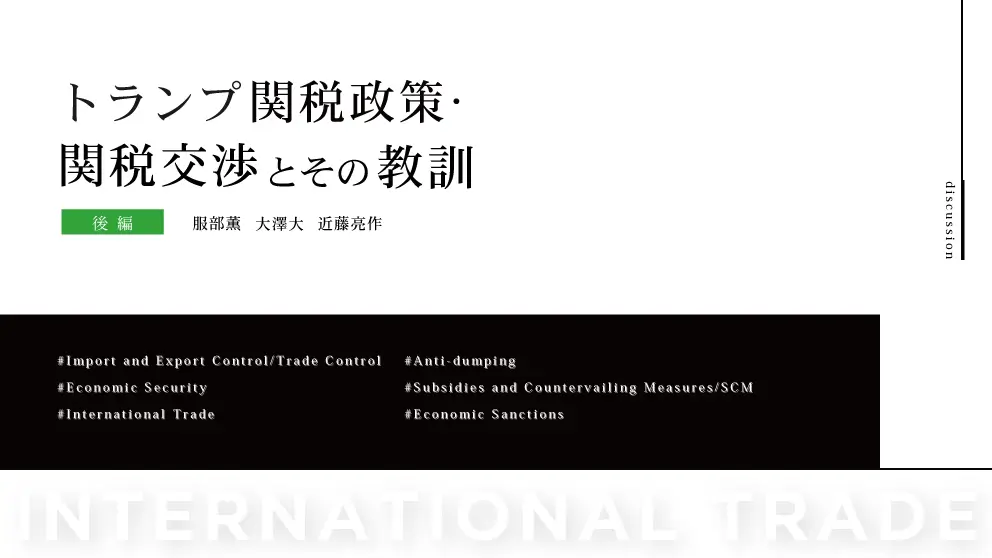SECTION.01
宇宙ビジネスに適用される国際宇宙法
-

大久保
- 『宇宙ビジネスの法務』が出版されました。この執筆プロジェクトを立ち上げたのが2年半前でしたので、大分時間がかかってしまいましたね。その間、執筆者である大島弁護士・宇治野弁護士の転職もありました。今回は、本の目次に沿って、簡単にポイントとなるトピックについて皆様とお話したいと思います。宜しくお願いします。
-

大久保
- では早速、最初のトピックである国際宇宙法ですが、国家間の取り決めである条約のもと、各国の宇宙法制が定められることを考えると、民間企業が行う宇宙ビジネスとの関係においても、国際宇宙法が関係してくることもありますね。例えば、宇宙空間での採掘などを行おうとする場合、宇宙条約が掲げる、国家による月その他の天体を含む宇宙空間の所有を禁止する「領有禁止原則」をどう整理するかというのは議論のあるところです。
-

髙橋
- はい、この領有禁止原則のもと、国、民間企業や個人が月や火星などの土地の所有権を主張することは違法と考えられていますが、更に月や火星で採掘された岩石などの宇宙資源の所有の可否の問題があります。天体の所有権と同様にそこから採掘される資源の所有も同様に禁止されるとの考え方もある一方で、資源は領有禁止原則の対象外とする考え方もあります。日本では、私人による宇宙資源に対する所有権を認める宇宙資源法が今年制定され、宇宙資源は領有禁止原則の対象外とする考え方を前提にした法整備を進めています。
-

大久保
- 1984年に発効した月協定以降、国際条約は策定されていません。近年は、条約に代わって、法的拘束力のないソフトローと呼ばれる規範も重要になってきていますね。
-

髙橋
- 日本やアメリカなどの宇宙活動に大きく関与している国とこれから宇宙活動に進出しようとする国の間の利害対立などによって、法的拘束力のある形でのルールメイキングというのは非常に難しくなっています。しかし、宇宙活動に関連する技術が急速に発展し、多くの国・民間企業が宇宙活動に進出しつつある中で、デブリ問題を始めとして、何らルールのない無秩序の環境を放置しておくというのも問題です。そこで、比較的コンセンサスのとりやすい法的拘束力がない形でのルールメイキング、例えば国連総会決議や宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)において策定されるガイドラインといったソフトローの重要性が増しています。