
鈴木謙輔 Kensuke Suzuki
パートナー
東京
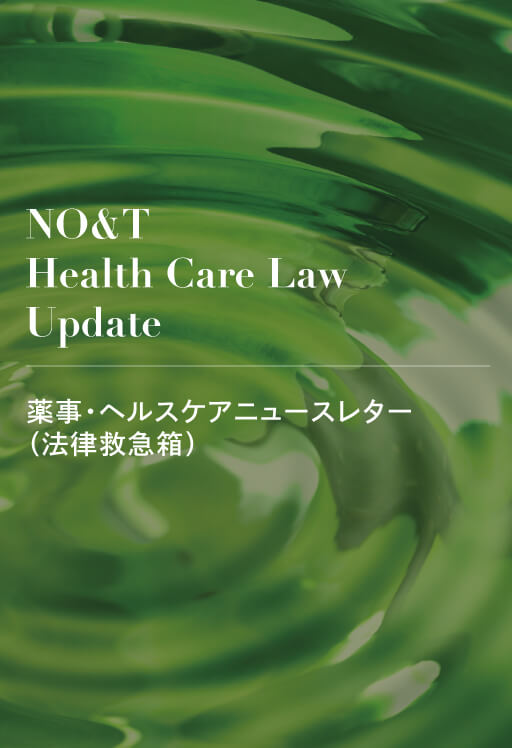
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
本ニュースレターに関連するウェビナーは以下をご覧ください。
薬事・ヘルスケアオープンスクール
「遺伝子・ゲノムビジネスに関わる規制と動向」
遺伝子関連技術を用いた疾患治療は、いわゆる低分子医薬品やバイオ医薬品に次ぐ新しいモダリティとして、近年実用化が進みつつあり、大きな期待と注目を集めている。一方で、新しい分野ということもあって、適用される法律や規制が複層的に絡み合っており、全体的な枠組みが見えづらい分野でもある。
本号では、遺伝子関連技術を用いた疾患治療を実用化していく際に適用のある、日本の主な規制の枠組みと動向を概観する。
遺伝子関連技術を用いた疾患治療に関する規制の枠組みを理解するためには、まず、いくつかの観点から、疾患治療の内容を分類してみると分かりやすい。具体的には、(1)遺伝子治療とゲノム編集治療、(2)in vivo治療とex vivo治療、(3)製品と個別治療という3つの観点から分類すると、日本の規制の枠組みの理解に役に立つ。
「遺伝子治療」とは、遺伝子を外から補充・付加する治療で、疾患の原因となる異常な遺伝子とは異なる場所に正常な遺伝子を組み込む方法を指すことが一般的である。一方、「ゲノム編集治療」とは、ゲノム編集技術を用いる治療で、疾患の原因となる異常な遺伝子そのものを破壊したり、正常な遺伝子に置き換えたりする方法を指すことが一般的である。遺伝子治療は複数実用化されているが、ゲノム編集治療はまだ実用化に至っていない。
「in vivo」「ex vivo」とは、それぞれ「生体内で」「生体外で」という意味を有するラテン語に由来している。そこから、「in vivo治療」とは、ウイルスやプラスミドといったベクターに、治療に用いる遺伝子を組み込んだ上で、直接患者の体内に投与する治療方法を指す。一方、「ex vivo治療」とは、一旦患者の細胞を体外に取り出した上で、当該細胞に治療に用いる遺伝子を導入し、患者体内に当該細胞を戻すという治療方法を指す。
「製品」とは、企業が疾患治療用の製品として各医療機関等に流通させる形態をいうものとする。一方、「個別治療」とは、医師が個々の患者に対する個別の治療行為の中で遺伝子関連技術を用いた細胞の加工等を行う形態をいうものとする。
ここでは、遺伝子関連技術を用いた疾患治療の開発段階に適用される規制のうち、特に臨床開発の段階において適用されるものについて概観したい。内容をごく簡単にまとめると、表1のとおりである。なお、これらの各種規制の枠組みに必ずしもそのまま当てはまらない事例もありうることに留意されたい。また、基礎研究・前臨床の段階で適用のある規制や、生殖医療の提供に特有の規制などについては、紙幅の関係もあり割愛する。
| 臨床研究 | 治験 | ||
|---|---|---|---|
| in vivo(※) | ex vivo | in vivo | ex vivo |
| 臨床研究法 |
再生医療等 安全性確保法 |
薬機法 (遺伝子治療用製品) |
薬機法 (細胞加工製品) |
|
遺伝子治療等臨床研究に 関する指針 (第1章・第3章) |
遺伝子治療等臨床研究に関する指針 (第1章) |
||
|
・遺伝子治療用製品等の品質及び安全性の確保に関する指針 ・ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療用製品等の品質・安全性等の考慮事項に関する報告書 |
|||
| カルタヘナ法(ウイルスを用いる場合等) | |||
臨床開発段階で適用される規制の枠組みは、当該臨床開発が、(1)製品としての上市に向けて実施される「治験」の形式か、(2)主として学術的研究や個別治療としての実用化を目指して実施される「臨床研究」の形式かによって、大きく2つに分かれる。また、当該開発の対象である疾患治療の内容が、①in vivo治療か、②ex vivo治療かによっても、適用される規制が異なってくる場合がある。他方で、各種臨床開発に横断的に適用される規制として、ウイルス等を用いた治療方法の場合には、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)に基づく規制が適用される場合があることにも注意が必要である。
製品としての上市に向けて実施される治験に対しては、他の医薬品等の治験と同様に、薬機法に基づく規制が適用される。通常、薬機法の下では、遺伝子関連技術を用いた疾患治療の製品は、「再生医療等製品」に分類される。その中でも、in vivo治療の製品は「遺伝子治療用製品」として、ex vivo治療の製品は「細胞加工製品」として、それぞれ分類されることになる。治験の実施にあたっては、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」を遵守する必要があるのはもちろんのこと、製造販売承認申請に向けて、「遺伝子治療用製品等の品質及び安全性の確保に関する指針」などに示された各種実務的な要件についても目を配る必要がある。
臨床研究の形式で臨床開発を行う場合において、当該治療方法がex vivo治療に関するものである場合には、細胞加工物を用いる医療技術を適用対象とする再生医療等安全性確保法に基づく規制が適用されることが通常である。他方で、当該治療方法がin vivo治療に関するものである場合には、臨床研究法に基づく規制が適用されることが多い。また、厚生労働省「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」(平成31年2月28日最終改正)の第3章に、臨床研究法の適用を受ける遺伝子治療等の臨床研究に固有の遵守事項が定められている点にも、留意が必要である。
なお、2021年10月8日開催の「第5回再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ」において、同法の次回改正に際して「遺伝子治療等臨床研究指針で定義するin vivo遺伝子治療を含めた『遺伝子治療等』技術について、再生医療等安全性確保法の範囲に含める」との方針が了承され、同年11月7日付で同ワーキンググループのとりまとめ資料も公表された。今後の同法の改正内容によって、規制の枠組みが変化することが予想されるため、動向を注視する必要がある。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)