
鐘ヶ江洋祐 Yosuke Kanegae
パートナー
東京

NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター
現在、裁判の迅速化・効率化を目的とした民事手続全般のIT化の検討が進められています※1。より良い司法サービスの実現のためにIT化の早期実現は必須ですが、特に倒産手続では、一定の書式に従った多数の書類の提出が求められるという手続の性質に加えて、例えば全国的な消費者被害が生じる事案など債権者数が多く事務量・コストが膨大となる場合もあり、IT化は重要な課題です。
倒産手続のIT化によって、債権者や管財人、裁判所の負担軽減も可能となり、効率的な手続遂行による弁済原資の確保といった効果も期待できます。このような背景から、事業再生研究機構において倒産実務家と研究者がメンバーとなった「倒産手続のIT化研究会」※2が発足し、2018年11月以降検討が進められてきました※3。また、多数の債権者が集会に集まることなく手続を遂行できる方策を確保することは、新型コロナウィルスのような感染症対策としても有益です。
同研究会における検討の結果、2019年9月、「倒産手続のIT化に向けた中間取りまとめ」(以下「中間取りまとめ」といいます。)が公表され、倒産手続のIT化の基本構想が提言されました。その後、2021年10月、同研究会より「倒産手続のIT化に向けた中間取りまとめⅡ」(以下「中間取りまとめⅡ」といいます。)が公表され、より具体的な提言がなされました。中間取りまとめⅡでは、主として破産手続における、(i)債権者集会非招集型による手続遂行、(ii)電子メール等を活用した手続遂行、(iii)債権調査留保型の手続の活用、(iv)オンライン債権届出システムの具体的検討の4点が提言されています。
本ニュースレターでは、まず、この「中間取りまとめ」と「中間取りまとめⅡ」を取り上げて、倒産手続のIT化で議論されている主要な項目について説明します。また、倒産手続のIT化に関し2021年12月に公表された、「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会」における報告書※4等の最新の動きについて紹介します。
倒産手続は、一定の書式に従った多数の書類の提出が求められるという手続の性質に加えて、多数の利害関係人が参加する集団的な手続であり、もともとIT化になじむ手続といえます。特に、債権者数が多数にわたる事案においては、書類の授受、債権届出・調査手続、計画案についての投票手続、配当・弁済手続といった手続の各場面で、債権者側だけでなく債務者・管財人側でも、また裁判所においても膨大な労力、時間、コストがかかることから、IT化によって利害関係人の負担を減少させる必要性が高いといわれます。また、経済活動の国際化によって、外国に居住する債権者が多数存在する倒産案件も珍しくなく、ITを活用して債権者の手続参加の負担を低減させたり、国内に所在する債権者との情報格差をなくすなどして公正・衡平な手続を実現することも必要です。
このような必要性を受けて、これまで現行法の範囲内での実務上の工夫として、債権届出・調査等をシステムにて管理したり、書面でなくデータで債権者との情報の授受を行うなど、倒産手続でITが活用された事案が既に相当数あります。近時、新型コロナウィルス感染症の影響に伴って、特に倒産手続のIT化の必要性が語られることもありますが、感染症の有無にかかわらず、法改正を伴う倒産手続のIT化は推進されるべきです。
このような背景から、内閣官房に発足した裁判手続等のIT化検討会が2018年3月に公表した「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-『3つのe』の実現に向けて」では、まず、民事訴訟全般のIT化の検討を進め、その成果や制度設計を活かして非訟事件や家事事件のIT化の検討が進められるべきであるとの方針が示される一方で、倒産手続においては、手続負担の軽減や手続の効率化による弁済原資の確保といった観点から、民事訴訟全般のIT化についての検討結果を待たずに、現行法下でのプラクティスの在り方を基本とするITの活用の検討を進めることも選択肢の1つであると言及されました。
前述1.の裁判手続等のIT化検討会が公表した「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-『3つのe』の実現に向けて」では、民事訴訟手続において「3つのe」(e提出、e事件管理、e法廷)を目指す方向性が示されましたが、倒産手続のIT化については、中間取りまとめで、3つのeのうちの「e提出」「e事件管理」に、倒産手続の特殊性を踏まえて、「e集会」「e届出」及び「e情報提供」を加えた「5つのe」の実現という観点が示されています。
申立人又は、破産管財人、再生債務者等及び更生管財人が裁判所に提出する申立書、報告書及び許可申請書等について、書面での提出でなく、電子情報での提出が原則になります。倒産手続では短期間で多くの書面の提出がされ、中には裁判所による迅速な対応が求められるものもありますので、e提出により、書面提出に比べて負担が減る上、裁判所による迅速な対応及び円滑な事件管理にも資するといわれています。
裁判所が、事件記録の保管を、紙でなく、原則電子情報で行うことになります。ただし、倒産手続は原則非公開であり、記録の閲覧・謄写を請求できる者も限定されていること、倒産手続において提出される書面に個人情報や営業秘密が記載されている可能性があることから、電子情報で事件記録を保管するにあたっては高い情報セキュリティが求められると指摘されています。
裁判所で行われている債権者集会を、ウェブ上で生中継し、遠隔地に所在する債権者が容易に債権者集会に参加できるようにするものです(さらには、債権者集会を裁判所で行わずウェブ上で行うことも検討に値するとされています)。ウェブ上での事後的な動画配信も考えられるとの指摘もされています。もっとも、倒産手続の原則非公開性により、視聴者を制限する必要があります。加えて、リアルタイムでの投票(議決権行使)ができるような工夫も求められると指摘されています。
オンライン債権届出システムを構築することにより、債権者がオンラインで簡易に債権届出をできるようにし、裁判所や管財人等が、当該システムで債権届出の管理を適切かつ簡易に行えるようにするものです。現在は、裁判所又は管財人等が手続開始を通知し、債権者が債権届出書を提出していますが、両者にとって事務負担、郵送費用の負担があり、オンライン化による負担軽減が期待されています。
管財人等が、債権者がアクセス可能な場所に、財産目録、収支計算書、貸借対照表、債権認否一覧表その他の情報をアップロードして、情報提供するものです。現在、債権者は、債権者集会における管財人等の説明や事件記録の閲覧・謄写等の方法を通じて情報収集していますが、e情報提供により、債権者もそれらの方法によらず容易に情報収集できるようになり、裁判所の事務負担も軽減されると指摘されています。
倒産手続のIT化に向けて、中間取りまとめⅡは大きく4つの提言を行っています。すなわち、破産手続における、(i)債権者集会非招集型による手続遂行、(ii)電子メール等を活用した手続遂行、(iii)債権調査留保型の手続の活用、(iv)オンライン債権届出システムの具体的検討の4つです。以下ではこれらの提言について説明します。
破産手続において破産管財人が選任される場合、通常は、債権者集会(財産状況報告集会、異時廃止意見聴取集会、任務終了計算報告集会)が同日に開催されますが、大阪地裁第6民事部(倒産部)では、①破産手続の開始後12週間で換価が完了して、配当ができないことが確定する②個人破産の場合は免責報告も可能であり、③債権者集会に出頭する債権者が皆無であるという要件がいずれも見込まれる場合、債権者集会を開催しないという運用(債権者集会非招集型)も行われています。特に、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、①の要件を満たさなくても、債権者集会非招集型による進行に支障がない場合には、同部の判断で、事案に応じ、より幅広い事件につき債権者集会非招集型の手続を認めています。
また、東京地裁民事第20部(破産再生部)においても、債権者集会非招集型の運用はもともと基本的には配当が見込まれない事案で採用されていたと思われますが、新型コロナウィルス感染症対策を契機として、配当が見込まれる事案でも債権者集会非招集型とされた例があるようです。
中間取りまとめⅡでは、破産手続が開始された時点で配当できることが明らかでない事案において、債権者集会非招集型の破産手続を積極的に推進し、同時に、e情報提供、e集会を活用することも合わせて提言しています。
多数の債権者が全国に所在するような事案や債権者の多くが海外に所在する事案では、債権者に手続開始通知を郵送して債権届出を受け付けたり、物理的な債権者集会期日への出頭を求めたりすることが困難ないしかえって債権者の不利益となる場合があります。そこで、手続全般にわたって電子メールやWebサイトを活用することにより可能な限り債権者集会を開催せず、債権者の物理的な出頭を必要としない手続の可能性について検討しています。
中間取りまとめⅡでは、破産手続において、①裁判所による手続開始通知書や債権届出書用紙等の送付、②破産債権者による債権届出書の提出、③破産管財人が認否で認めない場合や他の破産債権者により異議が出された場合における、裁判所書記官又は破産管財人による破産債権者への通知等における、電子メールやWebサイトの利用を提言しています。他にも、認否書、債権者集会資料の送付、配当に関する通知を含むその他の書類についても電子メールやWebサイトを活用する可能性が指摘されています。
債権調査には、いわゆる期間方式(破産管財人が作成した認否書が提出され、定められた債権調査期間内に、破産債権者等が書面で異議を提出することで手続が進行する方式)といわゆる期日方式(定められた債権調査期日に、破産債権者が出席する集会において破産管財人が口頭で認否を行い、破産債権者等が口頭で異議を述べることで手続が進行する方式)があります。
破産手続において、条文上は期間方式が原則とされており※5、裁判所は、必要があると認めるときは、期日方式を採用することもできるとされていますが(破産法第116条第1項、第2項)、実務では、定められた期間内に認否を行うことが容易でない場合に、期日方式であれば調査期日を柔軟に続行できること、配当の可能性がない事案で債権調査を留保する柔軟な運用ができること、債権者の手続保障及び情報配当の観点から管財人が選任される全件で債権者集会が開催されるので同日に債権調査期日も設定できること等に鑑み、基本的に期日方式が採用されています。
この点、中間取りまとめⅡでは、開始決定の時点では債権調査の方式としてどちらがふさわしいか決定し難い場合において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあるときには(破産法第31条第2項)、債権調査方式についての判断を留保して破産手続を開始し、その後、破産者の実態に関する調査や破産財団の換価が進み、債権調査及び配当の目途が立った段階で当該事案の性質にふさわしい債権調査手続の方式を決定するという運用(債権調査留保型)を行うことについて提言しています。そして、かかる手続進行は、債権者集会非招集型でかつ電子メールやwebサイトを利用した手続にもなじみやすいと指摘されています。
中間取りまとめⅡでは、破産債権届出をオンラインで行うことを可能にするシステム(以下「オンライン届出システム」といいます。)の具体的な検討をしています。ここでは現行法を前提とし、大規模破産事件でなく、一般的な規模の破産事件において全債権者が利用可能なシステムが前提とされており、具体的には、オンライン届出システムに債権届出の受付・管理、債権認否一覧表作成、配当用データの作成、債権者への各種通知、破産管財人による情報開示などの機能を持たせることが想定されています。
債権届出については、破産管財人から債権者に対し、システム利用に必要なID等の情報が送付され、債権者は当該情報を使ってシステムにログインし、届出事項等の必要情報を入力することで、債権届出手続を完了できるものと設計されています。このほか、届出事項の変更、名義変更等を可能にすることも想定されています。
なお、他人が届出債権者になりすましてログインすることを防止する方法として、届出債権者は初回ログイン時にパスワードを設定し、その後のログイン時にもその入力が求められること、届出事項の変更に際しては、登録したメールアドレスに変更等に必要な情報が送付されること、変更につき登録メールアドレスにメールが送信されることなどが提案されています。
2021年12月、「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会」において、倒産手続のIT化の検討状況を含む報告書が提出されました。そこで取り上げられている事項を幾つかご紹介します。
これに加えて、同月24日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」※6においては、法務省が「倒産手続における債権届出等、デジタル化の効果が大きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にかかわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討し、令和4年度(2022年度)に結論を得る」、「家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和5年(2023年)の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから、令和5年度(2023年度)以降、試行や先行運用を開始し、令和7年度(2025年度)以降、民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開始できるように環境整備に取り組む」等とされています。
倒産手続のIT化の議論はこれからさらに活発になっていくと思われ、今後、実務上各関係者が使いやすい制度を目指してより各論的・具体的議論が行われることになりますので、その議論の行方が注目されます。
※1
民事訴訟のIT化については、現在、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会で検討が進められています。
※2
弊事務所の小林信明弁護士、鐘ヶ江洋祐弁護士及び大川剛平弁護士は同研究会のメンバーです。
※3
同研究会は、民事訴訟のIT化の議論は倒産手続のIT化にも影響を及ぼし得ることから、脚注1の部会が公表した「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見も提出しました。
※5
民事再生手続、会社更生手続においては、債権調査の手続はいわゆる期間方式により行うこととされています(民事再生法第100条、会社更生法第145条)。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年5月)
酒井嘉彦


(2025年4月)
酒井嘉彦


酒井嘉彦
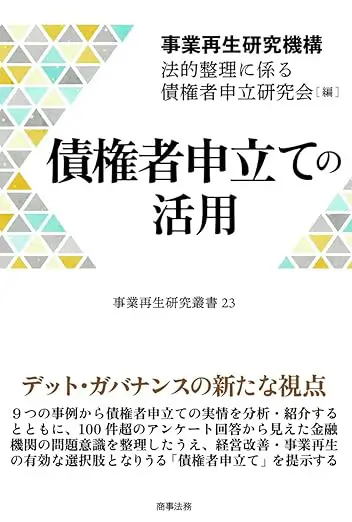
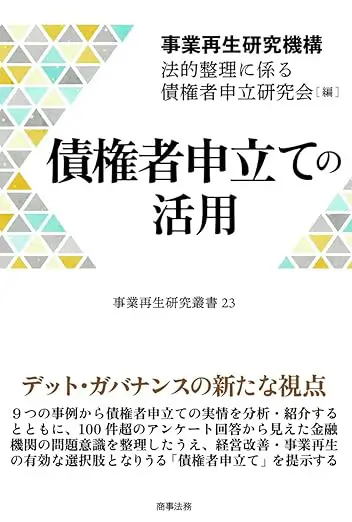
事業再生研究機構 法的整理に係る債権者申立研究会 (2025年3月)
小林信明、鐘ヶ江洋祐、大川友宏(共著)