
犬島伸能 Nobuyoshi Inujima
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
ドローン関係の話題としては、最近では、ウクライナの戦場における軍事利用など暗いュースが目立ちますが、他方でレベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)の実現に向けて日々行われている実証実験のニュースやドローンを活用した新しいサービス提供のニュースなど明るい話題を耳にする機会も増えてきています。
本稿においては、レベル4飛行の実現に向けた2021年改正航空法の施行日(2022年12月5日)が直前に迫ったこの時期に、改正のポイントについて改めて確認するとともに、誤解しやすいと思われる箇所について解説を行います。
(以下、特に断りのない限り、航空法及び航空法施行規制の条文番号は2021年改正航空法施行後のものを記載しています。)
2021年改正航空法の概要について解説する前に、それに先だち2020年改正航空法の施行が今年の6月20日に完了していますので、同改正法によって変更された点をまずおさらいしておきたいと思います。
まず、大前提として、航空法の適用を受けるドローンは、「無人航空機」の定義※1に該当するものに限られますが、2020年改正航空法によってその範囲が拡大されています。
従前は国土交通省令によって重量が200g未満のものは「無人航空機」の定義から除外されていました。しかしながら、技術の進歩により200g未満でも高性能で飛行速度の速い(=事故が重大なものとなりやすい)機体が増えてきたため、2020年改正航空法の施行日(2022年6月20日)からは除外される対象が重量が100g未満のもの(現行航空法施行規則第5条の2)に変更されました。これにより、「無人航空機」に該当する範囲が拡大され、従前より規制が強化されていますので注意が必要です。
100gというとマンガン単一乾電池程度の重さに過ぎないため、「無人航空機」の定義から除外されるのは主に軽量なホビー用ドローンなどに限られると思われます。産業用に用いようとするドローンについては、種々の機能を搭載する必要があるため、重量100g未満の除外要件を満たすことは難しく、一般的には「無人航空機」の定義に該当して航空法の適用を受けることになると思われます。※2
また、2020年改正航空法では、無人航空機の登録制度が新たに導入されたことが重要です。
無人航空機が広く活用されるようになると、それに伴う事故の発生も必然的に増えることになりますが、事故の際にそもそも所有者が分からなければ原因究明や再発防止策を採ることが困難です。また、そもそも安全上問題のある機体は飛行が許されるべきではありません。そこで、2020年改正航空法の下では、無人航空機を飛行させようとする場合、原則として※3、無人航空機の情報や所有者・使用者の氏名・住所等を申請して、無人航空機登録原簿に登録を受けなければならないこととなりました(現行航空法第131条の4,第131条の6)。
もし無人航空機登録原簿に登録を受けないまま無人航空機を飛行させてしまうと罰則(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)の対象となりますので、注意が必要です(現行航空法第157条の4)。
無人航空機登録原簿への登録が完了した場合、国土交通省から所有者に対して登録記号その他の登録事項が通知されます(現行航空法第131条の6第3項)。
通知を受けた所有者は、遅滞なく無人航空機に登録記号を表示するなど、無人航空機の登録記号を識別するための措置※4を講じなければならず(現行航空法第131条の7)、かかる措置を講じないまま無人航空機を飛行させた場合にはやはり罰則(五十万円以下の罰金)の対象となります(現行航空法第157条の6第1号)。
無人航空機登録原簿への登録は、3年毎に更新を行わなければ、効力を失います(現行航空法第131条の8第1項、現行航空法施行規則第236条の8第1項)。
さて、次に2022年12月5日に施行される2021年改正航空法についてポイントを解説します。2021年改正航空法においてはかなり大規模な改正が行われており、無人航空機に関する条文も改正前から格段に増えていますが、そのポイントとなるのは主に以下の3つです。
各々の改正ポイントについて概要を説明する前に、まず2021年改正航空法の背景にあるカテゴリー区分について説明します。
2021年改正航空法におけるカテゴリーとは、飛行のリスクの程度に応じてリスクが高い方からカテゴリーⅢ・Ⅱ・Ⅰという3つの区分を設けたもので※5、具体的には下記のとおりです。
2021年改正航空法においてはカテゴリー毎に異なる規制が設けられ、以下で説明する①機体認証・型式認証制度、②操縦者技能証明制度、③飛行禁止空域と飛行方法に関する規制の再構成のいずれの改正ポイントにおいても、この3つのカテゴリーを意識した制度設計が行われています。
2021年改正航空法においては、まず機体認証・型式認証制度が新たに創設されたことが重要です。
機体認証とは、申請を受けた国土交通大臣が、無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(安全基準)に適合するかどうかを設計、製造過程、及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めた場合に与える認証のことをいいます(航空法第132条の13第1項、第4項、航空法施行規則第236条の15)。
この機体認証では機体毎に検査が行われますが、大量に生産される量産機の場合、同一の設計・製造過程を経ているにもかかわらず、機体毎に検査しなければならないとするのは非効率です。他方で、量産される機体のうちある一機の安全基準への適合が認められたとしても、機体毎の性能にばらつきがあるのであれば、不十分です。
そこで機体認証制度と同時に設けられたのが型式認証制度です。
型式認証においては、機体毎の現状の検査は行われず、無人航空機の型式の設計及び製造過程に関し、安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(均一性基準)に適合するか否かが検査され、適合すると国土交通大臣が認めた場合に型式認証が与えられることになります(航空法第132条の16第1項、第3項、航空法施行規則第236条の24)。そして、型式認証を受けた者は、当該型式認証を受けた型式の無人航空機を製造するにあたっては、当該無人航空機がその型式認証に係る型式に適合するようにしなければならない義務を負い、また、個別の機体について自ら検査を行い、検査記録を作成して保存する義務を負うことになります(航空法第132条の18)。
上記安全基準及び均一性基準の内容は、航空法施行規則において概要が定められているとはいえ、依然として抽象的な内容にとどまります。そのため、各基準の具体的な内容を定める「無人飛行機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」が制定されており※7、機体認証及び型式認証においては同要領にしたがった検査が行われることとなります。また、同要領の安全基準及び均一性基準への適合性証明方法の事例、検査のポイント、検査側の関与度等、及び型式認証プロセスについてとりまとめた「無人航空機の型式認証等の取得のためのガイドライン」※8の制定も予定されています。
誤解しやすい点ですが、型式認証は機体認証に代わるものではなく、型式認証を受ければ機体認証を得るプロセスが不要となるわけではありません。量産機については、設計・製造者がまず設計及び製造過程について型式認証を受け、その後量産された機体を購入した使用者等が機体認証を受けるという流れが想定されています。ただし、設計及び製造過程については型式認証を受ける際に既に安全基準への適合性が確認されているため、機体認証における国の検査においては検査の全部又は一部を省略することが可能となっているほか(航空法第132条の13第5項第1号、第6項第1号)、機体認証申請書の添付書類も、型式認証を受けた型式の無人航空機に関しては大幅に簡略化されています(航空法施行規則第236条の12第2項)。
このように、型式認証を受けている無人航空機についてはユーザー側での機体認証の負担が軽減されるため、量産機については型式認証を受けたものが販売されることが一般的になるものと思われます。
機体認証と型式認証は、無人航空機が想定している飛行形態に応じて、いずれも第一種と第二種に区分されています(航空法第132条の13第2項、第132条の16第2項)。
カテゴリーⅢの飛行を行うことを目的とする機体には第一種機体認証(あるいは第一種型式認証+第一種機体認証)が必要となります。
また、カテゴリーⅡの飛行を行うことを目的とする場合にも、第二種機体認証(あるいは第二種型式認証+第二種機体認証)以上を得ることによって、個別の許可・承認が不要となったり(航空法第132条の85第1項・第3項、第132条の86第2項・第4項)、あるいは個別の許可・承認において検査が簡略化されるといったメリットを受けることができます。
カテゴリーⅠの飛行を行うことを目的とする場合には、機体認証・型式認証は不要です。
機体認証及び型式認証の検査事務につき、国土交通大臣は、登録を受けた者(登録検査機関)にその全部又は一部を行わせることができます(航空法第132条の24)※9。第一種機体認証及び型式認証については当面国が行い、第二種機体認証及び型式認証に関する検査は基本的に登録検査機関が検査事務を行います。
2021年改正航空法においては、上述した機体認証・型式認証制度とともに、操縦者技能証明制度が創設されました。
操縦者技能証明とは、無人航空機を飛行させるのに必要な技能について、申請により国土交通大臣が証明するものです(航空法第132条の40)。
操縦者技能証明についても、想定している飛行形態に応じて必要となる技能のレベルが異なるため、機体認証・型式認証制度と同様に一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の二種類の資格が設けられています(航空法第132条の42)。
カテゴリーⅢの飛行に必要な技能があることを証明するのが一等無人航空機操縦士の資格、カテゴリーⅡの飛行に必要な技能があることを証明するのが二等無人航空機操縦士の資格となります。
操縦者技能証明を得ようとする者は、取得したい資格(一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士)について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定してもらうために、試験(身体検査、学科試験及び実地試験)を受けて合格する必要があります(航空法第132条の47)。
かかる試験の運営については、国土交通大臣は、申請により指定する者(指定試験機関)に、試験の実施に関する事務(試験事務)を行わせることができるとされており(航空法第132条の56)、実施体制や経理的基礎等の要件を満たす民間機関が全国で1社指定されることが予定されています 。※10
また、施設及び設備、講師に係る要件を満たす機関として国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行う講習(無人航空機講習)を修了した者については、実地試験の全部が免除される予定です(航空法第132条の50)※11。なお、航空法第132条の50では「学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる」と規定されているため、学科試験の免除も法律上は可能ですが、登録講習機関の講習により学科試験に合格する水準の知識及び能力が習得できているかの確認が現時点では困難なため、少なくとも当面は行われない模様です。
操縦者技能証明制度が導入される前の現時点においても、多数の民間の講習団体が存在し、操縦技術や安全意識の向上に大きく貢献してきました。これらの民間の講習団体のうち、講習での飛行時間等を確認して一定の要件を満たすものについては航空局のホームページ※12に掲載され(「HP掲載講習団体」)、HP掲載講習団体の講習修了者は、現行の特定の飛行空域・飛行方法における許可・承認制度の運用においては、審査の簡略化というメリットを受けることができました。国による操縦者技能証明制度が2022年12月5日に開始された後は、同制度への一元化を図るために、新たなHP掲載講習団体の掲載は原則として停止され、その後一定の期間を経たのち、上記許可・承認の審査簡略化の運用も廃止される予定です。他方で、民間の講習団体から既に民間技能認証を取得している者等既に一定の経験を有している者については、当該経験が評価され、登録講習機関における講習時間の減免が認められる予定です。※13
操縦者技能証明制度の概要は上記のとおりですが、大まかなイメージとしては、全般的に自動車における運転免許制度に似た制度ということができるでしょう。
原則として飛行が禁止される空域と禁止される飛行方法については、現行の航空法(現行航空法第132条第1項、第132条の2第1項)と2021年改正航空法(第132条の85第1項、第132条の86第1項・第2項)で基本的に違いはありません。
他方、許可や承認が必要となる場面については、現行法では比較的シンプルであったのが、2021年改正航空法においては、上述のとおり、飛行のリスクの程度に応じてカテゴリーⅢ・Ⅱ・Ⅰという3つのカテゴリーに区分され、カテゴリー毎に異なる規制が設けられることとなったため、少々複雑な条文構成になっています。
カテゴリー毎の規制の概要をまとめると、下記図のとおりとなります。
【現行航空法における規制】
| 飛行の空域 | 飛行の方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132条第1項 | 132条の2第1項 | ||||||
| 1号 | 2号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 |
| 空港周辺・150m以上 | 人口集中地区(DID) | 夜間 | 目視外 | 人・物件30m未満 | イベント上空 | 危険物輸送 | 物件投下 |
| 飛行毎に許可・承認が必要 | |||||||
【2021年改正航空法における規制】
| 飛行の空域 | 飛行の方法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132条の85第1項 | 132条の86第2項 | |||||||||
| 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | |||
| 空港周辺・150m以上 | 人口集中地区(DID) | 夜間 | 目視外 | 人・物件30m未満 | イベント上空 | 危険物輸送 | 物件投下 | |||
|
カテゴリーⅢ 立入管理措置を講じない飛行(=第三者上空の飛行) |
機体認証(第一種)・操縦者技能証明(一等)の取得が必要 | 飛行毎に許可・承認が必要 | ||||||||
|
カテゴリーⅡ 立入管理措置を講じる飛行(=第三者上空以外の飛行) |
機体認証(第二種以上)・操縦者技能証明(二等以上)を取得する場合 | 総重量25kg以上 | 飛行毎に許可・承認が必要(但し、審査は簡略化可) | |||||||
| 総重量25kg※14未満 | 飛行毎に許可・承認が必要(但し、審査は簡略化可) | 飛行毎の許可・承認は不要 |
飛行毎に許可・承認が必要 (但し、審査は簡略化可) |
|||||||
| 機体認証・操縦者技能証明を取得しない場合 | 飛行毎に許可・承認が必要 | |||||||||
| カテゴリーⅠ | 機体認証・操縦者技能証明の取得は不要 | (飛行の空域、飛行の方法がこれらに該当しないため、許可・承認は不要) | ||||||||
(出典)国土交通省資料(前出の2021年3月に公表された「中間とりまとめ」)を参考に筆者らが作成
カテゴリー毎の規制のポイントは下記のとおりです。誤解しやすい点ですが、上記図からもお分かりのとおり、機体認証や操縦者技能証明は、無人飛行機を飛行させようとする場合に必ず必要となる(ただし、試験飛行等の例外あり)登録制度とは異なり、どのような飛行においても必ず必要というわけではありません。
今回のニュースレターでは、2021年改正航空法の施行日(2022年12月5日)が近づく中、改正のポイントについておさらいさせていただきました。
2021年改正航空法の関係では、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領について、11月9日付けで「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正されており※15、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」についても本稿執筆時点においてパブリックコメントに付されていますので※16、引き続き注意が必要です。この新しい審査要領についても、改めて情報提供させていただく予定です。
※1
「無人航空機」は、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」と定義されています(現行航空法第2条第22項)。
※2
最近ドローンと並んで話題に上ることの多い、いわゆる「空飛ぶ車」については、人が乗ることを前提としているため「無人航空機」には該当しません。ただし、「航空機」として航空法の適用を受けるため、ドローンよりもより厳しい規制に服することになります。
※3
例外として、一定の要件を満たした試験飛行の場合には登録義務が免除されていますが、その場合でも氏名、住所、連絡先、試験飛行の目的等につきあらかじめ国土交通大臣に届け出る必要があります(現行航空法第131条の4但書,現行航空法施行規則第236条)。
※4
原則として、①機体への物理的な表示と②リモートID機能(登録記号を識別するための信号を電波を利用して送信することにより、当該電波を受信可能な通信端末機器を使用する者による登録無人航空機の識別を当該登録無人航空機の飛行中常時可能とする機能)の具備の両方が求められています(現行航空法施行規則第236条の6)。
※5
なお、このカテゴリー区分は、2021年改正航空法の成立に向けて国土交通省交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会 の下に設置された「無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会」が2021年3月に公表した「中間とりまとめ」において導入された概念です。2021年改正航空法はこのカテゴリー区分を意識した条文構成となっていますが、2021年改正航空法の中でこれらの用語が直接使用されているわけではありません。
※6
2021年改正航空法において実現の道が拓けたレベル4飛行はここに該当します。
※8
「第1部 共通」及び「第3部 安全基準について」:
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221229&Mode=0
「第2部 型式認証プロセス」及び「第4部 均一性基準について」:
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221245&Mode=0
※9
登録の申請、検査事務の実施基準等の詳細については、「無人航空機登録検査機関に関する省令」
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800057_20221205_000000000000000)において定められています。
※10
指定検査機関にかかる指定の申請、基準等の詳細については、「無人航空機操縦士試験機関に関する省令」
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800058_20221205_000000000000000)において定められています。
※11
登録講習機関にかかる登録の手続、無人航空機講習事務の実施基準等の詳細については、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504M60000800059_20221205_000000000000000)において定められています。
※13
経済産業省と国土交通省が合同で開催する「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」が2022年4月に公表した「とりまとめ」21頁(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478581.pdf)をご参照ください。
※14
航空法施行規則第236条の73
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(監修)、水越政輝、松﨑由晃(共著)


犬島伸能、中村彰男(共著)
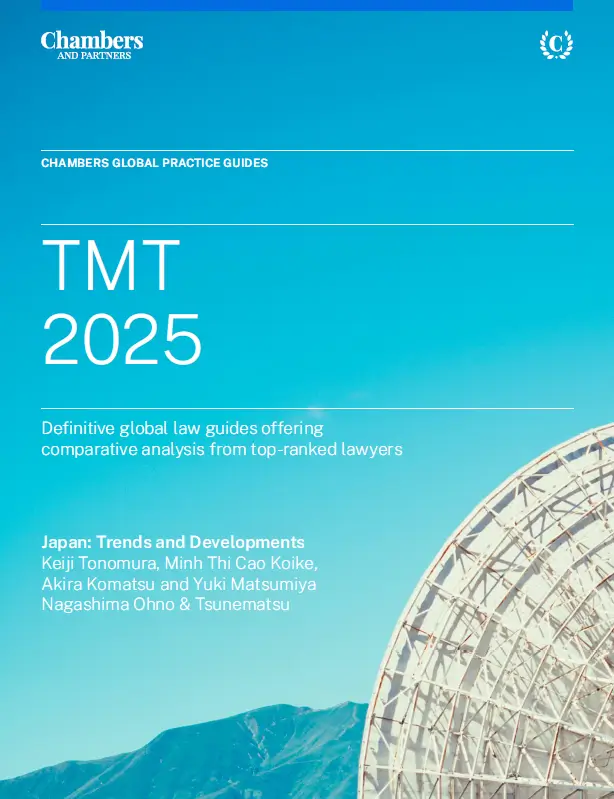
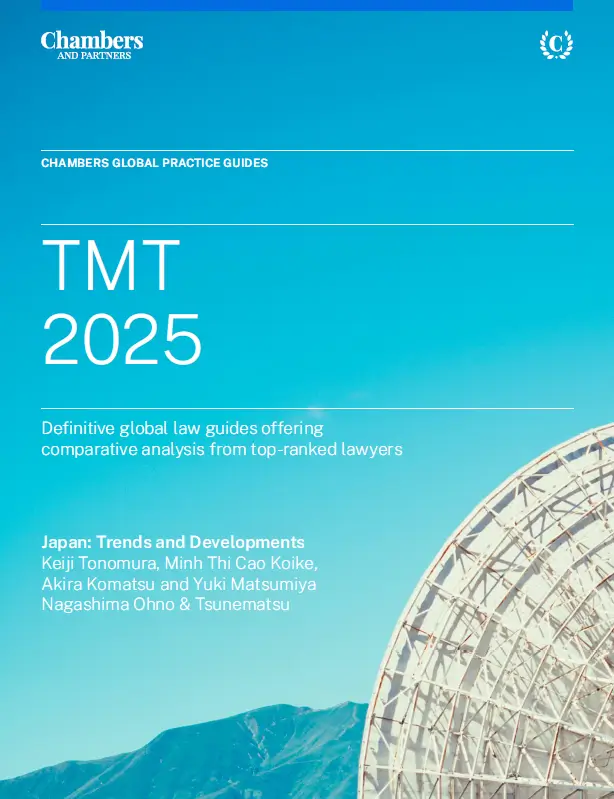
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


(2024年5月)
水越政輝、小松諒(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)