
ジャスティン・イー Justin Ee
パートナー
シンガポール

NO&T Dispute Resolution Update 紛争解決ニュースレター
本ニュースレターは、「全文ダウンロード(PDF)」より日英併記にてご覧いただけます。シンガポール・オフィスの紛争解決チームについてPDF内にてご紹介しております。
シンガポール最上級審たる上訴裁判所の2023年最初の公表された判決、Anupam Mittal v Westbridge Ventures II Investment Holdings [2023] SGCA 1 (以下「Westbridge判決」という)は、契約の相手方との紛争を仲裁によって解決しようと考える当事者にとって重要な論点についての判断を示した。裁判所は、紛争の仲裁可能性(仲裁による解決が可能かどうか)に適用される法は仲裁合意の準拠法であると判示した。
紛争の仲裁可能性の判断基準はシンガポールにおいては既に確立されている。当事者が仲裁に付託することに合意した紛争は基本的になんでも仲裁による解決の対象となるが、①問題となる紛争について仲裁による解決を許すと公序に反する場合、又は②法律若しくは立法過程によれば問題となる紛争の仲裁による解決が敢えて許されていない場合には、例外として仲裁可能性が否定される。
他方、仲裁判断前における仲裁可能性の適用法の問題という、一見すると些末な、しかし実は重要な前提問題について、シンガポールでは決定的な解がない状況が続いていた。①仲裁地法、②仲裁合意の準拠法、③主たる契約の準拠法、又は④法廷地法(事件が係属する裁判地の法)といった選択肢があり得る。
Westbridge判決によってようやくこの点の解釈が確立した。上訴裁判所は、仲裁判断前の仲裁可能性の適用法は仲裁合意の準拠法であると判示したのである。
上訴人(インド居住者)と被上訴人(モーリシャス籍の会社)は、ともにインド籍の会社の株主であり、シンガポールを仲裁地とする仲裁に付託する次の紛争解決条項を含む株主間契約を締結した。
“20 準拠法及び仲裁
20.1 本契約とその履行については、インド法を準拠法とし、全ての局面において同法による解釈がなされるものとする。当該会社の経営又は本契約に規定される事項全てに関する紛争が生じた場合、当該紛争の当事者は、紛争を解決するための誠実交渉を行うために自身の指名する者又は代理人を選任する。30暦日以内に解決に至らなかった場合、当該紛争は下記20.2項に従って仲裁に付託されることとする。
20.2 第20.1項によって満足的解決に至らなかった全ての紛争を、両当事者が共同で選任する仲裁人1名が執り行う仲裁に付託する。[中略]仲裁手続は国際商業会議所(International Chamber of Commerce, ICC)の制定する規則に従うこととし、仲裁地はシンガポールとする。[後略]”(下線強調追加)
数年後、株主間の関係が悪化した。2021年3月3日、上訴人が被上訴人(及びその他株主)に対して、インドの会社法審判所(National Company Law Tribunal, NCLT)において少数株主の抑圧と不適切経営に対する措置として法的紛争手続を開始した。
2021年3月15日、被上訴人は、シンガポール高等裁判所において上訴人に対する(インド会社法審判所における)訴訟の差止の仮処分を得た。この仮処分の前提となっていたのは、当事者間の紛争を仲裁に付託する合意が存在するにもかかわらず上訴人がインドの法的手続を開始したことを理由とする仲裁合意違反であった。2021年10月26日、シンガポール高等裁判所は、上訴人に対してインドの法的手続の遂行を禁ずる無期限の訴訟差止命令を出し、その理由として、①仲裁判断前の仲裁可能性の適用法は仲裁地法(すなわちシンガポール法)であり、②シンガポール法の下では当該紛争は仲裁により解決可能であると判示した。
上訴人は、高等裁判所の決定について上訴裁判所に対して上訴を行った。
上訴人の主張は、①インドの法的手続の審理対象(少数株主の抑圧と不適切経営)についての仲裁可能性の適用法は仲裁合意の準拠法(すなわち上訴人の主張においてはインド法)であり、②インド法の下では、当該紛争につきインド会社法審判所が専属管轄を有するので仲裁による解決は許されず、仲裁合意違反はない、というものであった。
被上訴人の主張は、①仲裁可能性の適用法は仲裁地法(すなわちシンガポール法)であり、②仮に上訴人が主張するように仲裁可能性の適用法が仲裁合意の準拠法であったとしても、当該仲裁合意の準拠法はインド法ではなくシンガポール法であり、インドの法的手続の審理対象はシンガポール法の下では仲裁によって解決可能である、というものであった。
上訴裁判所は仲裁合意の準拠法が仲裁判断前の仲裁可能性の適用法になると判断し、その理由として次のものを挙げた。
① 仲裁可能性の有無の重要な要素は、問題となる紛争の対象が仲裁で解決される場合に本質的に公序に反することとなるかという点である。これは、シンガポール国際仲裁法第11条(1)の「問題となる紛争について仲裁による解決を許すと公序に反することとなる場合を除いて当事者が仲裁に付託することに合意した紛争は仲裁による解決の対象となる」との規定から導かれる。この文脈における「公序」という用語はシンガポールの公序に限定されるものではなく、その他の国の公序をも指す。したがって、仲裁合意の下発生した紛争を裁定することがシンガポールの公序のみならず問題となる他の国の公序に反する場合には、当該紛争はシンガポールにおいて仲裁に付託することはできない。
② 仲裁合意の効力の根拠は当事者の合意にある。そしてそれが仲裁廷の管轄の基礎となる。したがって、仲裁合意及び仲裁合意の準拠法によって、当事者が何を仲裁に付託したかということが決定されるべきである。仲裁地法は手続を規制するものである。他方、仲裁合意の準拠法は仲裁合意の有効性を決するものであり、その観点からは仲裁手続の実施に先立つものである。
③ したがって、仲裁判断前の仲裁可能性は仲裁合意の準拠法によって決せられることとなる。もしそれが外国法であり、当該外国法によれば問題となる紛争の対象は仲裁による解決が不能とされる場合、シンガポール裁判所は仲裁の遂行を許容しない。なぜならそのような仲裁合意に効力を与えることは公序(この場合は外国の公序)に反することとなるからである。さらに、シンガポール国際仲裁法第11条(1)により、仲裁合意の準拠法によればある紛争が仲裁による解決可能であるものの仲裁地法たるシンガポール法によれば当該紛争は仲裁不可とされる場合、やはり仲裁の遂行は許されない。両方の場合において、仲裁の実施を許容すれば公序に反することとなる。
換言すれば、ある紛争は①仲裁合意の準拠法、及び②仲裁地法両方によって許容されている場合にのみ仲裁による解決が可能となる。この点は非常に重要である。仲裁合意の当事者が契約に至る段階でいかなる紛争が仲裁可能(又は不可能)かということについて確度を確保したいと考える場合、仲裁合意の準拠法を明示的に規定するだけでは不十分であることとなる。特定の仲裁地、ひいては仲裁地法の選択によって、仲裁合意に関して想定する紛争の仲裁可能性が認められるかどうかということを当事者は考慮しなければならない。
次に、上訴裁判所は仲裁合意の準拠法はインド法ではなくシンガポール法であると判示した。その際、裁判所は、BCY v BCZ [2017] 3 SLR 357において高等裁判所が示した3段階テストを適用した。上訴裁判所の分析は次のとおりである。
① 3段階テストにおいては次の3つを考慮することとなる。
(a) 第1段階:仲裁合意の準拠法を当事者が明示的に選択しているかどうか。
(b) 第2段階:明示的な選択がなされていない場合、当事者が黙示的に仲裁合意の準拠法を選択しているかどうか。その際、契約の準拠法が黙示の選択に関する最初の足がかりとなる。
(c) 第3段階:明示、黙示の選択双方がない場合、仲裁合意の最密接関連地法はどの国の法か。
② 第1段階:本件の当事者は仲裁合意の準拠法を明示的に選択していない。株主間契約第20.1項の文言は仲裁合意の準拠法を明示的に選択しているものとはいえない。第20.1項は「[株主間]契約とその履行」の「全ての局面において」の準拠法をインド法と規定するが、これは仲裁合意の準拠法を選択するものとはいえない。当該条項が主たる契約の一部であったとしてもである。仲裁合意の準拠法の選択はその旨の明確な文言がある場合にのみなされていることとなる。
③ 第2段階:仲裁合意の準拠法の黙示の選択は認定できない。原則論として、契約の準拠法(本件の場合はインド法)は仲裁合意の準拠法を強く示唆することから、その黙示の選択認定の鍵となる。この原則の例外となるのは、それと相反する示唆がある場合である。特に、黙示の選択を無効化するような条件が認められ、仲裁合意の準拠法として契約の準拠法を選択すれば、当事者が紛争を仲裁に付託することに明確に合意したにもかかわらず仲裁合意の存在意義が失われるような場合は上記例外にあたる。
④ 本件では株主間契約第20.1項によれば当事者が全ての紛争を仲裁に付託することを意図していたことは明らかである。しかし、この意図は仲裁合意の準拠法としてインド法を黙示に選択することと相容れない。なぜならインドにおいて少数株主の抑圧に関する請求を仲裁によって解決することは許容されておらず、インド法を黙示に選択したと認定すれば仲裁合意の存在意義が失われるからである。本件においては、株主間契約において仲裁合意に適用のある法としてインド法が意図されていたという推論は、全ての紛争を仲裁に付託するという当事者の意図と相容れないため、そのような推論を打ち消すだけの反対の示唆が十分に認められるといえる。
⑤ 第3段階:株主間契約第20.2項によればシンガポールが仲裁地とされる。仲裁地法たるシンガポール法が、仲裁廷の忌避事由や管轄権さらにはいずれ出される仲裁判断に関する紛争を含む仲裁手続に適用されることとなる。したがって、シンガポール法が仲裁合意の準拠法である。
紛争解決条項は契約交渉最終段階(深夜になることも多い)まで真剣に検討されることなくその対処を先延ばしにされることがあるため「真夜中の条項(midnight clause)」とも呼ばれる。しかし、Westbridge判決(及びその他仲裁関連の先例)によれば、仲裁合意条項は極めて重要かつ技術的であり、紛争が生じた際の紛争解決手続とフォーラムに関して当事者の意図を超える意味を持つことがある。
そのため、契約交渉において紛争解決条項を適切に検討し言語化することが肝要であり、将来の確度を高めつつ、当該条項が潜在的な紛争解決のあり方についての当事者の元々の意図や期待に沿うようにしておく必要がある。仲裁に関する不確実性を減らす観点からは、慎重を期し、仲裁地と仲裁機関を指定する以外に、(契約の準拠法に加えて)仲裁合意の準拠法を明示的に選択することが賢明な対応となり得る。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年5月)
小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
壱岐祐哉(講演録)


東崎賢治、平山貴仁(共著)


(2025年5月)
小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)


梶原啓


(2025年4月)
杉本花織
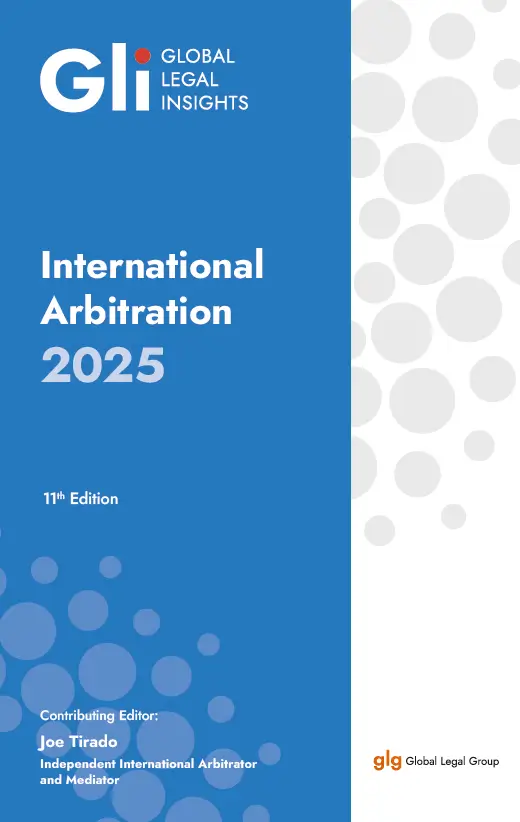
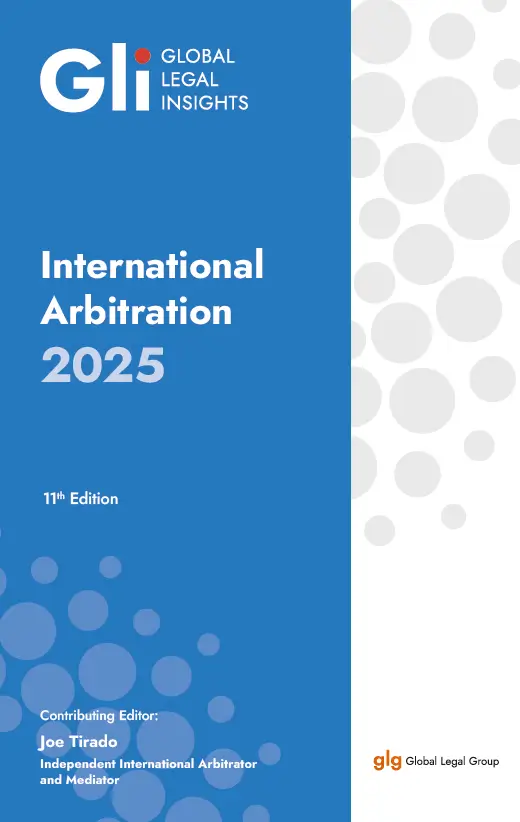
(2025年4月)
杉本花織、戸田祥太、室憲之介(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


井上皓子


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


井上皓子


長谷川良和


(2025年6月)
佐々木将平


(2025年5月)
福井信雄、山内建人(共著)


(2025年5月)
松﨑景子


(2025年5月)
酒井嘉彦


福井信雄、山内建人(共著)