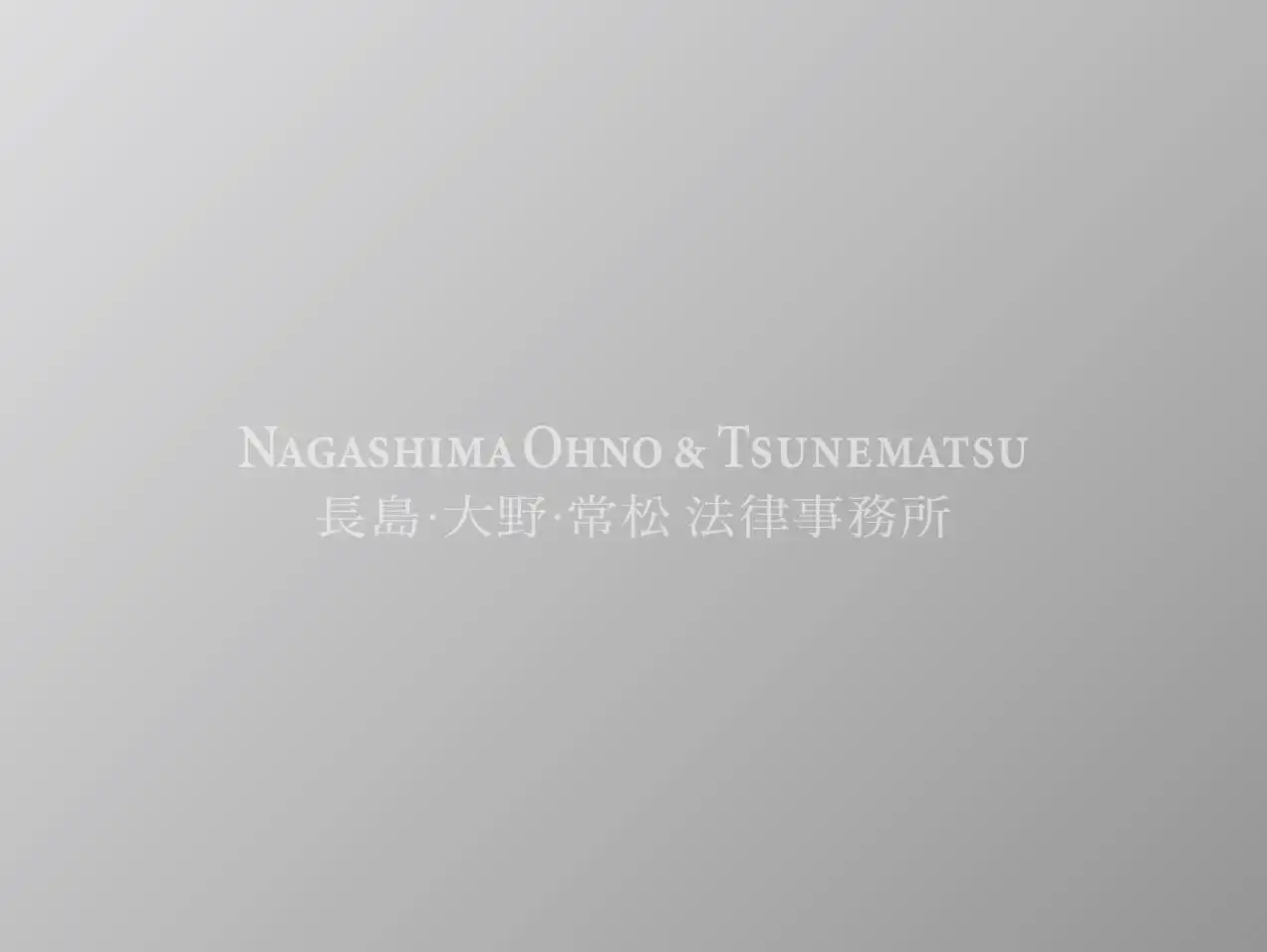
水野大 Ohki Mizuno
パートナー
東京

NO&T Finance Law Update 金融かわら版
ニュースレター
担保法制の見直しに関する中間試案①
「金融かわら版~担保法制の見直しに関する中間試案①~」においては、法制審議会担保法制部会(以下、「担保法制部会」といいます。)の2022年12月6日の第29回会議において取りまとめられた「担保法制の見直しに関する中間試案」(以下、「中間試案」といいます。)の第1章「担保権の効力」及び第2章「担保権の対抗要件及び優劣関係」につき、中間試案とともに公表された担保法制の見直しに関する中間試案の補足説明(以下、「補足説明」といいます。)や、その後に公表された担保法制部会資料等も踏まえて、特に金融実務の観点から重要と思われる点を中心に紹介いたしました。本稿では、それに引き続き、中間試案の第3章「担保権の実行」、第4章「担保権の倒産手続における取扱い」及び第5章「その他」のうち、金融実務及び倒産実務の観点から重要と考えられる項目を紹介します。
現行法上、個別動産を目的とする動産譲渡担保については、通常、担保契約書において実行方法が定められ、その定めに従って実行されること(いわゆる私的実行)が想定されています。具体的には、担保契約書において、(i)動産譲渡担保権者が目的となる個別動産を自己に帰属させて被担保債権の弁済に充てる方法(帰属清算方式)又は(ii)動産譲渡担保権者が目的となる個別動産を処分しその処分代金を被担保債権の弁済に充てる方法(処分清算方式)が担保権の実行方法として定められ、かつ、動産譲渡担保権者がいずれかの方法によって担保権を実行できる旨が定められることが通常です。個別動産を目的とする動産譲渡担保について、民事執行法第190条以下の規定による動産競売の方法での担保実行が可能であるか否かについては見解が分かれていますが、実際に民事執行法に基づく競売が選択されることは一般的ではないように見受けられます。
中間試案では、個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の実行について、以下の方法のうち担保権者が選択したものによって行うこととしています(中間試案第8の1)。
① 帰属清算方式
② 処分清算方式
③ 民事執行法第190条以下の規定に基づく競売
個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の実行方法として上記の3つが存在することに関しては、個別動産を目的とする動産譲渡担保に関する現在の実務との比較において、民事執行法第190条以下の規定に基づく競売による担保実行が可能である旨が明確になっている点以外は、特段目新しい点はないように思われます。他方、中間試案においては、個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の私的実行の手続について、詳細なルールが提案されているところ、そのルールについては、個別動産を目的とする動産譲渡担保に関する現在の実務との比較において、目新しい項目又は留意すべき項目が存在するように思われます。以下、それらの項目について述べます。
中間試案では、個別動産を目的とする新たな規定に係る担保権の私的実行をする場合、被担保債権の不履行があった後、私的実行に先立ち、私的実行をする旨及び被担保債権の金額を通知する必要があり、その到達から1週間経過後に目的物を帰属させたり処分したりする権限を取得するという案(中間試案第8の2における【案8.2.1】)が提案されていました。個別動産を目的とする動産譲渡担保に関する現在の実務において、このような事前の実行通知及び1週間の猶予期間が担保契約において定められることは一般的ではないように見受けられ、このような案が強行法規として明文化された場合、実務に及ぼす影響は小さくないと予想されます。しかしながら、中間試案後に公表された担保法制部会資料30(以下、担保法制部会資料を引用する際は、単に「部会資料」といいます。)では、そのような実行通知を義務づけることや画一的に1週間の猶予期間を設けることの必要性や相当性が疑問視された結果として、被担保債権について不履行があれば、実行通知及び猶予期間なしで、担保権者が目的物を自己に帰属させたり目的物を処分したりする権限を取得することができる旨の案(中間試案第8の2における【案8.2.2】)が採用されています(部会資料30第6の2)。私的実行前の事前通知を義務づけるか、事前通知到達後の猶予期間を設けるか(設けるとしてどの程度の期間とするか)は、担保権者と設定者の間の合意で定めれば足り、強行法規として画一的なルールを定めることによって弊害が生じるおそれがあることからすれば、この方向性は適切なものであると考えられます。
中間試案では、担保権者が帰属清算方式による私的実行をしようとする場合、設定者に対し、目的物の所有権を担保権者に帰属させる旨、被担保債権の額、担保権者が評価した目的物の価額及びその算定根拠の通知(以下、「帰属清算の通知」といいます。)をしなければならず、担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、帰属清算の通知に加えてその差額の支払又はその提供(以下、「清算金の提供等」といいます。)をしなければならないとされています(中間試案第8の3)。この点については特に異論がないところだと思われます。
論点となるのは、(i)被担保債権の消滅時期を帰属清算の通知及び清算金の提供等の時点とするのか、帰属清算の通知及び清算金の提供等の時点から一定期間が経過した時点とするのか(中間試案第8の3の(注1))、(ii)被担保債権が消滅した後においても、担保権者に対して目的物を引き渡すまでの間、設定者が、被担保債権が消滅しなかったとすれば支払うべき金額を支払うことにより目的物を受け戻すことができるものとするのか(中間試案第8の3の(注2))、(iii)担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をした場合において、設定者に対し目的物の引渡しを請求するとき、引換給付の関係に立つ支払債務の額を(a)担保権者が通知した目的物の評価額と被担保債権額の差額又は(b)目的物の客観的な価額と被担保債権額の差額のいずれとすべきか(中間試案第8の3の【案8.3.1】(4)と【案8.3.2】(2))の3点であり、今後の議論の展開を注視する必要があると思われます(部会資料30第6の3において若干のアップデートがありますが、基本的な論点の所在は変わりありません。)。
中間試案では、担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、被担保債権は、その処分時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅するとされています(中間試案第8の4)。ここでいう「処分」とは譲渡を指すことが部会資料30第6の4(1)において明らかにされています。現在の実務では、動産譲渡担保契約において、債務者が被担保債務を履行しない場合は担保権者が合理的な方法で目的物を第三者に売却することができ、このとき、売却価額をもって被担保債権が消滅する旨が定められることが多いように見受けられるところ、中間試案は、売却価額ではなく(売却代金と必ずしも一致するとは限らない)目的物の客観的な価額の範囲で被担保債権が消滅するとされている点に留意が必要です。
担保権者は、目的物を第三者に処分(譲渡)した場合、遅滞なく、設定者に対し、次に掲げる事項を通知しなければなりません(部会資料30第6の4(2))。
① 目的物を第三者に譲渡したこと
② 譲渡時の目的物の見積価額
③ 譲渡時の被担保債権の額
④ 上記②の見積価額の算定根拠
担保権者は、譲渡時の目的物の客観的な価額が被担保債権の額を超える場合は、その超過額を設定者に支払う義務を負います。設定者に対し担保権者又は譲受人が目的物の引渡しを請求するとき、引換給付の関係に立つ支払債務の額を(a)担保権者が通知した目的物の見積額と被担保債権額の差額又は(b)目的物の客観的な価額と被担保債権額の差額のいずれとすべきかについては、引き続き論点として議論されています(部会資料30第6の4(4))。
「金融かわら版~担保法制の見直しに関する中間試案①~」において紹介したとおり、中間試案では、新たな規定に係る動産担保権は集合動産を目的とすることができるものとするとされています(中間試案第3の1及び2)。集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権について、実行方法として帰属清算方式、処分清算方式及び民事執行法第190条以下の規定に基づく競売が認められる点は、個別動産を目的とする場合と同じです(中間試案の補足説明112頁参照)。
中間試案では、集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権の私的実行をする場合、被担保債権の不履行があった後、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)又は第三者に目的物を処分(譲渡)する旨の通知をする必要があるとされています(中間試案第11の1)。この通知が設定者に到達した場合、到達後に集合動産に加入した動産に担保権の効力は及ばないことになり、かつ、設定者は、集合動産の構成部分である動産の処分権限を失うことになります。この通知の後、新たに特定範囲に加入した動産に担保権の効力が及ぶ旨の担保権者と設定者の間の特約が有効であるか否か(いわゆる再度実行の可否)は論点ですが、部会資料30第1の6では、そのような特約が無効であるとされています。なお、設定者に倒産手続が開始した場合の集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権の効力については、後述の「倒産手続における取扱い」をご参照ください。
私的実行をする旨の通知の効果は、上記2.のとおりであり、この効果は、原則として集合動産全体について及びます。但し、担保権者がその集合動産譲渡担保権の特定範囲のうち種類、所在場所、量的範囲の指定その他の方法により特定された範囲を実行の対象として指定したときは、その範囲にのみ効果が生ずるものとされています(中間試案第11の3及び部会資料30第1の7)。
中間試案では、倒産手続における制限について、新たな規定に係る担保権は、他の担保権と同様、更生手続においては更生担保権として扱われ、破産手続及び再生手続においては別除権と扱われることになっています(中間試案第16)。その上で、倒産手続における担保権の実行制限として、中間試案では以下のとおり整理されています(中間試案第17)。
① 中止命令:譲渡担保、所有権留保等の非典型担保についても現行法の担保権実行手続中止命令(民事再生法第31条、会社更生法第24条)が適用されるという見解が支配的ですが、中間試案では、新たな規定に係る担保権についても中止命令の対象とされています。中間試案における中止命令は、後述の禁止命令・取消命令とは概念的に別個の命令と整理されており、「既に担保権の実行に着手しているが、実行手続がまだ終了していない」という状況に対応するもの(実行手続中の担保権の実行を止める命令)です。なお、現行法の中止命令は担保権の実行の着手前であっても発令できますが、中間試案では、実行の着手前時点での命令は後述の禁止命令とする、という概念的な整理がされています。
② 禁止命令:新たな規定に係る担保権の実行は短期間で終了する可能性があり、また、実行されてしまうと設定者の円滑な事業継続が困難になることから、中間試案では、担保権の実行に着手する前の時点で担保権実行をそもそも禁じる措置として、禁止命令が提案されています。禁止命令の要件は、現行法の中止命令の要件と同一とすることが想定されています。そして、新たな規定に係る担保権の私的実行については、中止命令及び禁止命令ともに、発令できる時限は被担保債権が消滅する時点までとされています。
③ 取消命令:中間試案では、新たな規定に係る集合動産担保権の実行通知がなされると、設定者は集合動産の構成部分である動産の処分権限を失うとされています。中止命令は、あくまで担保権の実行手続を現状のまま凍結させて、それ以上に進行させない効果を有するだけですので、設定者の処分権限は回復しません。債権譲渡担保も同様であり、いったん失われた設定者の取立権限が回復するものではないと考えられます。設定者が動産の処分権限や債権の取立権限を失った後に中止命令が発令されても、設定者の下で動産や債権の資金化はできず、設定者の事業継続は事実上困難となります。そこで、中間試案では、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがないときは、新たな規定に係る集合動産担保権の場合には実行通知の効力(処分権限の喪失)を取り消し、集合債権を目的とする担保権の場合には取立権限の付与の解除を取り消すことができる「取消命令」が提案されています。取消命令も、中止命令や禁止命令と同様、別除権協定の締結のための時間的余裕を得るためのものですので、発令できる時限は被担保債権が消滅する時点までと解されます。
現在の判例法理上も、事業再生を図るという再建型手続の趣旨に照らして、所有権留保売買やファイナンス・リース契約における、設定者について再建型手続(再生手続又は更生手続)の開始申立てがあった場合に解除権の効果を発生させる旨の特約(倒産手続開始申立特約)は無効と解されています(最判昭和57年3月30日、最判平成20年12月16日)。かかる判例法理の趣旨に照らすと、設定者に担保目的物について中止命令等や消滅許可といった対応をする機会が与えられずに設定者の責任財産から担保目的物を逸出させることになる契約条項の効力は否定すべきですので、中間試案では、再建型手続(再生手続又は更生手続)の開始申立てを理由に新たな規定に係る担保権の目的物を設定者に属しないものとし、又は属しないものとする権利を担保権者に与える契約条項は無効とすることが提案されています。ただし、これは、再建型手続の開始申立てに直接の効力(解除等)を付与する条項の効力を否定するものであり、このような申立てを期限の利益喪失事由として、それに伴う債務不履行を理由に解除等を行うことを妨げるものではありません。
なお、再建型手続(再生手続又は更生手続)の開始申立てを理由に、設定者が動産の処分権限又は債権の取立権限を喪失する旨の条項を無効とする規定を設けるべきかについては、かかる条項の効力について判例法理が確立しているわけではないことも踏まえ、中間試案では継続検討とされています。
また、破産手続については、事業再生を図る再建型手続の趣旨が当てはまらず、現行法の解釈も確立していないため、倒産手続開始申立特約の有効性はなお解釈に委ね、規定を設けないことが提案されています。
「将来債権を目的とする譲渡担保権の設定者について倒産手続が開始した場合、当該担保権の効力は倒産手続開始後に発生した債権に及ぶのか」という論点については、現行法上も多くの議論がなされてきましたが、中間試案では、立法によってルール化することが提案されています。中間試案では、以下の4つの方向性が示されています(案の番号付けは中間試案どおり)。
【案19.1.1】倒産手続が開始された後に発生した債権にも無制限に担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。
【案19.1.2】倒産手続が開始された後に発生した債権には担保権の効力が及ぶが、優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時に発生していた債権の評価額を限度とする(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。
【案19.1.3】倒産手続が開始された後に発生した債権であっても、担保権者が担保権を実行するまでに発生したものには、担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。
【案19.1.4】倒産手続開始後に発生した債権には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ既発生の債権について、倒産手続の開始によって取立権限を失う。)。
なお、若干補足すると、【案19.1.2】のルールは、担保価値の評価時点と担保実行の時点を一致させない考え方であり、担保実行の時点が倒産手続開始後であっても、倒産手続開始時に担保目的物の価値を固定させるものです。一方、【案19.1.3】のルールは、これを一致させ、担保実行の時点における担保目的物の価値を担保権者に配分するものです。
また、「新たな規定に係る集合動産担保権の設定者について倒産手続が開始した場合、当該担保権の効力は倒産手続開始後に取得した動産に及ぶのか」という論点についても、中間試案では、以下の3つの方向性が示されています(案の番号付けは中間試案どおり)。
【案19.2.1】倒産手続が開始された後に取得した動産には担保権の効力が及ぶが、優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時までに取得した動産の評価額を限度とする(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によっては、処分権限を失わない。)。
【案19.2.2】倒産手続が開始された後に取得した動産であっても、担保権者が担保権を実行するまで(実行通知が設定者に到達するまで)に取得したものには、担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によっては、処分権限を失わない。)。
【案19.2.3】倒産手続開始後に取得した動産には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によって処分権限を失う。)。
現在の担保法制は、個々の特定性のある資産に対する担保権の設定が前提となっており、債務者の事業を構成する全ての資産を包括的に担保として把握するものではありません。なお、財団抵当制度では一部の資産群(工場など)に対する担保設定が許容されていますが、債務者の事業全体を対象とするものではなく、また、企業担保制度は現在利用されていません。もっとも、不動産等の有形資産を持たない中小企業やスタートアップ企業では、事業価値やその将来性に依拠した成長資金の融資が求められており、また、プロジェクト・ファイナンスやLBOファイナンスにおいて見られる全資産担保の実務では事業キャッシュフローをベースとした担保価値の把握が求められるようになっています。そこで、政府は、「スタートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成長資金を調達できる制度を創設する」ことを目指しているところです(「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)34頁)。これを受けて、担保法制部会においては「事業担保権」の検討が進んでいますが、金融庁においても同時並行で「事業担保権」と同趣旨の「事業成長担保権」の創設に向けた検討が進められています(金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ報告」(令和5年2月10日公表)参照)。
本ニュースレターでは、中間試案における「事業担保権」の基本コンセプトを以下に記載します(中間試案第5章第23乃至第26)。
もっとも、上述のとおり、金融庁の下でも「事業成長担保権」として検討が進んでいる最中であり(ただし、上記の基本コンセプトは「事業成長担保権」にも当てはまります。)、実際に立法化される場合に、どの所管官庁の下でどのような形での立法(特別法かどうか等)がなされるかについては、今後の検討に委ねられることになります。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


遠藤努、中村日哉(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
近藤亮作(コメント)


(2025年4月)
淺野航平(共著)


(2025年5月)
酒井嘉彦


(2025年4月)
酒井嘉彦


酒井嘉彦
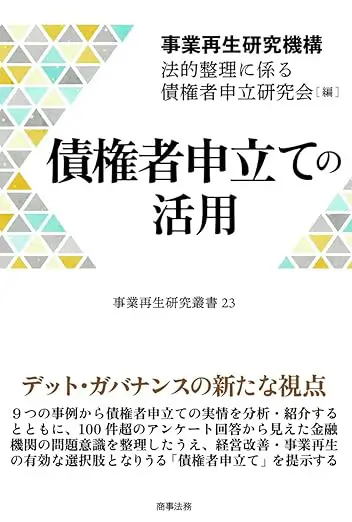
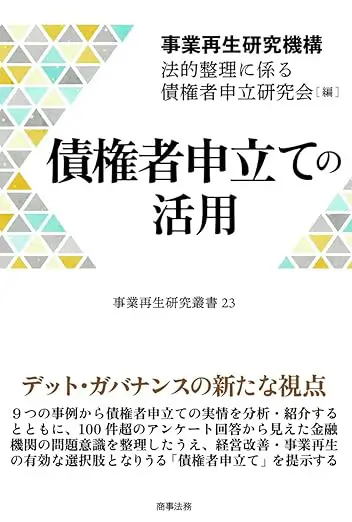
事業再生研究機構 法的整理に係る債権者申立研究会 (2025年3月)
小林信明、鐘ヶ江洋祐、大川友宏(共著)