
逵本麻佑子 Mayuko Tsujimoto
パートナー(NO&T NY LLP)
ニューヨーク

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
ご挨拶 – NO&T U.S. Law Update 100号の刊行に添えて
弊事務所のニューヨーク・オフィスが、クライアント及び日系企業の皆様に米国の最新の法律問題について情報を提供するべく発行をしておりますNO&T U.S. Law Updateも、本号をもちまして100号に達することになりました。1992年に創設されたMasuda International(桝田国際法律事務所)を母体に2010年に開設された弊事務所のニューヨーク・オフィスは、30年以上にわたってニューヨークからクライアントの皆様に対してリーガル・サービスを提供し、米国における事業活動をサポートさせていただいております。今後もより皆様のお役に立てますよう、米国の最新の法律問題についての情報発信を継続してまいります。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク・オフィス一同
近年、様々な米国の州において、「Right to Repair」法(修理権法)が立法されつつあり、また、修理権に関するFederal Trade Commission(以下、「FTC」といいます。)による摘発や、集団訴訟も相次いでいます。修理権法は、Original equipment manufacturer(オリジナル製品製造業者、通称「OEM」といいます。)により非公開とされていた機器(携帯電話、コンピュータ、自動車、医療機器、農業機械など)のプログラミングや診断情報に、消費者や第三者の修理者が正式にアクセスできるようにする法律です。これにより、機器のアフターマーケットでの修理や改造を可能にし、消費者がOEMやその認定修理業者だけではなく、第三者を利用して機器の修理や改造をより自由に行うことが可能になります。これらの法律は、アフターマーケットにおけるOEMの独占を制限し、消費者のコストを下げることが目的とされています。州によってその内容は様々ですが、本ニュースレターでは、多くの日系企業が事業を行っているニューヨーク州及びカリフォルニア州の最近の修理権法制の動向を紹介し、また、既に修理権法が成立している州の修理権法の内容を紹介します。加えて、最近の修理権に関するFTCの執行状況や集団訴訟について紹介し、最後に、修理権法に関して企業が対応すべき事項について議論します。
ニューヨーク州は、電子機器に関する幅広い修理権法を制定した最初の州です。2022年12月29日にニューヨーク州は「Digital Fair Repair Act※1」を制定し、OEMに対し、デジタル電子機器の診断、メンテナンスまたは修理に必要な書類、部品やツール※2、を独立の修理業者や消費者に公正かつ合理的な条件※3で提供することを義務付けました。この法律は2023年7月1日に施行され、この日以降にニューヨーク州において初めて製造、販売または使用された製品にのみ適用されます。
Digital Fair Repair Actは、対象となるデジタル電子機器(digital electronic equipment)を、10ドル※4を超える製品であり、その機能の全部もしくは一部が、製品に組み込まれた、または製品に取り付けられたデジタル電子機器に依存するものと定義しています。ただし、家電製品、医療機器、自動車、農業用トラクターなどは除外されています。
カリフォルニア州では、修理権法は未だ制定されていませんが、現在州議会で二つの法案が審議されています。
一つ目の法案はSB271※5と呼ばれ、電動車椅子に対して適用されます。SB244※6と呼ばれる二つ目の法案は、電子機器及び家電製品メーカーに対し、その製品の最終製造日から一定年数、その製品の診断、メンテナンスまたは修理に関する部品、ツール、書類を第三者の修理業者や製品所有者が公正かつ合理的な条件で利用できるようにすることを義務付けるものです。上記の一定年数は製品の価格により異なり、50ドル以上99.99ドル未満の製品については3年間、100ドル以上の製品は7年間とされています。SB244は現在、カリフォルニア州議会の上院を通過し、下院で審議されています。
現在、ニューヨーク州に加えて、マサチューセッツ州、コロラド州、ミネソタ州の三つの州で一定の修理権法が制定されています。マサチューセッツ州では自動車を対象にした修理権法が2012年に成立し、その対象を自動車のテレマティクスに拡大する法案が可決されました※7。コロラド州では、車椅子と農業機械に適用される修理権法が存在し、OEMが農業機械の所有者や第三者の修理業者に修理用の部品、工具、ソフトウェアを提供することを義務付けています。最後に、ミネソタ州では、2023年4月にDigital Fair Repair Act※8が成立し、2024年7月1日から施行予定です。同法は、2021年7月1日以降に販売されたほとんどのデジタル電子製品を対象としており、ニューヨークのDigital Fair Repair Actよりも広範囲をカバーするものとなっています。
2022年に、FTCは、消費者が第三者の部品や修理業者を使用した場合に保証が無効になる旨定める保証規定は、消費者が特定のブランドの物品またはサービスを使用することを保証の条件とすることを違法とするMagnuson-Moss Warranty Act(以下、「Warranty Act」といいます。)、及び、不公正・欺瞞的な行為を禁じるFederal Trade Commission Actに違反するものであるとして、OEM三社を相次いで提訴しました※9。これ以前の過去10年間、FTCがWarranty Actの違反による提訴を行ったのは1件のみでしたが※10、FTCが2021年5月に連邦議会に提出したレポート※11で、OEMによる修理権の制限について懸念を示すなど、FTCがこの分野に強い関心を持っていることが明らかにされています。
さらに、FTCが修理権の制限に懸念を示したことをきっかけとして、修理権に関する複数の集団訴訟が起きています。これらの集団訴訟の原告は、アフターマーケットの規制に関するFTCの最近の声明を直接引用し、FTCが摘発したような違法行為により、OEMブランドの部品の値段がつり上げられており損害を被ったなどとして損賠賠償を請求しています。米国司法省も、トラクターメーカーが特定の修理用ソフトウェアやツールの提供を拒否していると主張されている集団訴訟において、原告を支持する意見書を提出しています※12。このような傾向に鑑みると、今後も修理権を巡る集団訴訟は増加するものと考えられます。
上記で説明した修理権法の拡大を受けて、米国で自社ブランドの機器等を販売する日本企業が取るべき対応として、以下のものが考えられます。
上述のとおり、FTCは、消費者が第三者の部品や修理業者を使用した場合に保証が無効になる旨定めることは違法であると判断しており、OEMとしてはこのような規定が保証条件を記載した保証書等に記載されていないことを確認する必要があります。また、Warranty Act上、保証の条件は分かりやすい文言で、保証の対象となる製品等及び対象から除外される製品等を明確にして記載すること等も求められており、これらの点についても確認が必要です。
FTCは、連邦議会に対するレポートにおいて、他の形での修理の制限(取扱いの拒否や排他的な取扱いなど)が競争法に違反する可能性を示しています。OEMが修理を制限する理由として、プライバシー上の懸念やデータ保護、安全性の確保といったものがあり、FTCも上記レポートにおいてそのような制限の根拠に言及しており、一定の理解を示しているものと思われます。OEMとしては、何らかの修理制限を設ける場合には、上記のような正当化根拠を十分に示すことができるかどうか、検討が必要です。
上述のとおり、各州で修理権法を制定する動きが広まっています。各州の修理権法において、適用対象となる製品が異なり、OEMの取るべき行為も異なってくるため、各州の修理権法の制定状況を継続的に把握しておくことが重要になります。
州の修理権法の拡大とFTCによる摘発の増加を受けて、OEMとしてはリスクを積極的に評価し、必要に応じて自社の保証内容を調整することが考えられます。修理権法に対するOEMの反発が高まっており、修理権法によりOEMが追加の対応を強いられることで製品の基本価格が上昇してしまっているという見方もありますが、今後も各州で修理権法が拡大していくことが予想されます。
※2
ツール(tool)の定義にはソフトウェアプログラムやハードウェアが含まれます。
※3
例えば、マニュアルなどの書類については、物理的な印刷物が要求されていない限り無料で入手可能なものとし、ツールについては原則として無料で、診断や修理のためにツールへのアクセスに障害のない形で入手可能なものとすることが要求されています。
※4
この額は消費者物価指数により毎年調整されるものとされています。
※7
なお、現在当該法律の有効性を巡って訴訟が係属しています。
※9
これらの訴訟は最終的に和解により解決されています(https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2022/07/ftc-announces-three-right-repair-cases-do-your-warranties-comply-law)。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年5月)
小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
壱岐祐哉(講演録)


東崎賢治、平山貴仁(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


宮城栄司、井柳春菜(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)
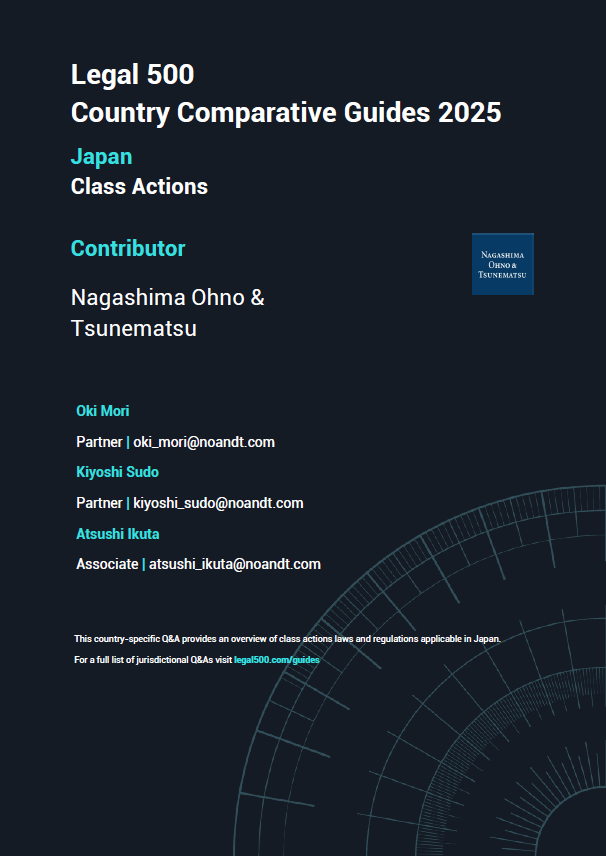
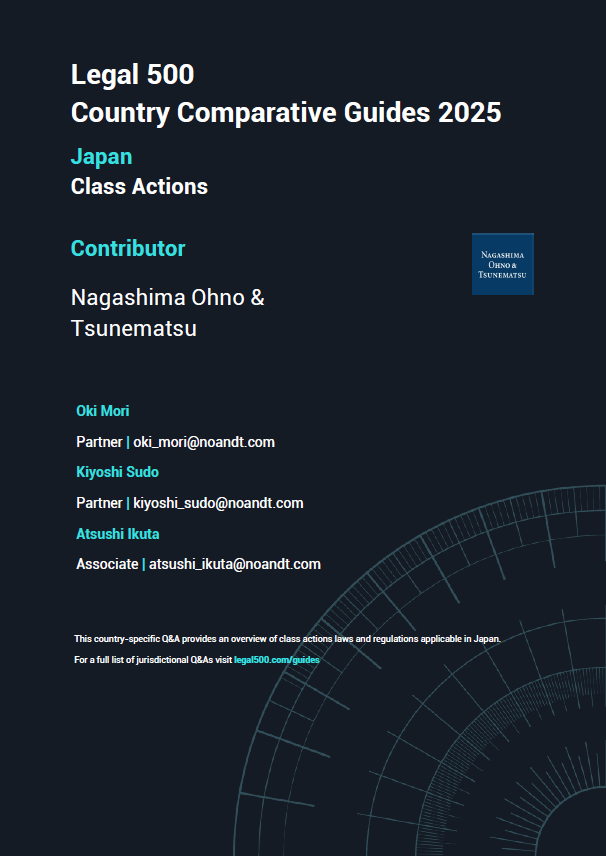
(2025年6月)
森大樹、須藤希祥、生田敦志(共著)
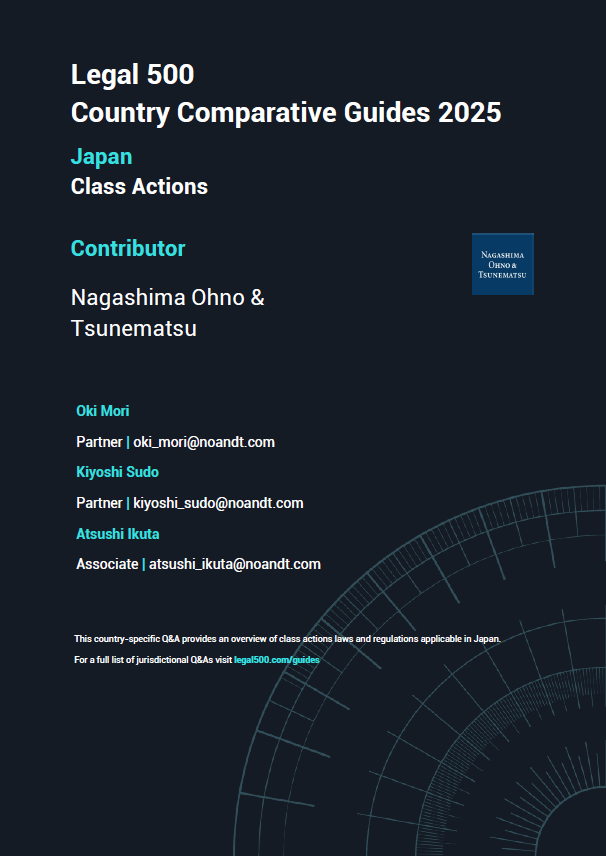
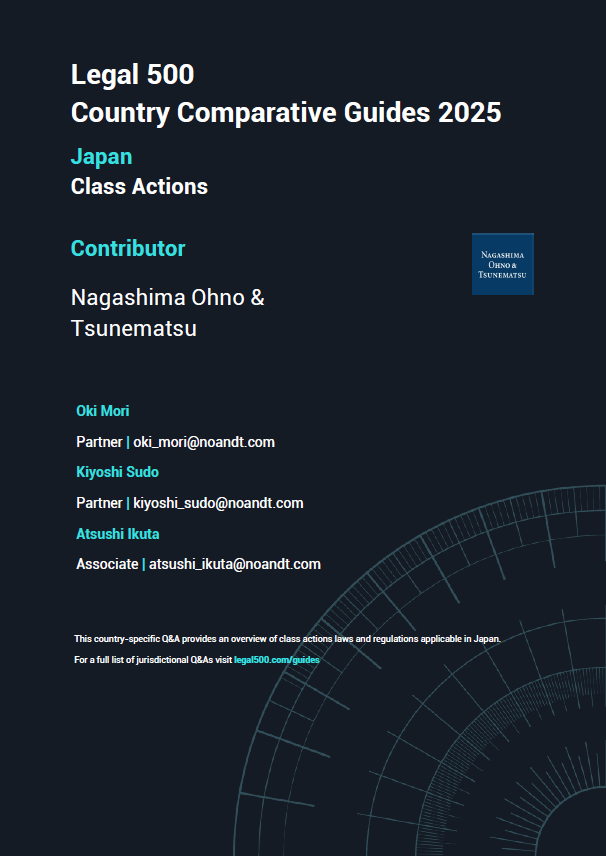
(2025年6月)
森大樹、須藤希祥、生田敦志(共著)
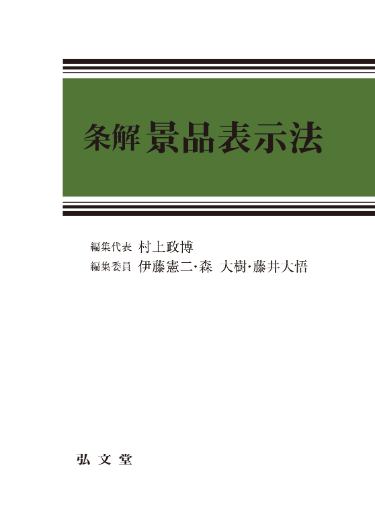
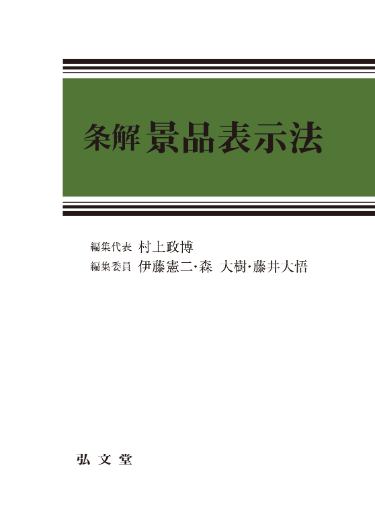
弘文堂 (2025年3月)
森大樹(編集委員)、須藤希祥(執筆責任者)、梅澤舞、馬渕綾子、野口夏佳、生田敦志、中坪真緒、本田陽希、栗原杏珠(執筆協力)
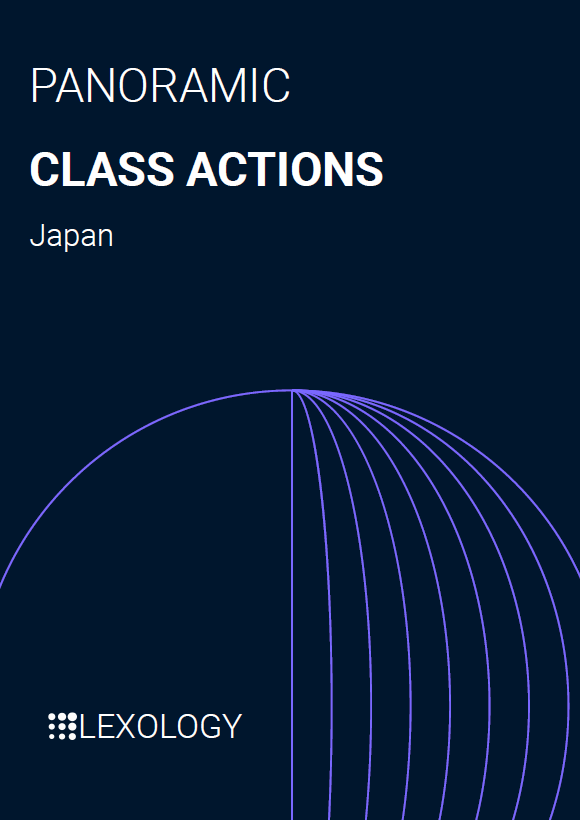
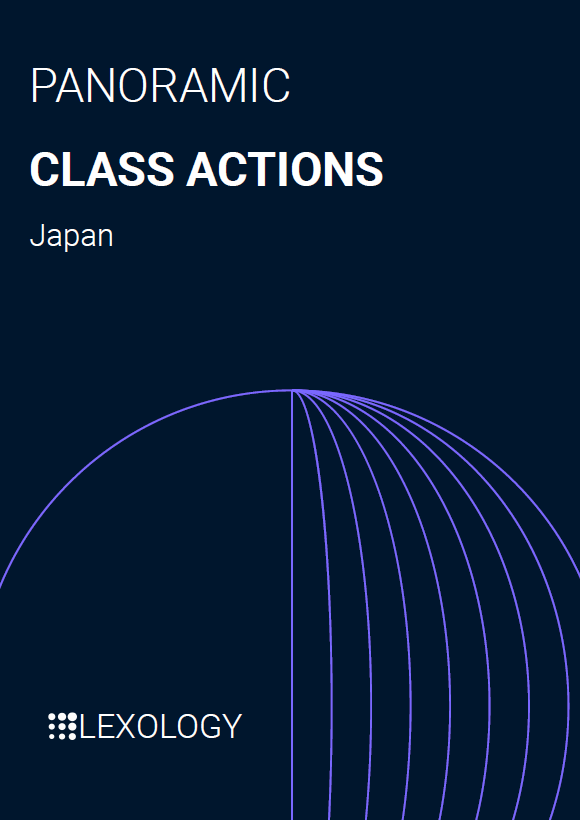
(2024年11月)
森大樹、梅澤舞(共著)
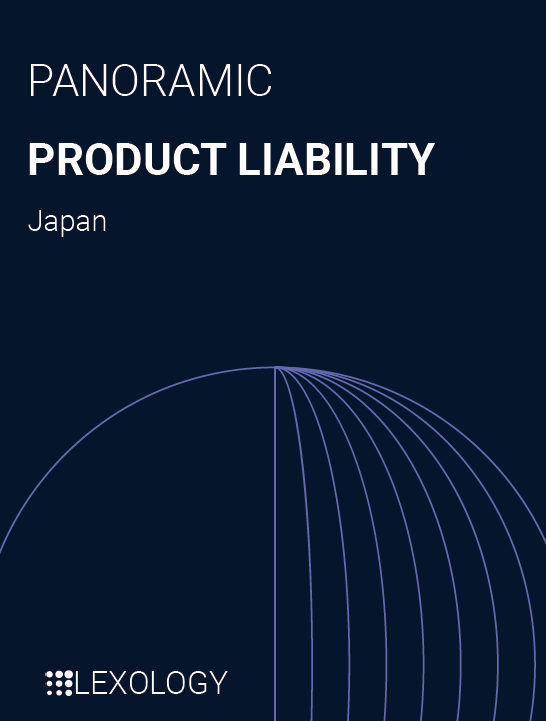
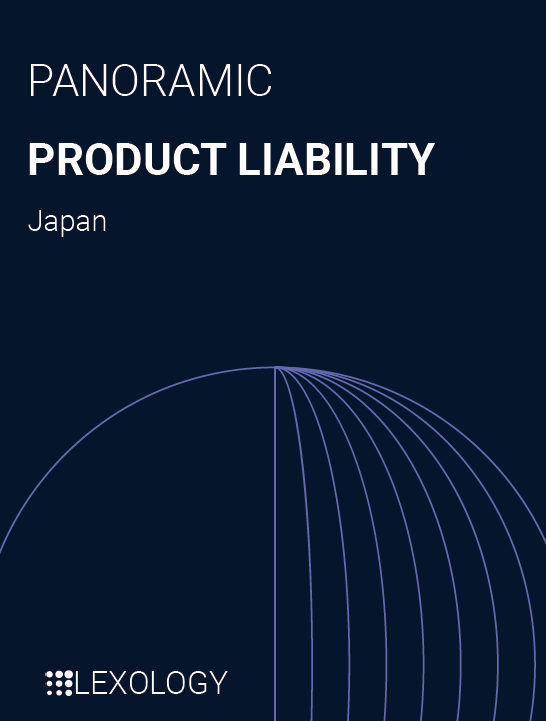
(2024年9月)
森大樹、井上皓子(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


井上皓子


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


大久保涼、内海裕也(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


(2025年5月)
近藤亮作(コメント)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


大久保涼、内海裕也(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


(2025年6月)
福原あゆみ