
鳥巣正憲 Masanori Tosu
パートナー
東京
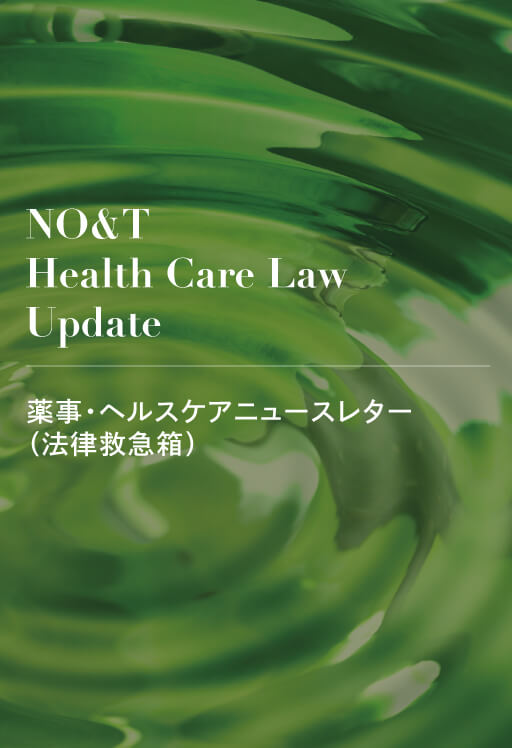
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。
2024年5月22日付で、後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(「本検討会」)の議論を取りまとめた報告書(「本報告書」)が公表されました。本検討会は、2021年の後発医薬品企業に係る行政処分に端を発する後発医薬品の供給不安を契機として議論が開始された「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」からの提言を受けて厚生労働省により新設された会議体です。後発医薬品産業を安定供給が確保された産業構造として再構築するため、産業構造の在るべき姿、その実現に向けた産業政策について幅広い議論を行うことを目的とし、2023年7月31日の第1回開催以降、計13回にわたり、完全非公開の形式で議論が重ねられました。本検討会の構成員には、医薬品業界について知見を有する各分野の専門家が任命され、本号の筆者も、法務分野の専門家として構成員を拝命し、微力ながら各回の議論及びその取りまとめに向けて尽力しました。
本号では、本報告書に取りまとめられた本検討会における議論の結果について、その概要をご紹介します。
本検討会における検討にあたっては、まずその背景及び出発点として、後発医薬品産業の現状及び安定供給等の実現に向けた諸課題について把握することが必要と考えられました。本報告書の第1章でも述べられているとおり、日本における後発医薬品の使用割合は過去15年間で約35%から約80%まで拡大しました。他方で、2021年以降後発医薬品企業による薬機法違反が相次ぎ発生し、違反企業の製品について出荷停止が行われたことを端緒として、約3年にわたり、後発医薬品の深刻な供給不安が継続しています。
このような供給不安が継続している背景には、上記のような違反事案を発端とした供給停止や限定出荷の拡大だけでなく、比較的中小規模の企業が多く生産能力や生産数量が限定的な中で、薬価下落等による各品目の収益性の低下を補うために新規製品の承認取得・薬価収載を繰り返し、少量多品目生産が拡大し、それが更なる生産の非効率化等につながるといった、構造的な問題があると考えられました。また、薬価収載後の流通慣行や価格競争により収益低下に拍車がかかること、それにより製造設備への投資や人材確保・人材育成に経営資源を投下することが難しくなることも要因の一つであると考えられました。
上述のような諸課題を解決するための各種具体的な対策を検討するにあたっては、前提として、後発医薬品産業として今後どのような在り方を目指していくべきかについて明らかにすることが重要と考えられました。そのため、本検討会でも、後発医薬品産業としての在るべき姿について、時間をかけて丁寧に議論が重ねられ、その結果は本報告書の第2章に示されています。具体的には、医薬品企業としての社会的責任の当然の前提として、品質の確保された医薬品を安定的に供給できるように、以下の3点の実現を目指していく必要があるとされました。
| 製造管理・品質管理体制の確保 | 全ての企業において製造管理・品質管理体制が整っていること |
|---|---|
| 安定供給能力の確保 | それぞれの企業において医薬品を安定的に供給できる体制が保たれるとともに、産業全体として必要に応じて増産を行う余力のある体制が確保できていること |
| 持続可能な産業構造 | 収益と投資の好循環が確立しており、産業として持続可能な形になっていること |
上述のような諸課題を解決するべく本検討会において議論され、最終的に本報告書において提案されるに至った具体的な対策の内容は、多岐にわたります。これらは、本報告書の第3章において、上述の後発医薬品産業の在るべき姿として目指していくべき内容に沿って、それぞれ整理されています。また、それらを実行していくためには一定のコストを要することや、生産効率・収益性向上のためにはある程度大きな規模で生産や品質管理等の体制を構築していくことが有効な選択肢になりうるという観点から、企業間の連携・協力の推進についても言及されています。これらの対策の概要は、以下のとおりです。
| 製造管理・品質管理体制の確保 |
<徹底した自主点検の実施>
|
|---|---|
<ガバナンスの強化>
|
|
<薬事監視の向上>
|
|
| 安定供給能力の確保 |
<個々の企業における安定供給確保体制の整備>
|
<医薬品等の安定供給確保に係るマネジメントシステムの確立>
|
|
| 持続可能な産業構造 |
<少量多品目生産の適正化等の生産効率の向上>
|
<収益と投資の好循環を生み出す価格や流通の在り方>
|
|
| 企業間の連携・協力の推進 |
<企業間の連携・協力による生産効率・収益性の向上等>
|
<企業間の連携・協力の取組の促進策>
|
|
<独占禁止法との関係整理>
|
なお、これらの対策については、5年程度の集中改革期間を設定して、実施できるものから迅速に着手しつつ、ロードマップを速やかに策定し、実施状況についての定期的なフォローアップ等も行いながら、着実に実施していくべきとされています。実際に、上記の対策の中には、本検討会の開催期間中に、既にその取組が開始されたものも存在します。また、企業間の連携・協力については、本検討会での議論に呼応して、後発医薬品企業の間で様々な形で連携・協力を進める検討が活発化しているといわれています。
本報告書の「おわりに」では、本検討会における議論が総括されるとともに、個々の後発医薬品企業だけでなく、業界団体や業界の中核を担う自覚のある企業による業界全体のリード、金融機関・投資家による関与、政府による支援、医薬品卸売販売業者や医療機関・薬局等の理解・支援等、後発医薬品産業に関わる各ステークホルダーへの期待が様々な形で示されています。その上で、本検討会における議論を通じて提案されるに至った様々な対策について、厚生労働省に対し、法的枠組みの必要性を含めて検討を行った上で早急に実行に着手することを求めている点は、注目に値します。
本報告書における取りまとめは、あくまで出発点に過ぎず、後発医薬品産業としての在るべき姿を実現するためには、あらゆるステークホルダーが一丸となって、各種の対策に短期間で集中的に取り組んでいくことが重要です。筆者自身も、本検討会の中で議論した内容を踏まえて、後発医薬品産業における課題の解決と同産業の更なる飛躍に向けた一助となるべく、引き続き様々な形で力を尽くしていきたいと考えています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、平山貴仁(共著)
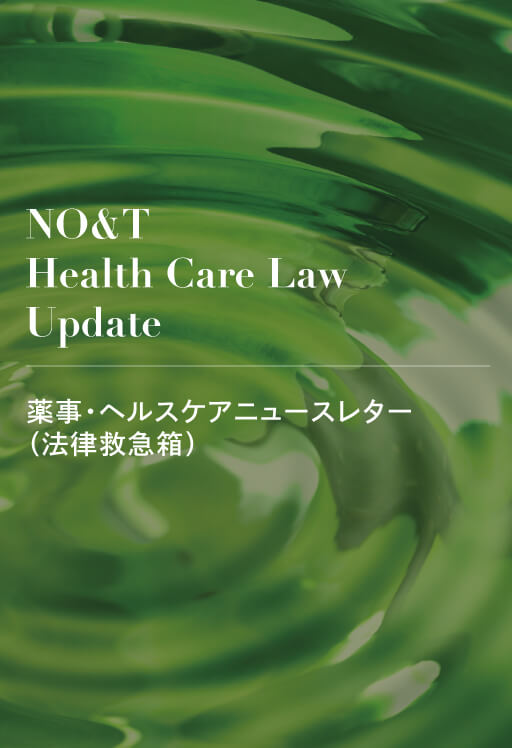
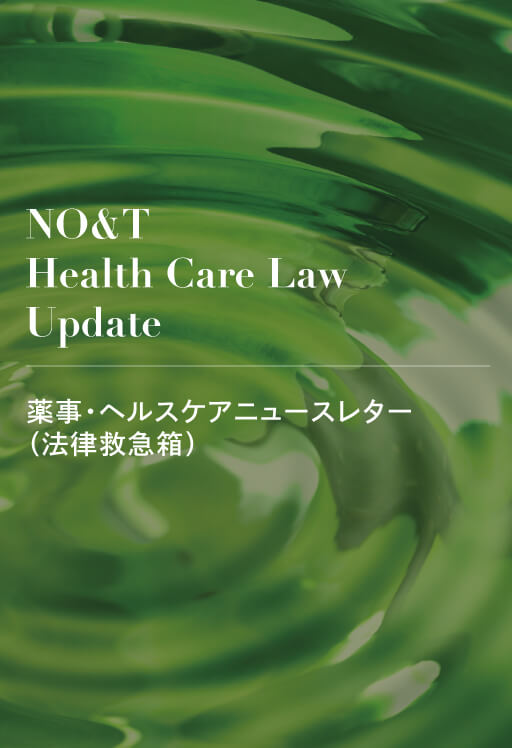
鈴木謙輔、中本優介(共著)


(2025年4月)
平山貴仁


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、平山貴仁(共著)
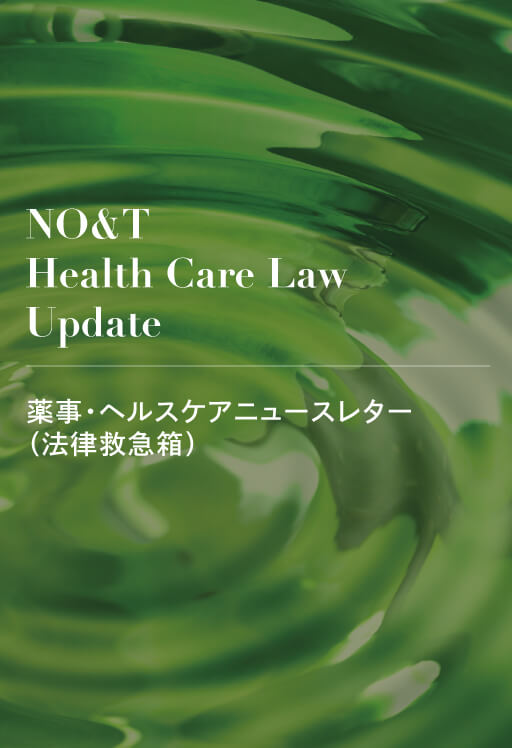
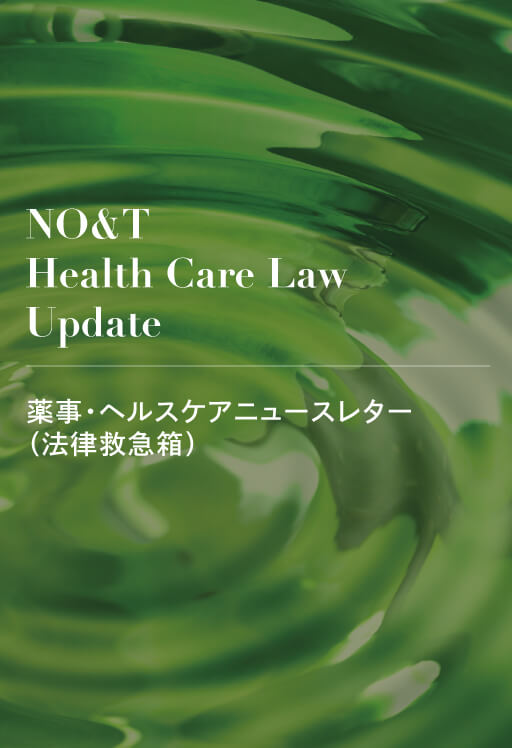
鈴木謙輔、中本優介(共著)


(2025年4月)
平山貴仁


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
大久保涼(コメント)


内海健司、門田正行、山中淳二(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
大久保涼(コメント)


内海健司、門田正行、山中淳二(共著)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
伊藤伸明
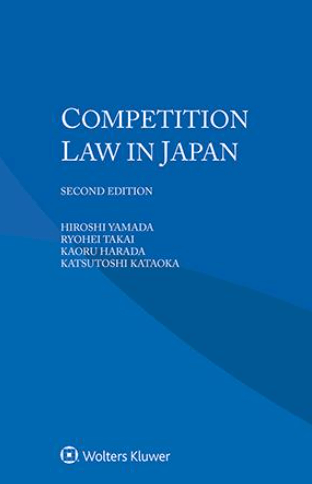
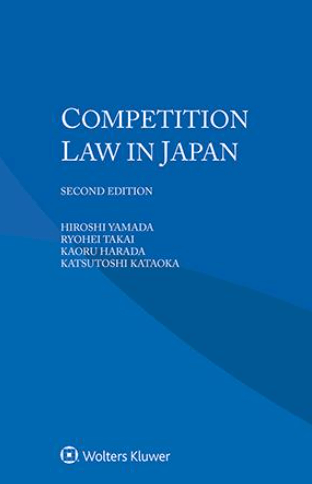
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)
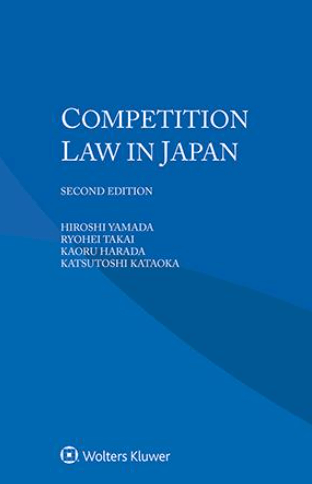
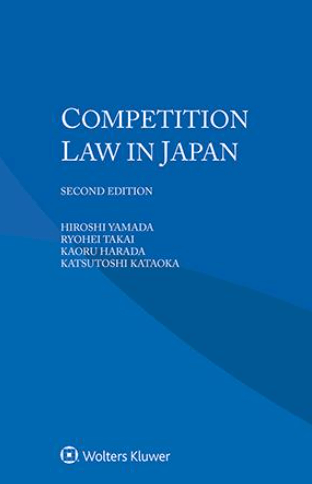
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2025年7月)
福原あゆみ(コメント)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


(2025年6月)
福原あゆみ