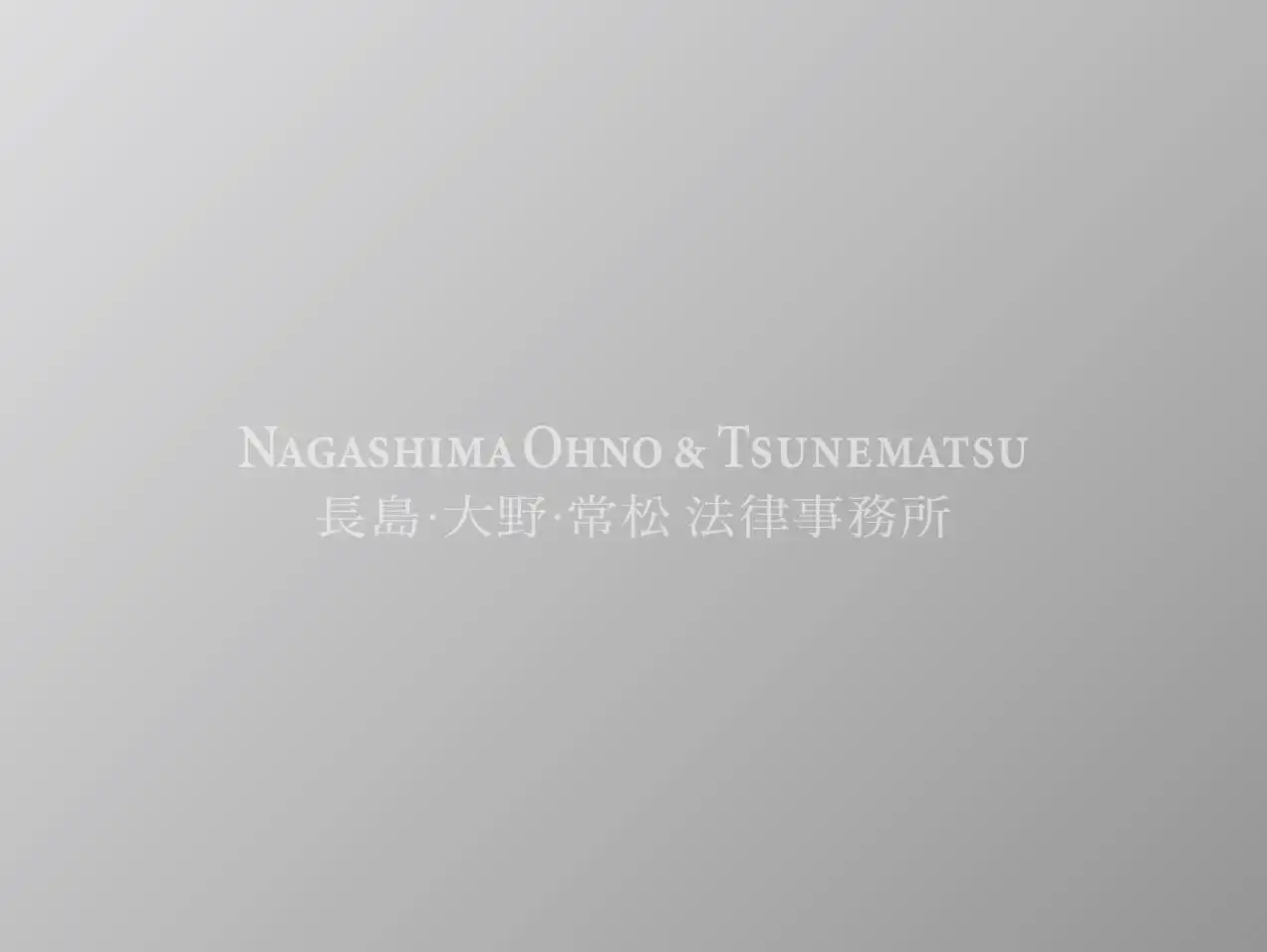
山本匡 Tadashi Yamamoto
パートナー
東京

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
ニュースレター
インドの非公開会社の有価証券の電子化(2023年11月)
インドの企業省(Ministry of Corporate Affairs、以下「企業省」という。)は、2025年2月12日に、インドの2013年会社法(Companies Act, 2013)に基づき制定された2014年会社(目論見書及び有価証券割当)規則(Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014、以下「PAS規則」という。)を改正し、非公開会社(private company)の有価証券の電子化の期限を2025年6月30日に延期した。
NO&T Asia Legal Update No. 172「インドの非公開会社の有価証券の電子化」(2023年11月)で記載したとおり、2023年10月のPAS規則の改正により、原則として全ての会社の有価証券を電子化する必要があることとなった※1。即ち、発行会社の義務として、インドの非公開会社は、原則として2023年3月31日以降に終了する事業年度の最終日から18か月以内(事業年度が4月1日~翌年3月31日であれば、2024年9月30日まで)に株券を含め有価証券を電子化して発行しなければならず、全ての有価証券の電子化を促進しなければならないこととなった。具体的には、発行会社は証券保管振替機構(National Securities Depository Limited又はCentral Depository Services (India) Ltd)に申請して各有価証券についてISINコード(International Security Identification Number)を取得し、有価証券保有者に電子化が必要となる旨を通知しなければならない。また、上記期限後に有価証券の発行、自己有価証券の取得、ボーナス株式の発行、株主割当新株発行を行おうとする場合、そのプロモーター(会社の経営を実質的に支配している者等)、取締役及び主要経営者(key managerial personnel)が保有する全ての有価証券が電子化されていることを確認しなければならない。
有価証券保有者は、上記期限以降に有価証券を譲渡しようとする場合、又は有価証券の引受けを行おうとする場合、事前に自己が保有する有価証券を電子化しなければならない。
有価証券の電子化は時間と手間のかかる手続であり、多くの非公開会社にとっての期限であった2024年9月30日が近づくにつれ、期限の延期や適用免除の設定の要請が企業省に対して出されていた※2。企業省は、producer companyという特別な種類の会社(通常の事業会社はこれに該当しない。)についてのみ、2024年9月のPAS規則の改正により期限を18か月から5年に延期していたが、それ以外の非公開会社については期限の延期や適用免除を認めなかった。
しかしながら、企業省は、2025年2月12日にPAS規則を改正し、非公開会社の有価証券の電子化の期限を2025年6月30日に延期した。これにより、有価証券の発行や譲渡に関しては、当面の間、電子化の猶予期間が設けられ、非公開会社の有価証券を電子化しないまま発行、譲渡することが可能となり、電子化の手続に時間と手間がかかることによって、発行や譲渡のタイミングが遅れることを回避することはできる。しかしながら、期限の延期は2025年6月30日までと長くはない。いずれにしても、発行会社及び有価証券保有者のいずれも電子化の手続を粛々と進めるべきであろう。
なお、小会社(small company)※3に該当する会社については適用除外が認められているので、引き続き電子化しないまま有価証券の発行や譲渡が認められる。一方、公開会社については、今回のPAS規則の改正の対象となっていない。
※1
2023年10月のPAS規則の改正は、非公開会社の有価証券の電子化に関する改正である。公開会社(public company)の有価証券については、先行して、2018年9月のPAS規則の改正により、同年10月2日以降電子化が求められていた。
※2
たとえば、インド会社秘書役協会(Institute of Company Secretaries of India)は、完全子会社等の一定の会社について適用免除とするとともに、期限の延期を企業省に要請していた。
※3
払込済み株式資本金が4,000万ルピー以下で売上高が4億ルピー以下の会社をいう(2025年2月17日現在、1ルピー=約1.7円)。ただし、他の会社の親会社である会社や子会社である会社は小会社に該当しない。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年10月)
三笘裕、濱口耕輔、奥野晟史(共著)


対木和夫、半谷駿介(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
三笘裕、平松慶悟(共著)


斉藤元樹、大島岳(共著)


山本匡


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


(2025年10月)
玉井裕子、田村優(共著)、生川大祐、乾正知、岩﨑莉乃(執筆協力)


山本匡


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


(2025年10月)
玉井裕子、田村優(共著)、生川大祐、乾正知、岩﨑莉乃(執筆協力)


(2025年8月)
前川陽一


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


山本匡


梶原啓


箕輪俊介


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


山本匡


安西統裕、一色健太(共著)


山本匡


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)