
犬島伸能 Nobuyoshi Inujima
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
本ニュースレターでは、2025年2月25日に公布され、3月24日から施行された「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の改正について、概要をお知らせします。※1
まず、これまでの経緯として、ドローン分野においては、2022年に航空法が大きく改正され、機体認証・型式認証制度と操縦者技能証明制度が創設されるとともに、飛行禁止空域と飛行方法に関する規制の再構成が行われました。具体的には、下記表記載の空域及び方法での飛行(特定飛行)については、飛行のリスクの程度に応じて設けられた3つのカテゴリーに応じて、下記の規制が設けられています。
| 飛行の空域 | 飛行の方法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132条の85第1項 | 132条の86第2項 | |||||||||
| 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | |||
| 空港周辺・150m以上 | 人口集中地区(DID) | 夜間 | 目視外 | 人・物件30m未満 | イベント上空 | 危険物輸送 | 物件投下 | |||
| カテゴリーⅠ | 機体認証・操縦ライセンスの取得は不要 | (飛行の空域、飛行の方法がこれらに該当しないため、許可・承認は不要) | ||||||||
| カテゴリーⅡ | 機体認証・操縦ライセンスを取得しない場合 | 飛行毎に許可・承認が必要 | ||||||||
| 機体認証・操縦ライセンスを取得する場合 | 総重量25kg未満 | 飛行毎に許可・承認が必要(但し、審査は簡略化可) | 飛行毎の許可・承認は不要 | 飛行毎に許可・承認が必要(但し、審査は簡略化可) | ||||||
| 総重量25kg以上 | 飛行毎に許可・承認が必要(但し、審査は簡略化可) | |||||||||
| カテゴリーⅢ | 機体認証(第一種)・操縦ライセンス(一等)の取得が必要 | 飛行毎に許可・承認が必要 | ||||||||
(出典)国土交通省の公表資料を参考に筆者らが作成
この改正により、カテゴリーⅢに含まれる、いわゆるレベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)が解禁され、一等無人航空機操縦士の資格を取得した者が、第一種機体認証(あるいは第一種型式認証+第一種機体認証)を得た機体を飛行する場合には、飛行毎に許可・承認を得ることによって、レベル4飛行も可能となりました。
しかしながら、現時点までに第一種機体認証を得た機体は1機のみで※2(申請中の機体は4機)、レベル4の実証実験が行われた件数も5件と、依然レベル4飛行のハードルは高く、実用化までにはまだ時間がかかる見通しです。
したがって、現時点においては、飛行許可・承認の申請のうち大半を占めるのはカテゴリーⅡ飛行(上記表のグレーハイライト部分)であるところ、カテゴリーⅡ飛行の許可・承認申請においても、申請手続が比較的厳格であり、審査が終わるまでに時間がかかるという問題がありました。
そのような中、規制改革推進会議により2024年5月31日に公表された「規制改革推進に関する答申~利用者起点の社会変革~」※3において、様々な分野での活躍が見込まれるドローンの事業化を促進すべく、許可・承認手続の迅速化(1日化)を目指すことが掲げられ、それを受けて行われたのが、この度の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」の改正(2025年2月25日公布、3月24日施行)です。
審査要領(カテゴリーⅡ飛行)においては、審査基準に適合するか否かを審査するために、主に①飛行概要、②機体、③操縦者、④安全対策の4点について申請することが要求されています。今回の改正は、そのうち②機体と③操縦者について申請手続の簡素化を図るものです。
改正前においては、許可・承認申請にあたり、基準に適合していることを確認するために、下記資料の提出が要求されていました。
機体
操縦者
今回の改正によって、上記各資料の提出は不要となり、代わりに、申請者が自らにおいて、上記各資料をもとに基本基準・追加基準への適合性を確認し、その確認結果を原則「適・否」で申請すれば足りることになりました。これに伴い、許可・承認申請に用いられる「ドローン情報基盤システム」(DIPS)の改修もなされました。
従前要求されていた各資料の準備には手間と時間がかかるものもありましたので、その提出が不要となることで、申請者の負担は大幅に軽減され、審査にかかる期間も短縮されることが期待されます。冒頭で述べたように、現時点においては、飛行許可・承認の申請のうち大半を占めるのはカテゴリーⅡ飛行の申請であるため、その審査手続を大幅に簡素化する今回の改正は、実務に大きな影響を与えるものといえるでしょう。
今回の改正によって提出が不要となる資料についても、全く不要になるわけではなく、申請者において用意し、具備する必要があることについては注意が必要です。許可・承認申請時においては提出不要でも、許可・承認の条件として、当局は上記各資料の提出又は説明を求めることができるとされているため、後日当局から提出を求められる可能性があり、その際には速やかに提出できる状態にある必要があります。もし、資料が具備されておらず速やかに提出できない場合、あるいは提出できたとしても基準に適合していないことが判明したような場合には、条件違反として認可・承認が取り消される可能性もあります。今回の改正は、手続面で申請者の負担を軽減するものではあるものの、基準に適合していることについての責任を軽減するものではないことについては十分理解しておく必要があります。
上記「規制改革推進に関する答申~利用者起点の社会変革~」によれば、今後ドローンについて、総重量25kg以上のドローンの社会実装を進め審査要領の要件を具体化する※5、外国人等を役員に含む企業であっても登録講習期間及び登録更新講習期間として認定されるよう省令を改正する、といった制度改正が行われる可能性があります。また、内閣府、厚生労働省、総務省、経済産業省等の他省庁においてドローンの利活用の促進に関する検討を行うことが予定されており、多分野にわたって今後の動向に注目する必要があります。
※1
なお、その後、総重量25kg以上の無人航空機に関する改正(2025年3月19日公布、3月24日施行(一部については10月1日施行))も行われています。
※3
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/240531.pdf
概要:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/240531point.pdf
※4
本文に記載のとおり、今回の改正によって原則として提出不要となりましたが、例外として、補助者を配置せずに飛行させる場合には、改正前と同様、かかる資料を提出する必要があります。但し、その場合でも、①ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、名称、総重量及び飛行形態の場合、又は、②機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入が無いことを確認できる場合には、原則に戻り、かかる資料の提出は不要とされています。すなわち、資料の提出に代え、申請者が自らにおいて、上記各資料をもとに基本基準・追加基準への適合性を確認し、その確認結果を原則「適・否」で申請すれば足りるものとされています。
※5
本ニュースレターで取り上げた審査要領の改正の後に行われた2025年3月19日付けの改正(注1ご参照)においても、総重量25kg以上の無人航空機につき、①機体が備えるべき機能及び性能としての従前の「堅牢性」や「耐久性」との曖昧な文言が、「実施しようとする飛行において想定される気象条件その他の運用条件を設定し、当該条件下において、安定した離陸、着陸及び飛行ができること。」との文言に修正され(審査要領4-1-2(1))、また②飛行にあたって第三者賠償責任保険への加入が義務づけられました(審査要領4-3-1(19))。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(監修)、水越政輝、松﨑由晃(共著)


犬島伸能、中村彰男(共著)
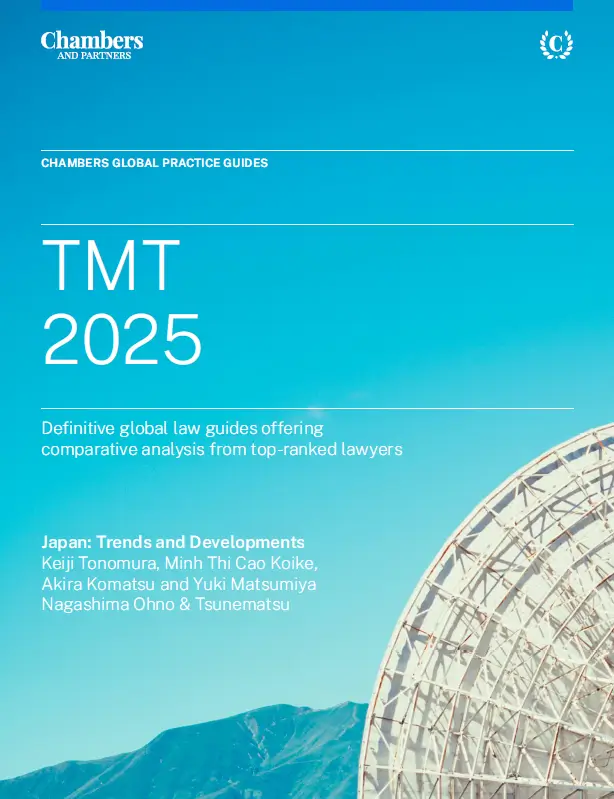
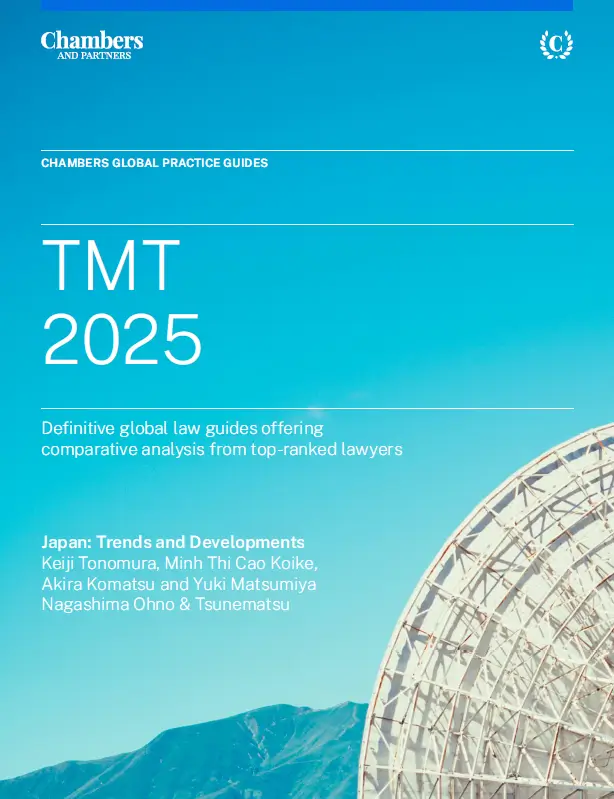
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


(2024年5月)
水越政輝、小松諒(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)