
工藤靖 Yasushi Kudo
パートナー
東京

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
ニュースレター
サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク対応の近時の動向(1)(2025年8月)
サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク対応の近時の動向(3) ~DDoS・ランサムウェア攻撃におけるインシデント報告様式の統一化等~(2025年8月)
前回のニュースレターでは、サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク管理の近時の動向として、SBOMの作成・利用を通じたシステム・ソフトウェアにおける脆弱性への対応についてご紹介しました。
今回のニュースレターでは、取引先等のシステム・セキュリティ上の脆弱性が攻撃者に悪用され、何らかのネットワークによってつながれた自社システム上で生じるセキュリティリスクや、サイバー攻撃によって発生した取引先等における事業停止等により生じる自社の事業リスクへの対応について、設例を用いて解説します。
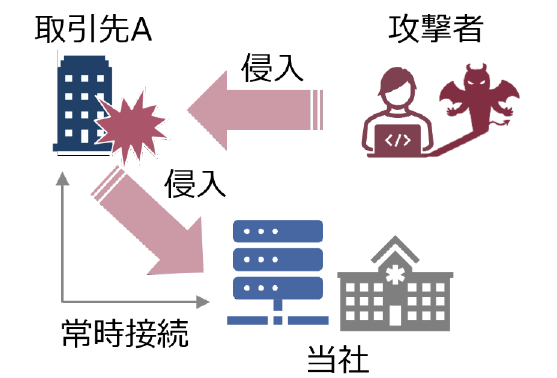
上記の設例において、取引先Aや当社における技術的な管理措置として、どのような対応が考えられたかを検討しますと、まず、取引先AにおいてはVPN機器の脆弱性対応やその診断を実施していることが重要であったと考えられます。前回のニュースレターでも紹介しました、警察庁が2025年3月13日付けで公表した「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」においても、VPN機器の脆弱性を狙った攻撃によるランサムウェア被害の割合は有効回答中の約6割を占めており、慎重なセキュリティ対応が求められます。またID/パスワードについても、重要なシステム・ネットワークであれば、より一層厳重なログイン管理・運用が求められていたものと考えられます。
また、上記の設例ですと、最終的には当社は、リモートデスクトップ通信からの侵入により被害を受けています。そこで、多要素認証化し不正ログインの可能性を少なくする、仮に認証成功されたとしても、その認証成功・失敗状況を記録し、可能であればリアルタイムに監視し、予定されていた作業と一致した挙動であるか確認するなどにより対応しておくことが考えられます。また、接続元となる取引先Aの端末のセキュリティレベルなどを事前にヒアリングし、自社と同等レベルのセキュリティ対策を求めるといった対応も考えられます。
上記を踏まえると、当社として取引先Aに対して、どこまで踏み込んだ対応を求めるべきであったかという問題につながっていきます。当社が取引先Aに対し、必要と考える一定の対応を求めるには、契約により合意し、その条項においてセキュリティ対策上の具体的な要求事項を定めておく必要があります。取引内容・委託内容に照らして検討する必要がありますが、一般論としては、取引先・委託先が実施すべきセキュリティ対策上の水準や要求事項のほか、セキュリティ対策の実施状況に対する検証を可能にするためのエビデンスの提出や監査への協力、サイバー保険の付保、再委託の禁止又は制限・管理策、インシデント対応や責任分担の明確化、契約期間中に関係するシステム等に脆弱性が確認された場合には情報を共有し対応について協議すること、などが考えられます。
取引先・委託先が実施すべきセキュリティ対策上の水準や要求事項に合意し、その実施状況に対する検証を可能にするためにエビデンスの提出や監査協力を求める場合、実務的には一定の制約があります。
すなわち、取引先や委託先に対して一定のセキュリティ対応を求めるにあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独禁法)上の優越的地位の濫用や下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)の規制にも注意が必要となります。経済産業省・公正取引委員会は、「サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ向上のための取引先とのパートナーシップの構築に向けて」を公表しており、例えば取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、①サイバーセキュリティ対策の実施を要請する一方で、相手方に生じるコスト上昇分を考慮することなく一方的に著しく低い対価を定める場合、②セキュリティ対策費などの名目で金銭の負担を要請するなどして、取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、③サイバーセキュリティ対策の実施の要請に際して、合理的な必要性がないにもかかわらず、自己の指定する商品の購入や役務の利用を強制する場合などには、上記規制上の問題になりえます。このため、実務上の対応としては、委託先等に対してセキュリティ対策の実施を要請するにあたり、十分な周知期間を確保した上で、丁寧な説明・協議を行い双方の負担を合意する、これらの説明・協議のプロセスを適切に記録化(議事録・説明資料の保管等)しておくことなどが肝要です。
なお、本年5月、下請法の改正が成立し、改正法は2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に名称変更の上で施行されます。同改正により、新たな委託事業者の禁止事項として、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止が追加されました※1。本号は、従来から親事業者による下請代金の一方的な減額や買いたたきが禁止されていたものの、コスト上昇局面における価格転嫁等に対する問題意識があったことから導入されることとなりました。従来から、公正取引委員会は、下請法の運用上、コスト上昇局面における価格転嫁に関する必要性について明示的に協議せず、又は、下請事業者からの価格引き上げ要請について理由も示さずに従来通り価格を据え置く行為は買いたたき行為に該当すると解釈しており、その意味においては、従来から上記行為は規制対象であったとも考えられます。しかし、本号の追加により禁止行為として法律上明確化されたことから、今後、公正取引委員会がこの種の行為に対する法執行を厳格に行うこととなる可能性は否定できない点に留意が必要です。
また、セキュリティ対策上の水準や要求事項の合意に至った後の検証や監査については、①セルフチェックリストを送付し回答を求める、②外部監査法人等によるセキュリティ監査を実施している場合は、その監査報告を確認する方法などがありますが、①は正確なリスク把握ができないおそれがあり、②はそのような外部者によるセキュリティ監査を強制することまではできないという問題点があります。
こうした中で、関係当局や自主規制団体は、サプライチェーン全体でのセキュリティ水準の向上と、そのセキュリティ対策の実施状況の可視化の推進を目的とするガイドライン等を公表しており参考になります。
経済産業省は、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ強化に向けたサプライチェーン対策評価制度の整備を進めています※2。サプライチェーンを通じた情報漏えい・事業中断のリスクが深刻化しており、中小企業を含む受注側に過重なセキュリティ対応要求が発生している中で、発注者側も取引先の対策の実施状況が不明確な状況にあることを背景としています。現時点では中間取りまとめが公表された段階ですが※3、自社のIT基盤(オンプレミス+クラウド環境)を中心としたサプライチェーン企業(特に中小企業)を対象組織として、★3:基礎的な対策(自己評価)、★4:包括的な標準対策(第三者評価)、★5:到達点として目指すべきベストプラクティスに基づく対策(第三者評価)の評価段階を設けることが想定されています。対策には、経営責任、サプライチェーン防御などが盛り込まれ、要求事項の具体例として、ネットワーク境界管理、アクセス権管理、パッチ適用などランサムウェア対策の基本措置も掲げられており、ISO27001や海外の情報セキュリティ制度との整合性を持たせる形式でのベンチマークが検討されています。この制度の活用を通じて、発注企業にとっては取引先の対策状況を把握しやすくなり、サプライチェーンに起因するリスクを低減することを可能とし、受注企業にとっては自社がとるべき対策水準が明確となり、セキュリティ投資と説明責任を果たすことが可能となります。
経済産業省は、事業の性質上、安定供給・稼働が要求されることからその利用を停止させることが基本的には想定されていないビルシステムや、工場・プラント、発電所等を保有・利用する業種に関するサイバーセキュリティ対策に向けたガイドラインも公表しています。これらのガイドラインは、同種の施設を保有・利用する業種や、同様の性質を有するシステムを保有・利用する事業者にとって参考になる対応が含まれています。
まず、ビルシステムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン(第2版)は多種多様な関係者(マルチステークホルダ)が関与していることを背景に、サプライチェーンを構成する各関係者が共通して参照できるサイバーセキュリティ対策の指針として策定・公表されています。
次に、工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラインでは、工場システムはIoT化や自動化の進展に伴いネットワーク接続の機会が増加しており、サイバー攻撃のリスクが増大していることから、各業界・業種が自ら工場のセキュリティ対策を立案・実行することで、産業界全体、とりわけ工場システムのセキュリティの底上げを図ることを目的としてガイドラインが策定されています。このガイドラインでは、「サプライチェーン対策」という独立した項目を設けており、その重要性を強調し、対策として、「取引先や調達先に対するセキュリティ対策の要請、対策状況の確認」などが挙げられています※4。そして、現在、様々な業種の中でも、半導体産業の経済及び安全保障上の重要性やサイバー脅威/リスクの高まりを踏まえ、重層的なサプライチェーンにより成り立っている半導体産業における安定供給を維持するため、高度なサイバー攻撃に対するサプライチェーン全体でのセキュリティ対策の指針を示すことを目的として、半導体デバイス工場におけるOTセキュリティガイドライン(案)が検討されています※5。このガイドラインの対象には、半導体デバイスメーカーの製造部門だけでなく、製造装置メーカーや素材メーカーの製造部門も含まれます。その中では、デバイスメーカーと装置メーカーの間のセキュリティ連携強化が求められており、「既存の装置ツール調達プロセスにおける調達仕様書及び運用時の保守契約書に、セキュリティ要件(SEMI E187/E188 Capability Requirements 等)を追加することが重要である」とされています。
また、電力制御システムに関するサプライチェーンリスクに対するサイバーセキュリティ対策を支援・促進することを目的として、電力制御システムに関するサプライチェーン・セキュリティ対策の手引きが策定されています※6。「電力制御システムのサプライチェーンリスク」とは、電力制御システムが電気事業者に納入されるまでの開発や製造に関する一連の工程に加え、調達・運用・保守・廃棄を含むシステムライフサイクル全般におけるサイバーセキュリティ上のリスクを意味します。具体的な事例として、ネットワークスイッチの偽造品に不正プログラムが埋め込まれていた事例や、半導体の偽造品流通の増加が挙げられています。この手引きの対象には、電力制御システムを運用する電気事業者に加え、「委託先等」(委託先、再委託先、発注先、すなわちサプライチェーンに関係する全事業者)が含まれるとされ、「サプライチェーンリスク管理」として、委託先等の役割と責任範囲の明確化、サプライチェーンの依存関係と委託先等のセキュリティ対策状況の把握、及びリスク管理の実施が求められています※7。また、「セキュリティ仕様の確認」として、電力制御システムの調達時にセキュリティ仕様を明確にし、その準拠性を確認すること、及び仕様変更時の適切な管理が重要とされ、不正プログラム対策の管理や感染防止機能の要件化が推奨されています。そして、「機器の適切な管理」として、機器のライフサイクルを通じて管理・保護することが求められ、これには、機器の選定・設置、管理者・利用者の登録、データバックアップ、故障対応、廃棄方法、保存データの抹消までが含まれるとされています。
これらのガイドラインは、それぞれの産業分野の特性(ビルシステムにおける多種多様な関係者(マルチステークホルダ)による関与、半導体工場の国家安全保障上の重要性、電力制御システムの社会基盤性など)を踏まえつつ、サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク管理の重要性とその具体的な対策の方向性を示しています。特に、ライフサイクル全体にわたるセキュリティ要件の明確化、サプライヤーとの連携、そしてインシデント発生時の迅速な対応と情報共有の体制構築は、これらの産業分野に限られず、サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク対応として一般的に参考になるものと考えられます。
今回のニュースレターでは、取引先等のシステム・セキュリティ上の脆弱性が攻撃者に悪用され、ネットワークによってつながれた自社システム上で生じるセキュリティリスクやサイバー攻撃により発生した取引先等における事業停止等により生じる自社の事業リスクへの対応について、設例を用いて取引先・委託先が実施すべきセキュリティ対策上の水準や要求事項のほか、セキュリティ対策の実施状況に対する検証を可能にするためのエビデンス提出共有や監査への協力等について解説しました。次回のニュースレターでは同様の設例を用いて、再委託先等の管理策、インシデント対応等について解説します。
※1
「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」(改正法第5条2項4号)
※4
契約開始時や定期的なセキュリティ教育、脆弱性情報の迅速な共有、サプライチェーンにおける脅威や影響度、対応状況の把握が含まれています。
※7
この中で、発注先・委託先の選定基準として、管理体制の構築、インシデント発生時の連絡体制、再委託の制限、従業員教育、意図しない変更が行われない管理体制、不正変更時の追跡調査協力、外国の法的環境による契約違反の報告などが具体的に挙げられています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


日本証券業協会 (2025年9月)
梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)


(2025年9月)
福井信雄


塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年10月)
犬飼貴之


(2025年9月)
関口朋宏(共著)


工藤靖


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年8月)
杉本花織


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


(2025年8月)
杉本花織


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


工藤靖


ジャスティン・イー、室憲之介(共著)


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


工藤靖


(2025年7月)
平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)


ジャスティン・イー、室憲之介(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
三笘裕、平松慶悟(共著)