
鈴木謙輔 Kensuke Suzuki
パートナー
東京
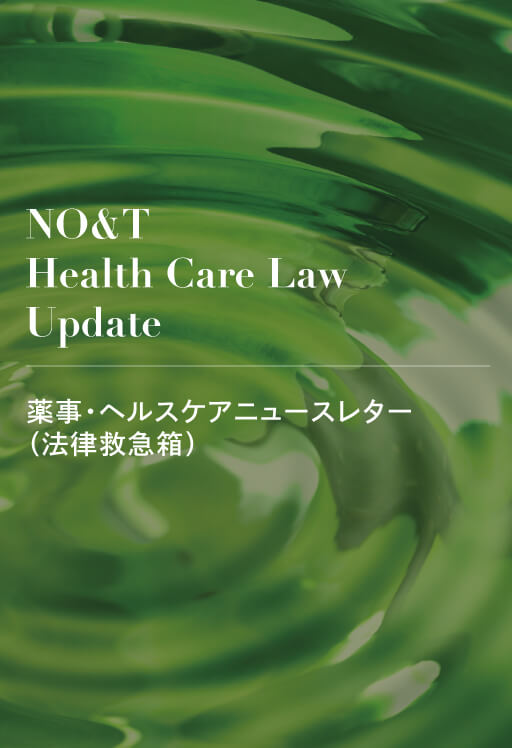
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
本ニュースレターに関連するウェビナーは以下をご覧ください。
薬事・ヘルスケアオープンスクール
「遺伝子・ゲノムビジネスに関わる規制と動向」
本ニュースレターの中国語版はこちらをご覧ください。
遺伝情報を利用するビジネスは、ゲノム医療や疾患リスクの判定等を行う遺伝子分析サービスといった形で、身近なものになりつつあり、大きな期待と注目を集めている。一方で、遺伝情報の取扱いについては、包括的な規制を定めた一元化された法律はなく、適用される法律や規制が複層的に絡み合っており、全体的な規制枠組みが見えづらい分野でもある。
本号では、遺伝子ビジネスを行うに当たって、遺伝情報の特性を踏まえ、参照する必要がある遺伝情報の取扱いに関する規制を概観し、留意点を紹介する。
遺伝情報の取扱いに関する規制を考える前提として、そもそも遺伝情報とは何か、どのような特性があるのかを理解することが有用となる。
遺伝情報は、文脈により様々な定義がなされるが、特に個人情報保護法制との関係では、「ゲノム情報の中で子孫へ受け継がれるもの」を指すとされる(ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース「ゲノム医療等の実現・発展のための具体的方策について(意見とりまとめ)」(平成28年10月19日))。ここでいうゲノム情報とは、塩基配列に解釈を加え意味を有するものを指す。塩基配列を文字列で表記したものをゲノムデータといい、ゲノムデータを解釈することによって導かれる一定の命題がゲノム情報であるといえる。
遺伝情報は、他の情報と異なる種々の特性を有するが、一つの重要な特性として、源泉情報性が挙げられる。源泉情報性とは、ゲノムデータに含まれる情報の意味内容や分量が膨大であり、ゲノムデータからは様々な遺伝情報を引き出すことが可能となるというものである。これを本人の視点から見ると、遺伝情報の提供は、それが本人の意思に基づくものであったとしても、本人の知らないでいる権利を害するおそれがつきまとうことを意味する。遺伝情報を取り扱う事業者としては、このような本人の権利にも注意を要する。
遺伝情報は、多くの場合、「個人情報」、さらには、「要配慮個人情報」に該当するものとして、個人情報保護法の適用対象になると考えられる。すなわち、「要配慮個人情報」の一類型である「医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果」に関して、「医療機関を介さないで行われた遺伝子検査により得られた本人の遺伝型とその遺伝型の疾患へのかかりやすさに該当する結果」が含まれるとされており(個人情報保護法ガイドライン(通則編)2-3(8))、これによれば遺伝情報が広くカバーされることになると思われる。要配慮個人情報については、個人情報保護法上、通常の個人情報よりも慎重な取扱いが求められており、本人の同意なく取得することが原則として禁止されるほか、第三者提供に当たっていわゆるオプトアウトの利用が認められていない。
個人情報保護法については、各省庁より様々なガイドラインが公表されているところ、個人遺伝情報を用いた事業には、経済産業省によって「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」が定められている。この経産省ガイドラインは、塩基配列・一塩基多型、体質検査等の遺伝子検査、親子鑑定等のDNA鑑定、遺伝子受託解析といったビジネスを適用対象としており、遺伝情報の特性に着目して、個人情報保護法よりも厳格な規制を定めている。例えば、本人から個人遺伝情報を取得する際には、予測される結果や不利益、事業終了後の試料の取扱い等の事項につき、インフォームド・コンセント(本人が十分な説明を受け、理解し、自由意思に基づいて同意を与えること)を得ることが必要とされており、極めて慎重な配慮が求められている。
遺伝情報の特性及びこれを踏まえた取扱いに関わる問題点については、様々な議論がなされているが、現時点では、議論が成熟し法規制の枠組みが整備されている状況にはないといえる。例えば、発症済みの疾患に対する診断のために行われた遺伝子検査の結果と比べて、将来特定の疾患に罹患するリスクを予示する遺伝子検査の結果は、健康な者を前もって区別し得る点でプライバシー・平等の観点から保護の必要性が高いと考えられるし、自発的に受検した遺伝子結果の取得と比べると、遺伝子検査を受検させた上でその結果の提供を求めること(例えば、保険加入の条件とすること)は、本人の知らないでいる権利を害する危険性が高いといえる(保険領域における遺伝情報の取扱いに係る諸外国の動向やその日本における規律への示唆については、山本龍彦、石本晃一ほか「保険領域における遺伝情報の保護および利用について」(慶應法学47号)も参照されたい)。これらの議論を踏まえ、将来的には規制内容のさらなるアップデートも予想されることから、遺伝子ビジネスを行う事業者としては、今後も議論の動向を注視し、法令・ガイドライン等の改正・新設や規制環境の変化をフォローしていくことが重要となる。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)