
木村聡輔 Sosuke Kimura
パートナー
東京

NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター
ニュースレター
プレ・ヒアリング、コーナーストーン・プロセス等のローンチ前のエクイティ投資家とのコミュニケーション(2)(2022年2月)
プレ・ヒアリング、コーナーストーン・プロセス等のローンチ前のエクイティ投資家とのコミュニケーション(3)(2022年3月)
新規上場(IPO)や上場会社による公募増資といったエクイティ・オファリング案件を行う際、案件公表・ローンチ前の準備期間中における投資家候補とのコミュニケーションは厳しく制約されます。他方、プレ・ヒアリング(需要の見込み調査)や親引けの準備行為といった枠組みのなかで投資家候補と一定のコンタクトをとる実務は従来から許容されており、また、第三者割当増資のようにローンチ前に割当予定先と協議することが当然に予定されているオファリング形態も存在します。さらに、近時は香港等の諸外国で行われているコーナーストーン投資家となりうる候補先とのコンタクトについても、ウォールクロス等の所定の手続きを経た上で認める動きも見られるところです※1。
他方で、エクイティ・オファリング案件におけるローンチ前の投資家コミュニケーションが、どのような範囲で認められるのか(言い換えれば、どのような規制に違反しうるのか)については必ずしも明確ではない部分もあるためか、実務的には過度に謙抑的な解釈・運営がなされる場面も少なくないように思います。近時、企業のリスクマネー調達や投資の活性化に関する様々な文脈でローンチ前の投資家候補とのコミュニケーションが話題になることがありますが、これを取り巻く規制の概要と実務上の課題を理解した上で議論を行わないと、実務の現場と噛み合わないことが懸念されます。
そこで、今回のニュースレターでは、各種のエクイティ・オファリング案件の類型毎に、ローンチ前の投資家コミュニケーションの規制の枠組みを整理し、実務上の問題点を検討することにします。
エクイティ・オファリング案件におけるローンチ前の投資家コミュニケーションの適法性を検討する前提として、理解しておくべき法令・自主規制は多くありますが、主なものと、それぞれの留意点は以下のとおりです※2。
規制の概要:
有価証券届出書の提出が要求されるオファリング案件(有価証券の募集・売出し案件)においては、原則として、有価証券届出書の提出前に勧誘行為を行うことは禁止されています(いわゆるガンジャンピング規制、金融商品取引法4条1項)。しかし、金融商品取引法上、勧誘行為の定義規定は設けられておらず、具体的にいかなる行為がかかる勧誘行為に該当するかは解釈に委ねられています。この点、エクイティ・オファリング案件の準備期間中において、投資家に対して企業内容等に関する情報を提供することは勧誘行為に該当するリスクがあると考えられており、実務上、相当程度謙抑的な運用がなされています。
いかなる場合に金融商品取引法が禁止する勧誘行為に該当するかという点については、最終的には個別案件毎の判断が必要となりますが、主に(1)「勧誘」に該当しない行為類型への該当性の判断と(2)勧誘場所の判断の2つの視点での検討が重要となります※3。
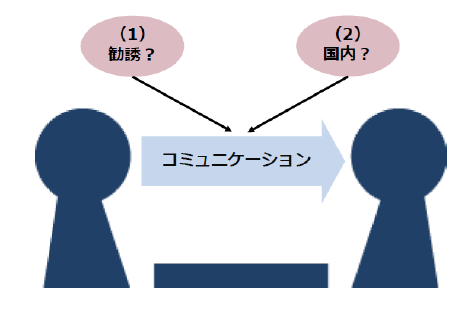
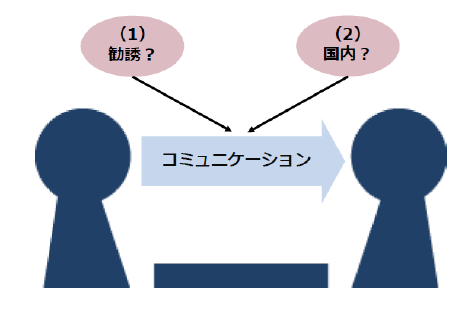
企業内容等開示ガイドラインにおいて、金融商品取引法上の「勧誘」に該当しない行為として、以下のような行為類型※4が例示されています(企業内容等開示ガイドラインB2-12)。そのため、エクイティ・オファリング案件の準備期間中における投資家とのコミュニケーションであっても、これらの行為類型に該当する限りは「勧誘」には該当せず、ガンジャンピング規制に違反することもありません。
第三者割当の割当予定先の選定等を目的とした調査、協議等を「勧誘」に該当しないとする規定です。
ただし、あらゆる第三者割当をカバーするわけではなく、割当予定先が限定され、かつ、当該割当予定先から当該第三者割当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれが少ない場合でなければならない点に留意が必要です。つまり、第三者割当の形態をとれば、いかなるコミュニケーションも許容されるというわけではなく、例えば、第三者割当の割当先が割当てた株式を割当後直ちに転売するおそれがある場合には、少なくとも本①を根拠に「勧誘」に該当しないということは困難といえます。
オファリングの対象となる有価証券に対する投資家側の「需要の見込み」の調査を「勧誘」に該当しないとする規定です。
需要の見込み調査を行う場面としては、募集(ただし、第三者割当は除かれています。)だけでなく、売出しも広く含むものですが、調査対象とできるのは特定投資家と一定の大株主に限定されている点、調査の実施に際しては証券会社がプレ・ヒアリングを行う際に法令上要求されている措置(後述)を講ずる必要がある(その結果、本②の類型は、通常、発行会社・売出人自身による需要の見込み調査目的での投資家とのコンタクトには利用しづらい)点に留意が必要です。
有価証券届出書の提出の1ヶ月以上前までに行う発行者に関する情報発信(情報の再発信防止措置を講ずることが必要)を「勧誘」に該当しないとする規定です。なお、有価証券届出書の提出の1ヶ月以上前であっても、オファリングに関する情報発信を行うことはできないこととされています。
ただし、実際には、ある投資家とのコミュニケーションが上記の行為類型に該当するか否かの判断が容易でない場合もあり、やはり個別検討が必要となる場面が少なくありません。例えば、②のプレ・ヒアリングについては、調査できるのは需要の「見込み」であり需要そのものを調査することはできない点、調査のためには投資家候補に対して予定しているオファリングに関する一定の情報提供が必要となりますが、何を提供できるかについて明確化されていない点なども踏まえた個別検討が必要となります。また、③のローンチの1ヶ月以上前のコミュニケーションについても、許容される「発行者に関する情報発信」と禁止される「オファリングに関する情報発信」の線引きは曖昧であり、やはり個別検討が必要となります。
もっとも、ある行為が上記の行為類型のいずれにも該当しない場合であっても、即座に「勧誘」と評価されるわけではなく、やはり実態を踏まえた個別検討を行い、その結果、「勧誘」ではないと整理する余地がある点にも留意が必要です。例えば、実務上許容されている「親引け(売先指定)」については、実際の勧誘行為は有価証券届出書の提出後に行われるとはいえ、それ以前の段階でも親引け先との間には一定のコミュニケーションが存在しうるところ、かかるコミュニケーションを「勧誘」とは評価しないのが確立した実務ですが、このような親引けの準備行為は、上記のいずれの行為類型にも該当しません。
エクイティ・オファリング案件の準備期間中における投資家とのコミュニケーションを実施するニーズは、必ずしも国内投資家を対象とするものだけでなく、その目的によっては海外投資家とのコミュニケーションが必要となるケースもあり得ます。この点、コンタクト先が国内投資家なのか海外投資家なのかにより、留意すべき規制内容にも大きな違いが生じうるところであり、議論の前提として国内外いずれの投資家を対象としようとしているかを明確にする意義は大きいといえます。
ガンジャンピング規制は有価証券届出書の提出が要求されるオファリング案件に適用される規制です。そして、有価証券届出書は日本国内で行われる募集・売出しについてのみ提出が求められるものです。言い換えれば、海外で行われる募集・売出しについては有価証券届出書の提出義務は無く、ガンジャンピング規制の適用もありません。その結果、エクイティ・オファリング案件のローンチ前に投資家に対して勧誘行為を行ったとしても、それが海外で行われている限り、少なくとも日本法上のガンジャンピング規制の違反になることはありません※5。
勧誘行為の定義規定と同じく、勧誘行為の実施場所をどのように判定するかという点についても、金融商品取引法は特段の規定を設けておらず、勧誘行為の実施場所が日本国内か海外かを明確に決定することが容易でない場合も少なくありません※6。この点、金融商品取引法上の開示規制は基本的には国内投資家の保護を目的として規定されていることは明らかですので、開示規制の適用の有無の決め手となる「勧誘行為の実施場所」の判断に際しては、保護の対象である勧誘行為の相手方(投資家)の所在地を一義的な判断基準とするのが合理的なように思われます。
もちろん、勧誘行為の相手方(投資家)の所在地の判断自体が難しい場合もある上、勧誘行為の相手方(投資家側で投資判断を行う者を含む)の所在地のみで画一的・形式的な判断を行うこととすると、潜脱的な行為を許容することにもなりかねませんので、最終的には事案毎の個別検討は避けられません。実務上は、勧誘場所に関して無用の疑義が生じる事態を避けるべく、可能な限り、関連する当事者・行為等を国外に配置することを検討することになりますが、かかる検討においては、あくまで開示規制の趣旨・目的との関係で合理的に必要性が認められる範囲での措置を必須の対応事項とすべきと思われます。また、そのような観点からは、投資家向けの情報発信の発信元やその準備行為が行われる場所については、「勧誘行為の実施場所」を判断する上で決定的な要素にはならないと整理可能な場合が多いように思われます。
金融庁も、過去に、ユーロCB案件など有価証券届出書の提出がなされないことが実務上確立されているケースにおいて、個別具体的な判断が必要という前提のもとですが、国内の金融商品取引業者が海外用の目論見書の作成に関与したり、海外の金融商品取引業者との事務連絡を行っていることをもって勧誘が国内で行われていると判断されるわけではない点や※7、一般的には、国外でのみ有価証券の取得勧誘が行われるものであって、国内居住者が当該有価証券の取得ができないものであれば、当該有価証券について電話等により国内から国外居住者に対してセールス活動を行ったとしても、我が国の勧誘規制は適用されない点を明示しているところです※8。
これに対して、企業内容等開示ガイドラインでは、無届勧誘の例示として「海外の相手方に勧誘を行ったが、当該相手方の代理等を行う金融商品取引業者に対する勧誘が国内で行われる等実態に鑑み、海外での募集又は売出しとはみなされないにもかかわらず、有価証券届出書等を提出しない場合」(B4-23)が挙げられています。これは、勧誘の相手方が海外にいれば常に海外勧誘と評価されるわけではない旨を指摘している点で厳格な見解を示すものとの評価もありえますが、他方で、勧誘行為の相手方(投資家側で投資判断を行う者を含む)の所在地が重要な要素であることを当然の前提としているようにも読める規定です。特に、上記ガイドラインで示されている事例は、投資家側の代理等を行う者が日本国内で勧誘を受けているというケースであり、まさに潜脱的な行為といえるため、「勧誘行為の相手方(投資家)の所在地を一義的な判断基準とする」という上記の整理と矛盾するわけでもないように思います。
なお、上場会社については、海外での募集・売出しがあった場合に臨時報告書の提出義務が発生する可能性があるため、その点についての留意も必要となります。この点は、上場会社による公募増資等の項目(次号以降)で別途ご説明します。
募集・売出し案件においては有価証券の引受業務を行う証券会社の関与が欠かせません。他方で、証券会社は、募集・売出し案件における発行会社・売出人と異なり、金融商品取引業者として金融商品取引業等に関する内閣府令(業府令)に基づく規制を受けます。この規制は証券会社を名宛人とするものですが、証券会社が規制される結果、オファリング案件全体に影響があるため、発行会社・売出人も間接的に影響を受けます。
とりわけ上場会社による公募増資の予定といった法人関係情報※9の取扱いについては各種の規制が設けられていますが、かかる法人関係情報に関する規制に関して、エクイティ・オファリング案件におけるローンチ前の投資家コミュニケーションを実施するに際しては、主に以下の2つの規制を意識する必要があります※10。
証券会社は、「有価証券の売買その他の取引・・につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為」が禁止されています。発行会社が上場会社である場合、ローンチを控えたエクイティ・オファリング案件の存在は、通常、法人関係情報に該当しますので、かかる法人関係情報を提供した上で、顧客に対して「勧誘」を行った場合、本規定に違反することとなります。
エクイティ・オファリング案件において、ローンチ前に投資家とコミュニケーションをとる場合、その目的に照らして、当該案件の予定を伝えないわけにはいかない場面が多いと思われるところ、その場合に本規制を遵守するためには、当該コミュニケーションが「勧誘」ではない(例えば、需要の見込みに関する調査である)といえることが決定的に重要となります。
証券会社は、エクイティ・オファリング案件のうち上場会社の株式・新株予約権・CBの募集案件について、ローンチ前に投資家に対してプレ・ヒアリング(需要の見込みに関する調査)を実施する場合、調査対象者又は調査の委託先である第三者に対し当該募集に係る法人関係情報(すなわち準備中のエクイティ・オファリング案件に関する情報)を提供するには、所定の措置をとることが要請されます。本規制が適用されるプレ・ヒアリングの対象は国内投資家に限定されておらず、海外投資家に対するプレ・ヒアリングであっても本規制に従った措置が必要となります。
他方、本規制は、非上場会社の案件(例えば、IPO)や上場会社のエクイティ・オファリング案件であっても売出し・ブロックトレード案件には適用がなく、上記「1.(1) 「勧誘」に該当しない行為類型への該当性の判断」に記載した「②プレ・ヒアリング(需要の見込み調査)」として規定されているプレ・ヒアリングとは対象範囲が異なる点に留意が必要です※11。
証券会社は、本規制の適用がある案件においてプレ・ヒアリングを実施する場合、以下の措置をとる必要があります。なお、証券会社が第三者に委託してプレ・ヒアリングを実施する場合も上記と同等の対応を取る必要がありますので、例えば、証券会社の海外関連法人が海外投資家向けにプレ・ヒアリングを実施する場合も基本的に同等の規制に服することになります。
法令遵守管理に関する業務を行う部門から、下記の事項について、あらかじめ承認を受けていること
・当該調査を行うこと
・調査対象者
・調査対象者に提供される法人関係情報の内容
・その法人関係情報の提供の時期及び方法が適切であること
調査対象者の間で、インサイダー取引規制違反となるような取引の禁止及び秘密保持について定めた契約(NDA)をあらかじめ締結すること
証券会社内における当該プレ・ヒアリングに係る事務責任者及び当該プレ・ヒアリング調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後5年間これを保存するために必要な措置を講じていること
なお、このようなプレ・ヒアリングに関する規制が存在することは、ローンチ前にエクイティ・オファリング案件の存在を投資家に伝達した上で行うコミュニケーションであっても、「勧誘」ではなく「需要の見込み調査」に該当すると評価可能な範疇が存在しうる(そのようなコミュニケーションが常に「勧誘」となるわけではない)という理解を当然の前提にしているといえます。もっとも、ある投資家とのコミュニケーションが「勧誘」ではなく「需要の見込み調査」に該当すると整理できるかは、個別検討が必要であり、実務上最も悩ましい問題の一つともいえ、一般的には、上記「1.(1) 「勧誘」に該当しない行為類型への該当性の判断」に記載した「②プレ・ヒアリング(需要の見込み調査)」への該当性のほか、需要の見込み調査の実施のために提供が必須といえる情報の範囲(例えば、発行会社の名称、発行する証券の種類、発行予定数、発行予定時期、発行体の財務情報等)を慎重に検討していく必要があるところです。
日本証券業協会は、上記「2.(2) プレ・ヒアリングに関する規制(業府令117条1項15号)」に記載の法令に対応する形で、自主規制として「協会員におけるプレ・ヒアリングの適正な取扱いに関する規則」(プレヒア規制)を設けています。このプレヒア規制は、基本的には業府令がプレ・ヒアリングの実施(海外関連法人に委託して実施する場合を含みます。)に際して各証券会社に求められる措置・社内体制を具体化するものですが、引受けを伴う国内における募集に係るプレ・ヒアリングを原則禁止としている点で追加的な規制を課す内容となっています。その結果、現在、上場会社による国内公募増資案件においてプレ・ヒアリングは行われていないため、プレヒア規則により、事実上、上場会社による公募増資においては海外プレ・ヒアリングのみが許容されることとなっています。
なお、プレヒア規制についても、非上場会社の案件や上場会社の売出し・ブロックトレード案件(ただし、上場会社による子会社上場案件等、何らかの法人関係情報が存在しうるケースについては別途の留意が必要です。)は規制対象としていないため、これらの案件のために国内でプレ・ヒアリングを実施したとしても、プレヒア規則の違反とはなりませんが、万が一、需要の見込み調査を超えて勧誘に至るコミュニケーションを取ってしまうと、その他の規制に違反するリスクがあるため、投資家とのコミュニケーションの内容や実施場所については、慎重な検討が必要となります。
日本証券業協会は、「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(配分規則)において、証券会社が募集・売出しの引受業務を行うに際して「親引け」、すなわち発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等の実質的に類似する行為を含みます。)を行うことを原則として禁止しています。親引け規制は、プレヒア規制とは異なり、広く募集・売出しの引受業務を行う場合に適用されるため、非上場会社の案件(例えば、IPO)や上場会社の売出し・ブロックトレード案件においても遵守が必要となります。
本規制では、証券会社は、募集等の引受けを行うに当たっては、市場の実勢、投資需要の動向等を十分に勘案した上で、当該募集等の引受け等に係る株券等の配分が、公正を旨とし、合理的な理由なく特定の投資家に偏ることのないよう努めなければならないとされており、「親引け」は下記の条件を満たす場合にのみ例外的に許容されるものとされています。
親引けを行ったとしても上記の公正配分等の規定に反する配分にならないと証券会社が判断したこと
発行者が、当該親引けについて、親引け予定先の状況※12、当該親引けに係る株券等の譲渡制限、発行条件に関する事項、当該親引け後の大株主の状況、株式併合等の予定の有無及び内容、その他参考になる事項を、有価証券届出書(又は発行登録書)の提出後において適切に公表すること
当該募集に係る払込期日若しくは払込期間の最終日又は当該売出しに係る受渡期日から180日を経過する日まで継続して所有することの確約を、主幹事証券会社が親引け予定先から書面により取り付けること
なお、日本証券業協会は、上記に関連して、親引けガイドライン※13を制定しており、上記「①証券会社の判断」に当たっては、当該親引けの必要性及び内容について、当該親引けにより配分を受ける投資家による中長期的かつ安定的な保有の見込みも勘案しながら、例えば、当該投資家による発行者の経営に対する一定の関与の有無、当該親引けによる発行者の企業価値向上の可能性の有無、当該親引けの背景における支配権争いの要素の有無等の観点を考慮すべきことを示唆しています※14。他方で、親引けを認めるという判断が許される場合については、親引けガイドラインにて一定の例示がなされていますが、あくまで例示という位置づけであり、限定列挙はなされておらず、上記の制度趣旨を踏まえた柔軟な対応を行う余地を残す規定となっています。
加えて、配分規則は、「引受会員が引受けを行う株券等の募集又は売出しと並行して行われる、当該株券等の発行者が発行する株券等の第三者割当」を「並行第三者割当」と定義し、並行第三者割当が行われる場合には、引受証券会社が、発行会社に対して、上記の親引け規制の趣旨を尊重するよう要請することを求めています。
以上が、エクイティ・オファリング案件におけるローンチ前の投資家コミュニケーションに関連して留意すべき法令・自主規制の概要です。次号以降では、具体的な案件類型毎に、これらの規制をどのように遵守すべきか等についてご紹介します。
※1
例えば、日本証券業協会の「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」でも明示的にその可否等についての議論がなされています。
※2
なお、海外オファリングを実施する際には、海外法に基づく検討も必要となります。
※3
加えて、損害賠償責任等のライアビリティリスクの観点から、コミュニケーションの際に提供する情報の内容の正確性等についても案件毎に慎重な検討が必要となります。
※4
本文記載の行為類型のほか、④法令又は金融商品取引所の規則に基づく情報の開示、⑤発行者の通常の業務過程で行われる定期的な企業情報(募集又は売出しに関する情報を除く。)の発信、⑥発行者の通常の業務過程で行われる新製品又は新サービスの発表、⑦(記者、アナリスト、投資家等からの)発行者に対する自発的な問合せに対して、その製品・サービスその他の事業・財務の状況に関する回答、⑧金融商品取引業者等が通常の業務過程で行う上場会社である発行者に係る従来から継続的に行われているアナリスト・レポートの配布又は公表も掲げられており、実務上の重要性は非常に高いものの、今回のニュースレターでは詳細は割愛しています。
※5
なお、上場株式の売出し・ブロックトレード案件も有価証券届出書の提出は要求されておらず、やはりガンジャンピング規制の適用はありません(ただし、国内売出し案件については勧誘開始前に有価証券通知書を提出する必要が原則としてありますので、やはり「勧誘」の実施時期には留意が必要です。)。そのため、ガンジャンピング規制の適用に留意すべき売出しとは、新規上場(IPO)に伴い実施される国内売出しということになります。
※6
特に海外投資家とのやりとりは電話・Eメールや電話会議・Web会議といった手段で行われることが多く、このような遠隔地にいる者同士のコミュニケーション手段を講じた場合には行為地を直接的に認定しづらい(認定することに特段の意味を見出しづらい)ように思われます。
※7
平成22年6月4日パブリックコメント回答No.24(https://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100604-4/01.pdf)
※8
規制改革ホットライン(平成27年度分)への金融庁の回答(管理番号271215103)(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/siryou2/27_kinnyuu.pdf)
※9
「法人関係情報」とは、大要、上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものを指すため、未上場会社の案件では基本的には適用がありません。ただし、IPOを行おうとする未上場会社の株主に上場会社がいるようなケースでは、IPOを実施するという事実が、当該上場会社にとっての法人関係情報に該当する可能性があり、その場合にはやはり法人関係情報に関する規制に留意が必要となります。
※10
なお、本文記載の2つの規制に加えて、エクイティ・オファリング案件に限らず、広く法人関係情報に関する管理義務として、不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる必要があること(業府令123条1項5号)も重要です。
※11
なお、本規制が非上場会社による新規上場(IPO)や上場会社の売出し・ブロックトレード案件について適用されないことは、証券会社において、これらの類型の案件においてプレ・ヒアリングの実施が法令上禁止されていることを意味するわけではありません。これらの案件においても、業府令117条1項15号に従った(又は準じた)措置を実施した上で、投資家とのコミュニケーションが「勧誘」に至らない範囲でのプレ・ヒアリング(需要の見込み調査)を行うことは法令上可能なはずです。
※12
具体的には、親引け予定先の概要、発行者と親引け予定先との間の関係、親引け予定先の選定理由、親引けしようとする株券等の数、当該親引けに係る株券等の保有方針、親引け予定先における払込みに要する資金等の状況及び親引け予定先の実態をいいます。
※14
親引けガイドラインでは、親引けの原則禁止ルールについて、「発行者による株主や支配権の所在の恣意的な選択を抑止する、株式持合いを助長しない、特定の者に対する利益供与に用いられないようにする、といった趣旨」があるとの説明がなされており、例外的に親引けを認める場合も、かかる趣旨が全うされているかを確認する必要があるといえます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年9月)
金田聡


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)