
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
近年、NFT(Non-Fungible Token)というブロックチェーン上の非代替トークンが様々な分野で活用されています。例えば、NFTは、アート作品やスポーツ関連コンテンツの販売において積極的に活用されており、その他にも様々な分野で目覚ましい発展を遂げています。
NFTの主流な販売方法の一つとして、提供されるNFTがランダムに決定される、ランダム型販売という方法が挙げられます。例えば、海外においては、プロバスケットボール選手の試合動画のNFTをランダムに組み合わせたパッケージが販売されており、ランダム型販売が活用されています。NFTの中には、二次流通市場において発行時と異なる価格で取引されるものがあり、ランダム型販売のうちの一部は賭博にあたるおそれがあることについて懸念が示されていたところ、「NFTホワイトペーパー」※1でも賭博に該当しない販売手法の明確化が課題として認識されていました。
もっとも、全てのランダム型販売が賭博に該当するわけではないところ、業界団体を中心に議論が重ねられ、スポーツエコシステム推進協議会が本年9月20日に、また、ブロックチェーン関連業界団体から構成される合同会議(以下「合同会議」といいます。)が本年10月12日に、それぞれ、賭博に該当しないようなランダム型販売について、ガイドラインの形で一定の見解を示しました※2・3。
以下、NFTホワイトペーパーや業界団体によるガイドラインを踏まえて、NFTのランダム型販売について、賭博との関係(以下2)、消費者保護の考え方(以下3)、その他の法的課題(以下4)について説明していきます。
賭博罪(刑法185条)における「賭博」とは、2人以上の者が、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うことであると考えられています※4。この「賭博」該当性を判断するためには、①「偶然の勝敗」、②「財物や財産上の利益」、③「得喪を争う」の3つの要件が満たされるか否かを検討する必要があります。
ランダム型販売において、購入者がいかなるNFTを取得するか否かは偶然性に左右されるため、①「偶然の勝敗」の要件は満たされると考えられます。また、NFTは対価を支払って取得する対象である以上、基本的には②「財物や財産上の利益」にあたると考えられます※5。
もっとも、ランダム型販売が、③「得喪を争う」ものと評価されない場合、賭博罪は成立しないことになります。
「得喪を争う」とは、勝者が財産を得て、その反面、敗者がそれを失うことをいいます※6。
一般的なNFTは、新規に発行される場合、実際の販売行為における価格設定以外にその価値を算定するための客観的な指標を見出すことが難しいため、一次販売におけるNFTの価値は、原則として、NFTを新規発行して販売する者(以下「発行者」といいます。)が決定した販売価格を基準にすることが相当であると考えられています※7。このように当該NFTの価値が発行者によって決定された販売価格を基準に判断される場合には、発行者は販売価格相当額のNFTを購入者に提供し、購入者は販売価格相当額の対価を発行者に対して支払うに過ぎず、いずれかが財産を得て、その反面、他方がそれを失っている関係があるとは言えないと考えられます。また、この場合、発行者が、当該ランダム型販売について、いかなる購入者に対しても同じ金額でランダム型販売を行うのであれば、いかなる購入者も販売価格相当額の対価を出捐して販売価格相当額のNFTを取得するに過ぎず、購入者間においても、いずれかが財産を得て、その反面、他の購入者がそれを失っている関係があるとは言えないと考えられます。
したがって、上記のとおり、当該NFTの価値が発行者によって決定された販売価格を基準に判断される場合、NFTの新規発行にかかるランダム型販売は、発行者購入者間及び購入者間において「得喪を争う」関係が認められず、賭博罪の成立が認められないと考えられます。
NFTの新規発行にかかるランダム型販売が賭博にあたらないことの前提として、発行者が決定した販売価格が当該NFTの価値として認められることが重要です。NFTのランダム型販売を行うにあたって、当該NFTの価値が発行者によって決定された販売価格であると認められない場合、「得喪を争う」という要件を満たし、賭博該当性が肯定される場合があるため注意が必要です。
まず、ランダム型販売の販売価格と異なる価格で同種類のNFTを別途販売する場合、ランダム型販売において発行者が決定した販売価格が当該NFTの価値であるとは言えなくなり、「得喪を争う」関係が認められる場合があります。例えば、発行者が、A、B、C、D、EのNFTのいずれか一つを20,000円の販売価格でランダムに販売するとき、Aを30,000円で別途販売し、Bを10,000円で別途販売する場合、ランダム型販売の販売価格20,000円が当該NFTの価値であると考えることが難しくなり、特にA及びBの価値はそれぞれ30,000円及び10,000円であると評価される可能性があります。この場合、ランダム型販売において、NFTの購入者は、20,000円の対価を出捐する代わりに20,000円より価値の低いBを取得する可能性があり、その差分について発行者が財産を得て、その反面、購入者がそれを失う関係が認められる可能性があります。そのため、この場合には「得喪を争う」関係が認められ、賭博罪が成立するおそれがあります。
また、ランダム型販売において、NFTの発行者またはその関係者が二次流通市場で当該NFTを常時異なる価格で購入する場合も同様に、「得喪を争う」関係が認められる場合があるため注意が必要です。
さらに、NFTの二次流通市場では利用者間でNFTの売買が行われるところ、二次流通市場の運営者としては、利用者間で賭博に該当するランダム型販売が行われないように措置を講じることも重要です。
なお、NFTの中には時間の経過や一定の作為を行って初めてランダムにその内容が明らかになる、リビール機能を有するNFTも存在するところ、上記のランダム型販売と同様、内容が明らかになる前のNFTの売買が、売買当事者間で「得喪を争う」関係に至っていないかどうかを慎重に検討することが重要です。
上記のとおり、NFTのランダム型販売は賭博罪の成否との関係で注意すべき点がありますが、賭博にあたらないランダム型販売を行うことは可能であると考えられます。特に得喪関係が生じないようにランダム型販売を行うことが重要となります。
上記のランダム型販売と賭博に関する考え方は、NFTゲームにおいても応用することが可能です。NFTゲームの中には、NFTキャラクター同士を掛け合わせて新たなNFTキャラクターをランダムに生成させる仕組みが採用されることがあります。かかるNFTの生成過程にはランダム性が認められ、賭博該当性が問題になると考えられます。もっとも、得喪関係が生じないのであれば、上記のようなNFTキャラクターの生成について賭博罪が成立することはありません。NFTのランダム型販売に関する基本的な考え方を前提に、当該NFTの生成方法や当該NFTの性質を十分検討し、賭博にあたらない仕組みを構築することが重要です。
NFTのランダム型販売が賭博にあたらないとしても、消費者の射幸心が過度に煽られる場合や当該NFTに関する説明が不十分な場合には、NFTの購入者の保護に欠けることになります。NFTホワイトペーパーでも、消費者保護の観点から事業者によるガイドラインの策定が期待される旨述べられています。そして、合同会議による業界団体のガイドラインにおいても、NFTホワイトペーパーを受けて、適正な情報提供や未成年者保護に関するルール整備が試みられています。
例えば、ガイドラインは、NFTの投機的価値が高いことを意識させ、消費者の購買意欲を過度に煽ることを避けるよう求めています。NFTのランダム型販売において当該NFTの広告をする場合、投機的側面を強調し過ぎてしまうと利用者の射幸心を過度に煽ることになり、消費者被害につながるおそれがあります。ランダム型販売の対象となるNFTを広告するに際しては、ガイドラインを遵守しつつ、消費者被害を生じさせないように十分注意する必要があります。
また、NFTには様々な種類があるところ、発行予定総数や出現確率、付与されるユーティリティなどは、消費者がNFTの購入を判断する上で重要な情報になります。当該NFTを取り巻くプロジェクトの内容にもよりますが、消費者にとって重要であると考えられる情報については可能な限り事前に説明することが望ましいと考えられます。
さらに、ガイドラインは、未成年者に対して一定の配慮をすることを求めています。未成年者の中には、判断能力が不十分であるために高額課金トラブルに巻き込まれる者も多いです。ランダム型販売を通じて購入できるNFTの金額や回数を制限するなど、未成年者に対して一定の配慮をする必要があります。Wallet ConnectなどによりNFTの取引市場にアクセスできるサービスを提供する事業者にとっては、利用者が未成年者であるか否かを判断することが難しい場合も多いため、利用規約の整備やアプリケーションの仕組みにより未成年者保護の体制を整えることが重要となります。
NFTの決済方法については、現金決済、クレジットカード決済、トークン決済など様々な手段が考えられます。ここでNFTのエコシステムを発展させるためにトークン決済が採用されることがありますが、当該トークンが暗号資産や前払式支払手段、電子決済手段等にあたるか否かを検討する必要があります。トークンの法的性質に応じて検討すべき規制が異なることには注意が必要です。
また、販売するNFTの種類によって様々な法的課題を検討する必要があります。アート作品をNFTにして販売する場合は、NFTの保有者にどのような権利を付与するのかという点も含めて、著作権などの知的財産権の保護範囲について検討する必要があります。そして、スポーツの試合映像を切り取ってNFTにする場合は、選手のプライバシー権や肖像権、試合の放映権などについて調整を行う必要があります。また、NFTの転売時におけるロイヤリティの設定をする場合は、発行者及び発行関係者並びに購入者との間の権利関係について慎重に検討する必要があります。
さらに、当該NFTに何らかの権利を付与する場合には、当該NFTが有価証券にあたるか、あるいは前払式支払手段などの決済手段に該当するか、また付与する権利利益が景品類に該当するかなどの問題について検討する必要があります。どのような権利を付与するかに応じて、個別具体的な検討が必要になります。
これらの問題を適切に調整するためには、発行側の関係者間における契約書や、NFT販売時における利用規約が重要になります。様々な法令を念頭に置きつつ、効果的なNFTのエコシステムが形成されるように関係文書を丁寧に作成する必要があります。
NFTそれ自体はブロックチェーン上の記録に過ぎませんが、財産そのものとして機能しており、様々な法規制の適用を受ける可能性があります。もっとも、業界団体によるガイドラインにおいて、現行の日本法の下においても一部のランダム型販売は適法に行うことが可能であることが示されたように、適切な法的整理をすることでNFTのエコシステムを適法に発展させることができます。今後も、NFTの新規発行や販売について丁寧に法的整理をしつつ、技術上の手当てや実務上の工夫を組み合わせて、実効性のある形でNFTプロジェクトを推進していくことが重要になります。
※1
自民党「デジタル・ニッポン 2022~デジタルによる新しい資本主義への挑戦~」
別紙1 自民党デジタル社会推進本部 NFT政策検討プロジェクトチーム「NFTホワイトペーパー Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略」(2022年4月)
※2
スポーツエコシステム推進協議会「スポーツコンテンツを活用したNFTのパッケージ販売と二次流通市場の併設に関するガイドライン」(2022年9月)
※3
日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)他「NFTのランダム型販売に関するガイドライン」(2022年10月)
※4
山口厚『刑法各論〔第2版〕』(有斐閣、2010)517頁
※5
橋爪隆「賭博罪をめぐる論点について」(経済産業省 第5回 スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会 資料5)(2022年3月)1頁
※6
大塚仁ら編『大コンメンタール刑法第9巻〔第174条~第192条〕〔第三版〕』(2013、青林書院)〔中神正義、高嶋智光〕128頁
※7
橋爪・前掲注5「賭博罪をめぐる論点について」2頁も、同趣旨の考え方を示していると考えられます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)


有斐閣 (2025年8月)
小川聖史(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年9月)
関口朋宏(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
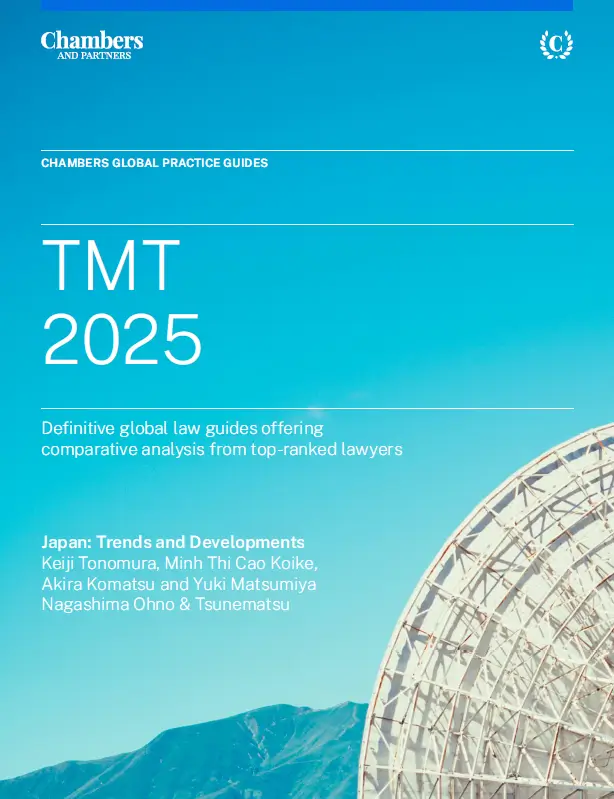
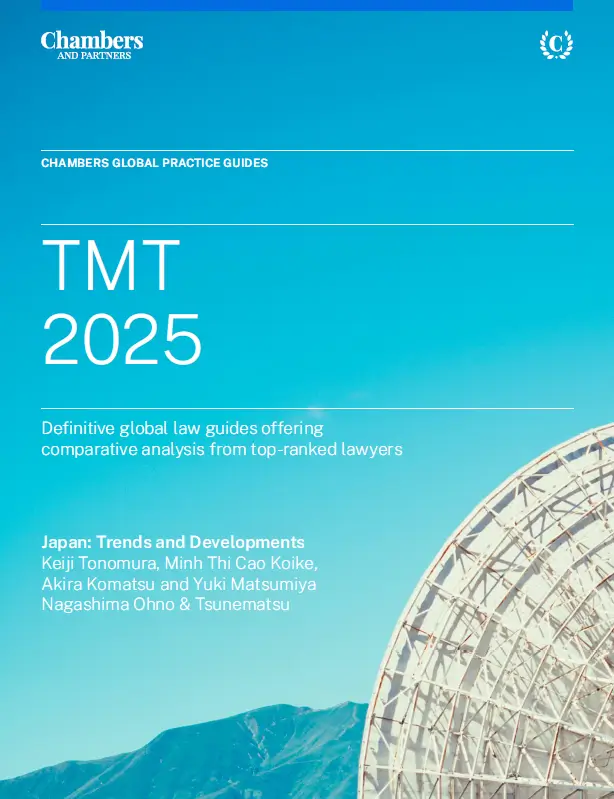
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


殿村桂司、丸田颯人、小宮千枝(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年5月)
東崎賢治(共著)


(2025年5月)
今野庸介


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年5月)
東崎賢治(共著)


(2025年5月)
今野庸介
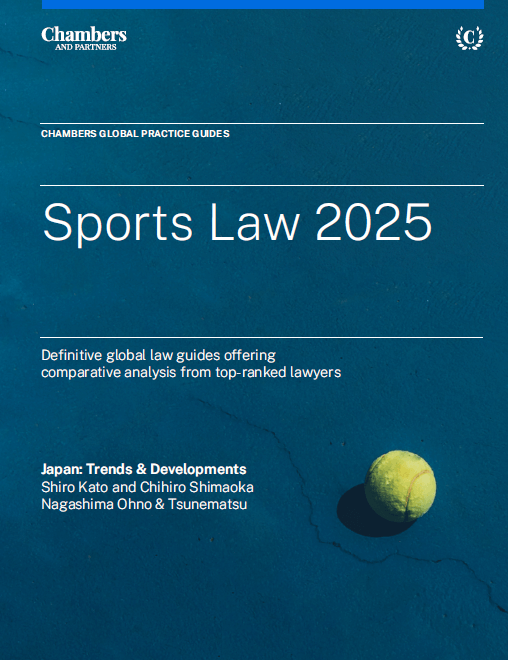
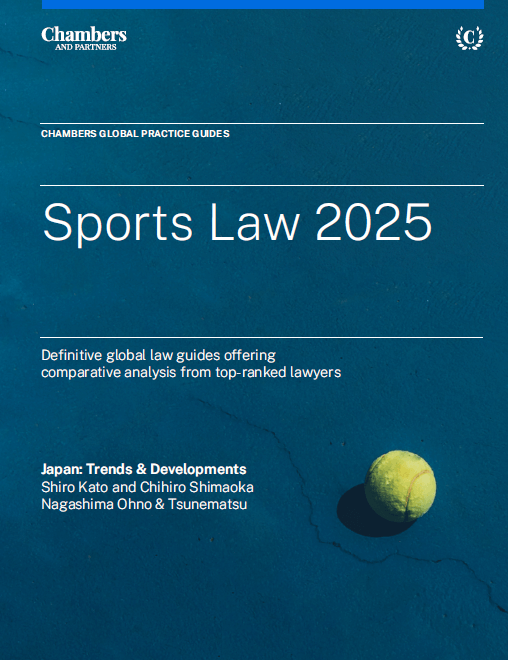
(2025年4月)
加藤志郎、嶋岡千尋(共著)