
鈴木謙輔 Kensuke Suzuki
パートナー
東京
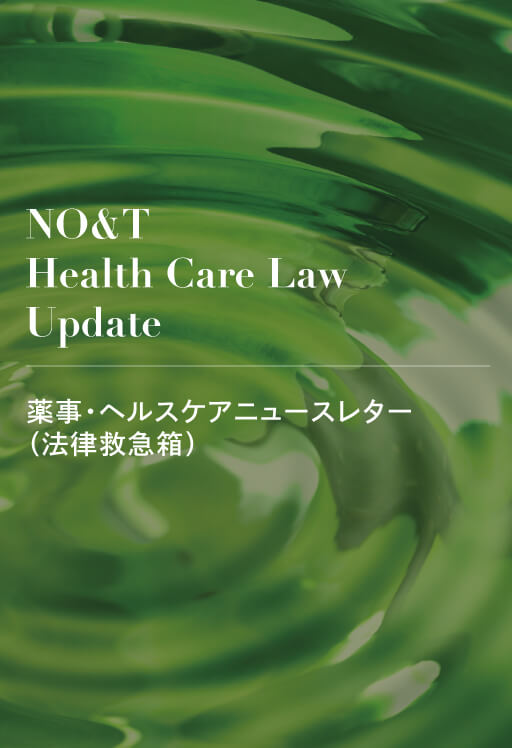
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
ヘルスケア分野におけるテクノロジーの活用は日々進化しており、ヘルスケアアプリ、医療DX、PHR、再生医療・ゲノム医療など、実に多種多様です。一方、ヘルスケア分野に関わる法規制は一元化されておらず、複層的に入り組んでいますし、テクノロジーの活用によって、従来の法規制が想定していなかった態様での活動やサービスが出現しており、ヘルステックに係る規制を正確に理解することは益々重要となっています。本号では、ヘルステックを巡る各種規制を概観して、最新の規制動向についてご紹介します。
ヘルスケアアプリは、それ自体は手に取ることができない無体物ですが、薬機法に基づく「医療機器」に該当する場合があります。ヘルスケアアプリが医療機器に該当する場合には、アプリ毎に承認または認証が必要となり、また、アプリのアップデート等により承認・認証された事項を変更しようとするときには、原則として承認・認証事項の変更に係る手続が必要になります。さらに、ヘルスケアプリ自体についての承認・認証とは別に、アプリの開発・販売を行う業者には、医療機器製造販売業の許可等が必要になります。
このように、ヘルスケアアプリが医療機器に該当する場合には厳格な医療機器規制に従う必要があるため、あるヘルスケアアプリが医療機器に該当するかどうかはアプリを開発するにあたって非常に重要ですが、その判断基準は必ずしも明確ではありません。このため、厚生労働省から2021年3月に出された「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」が2023年3月に改訂され、判断基準の明確化・精緻化等が図られました。その他、厚生労働省のウェブサイトにおいて「医療機器プログラム事例データベース」が公表され、随時更新されており、様々な事例が、当該事例についての厚生労働省の判断のポイントと共に紹介されています。ヘルスケアアプリの開発を実際に検討するにあたっては、その医療機器該当性について、最新のガイドラインや判断事例を参考にして十分検討することが重要です。
医療分野についても、医療法や医師法などの各種厳格な規制が設けられています。医療DXをはじめ、特に医療や医療機関に関連するヘルステックにおいては、これら医療に関わる規制に注意する必要があります。ヘルステックにより提供する医療や健康に関連するサービスが、医師法で規制される医行為に該当するかといった医療資格に関する規制のほか、医療機関が関与する場合には、医療法人の業務範囲規制、医療広告規制、患者紹介に関する規制など、医療機関に関わる各種規制も問題となります。また、オンライン診療やオンライン服薬指導について指針・実施要領が定められているように、個別のヘルステック領域において適用されるルールも設けられており、注意を要します。
そして、これらの規制は随時見直しがなされ、アップデートされていますので、その時点で適用される規制内容を正確に把握し、理解しておくことが重要となります。例えば、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」については、2022年1月に、初診からのオンライン診療は原則としてかかりつけ医が行うこととするなどの重要な改訂がなされていますが、その後2023年3月にも、不適切な診療に対する必要な措置や情報セキュリティ確保のための方策についての見直しが行われており、医療機関は患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティリスクを説明して同意を得なければならないなどの改訂がなされています。医療広告規制については、医療広告ガイドラインに詳細な規定が設けられているほか、2023年10月に「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)」が公表されており、症例モニターとして治療を受ける際の価格として費用の割引を強調した広告など、取り上げられている事例の追加がなされています。
従来の医薬品等では治療が難しい疾患の新たな治療法として期待される再生医療やゲノム医療に対する規制の枠組みも複雑です。対象となる治療法の種類や研究開発等の方法・段階、どのように患者のもとに届けていくかなどによって、適用される法令や規制が異なります。例えば、法律でいえば、薬機法、臨床研究法、再生医療等安全性確保法、カルタヘナ法などが場面に応じて適用されます。また、「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」をはじめとする各種指針や、実務的な解釈・運用について規定する通知等にも細かく目配りすることが求められます。さらに、研究開発等に要するコストが大きいことなどから、実際に患者に提供する際の価格が高額になりやすいのも再生医療・ゲノム医療の特徴です。そのため、薬価制度をはじめ公的医療保険に関する仕組みの理解も重要となります。
新たなテクノロジーを活用した医療に関連することから、適用される規制も随時見直しがなされています。例えば、再生医療・ゲノム医療の研究開発に適用される場合がある臨床研究法および再生医療等安全性確保法は、いずれも施行から10年以内という比較的新しい法律ですが、現在、同法および関連する規制の見直しが図られています。臨床研究法については、臨床試験の実施に関する国際整合性の観点から、スポンサー類似の概念を導入することや企業主導の臨床試験への同法の適用に関する見直しなどが検討され、一部については既に同法の改正以外の形で措置がなされています。また、再生医療等安全性確保法については、現行法の下では適用対象とされていない種類の再生医療・ゲノム医療に対しても同法の適用を広げることなどが検討されています。さらに、受精卵へのゲノム編集技術の利用など、生命倫理の観点から難しい問題が生じる場面について、従前の指針や学会等の自主規制のみではなく、法令で積極的に規制していくべきとの意見もあり、今後の動向が注目されます。
【関連書籍のご案内】
本号でご紹介したヘルステックに関する各種規制を含め、様々なヘルステックに関する法規制の枠組みや法的アプローチのための基本的考え方を紹介する書籍をご案内します。
『ヘルステックと法』
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


工藤靖


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


工藤靖


(2025年6月)
小池晨


(2025年5月)
小池晨
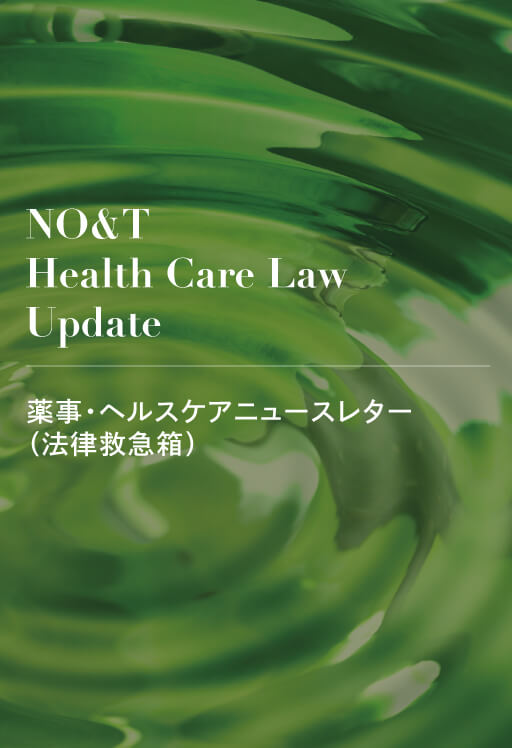
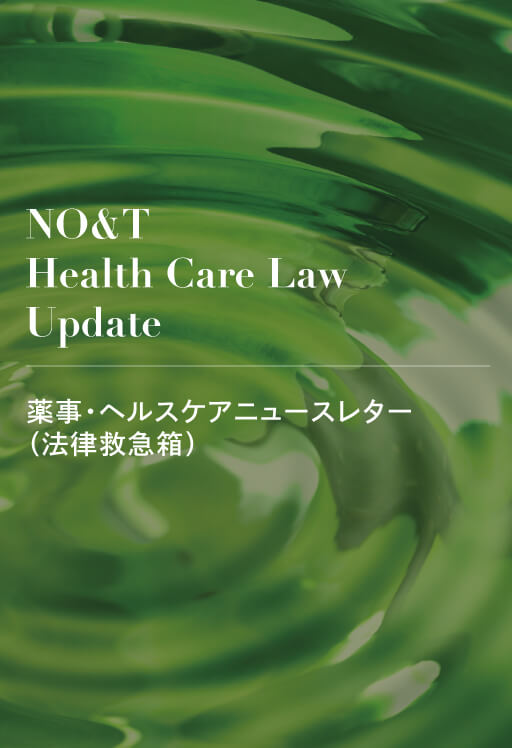
鈴木謙輔、中本優介(共著)
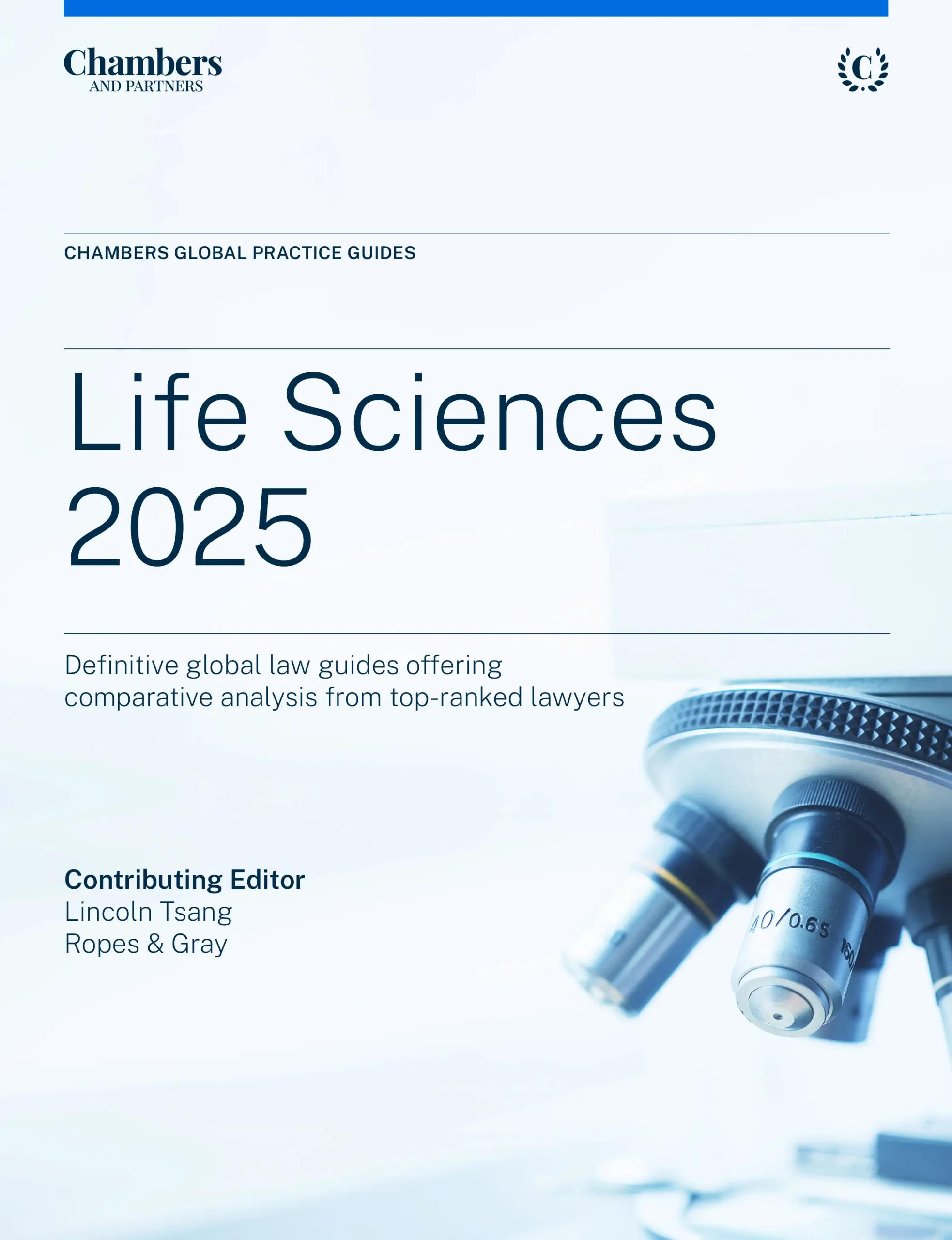
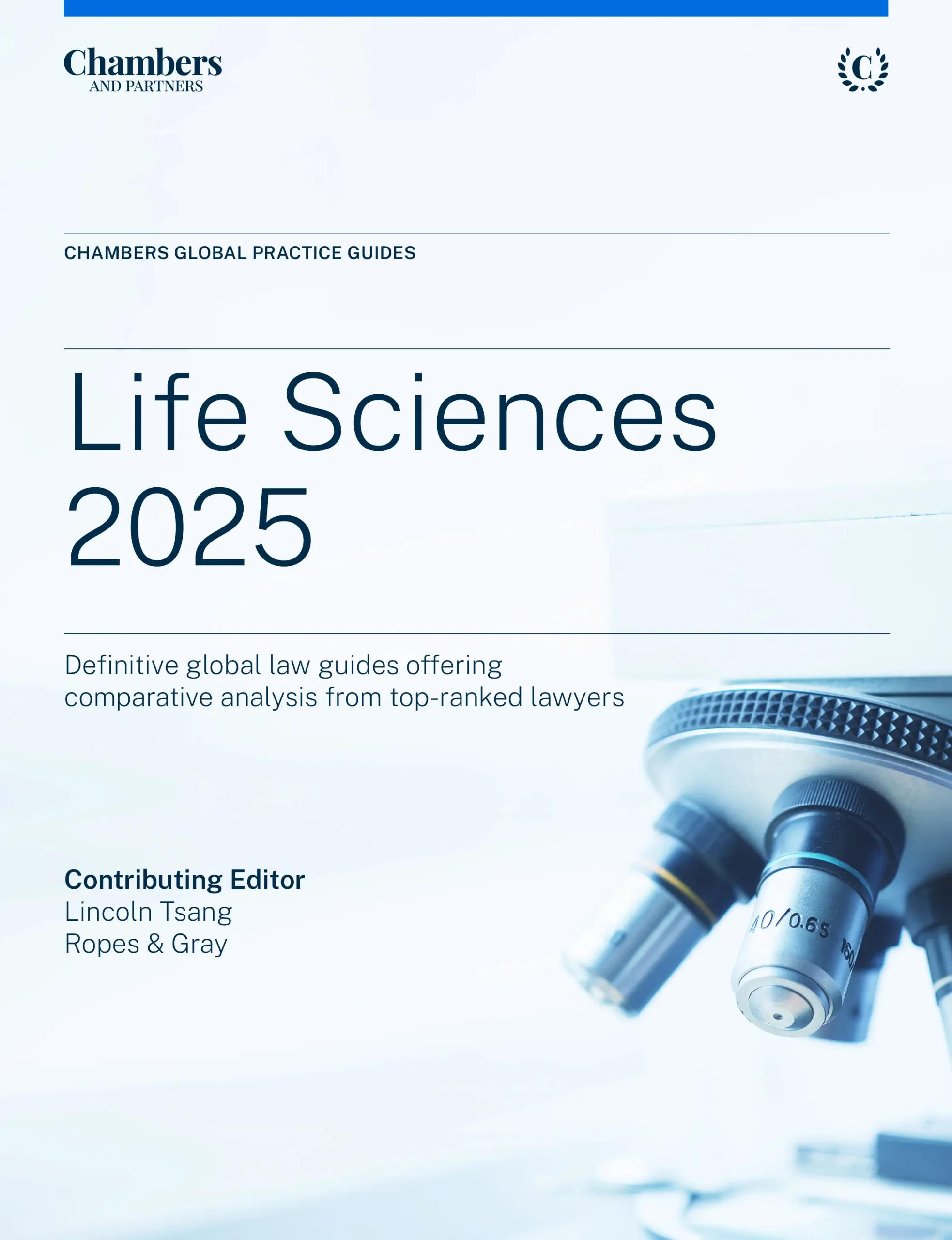
(2025年4月)
内海健司、鈴木謙輔(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
犬飼貴之


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒(監修)、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年4月)
平山貴仁
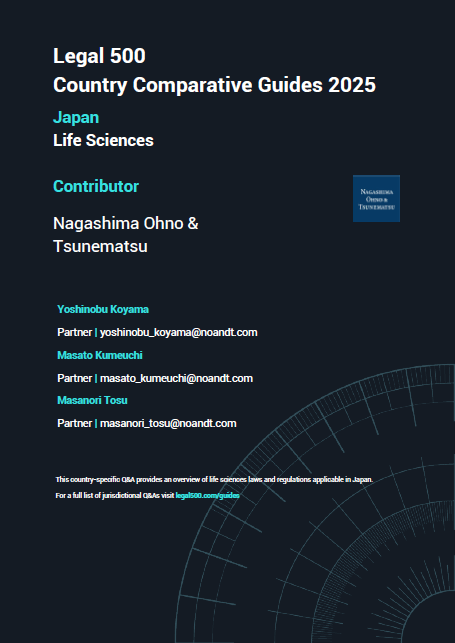
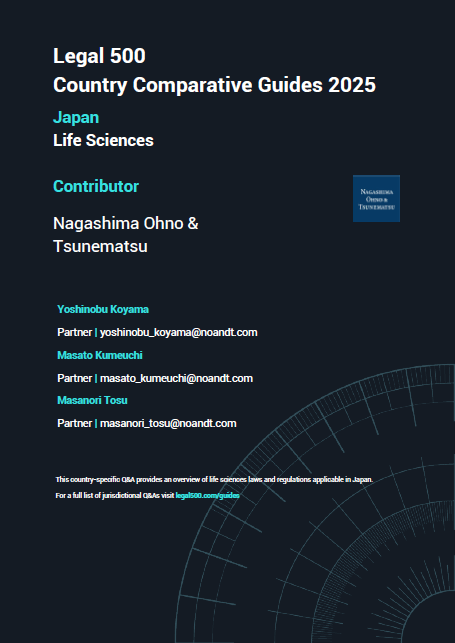
(2025年3月)
小山嘉信、粂内将人、鳥巣正憲(共著)


(2025年3月)
東崎賢治、鳥巣正憲(共著)