
木村聡輔 Sosuke Kimura
パートナー
東京

NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター
ニュースレター
財務コベナンツの開示拡充に関する内閣府令の改正とローン契約実務への影響 ―2025年4月から財務コベナンツの開示が拡充、既存のシローン等への影響もあり―(2024年1月)
2023年12月、金融庁より、いわゆる「重要な契約」について有価証券報告書等での開示を求め、また、財務上の特約が付されたローン契約・社債に関する臨時報告書の提出事由を追加するための企業内容等開示府令等に係る改正案(本改正)の最終案が公表されました。本改正は2022年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を受けて、2023年6月に金融庁より改正案が公表されるとともに、パブリックコメントに付されていたものを最終化するものです。本ニュースレターでは、主に上場企業のガバナンスに関する「重要な契約」の開示に係る新規制の内容について説明していきます※1。
本改正が規制対象とするのは上場会社等のいわゆる有価証券報告書の提出会社です。上場会社等が所定の合意を行っている場合、その概要や目的等について有価証券報告書等での開示が求められることとなります。
具体的には、①②③に該当する合意について有価証券報告書等及び臨時報告書※2における開示が求められることとなります。なお、下記②の合意は株主側が大量保有報告書の提出者である場合に限られます※3。
| ① 「企業・株主間のガバナンスに関する合意」 | |
|---|---|
| (a) 役員指名権 | 役員候補者を指名する権利を株主が有する旨の合意 |
| (b) 議決権行使の制限 | 株主による議決権行使に制限を定める旨の合意 |
| (c) 事前承諾事項の合意 | 株主総会又は取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意 |
| ② 「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」 | |
| (a) 株式譲渡制限 | 株主による株式の譲渡その他の処分について会社側の事前承諾を要する旨の合意 |
| (b) 買増し禁止 | 合意した株式保有割合を超えて当該会社の株式を保有することを制限する旨の合意 |
| (c) 株式保有割合維持の合意 | 会社側が株式発行その他の当該株主の株式保有割合の減少を伴う行為を行う場合に、当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意 |
| (d) 契約終了時の売渡請求権 | 当該契約が終了した場合に、会社側が当該株主に対しその保有する株式を当該会社又はその指定する者に売り渡すことを請求することができる旨の合意 |
| ③ 「ローン契約と社債に付される財務上の特約」 | |
本改正に従った開示が求められるタイミングは、大要、以下のとおりです。
上記の各但書きは、「重要な契約」に該当する限り、その締結日を問わず開示対象となるという理解を前提に、開示対象となる各契約について守秘義務等の観点から見直しが必要になるものが生じることを踏まえて、追加の猶予期間を認めるものです。このように「重要な契約」の締結タイミングが2024年3月31日以前か否かで開示上の取扱いが異なりますので留意が必要となります。
本改正により、上場会社等が、その株主との間で①「企業・株主間のガバナンスに関する合意」及び②「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」をしている場合、有価証券報告書に以下の情報を開示する必要が生じます。
さらに、「企業・株主間のガバナンスに関する合意」との関係では、(d)当該合意が会社側の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)の記載も求められます。
なお、企業と株主との間でガバナンス等に関する合意を含む契約がなされていても、それが「重要性の乏しいもの」であれば開示対象から除外されることとなりました。その具体的な範囲については個別事案毎の検討が必要とされていますが、パブリックコメントにおいて、いくつかの例が示されています。
本改正に際しては多くのパブリックコメントが寄せられており、これらに対して金融庁からは、実務上も留意したい回答が多くなされています。以下では、上場会社等として知っておきたい重要なポイントをピックアップして記載しております。
本改正の最終化により、「重要な契約」の開示に関する規制内容の全貌が明らかになりました。これを踏まえて、上場会社等として、今後、対応すべき事項としては以下のようなものがあげられます。
まずは、自社が締結済みの契約で、本改正により開示対象となる「重要な契約」に該当する合意を含むものの有無のチェックが必要となります。本改正及びパブリックコメントの結果により、開示すべき「重要な契約」の範囲は相当程度明確化されたと思われます。もっとも、パブリックコメントにより、あらゆる疑問が解決されたわけでもありません※8。また、契約の内容は千差万別であり、その全てが明確に「重要な契約」に該当するか否かを判断できるとも限りません。まずは、自社の契約書の内容の再チェックを行うことは急務だと思われます。
本改正に基づく有価証券報告書等での開示項目は、いずれも合理的なものと思われるものの、個別の「重要な契約」について具体的に何を書けばよいか(どの程度の・どのような記載が求められるか)という点については、中々に悩ましい問題といえます。例えば、「取締役会における検討状況その他の当該会社側における当該合意に係る意思決定に至る過程」等は、一見して、どこまでの記載を求められているのか悩ましい開示事項であろうと思われます。
また、開示対象となる合意の内容を改めて見ると、株主側に義務を課すものもあれば、会社側に義務を課すものもあります。前者であれば、会社側としての「合意の目的」も含めて比較的容易に記載できるかもしれません。他方、後者については、当該合意それ自体は会社側にとってメリットがないことが通常であるため、当該合意のみを取り出して「合意の目的」を記載するのは困難であり、結局、当該合意が含まれる契約全体の目的(契約全体で会社として権利・利益を得ている反面、一定の義務を負っている)を説明するほかないように思われます。そうした場合に、開示対象となる合意の範囲は、実際には相応に広範になるおそれがあります。
将来的に好事例が公表されるとはいえ、規制導入当初は、自社で独自に検討するほかなく、一度、有価証券報告書等で開示した内容を、翌年度から(好事例にあわせたとしても)限定するのは実務上ハードルが高いように思われますので、やはり当初の開示文の検討が重要であることは否定できないと思われます。
また、ガバナンスに影響を及ぼす「重要な契約」を締結していることについて、事業等のリスク等、他のパートでの記載の要否や、「「重要な契約」に該当する契約が存在している」という情報自体を重要情報として取り扱う必要が無いかといった派生論点についても合わせて検討することが望ましいところです。
「重要な契約」には、対外的な公表を予定してこなかったものが多く含まれる可能性があります。その場合、上記②の検討結果も踏まえつつ、契約の相手方である株主との間で、開示の範囲・内容について協議し、その了解をとっておくのが実務的に穏当であろうと思われます。他方、株主側としても、特に規制導入当初は、どの程度の記載が求められるのか(一般的か)という点についての感覚は持ち得ないため、場合によっては、協議が難航する可能性も否定できません(また、株主側が大量保有報告書の提出を済ませているときには、既に一定の整理がなされている可能性もあります。)。このような株主側との協議も、スケジュールに余裕をもって対応したい事項です。
今後、新たに「重要な契約」を締結する場合、将来的に有価証券報告書等にて所定の開示が求められることを前提とした協議が行われる必要があります(対外公表に耐えられないような合意は避ける必要がある)。
また、実務上は、このような合意は上場会社がファンド等よりエクイティ出資を受け入れる際の出資契約や上場会社が提携先と締結する資本業務提携契約において定められることが多いところ、これらの案件では実施当初において適時開示や有価証券届出書(又は臨時報告書)での開示を行う必要がありますので、案件当初に行うこれらの開示においても、「重要な契約」に該当する合意については、本改正を踏まえて従来よりも踏み込んだ記載を行うべきではないかといった点は検討ポイントになろうかと思われます。契約の相手方となる株主に対しても、契約締結前の段階から本改正についての理解を求め、会社側として必要となる開示内容について予め承諾を得ておくことで、事後的なトラブルを回避するのが得策ではないかと思われます。
※1
財務上の特約(いわゆる財務コベナンツ)が付されたローン契約に関する新たな開示義務の詳細についてはキャピタルマーケットニュースレターNo.34(事業再生・倒産法ニュースレターNo.23)「財務コベナンツの開示拡充に関する内閣府令の改正とローン契約実務への影響 –2025年4月から財務コベナンツの開示が拡充、既存のシローン等への影響もあり–」(月岡崇・鐘ヶ江洋祐・水越恭平、2024年1月)をご参照下さい。
※2
四半期報告書については、2024年4月1日に施行予定の令和5年金商法改正により廃止されるため、本改正に係る継続開示対応としては有価証券報告書・臨時報告書の他には半期報告書の記載内容の検討が必要ということになると思われます。また、本改正においては、①②に該当する合意について臨時報告書の提出事由とはされておりませんが、本改正とは別に2023年12月8日に令和5年金商法改正(四半期報告書の廃止)に伴う政令・内閣府令案等の改正案が公表されており、当該改正案により、①②に関する合意についても臨時報告書の提出事由とされる予定です。当該改正案はパブリックコメントの結果を踏まえた修正を加えて最終化されるものと見込まれますが、現在公表されている案においては2025年4月以降の適用が予定されています。
※3
2023年6月公表の当初案では「その他の投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある者」との合意も対象とされていましたが、パブリックコメントを経て、最終案では削除されています。なお、共同保有者がいる場合、その全員が「大量保有報告書を提出した者」に該当するとされています(但し、開示対象となるのは実際に該当する合意を行っている者のみです。)。
※4
事業年度末が3月末の企業にとっては2025年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書まで、事業年度末が12月末の企業にとっては2025年12月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書まで記載の省略が可能となります(但し、記載を省略する旨の記載は必要とされています。)。
※5
ただし、パブリックコメント回答において「いわゆる実質株主との間で合意を締結しており、当該株主が実質株主であることを提出会社が把握している場合には、これを任意に開示することが望ましいと考えられます」と言及されています。
※6
他方、有価証券報告書等の記載内容を「補完する詳細な情報については、任意開示書類等を参照することも可能」とされています。
※7
もっとも、この点は個別契約の秘密保持条項の解釈の問題であるため、法令の定めに基づき開示すれば常に契約違反を構成しないと言い切れるかについては慎重に検討するべき問題であるように思われます。また、そもそも本改正対応の開示としてどこまでの記載を行うかは各社毎の裁量・判断が介在するため、どこまでの開示であれば法令に基づき開示したといえ、どこからが会社の裁量・判断による任意の開示となるかの線引きも必ずしも容易ではないように思われます。
※8
例えば、開示対象となる事前承諾事項の合意は、「取締役会において決議すべき事項」とされていますが、会社法上、取締役への委任を許容されている取締役会の決議事項は多く存在します。指名委員会等設置会社であれば、執行役に対して非常に多くの事項を委任することができます。このような会社において「取締役会において決議すべき事項」とは、どの範囲の事項を意味するのかは必ずしも明確ではありません。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年6月)
松尾博憲


宮城栄司、井柳春菜(共著)


(2025年6月)
水越恭平


(2025年6月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


宮城栄司、井柳春菜(共著)


(2025年6月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


井上皓子


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
水越恭平
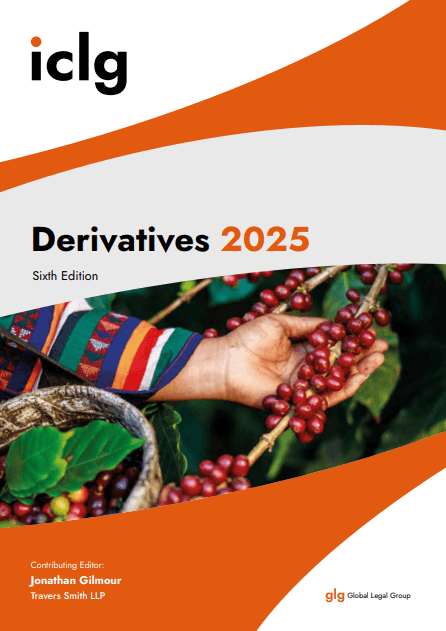
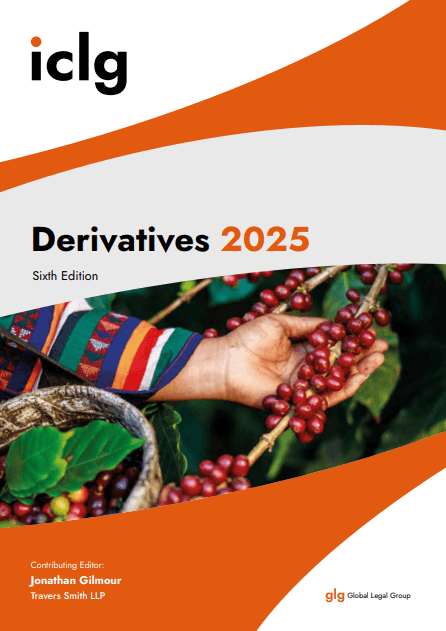
(2025年6月)
大矢一郎、福田政之、須田英明、遠藤努(共著)


(2025年6月)
水越恭平


(2025年6月)
吉良宣哉


糸川貴視、北川貴広(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
大久保涼(コメント)


内海健司、門田正行、山中淳二(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
大久保涼(コメント)


内海健司、門田正行、山中淳二(共著)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)