
粂内将人 Masato Kumeuchi
パートナー
東京
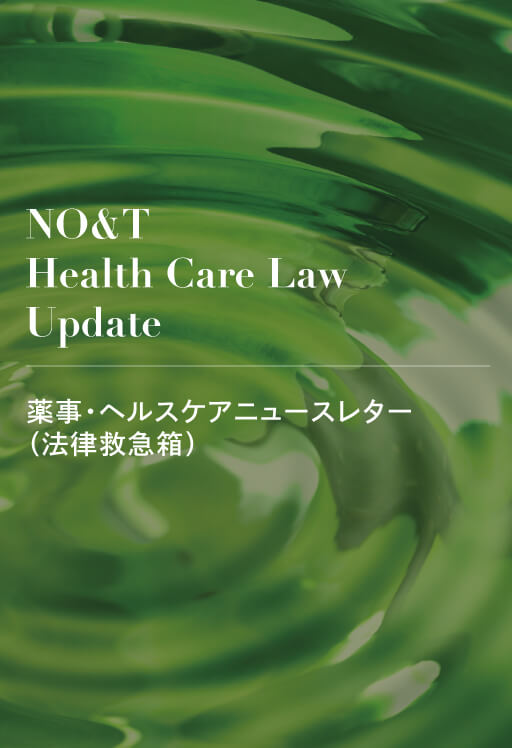
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
ニュースレター
パテントリンケージ制度における特許権者の情報提供についての不正競争の成否に関する2件の東京地裁決定(2025年4月)
後発医薬品の販売開始後に、特許侵害訴訟等によってその供給が途絶えてしまうと、医療現場に混乱が生じる等の弊害があるため、日本を含む世界各国において、薬事当局が、後発医薬品の承認にあたって先発医薬品に係る特許を考慮する仕組みが採用されており、この仕組みは、パテントリンケージと呼ばれています。日本においては、「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(平成21年6月5日付医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号)(いわゆる「二課長通知」)によってパテントリンケージの仕組みが採用されています。本ニュースレターでは、近時の関連する裁判例(東京地判令和4年8月30日及び知財高判令和5年5月10日)にも触れながら、日本版のパテントリンケージ制度の現状の課題と今後について検討したいと思います。
上記のとおり、日本版パテントリンケージ制度は、二課長通知と呼ばれる通知に基づいて運用されています。二課長通知には、以下の内容が記載されています。
後発医薬品の薬機法上の承認審査にあたって、
上記のとおり、日本版パテントリンケージ制度の下においては、後発医薬品の製造販売を承認するか否かを医薬品医療機器総合機構(PMDA)及び厚生労働省が判断する場面と、後発医薬品の製造販売の承認を受けた後発医薬品メーカーが薬価収載の手続きをとるか否かを判断する場面の二つのフェーズで、先発医薬品の特許との調整が行われることが予定されています。
例えば米国のパテントリンケージ制度と比較すると、日本においては、先発医薬品の特許に関する情報が公表されていない点や、後発医薬品の承認申請がなされても、先発医薬品の製造販売業者にその事実(後発医薬品の承認申請がなされたという事実)が知らされない点及びパテントリンケージの仕組みの中に裁判所の判断を得る機会が組み込まれていない点等が異なっています。
先発医薬品の製造販売業者と後発医薬品の製造販売業者のいずれの立場からも、特許紛争の早期解決が難しく、また、本来、裁判所においてなされるべき判断がPMDAや厚生労働省によってなされており、その判断理由も明確でない等の課題が指摘されています。
上記のような課題が指摘される中、後発医薬品の製造販売承認の申請を行った後発医薬品メーカー(「X」)が、先発医薬品の発明に係る特許権(「本件特許権」)を有する者(「Y」)らに対し、特許権に基づく差止請求権(予備的に将来の差止請求権)の不存在確認の訴え、損害賠償請求権(予備的に将来の損害賠償請求権)の不存在確認の訴え及びXが製造販売しようとする後発医薬品がYの先発医薬品に係る発明の技術的範囲に属しないことの確認の訴えを提起しました。Xとしては、二課長通知に従った運用の下では、裁判所の判断を得ない限り、Xの製品について製造販売承認を受けられないであろうと考えて提訴したものと推察されますが、東京地判令和4年8月30日及び知財高判令和5年5月10日は、いずれも訴えの利益がないとして、訴えを却下(知財高裁は控訴を棄却)しました。
当事者の主張は多岐にわたりますが、東京地判令和4年8月30日は、Xが医薬品医療機器等法等の定めに則った事業活動をすると推認されること等を考慮すると、近い将来において、Xが、Yの特許を侵害する医薬品を製造販売する蓋然性が高いとは認められないことや、現在、YらはXに対し本件特許権に基づく主張をしていないこと等を理由に、現に、当事者間に紛争が存在し、Xの有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在しているとは認めるに足りないと判断しました。
控訴審においてもXは様々な主張をしていますが、以下の補充主張等がなされました。
これに対し、知財高判令和5年5月10日は以下のとおり判示してXの控訴を棄却しました。
本件において、Xは既に製造販売承認の申請をしていましたので、その事実関係の下に上記判断がなされたことを踏まえると、後発医薬品メーカーとしては、製造販売承認の申請をしただけでは足りず、少なくとも製造販売承認を受けないと確認の利益が認められない可能性が高い一方で、非侵害であることについて公的な判断がなされていない状況下では、二課長通知に基づく運用により、製造販売が承認されないというジレンマに陥ってしまう可能性があるように思われます。また、知財高裁の判決の中で、「かかる公法上の紛争については承認申請に対して不作為の違法確認の訴えの提起や厚生労働大臣等に対する不服申立て等の法的手段によって救済を求めるべき」と判示されていますが、特許権者はこれらの訴訟の当事者にはならないため、侵害の有無等に関する攻撃防御が当事者間で行われないまま行政法の観点からの違法性のみが判断され、実質的な紛争解決が先延ばしになってしまう可能性があるように思われます。
上記のとおり、現在の日本版パテントリンケージ制度は、先発医薬品メーカー及び後発医薬品メーカーのいずれにとっても不明確な点が多い上に、上記裁判例における判示内容も踏まえると、裁判所等を通じた紛争の早期解決が困難となっており、日本製薬工業協会等の業界団体が厚生労働大臣に対してパテントリンケージ制度の改善要望を提出する等の動きがあるほか、海外からも、日本版パテントリンケージ制度の問題点について指摘がなされています。
パテントリンケージ制度は、医薬品の安定供給はもちろん、新たな医薬品の開発や日本における上市に対するインセンティブにも深く関わっており、我々国民の生活やQOLに直結しているほか、先発医薬品メーカー及び後発医薬品メーカーのそれぞれの命運を左右することもあり、社会に与える影響の大きな制度と言えます。
製造販売承認の段階で裁判所の判断を仰ぐ機会を設けることを含め、具体的な制度設計については種々議論のあるところではありますが、いずれに致しましても、上記のような国民全体への影響の大きな重要な制度を対外的に法的な効力を持たない通知に基づいて運用するのではなく、国民の多様な声を広く採り入れた上で、国会の場で丁寧に議論をし、法律上の根拠を有し、かつ透明性の高い制度として、日本版パテントリンケージ制度を設計し、運用していくことが望ましいと思われます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
髙取芳宏


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)