
井上皓子 Akiko Inoue
カウンセル
東京

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
コロナ禍を一つの契機として、ベトナムにおいてもデジタル経済・電子商取引が急速に発展し、デジタル化に関する関連法令・首相決定が次々と発表されている。そのような中、このほど、ベトナム国際仲裁センター(Vietnam International Arbitration Center; VIAC)が申立・事件管理までを可能とするオンラインプラットフォームの導入を発表した。ベトナムではすでに裁判所で一部「IT化」が導入されて久しいが、裁判所のオンライン手続きはそれほど使われていないともいわれている。現状を本稿で紹介する。
VIACは、2024年6月、「eCaseプラットフォーム」と題するオンラインプラットフォームの立ち上げを発表した。現在は、試験版プラットフォームとされているが、すでに、同プラットフォームを通じた申立も可能なようであり、実例も出てきているとのことである。また、すでに申立済みの事件でも、プラットフォームへの移行が可能である。
「eCaseプラットフォーム」の主要な機能は以下のとおりである。
VIACでは、従前から、申立書を含む通知・書面等は、書留・ファクシミリ・電子メール等で送信することとされており(VIAC仲裁規則3条2項)、実務上は電子メール方式が好まれていたようであるが、プラットフォームを利用することにより、一元的な管理を行えるようになることが期待される。
なお、このプラットフォームは、現時点ではあくまでも書面のやりとりとスケジュール管理に特化したものである。オンラインのヒアリングについては、当事者の希望を聞いて電話会議やビデオ会議で行うことも可能とされているが(VIAC仲裁規則25条1項)、今後は、スケジュール調整等の会議やヒアリングもプラットフォームを使用して行うことも想定されているとのことである。
VIACは、国際仲裁を取り扱うことで、国境を越えた貿易・投資活動等支援に資することを目指し、またそれが期待されている。プラットフォーム方式は、国際的な潮流でもあるが、異なるタイムゾーンに所在する当事者でも容易にいつでも申立を行うこと、時差にかかわらず事務局のマニュアル作業を通さず即時の通知を受け取ることが可能となり、国境を越えた当事者間の紛争により馴染みやすい。
また、VIACは、EU一般データ保護規則を含む国内外の基準に準拠した情報のセキュリティ確保を行うことも、プラットフォーム化の一つの目的として挙げている。もっとも、具体的にどのようなセキュリティ措置を施すのかについては明確ではない。
また、プラットフォームに一元化することにより、管理費用の削減も期待されている。このようなプラットフォームによるオンライン化は、例えばアメリカやシンガポールでは裁判所による訴訟手続きではすでに一般的となっているが、仲裁機関では、電子メールでの申立・書面提出はすでに一般的になっていると思われるものの、プラットフォームを通じた提出・一元管理が行われている事例はそれほど多くはないように思われる。
一方、ベトナムでは、国内裁判所において、すでにプラットフォームでの申立は導入されていた(2018年11月から一部裁判所で、2022年から全国で運用を開始。)。
国内裁判において、プラットフォームによる提出がどの程度活用されているのかについてのまとまったデータは存在しないが、実際にはあまり活用されていないとの意見も聞かれる。その理由としては、大きく以下の点がある。
紛争手続きのIT化は避けられない国際的潮流である。VIACは、今回のeCaseプラットフォームの導入により、国際仲裁としての利便性を広く打ち出すとともに、ベトナム企業に対して、馴染みやすいプラットフォーム形式を利用し、裁判所プラットフォームの難点とされる電子署名を不要とし、プラットフォームに機能性を持たせるなど、使いやすさをアピールしている。
ベトナムでは、国外仲裁機関(JCAA、SIAC、ICC等)での仲裁は、一定の要件を満たす外資企業が当事者となる紛争についてのみ認められているうえ、仲裁判断の国内執行は、論理的には可能であるものの、実際には裁判所が執行判断を認めないなど、現実の執行に困難が伴うことが多いともいわれる。この点、VIACは国内仲裁であり、国内仲裁ゆえの問題点もあるものの、執行にあたってのハードルは、国外仲裁機関のそれよりはハードルが低いと考えられており、透明性の高くない国内裁判所での裁判への忌避感もあり、紛争解決機関として契約上選択されることも増えている。
今回のVIACの試みは、国際仲裁機関としての魅力を打ち出し、仲裁誘致を図ることを目的としたものと考えられる。他方で、もともと他の仲裁機関よりも事件管理事務が弱いなどのVIACの弱みとして指摘されていた点が、プラットフォーム化だけにより十分に克服されるとは思われず、更なる努力が必要な面もあるように思われる。また、ベトナム国内法(商事仲裁法)において、現時点では、オンラインにより提出・管理・審理された仲裁手続き・仲裁判断についての明確な法的根拠がなく、このプラットフォームを利用して出された仲裁判断が、承認執行手続きの中で、国内裁判所においてどのように判断されるのか不安定さが残る。この点については、現在、商事仲裁法の改正が議論されているところであり、オンラインによる紛争解決手続きについても何らかの法的根拠が付与されることが期待される。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


梶原啓


クレア・チョン、加藤希実(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


井上聡、松永隼多(共著)


クレア・チョン、加藤希実(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
杉本花織


ジャスティン・イー、室憲之介(共著)


(2025年8月)
杉本花織
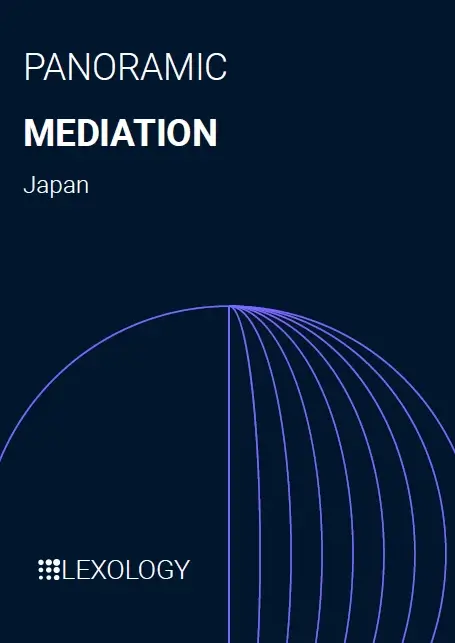
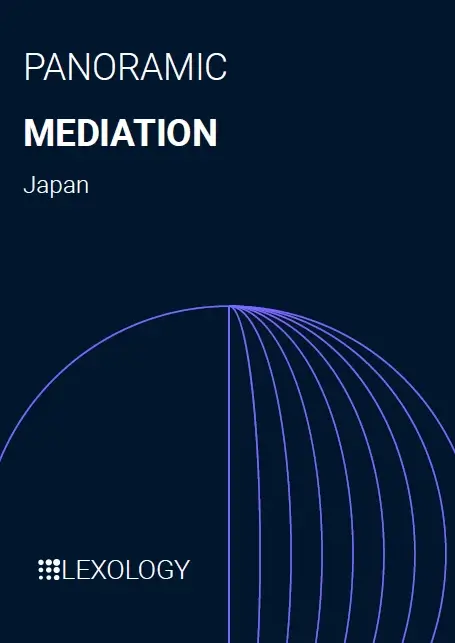
(2025年7月)
池田順一、鍋島智彦、井上皓子(共著)


(2025年4月)
杉本花織
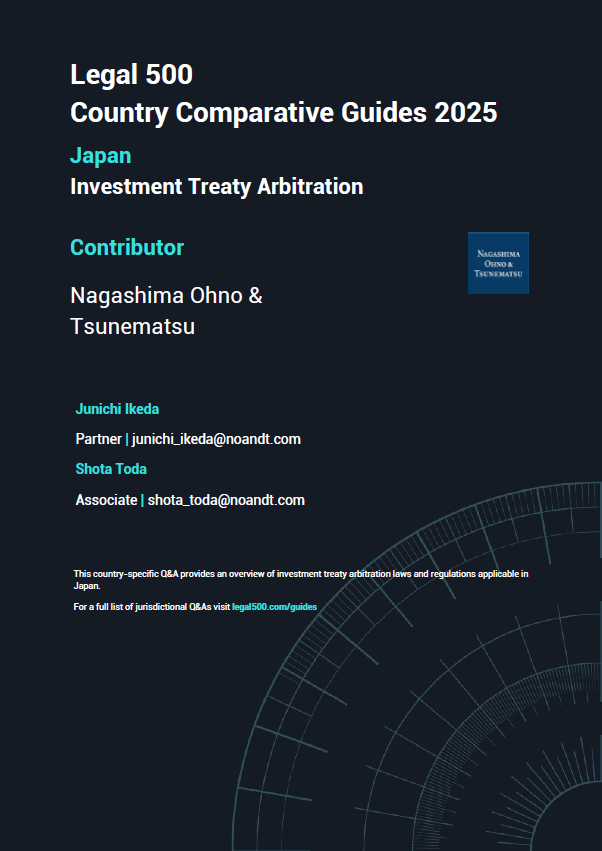
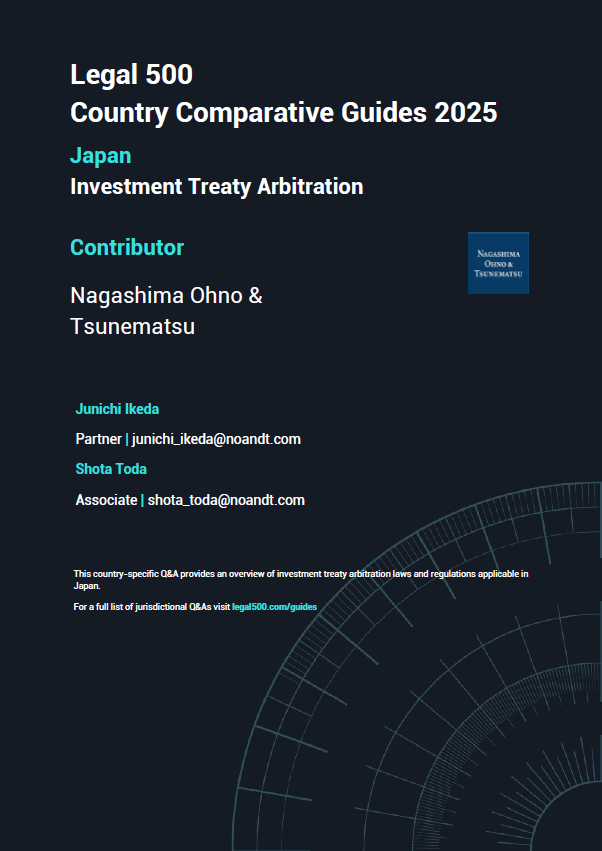
(2025年3月)
池田順一、戸田祥太(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


山本匡


梶原啓


箕輪俊介


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年7月)
澤山啓伍


澤山啓伍、ズン・パイ、犬飼貴之(共著)


(2025年6月)
井上皓子


井上皓子