
平野倫太郎 Rintaro Hirano
パートナー
東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター
ニュースレター
海外建設契約Memo(第1回)(2024年10月)
近時、洋上風力発電施設の建設など、国内の大型プロジェクトにおいて、国際建設プロジェクトで利用される建設契約約款が用いられている例が少なからず見受けられるようになっています。FIDIC※1の発行している契約約款はその典型です。
その一方で、FIDICの建設契約約款は、国内の約款には見られない条項が定められていたり、国内の約款とは異なる規律をしている条項も少なくなく、用いる際には若干の注意が必要です。このシリーズでは、FIDICの建設契約約款を国内のプロジェクトで用いるに際して注意する必要のある事項について、国内の約款と比較しながら、解説していきます。国内の約款として想定しているのは、主として、中央建設業審議会による公共工事標準請負約款※2(「公共工事約款」)及び民間(七会)連合協定による工事請負契約約款(「民間連合約款」)ですが、必要に応じて、日本建設業連合会による設計施工契約約款(「設計施工約款」)にも触れていければと思います。そして、国際建設契約約款として想定しているのは、FIDICの発行する1999年版のYellow book(「イエロー(1999)」)ですが、必要に応じて2017年版(2022年修正版)(「イエロー(2017)」)についても言及したいと思います。
今回は、FIDICの建設契約約款における特徴的な当事者であるEngineer(「エンジニア」)について、以下の点を取り上げて解説します。
FIDICの建設契約約款では、実務に精通したエンジニアが発注者のために受注者に対して適切な指図等を行使することを通じて、受注者の業務が円滑かつ適切に実行されて、契約の目的が確実に達成されることが期待されています。
FIDICの建設契約約款は、発注者と受注者という二当事者の間に建設契約が成立することを前提としており、エンジニアは建設契約の当事者ではありません。しかし、上記の観点からYellow bookではエンジニアの選任は発注者の義務とされており(イエロー(1999)第3.1条)、エンジニアは、FIDICの建設契約約款において重要な地位にある(契約外の)当事者です。
この点、日本においても、一定の規模の建築物の工事については、有資格者(建築士)の工事監理者の設置が義務づけられており(建築基準法第5条の6第4項)、それを受けて、民間連合約款は、発注者に「監理者」の選任を義務づけています(民間連合約款第1条第3項)。その趣旨は、FIDICの建設契約約款がエンジニアの選任を義務づけているのと同様であり、専門家による監理を通じて工事全体が円滑に履行されて請負契約の目的が確実に達成されることにあります。
ただ、その趣旨には重なるところがあるものの、エンジニアに与えられた権限は、後記の通り、国内の約款における監理者に与えられた権限を大きく超えるものになっています。
エンジニアには、大きく分けて、発注者のために行動する権限(代理権限)と、両当事者の間に立って様々な事項を決定する権限(決定権限)という2つの権限が与えられています。
一見すると相反するようにも見えるこの2つの権限がエンジニアに与えられていることが、エンジニアを理解する上で重要な点ですが、同時に、エンジニアの「分かりづらい」側面でもあります。
そして、実は、FIDIC自身も、エンジニアをどのように位置づけるかという点については、契約約款の改訂の都度、その立場に修正を加えており、この問題の微妙な側面を表しているともいえます。
イエロー(1999)に先立つ1987年版では、エンジニアは、中立な立場で(impartially)裁量を行使する旨定められていました(1987年版第2.6条)。それが、イエロー(1999)では、エンジニアは発注者のために行動するものとみなされると定められたうえ(イエロー(1999)第3.1条(a))、ただ、エンジニアが決定権限を行使する際には、公正(fair)な決定を行わなければならないと定められ(イエロー(1999)第3.5条)、中立性(impartiality)という文言が削除されました。FIDICが発行する注釈書では、発注者のために行動するものとみなされる以上、完全に中立な仲介者(wholly impartial intermediary)ということはできない、と説明されています※3。しかし、イエロー(2017)では、エンジニアは、決定権限を行使する際には、各当事者から中立に(neutrally)行動しなければならず、発注者のために行動するとはみなされないと定め(イエロー(2017)第3.7条)、改めて、中立性(neutrality)をいう概念が導入されています。
エンジニアは、建設契約に定められた範囲において、権限を与えられたものですので、(発注者を代理するといっても)契約自体を変更する権限はありませんし、各当事者の義務を免除する権限もありません※4。
しかしながら、Yellow Bookでは、目的物の引渡が完了するまでの受注者とのコミュニケーションはエンジニアに集約されており、エンジニアが発注者の代理人としての役割を果たすことが想定されているため、契約においてエンジニアに与えられた権限は広範です。
加えて、FIDICの建設契約約款の特徴的な点として、そのような権限の円滑かつ迅速な行使という観点から、①エンジニアの権限行使について発注者の事前の承認を要するものは、特約事項(Particular Conditions)に定められていなければならないものとされ、かつ、②仮にその旨が特約事項に定められていたとしても、エンジニアが当該権限を行使した場合には、発注者は必要となる承認を与えたものとみなされます。
その結果、エンジニアの行為については、特記事項において発注者の事前の承認が必要である旨定められている行為であるか否かにかかわらず、受注者は、原則として、発注者に確認をすることなく、有効なものとして扱うことができることになります※5 。
その一方で、エンジニアが受注者に対して付与する承諾、承認等によって受注者の契約上の責任が免除されることはないものとされており、留意が必要です。例えば、エンジニアが承認したContractor’s Documents(受注者作成書類)※6が契約に適合していなかったことが後日判明することがあり得ますが、受注者は、エンジニアが承認したことをもって契約不適合責任の免責を主張することはできません。
エンジニアは、いつでも、受注者に対して、受注者が業務を遂行する上で必要な指図をすることができます。国内の約款でも、監理者が受注者に対して指図をすることがありますが、FIDICの建設契約約款の特徴としては、以下の2つが挙げられます。
エンジニアは、受注者あるいは発注者からのクレームについて決定する権限が与えられていて、その決定について当事者から所定の期間内に適式な異議が提出されない場合には、発注者も受注者もエンジニアの決定内容に法的に拘束されます。異議を申し立てた場合には、Dispute Adjudication Board(「DAB」)※8において審議され(イエロー(1999)第20.4条)、その決定に対しても異議がある場合には、仲裁を申し立てることができますので(イエロー(1999)第20.6条)、その意味で、エンジニアの決定は必ずしも確定的なものではありませんが、それでも、エンジニアにこのような役割及び権限が与えられていることは、国内の約款にはない、FIDICの建設契約約款の大きな特徴の一つです。
上記の通り、エンジニアには、国内約款に見られない広範かつ強力な権限が与えられています。とりわけ、バリエーションの発出権限やクレームに対する決定権限は、発注者及び受注者のいずれにとっても大きな影響を及ぼし得る重要な権限です。エンジニアの権限行使は、自らのクレームの是非がエンジニアによって決定されるという点で受注者の権利義務に直接に影響が及びますが、発注者の権利義務にも直接に影響が及びます。エンジニアの発出するバリエーションによって、発注者は、当初合意した契約金額を超える出費を強いられることになり、また、当初想定した工期に完工しない結果を受け入れなければならないことになるからです。
エンジニアは、民間連合約款の監理者と同様、発注者が起用し、監理者の報酬も発注者が負担しています。その意味で、エンジニアは、発注者から完全に中立な地位にあるわけではありません。にもかかわらず、このような広範かつ強力な権限がエンジニアに対して専属的に与えられている背景には、実務に精通した専門家であるエンジニアがプロジェクトを主導することによって、契約が迅速、円滑かつ適切に実行されることが可能になる、というFIDICの価値判断があると考えられます。とりわけ、その決定権限については、プロジェクトを直接にかつ恒常的に監理しているエンジニアに決定させることがプロジェクトの迅速な遂行を確保するためには必要である、ということが強く意識されています。
それだけ、FIDICの建設契約約款は、エンジニアの役割を重視しているということであり、発注者は、FIDICの建設契約約款を用いるにあたっては、建設実務のみならずFIDICの建設契約約款をよく理解しているエンジニアを起用する必要がある、ということがいえると思います。
※1
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseilsの略称です。
※2
その名称にかかわらず、この約款は、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等が発注する工事を対象とするのみならず、電力、ガス、鉄道、電気通信等の常時建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることができるように作成されたものであるとの説明がなされています(国土交通省HP)。
※3
P35, The FIDIC Contracts Guide, First Edition 2000
※4
エンジニアにはVariationを出す権限が与えられており、エンジニアはVariationを通じて契約の内容を変更しているのではないか、と感じる方もいるのではないかと思いますが、その点については、別の機会に、改めて触れたいと思います。
※5
必要な承認を取得することなく行為に及んだエンジニアは、発注者との間で締結されている任用契約に違反している場合には、発注者に対してその責任を負うことになります。
※6
竣工図、マニュアル、許認可書類等、目的物の引渡にあたって発注者に引き渡すことを要する書類です。
※7
イエロー(1999)ではEmployer’s Requirement(発注者要求事項)又はWorks(業務内容)の変更と定義されています。ここでは、業務内容の変更、と理解していただいてよいと思います。
※8
イエロー(2017)では、機能の拡充と共に、Dispute Avoidance/Adjudication Board(DAAB)に改称されています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


宮城栄司、井柳春菜(共著)


(2025年6月)
本田圭


藤本祐太郎、松田悠(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2025年4月)
松本岳人


(2025年4月)
松本岳人


(2025年4月)
洞口信一郎、小山嘉信、渡邉啓久、杉本花織(共著)


(2025年4月)
杉本花織


(2025年6月)
本田圭


藤本祐太郎、松田悠(共著)


三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)
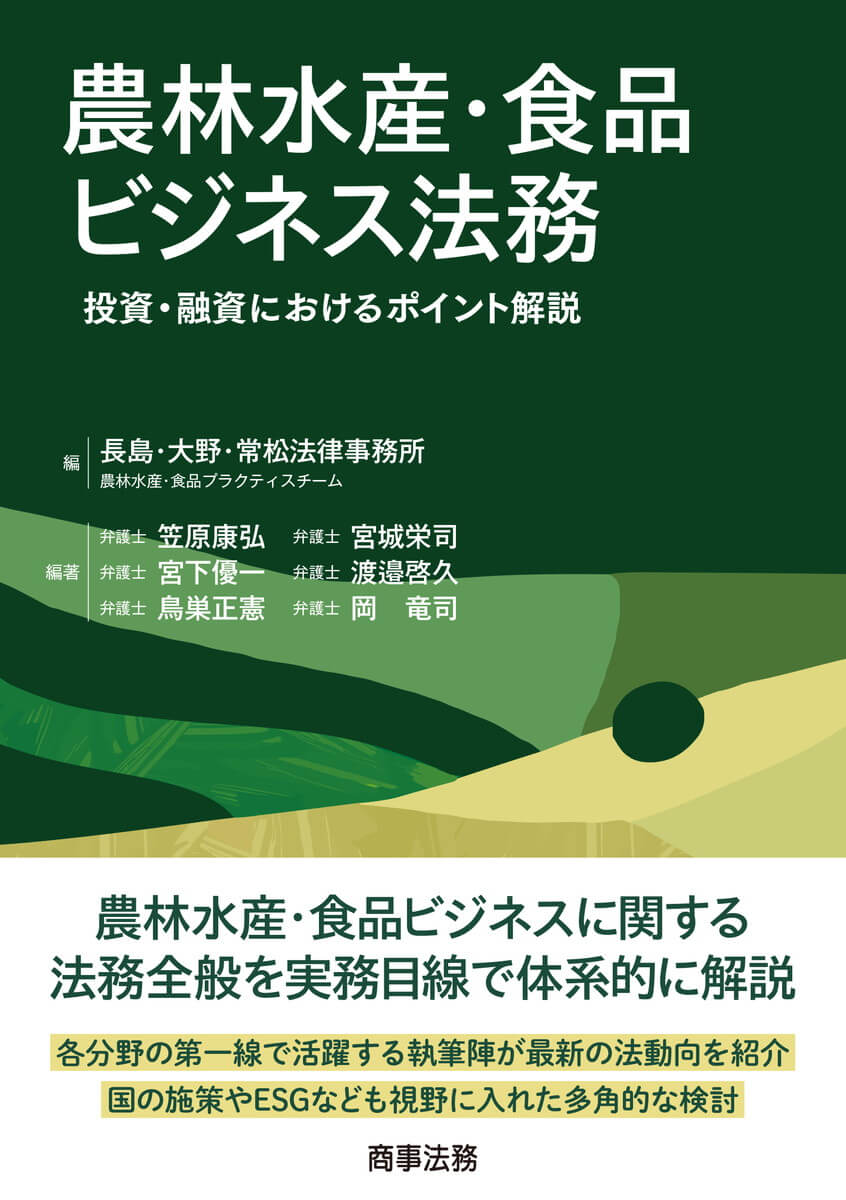
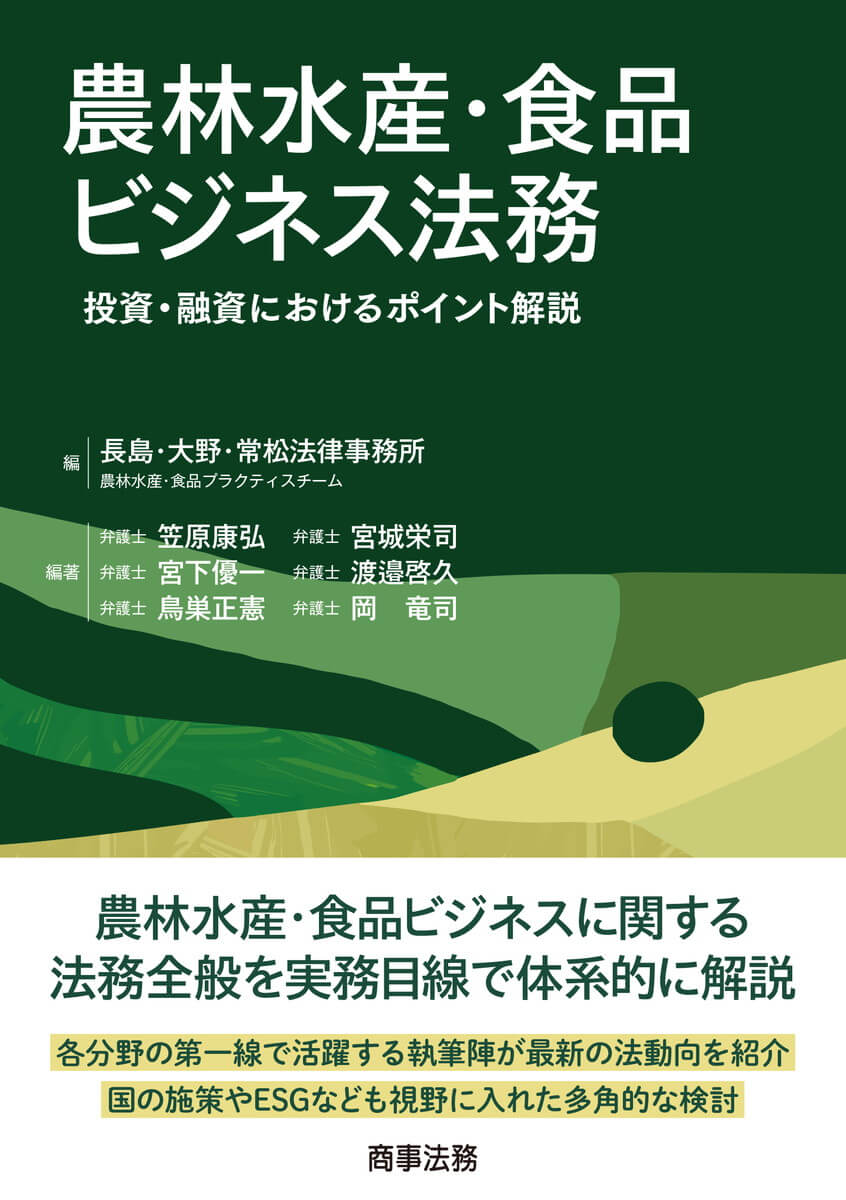
商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)