
宮城栄司 Eiji Miyagi
パートナー
東京

NO&T Food System and Nature Law Update 農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター
農林水産省が令和3年5月に策定した食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」※1は、我が国の食料・農林水産業が抱える様々な政策課題に対応し、食料・農林水産業の生産力の向上と持続性の両立をイノベーションにより実現することを目的としている。同戦略が定める14のKPIの中には、2050年までに化学農薬の使用量を50%低減させること(リスク換算)が含まれており、「バイオスティミュラント(植物のストレス耐性等を高める技術)を活用した革新的作物保護技術の開発」がそのための具体的な取組の一つとして挙げられている。
バイオスティミュラント(Bio Stimulants。以下「BS」という。)とは、近年国内外において注目されている、農業の効率化を促進するための新しい農業資材であり、今後さらに技術開発が進められ普及することが見込まれる。もっとも、BSは従来の農薬、肥料、⼟壌改良資材とは異なる新たなカテゴリーの資材であり、その意義や定義が明確でないうえ、その使用、表示、情報提供及び安全性などに関するルールが示されていなかった。これらの課題を踏まえて、農林水産省は、令和7年5月30日、使用者が効果のあるBSを安心して選択・使用できる環境を整えるため、BSの効果や使用に係る表示に関する事項を中心に、事業者がBSを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示すことで、事業者による自主的な取組を促すとともに、使用者による目的に合った製品の選択や適切な使用に資することを目的とした「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)を策定した※2。本稿では、BSと既存の法規制の関係にも注視しながら、本ガイドラインを概観する。
本ガイドラインにおいて「バイオスティミュラント」は、以下のとおり定義されている(本ガイドライン2.)※3。
を改善するものであり
BSについては様々な分類方法があるが、資材の起源別では、①腐植質、有機酸資材(腐植酸・フルボ酸)、②海藻・海藻抽出物、多糖類、③アミノ酸・ペプチド資材、④微量ミネラル、ビタミン、⑤微生物資材(トリコデルマ菌、菌根菌、酵母、枯草菌、根粒菌等)、⑥その他(動植物由来機能性成分、微生物代謝物、微生物活性化資材など)に分類される※4。
BSは新しい農業資材であり、基本的には、既存の法規制は及ばないと考えられるが、農業資材のうち、農薬、肥料、土壌改良資材についてはそれぞれ、農薬取締法、肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」という。)及び地力増進法により規制されている。
| 法 | 定義 | 主な規制内容 | 例 | |
|---|---|---|---|---|
| 農薬 | 農薬取締法 | 農作物等を害する病害⾍の防除に⽤いられる殺菌剤、殺⾍剤、除草剤その他の薬剤及び農作物等の⽣理機能の増進⼜は抑制に⽤いられる成⻑促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(肥料を除く)(第2条第1項) |
農薬の製造等に関する規制
|
|
| 肥料 | 肥料法 | 植物の栄養に供すること⼜は植物の栽培に資するため⼟壌に化学的変化をもたらすことを⽬的として⼟地に施される物及び植物の栄養に供することを⽬的として植物に施される物(第2条第1項) |
肥料の生産等に関する規制
|
|
| 土壌改良資材 | 地力増進法 | 植物の栽培に資するため⼟壌の性質に変化をもたらすことを⽬的として⼟地に施される物(第11条第1項) |
地力増進法に定められた基準に従った表示(原料・用途・施用方法など)(第11条) ※地力増進法施行令に規定された12の土壌改良資材に限る |
|
BSと農薬は、農薬が害虫、病気、雑草などの「生物的ストレス」を対象とするのに対し、BSは乾燥、高温、塩害などの「非生物的ストレス」を対象とする点で区別される。
また、BSと肥料とは、肥料がそれ自体の持つ栄養成分により効能を発揮するのに対し、BSは、定義上「バイオスティミュラント自体が持つ栄養成分とは関係なく」とあることからも、それ自体が持つ栄養成分が直接的には作用しないものも含まれる点で異なると考えられる。
BSと土壌改良資材については、土壌改良資材が土壌の物理的性質、化学的性質又は生物的性質に変化をもたらして、農業生産に役立たせる資材であるのに対し、BSは施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材である点で異なる。
もっとも、BSの中には、法令上の農薬、肥料又は土壌改良資材に該当する場合も考えられ、そのような資材を扱う事業者は、農薬、肥料又は土壌改良資材として適用される法律を遵守した上でBSとして本ガイドラインに沿った対応を行う必要がある。事業者がBSとして扱う資材が農薬、肥料又は土壌改良資材に(も)該当し得る場合としては、以下の場合が考えられる※6。
①について、本ガイドラインは、農薬に関して「病害虫や雑草の防除や農作物等の生理機能の増進・抑制といった農薬と誤認されるような効果の表示はしないこと」、肥料に関して「『植物の栄養となる』、『土壌に化学的変化を生じさせる』といった肥料と誤認されるような効果の表示はしないこと」を留意事項として挙げている(本ガイドライン3.(1))。
また、②については、「農薬登録のある有効成分が含まれるバイオスティミュラント製品が、登録農薬と同程度以上の濃度で農作物等の栽培・管理のために使用された場合、農薬としての効果が発現するため、当該資材は登録を受けていない農薬に該当する可能性がある」との指摘がされている(本ガイドライン脚注2)。
本ガイドラインは、事業者がBSを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示すことで、事業者による自主的な取組を促すことを目的としている。以下、BSの表示等に関して、本ガイドラインに規定されたルールの概要を記載する。
なお、景品表示法における不当表示※8や上記2.(2)記載のとおり農薬又は肥料と誤認されるような効果の表示は行わないよう留意する必要がある。
また、BS製品の効果や使用に係る表示を行うに当たり、事業者は以下を確認することが求められる。
関連情報として、以下の情報を確認することも求められる。
なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存することも併せて求められている。
なお、確認した情報は、必要な際に参照できるように保存することも併せて求められている。
事業者としては、使用者が栽培作物や栽培環境等に応じて効果のあるBSを安心して選択・使用できるよう、農業資材等に係る関連法令にも留意しつつ、本ガイドラインに沿った適切な表示等を行うことが期待される。脱炭素化、化学農薬・化学肥料の低減等の環境負荷軽減や持続的な食料システムの構築など、国内外におけるSDGsや環境に対する関心の高まりを受け、BSは、今後世界規模で市場が拡大していくことが見込まれるところであり、BSの市場拡大に応じて本ガイドラインの改定もあり得るため、状況を注視しておく必要があろう。
※1
農林水産省「みどりの食料システム戦略~食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~」(令和3年5月)
※2
農林水産省「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」(令和7年5月30日付け7消安第1353号消費・安全局長通知)
※3
農林水産省消費・安全局農産安全管理課「『バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン』に関するQ&A」(令和7年5月)(以下「本Q&A」という。)によれば、天然に存在しない合成物であっても、本ガイドラインにおけるBSの定義に該当する場合は、BSの原材料として、本ガイドラインの対象となることが示されている(本Q&A1)。
※4
日本バイオスティミュラント協議会Webサイト「バイオスティミュラントの定義と意義」参照
※5
本Q&Aによれば、「植物成長調整剤を施用することにより生理機能が増進又は抑制された結果として、バイオスティミュラントに期待されるような非生物的ストレスに対する耐性や栄養成分の利用効率の改善などの効果を発現することも考えられますが、それはバイオスティミュラントではなく、植物成長調整剤の効果と捉えるべき」と示されている(本Q&A2)ことから、植物成長調整剤については、農薬に該当する場合は、農薬取締法に従って取り扱う必要がある。
※6
農林水産省「無登録農薬であると疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導について」(平成19年11月22日付け19消安第10394号農林水産省消費・安全局長通知)参照
※7
BSの「効果」について、本Q&Aによれば、直接的な効果は、本ガイドラインの定義に記載している「土壌中の栄養成分の吸収性、農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性」の改善がなされることであるが、それに加えて、その結果としての農作物の品質又は収量の向上も含むことが示されている(本Q&A3)。
※8
BSの効果について、実際のものよりも著しく優良であると示すもの又は事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(景品表示法第5条第1号、優良誤認表示の禁止)である。
※9
本Q&Aによれば、BSを施用した結果、植物体内で起こる特定の遺伝子の発現量や特定の物質の定量的な変化等の生化学的な反応のほか、視覚的に観察できる植物の変化が例として挙げられている。なお、必ずしも作用機序全体を解明することを指しているわけではないとのことである(本Q&A4)。
※10
本ガイドラインによれば、BS製品の主な成分の含有割合を分析するときは、①品質のばらつきを把握するため、3ロット以上分析すること、②原材料の入手先が複数ある、天然物が原材料であるなど、品質がばらつく要因がある場合は、それらを考慮して分析点数や対象試料などを決めること、③分析に際して、肥料等試験法など参考となる公定法がある場合は、対象の類似性などを考慮しつつ、当該方法により実施することが求められている(本ガイドライン3.(3))。
※11
本Q&Aによれば、安全性試験を実施する場合、販売等を行う製品の原材料や使用方法等を考慮して、農薬登録において必要となる試験のうち、毒性に関する試験(急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性に係る試験等の中から必要なもの)を実施することが適切であるとされている(本Q&A5)。もっとも、様々な種類のBS製品がある中で、具体的な試験方法について判断が難しい場合は、農林水産省に相談することが望ましい。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年8月)
杉本花織


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


宮下優一、薄実穂(共著)


宮城栄司、井柳春菜(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
三笘裕、平松慶悟(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
森大樹、井上皓子(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年7月)
森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


宮城栄司、井柳春菜(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
森大樹、井上皓子(共著)


宮城栄司、井柳春菜(共著)
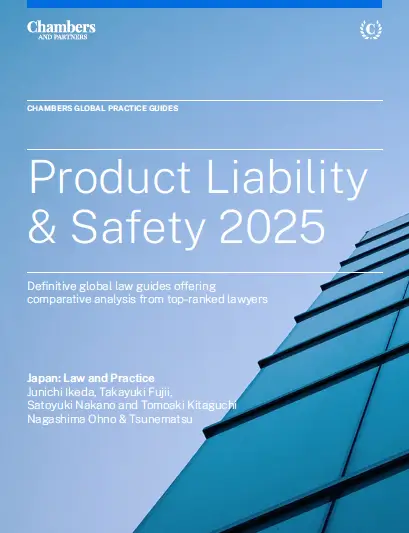
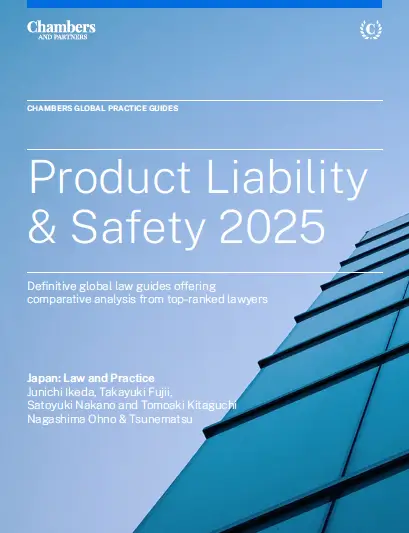
(2025年6月)
池田順一、藤井孝之、中野学行、北口智章(共著)