
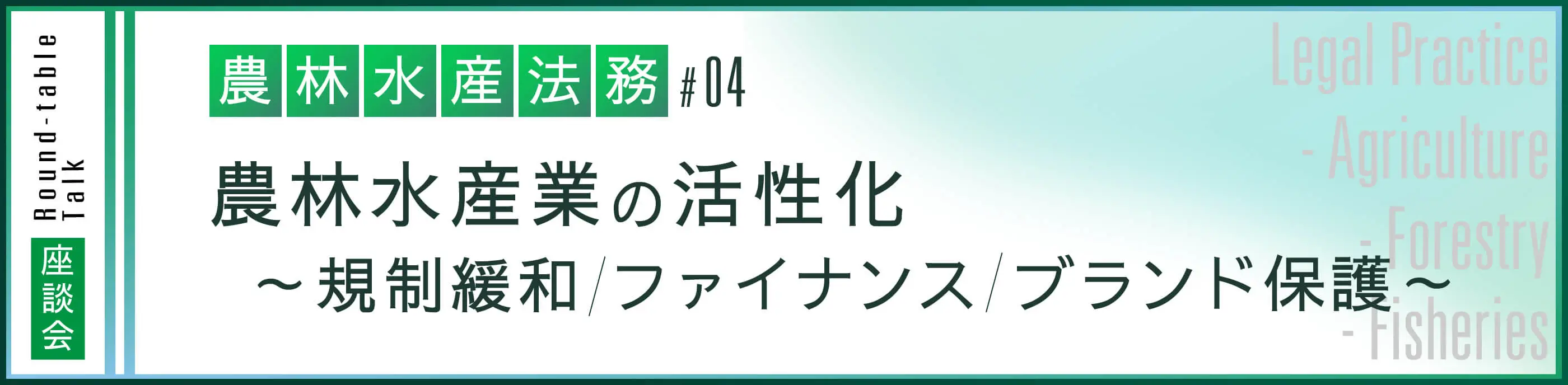
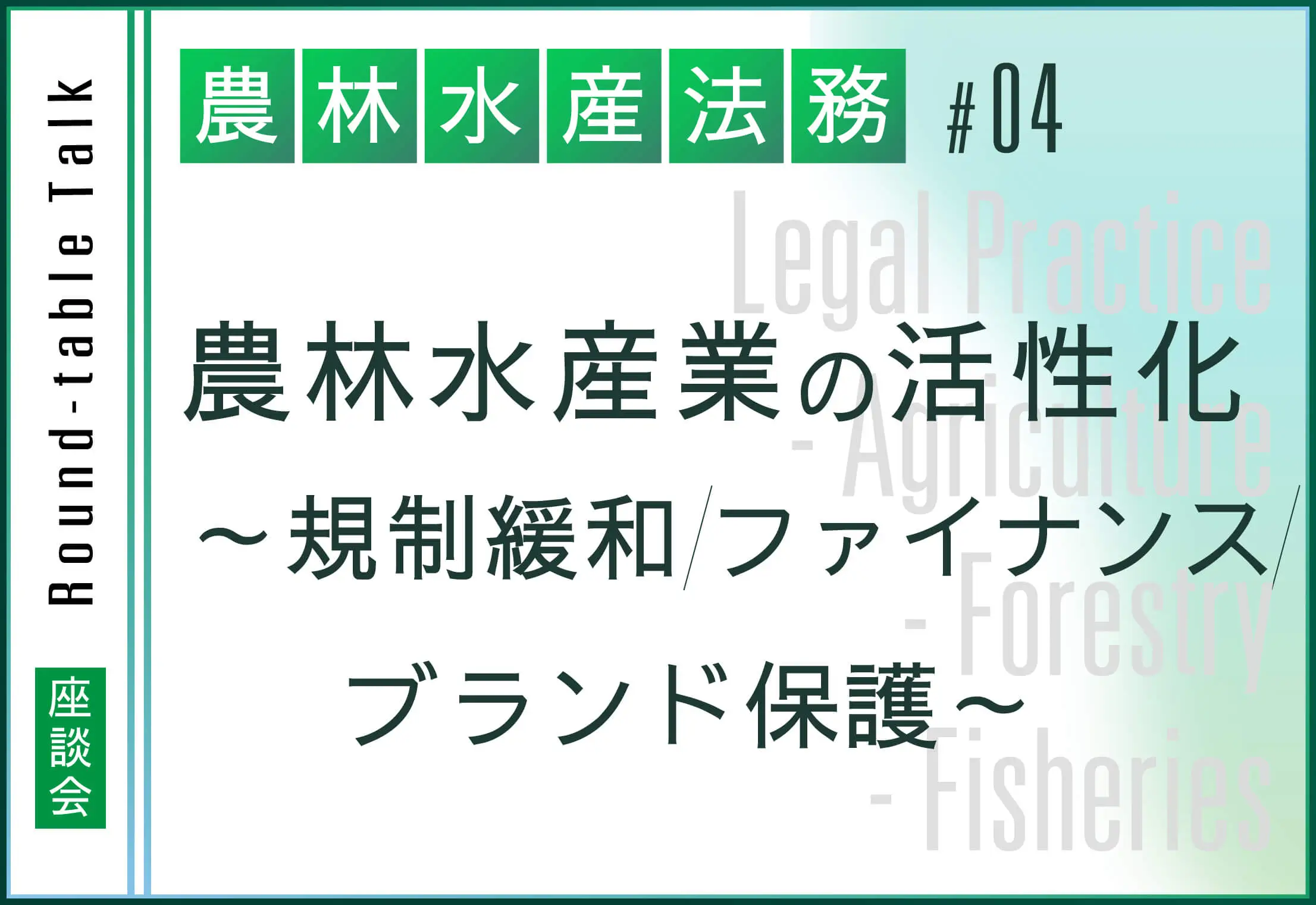
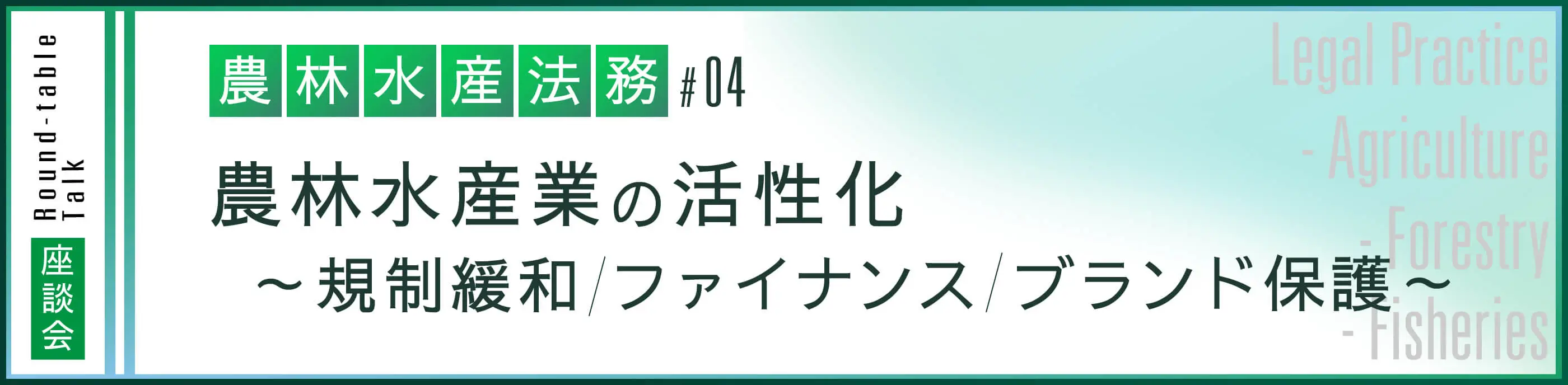
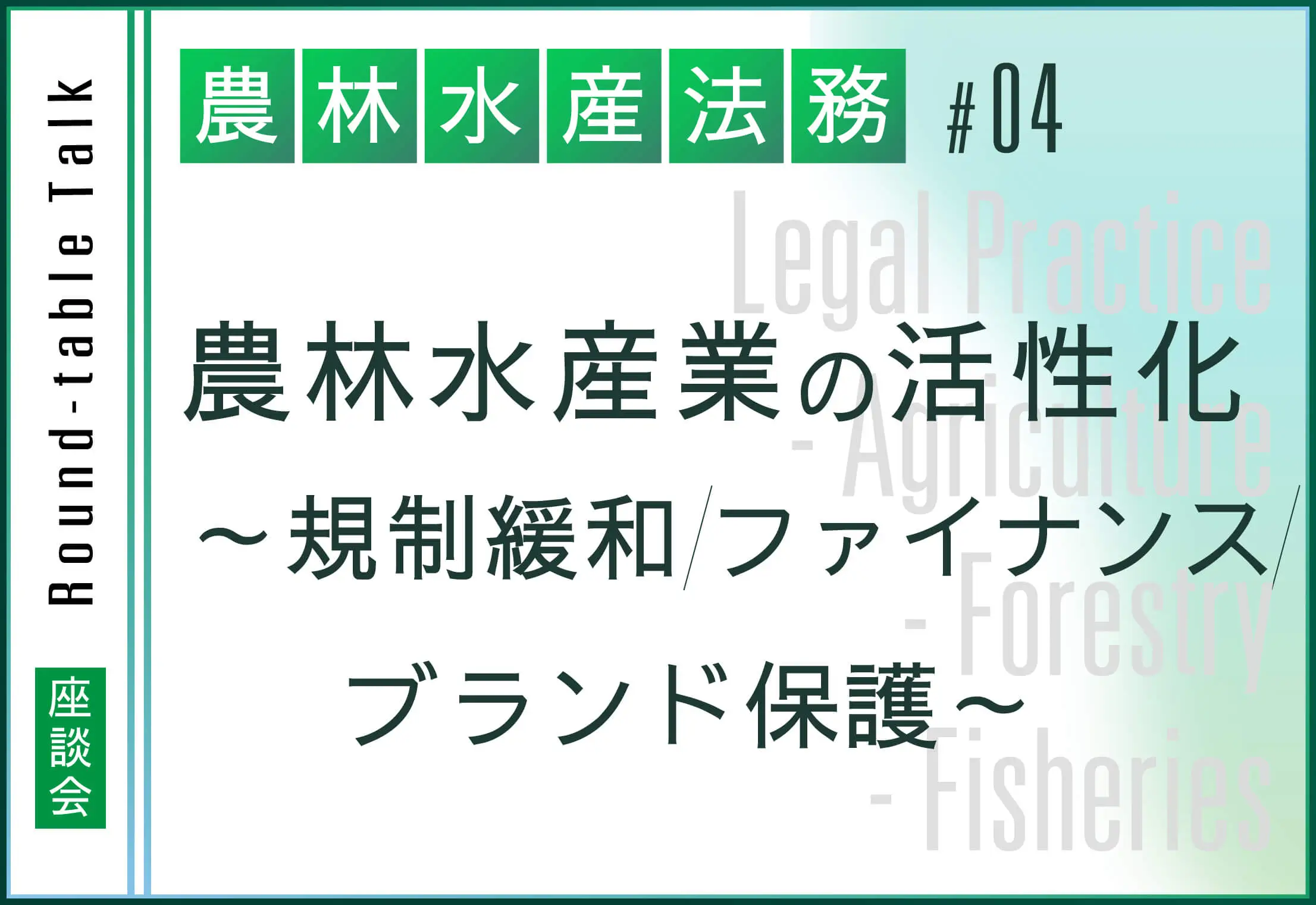

主な業務分野は、M&A/企業再編、プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル、一般企業法務。米国及びブラジルにおける勤務経験を活かし、北中南米を中心とした国際案件も幅広く取り扱っており、農林水産エリアへの投資についても助言している。

資源・エネルギー、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス、J-REIT及び私募ファンドの組成・運営等を含むインフラ・不動産取引全般、その他一般企業法務を取り扱う。近時は、テクノロジー、カーボンニュートラル、農林水産分野等に関する法律問題にも取り組んでいる。

買収ファイナンス、プロジェクトファイナンスを中心としたファイナンス取引、再エネプロジェクトを含むエネルギー関連案件その他企業法務について幅広く取り扱っている。近時は、農林水産分野におけるファイナンスなどにも取り組んでいる。

知的財産に関する国内及び国外の紛争やライセンス契約等の知的財産についての取引や契約などを中心に企業法務についてアドバイスを提供している。また、農林水産分野に関する法的問題への取り組みも行っている。

ファイナンス、インフラ/エネルギー、不動産取引、労務をはじめとした企業法務全般についてアドバイスを提供している。また、農林水産分野に関連する法律問題にも取り組んでいる。

ファイナンス、労務、危機管理をはじめとした各種の企業法務分野でアドバイスを提供する。また農林水産、自然環境保全に関連した法律問題にも取り組んでいる。
今回は、農林水産業の活性化というテーマで、主にこれまで行われてきた規制緩和の流れ、ファイナンスの観点からみた農林水産業、それから、海外輸出も視野に入れたブランドの保護という点について議論したいと思います。

宮城

岡

荒井

宮城



宮城

荒井

岡

荒井

宮城

岡

宮城



笠原

荒井

羽鳥

三浦

羽鳥

宮城

三浦

笠原

羽鳥

三浦

羽鳥

三浦

笠原

第5回 「農林水産業とカーボンニュートラル(仮)」
(渡邉啓久弁護士、宮城栄司弁護士、稗田将也弁護士、水野奨健弁護士)
※次回は、2月7日の公開を予定しています。
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。