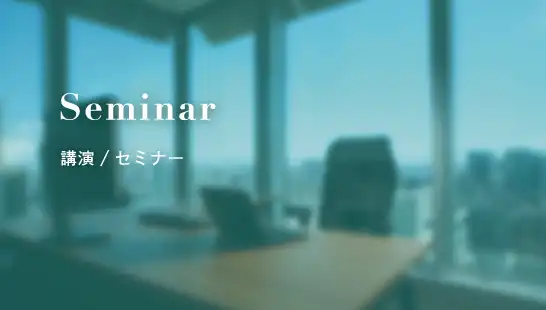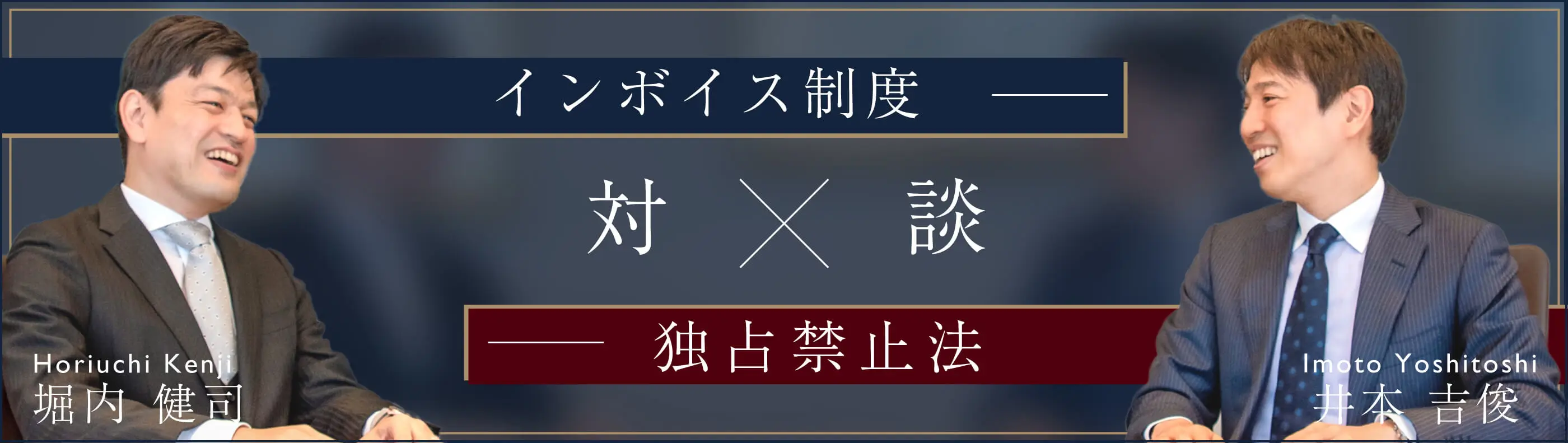【はじめに】
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、いわゆる「インボイス制度」が導入され、発注者は、免税事業者であるサプライヤーとの仕入取引に課される消費税について段階的に仕入税額控除が取れなくなります。これは免税事業者であるサプライヤーにとっても一大事です。免税事業者であるサプライヤーは、①免税事業者であり続けるのか、あるいは、課税事業者となることを選択した上で、インボイスを発行できるよう適格請求書発行事業者として登録するのか、②適格請求書発行事業者とならないことによる発注者からの取引の減少のリスクや金銭的インパクトを検討する必要があるといえます。発注者においても、免税事業者であるサプライヤーとの取引との在り方について検討を要するといえます。もっとも、発注者がサプライヤーに対して一方的な税務対応を要請したり、その要請を応諾しないサプライヤーとの取引を直ちに停止したりするなど、発注者の行動次第では、独占禁止法(優越的地位濫用)に違反するおそれもありますので、発注者においても周到な準備と慎重な対応が必要となります。
CHAPTER
01
2023年10月1日から
導入されるインボイス制度の概要
-
堀内:
-
本日は租税法と独占禁止法が交錯する問題ということでお話ししたいと思います。一見するとあまり結びつかない分野ではありますね。
-
井本:
-
実際にはそうでもないですよ。両分野に関連するものとして、消費税の増税に際して消費税転嫁対策特別措置法があります。2021年3月末で失効しましたが、公正取引委員会はこの特別措置法違反の事件の調査を積極的にやってきており、累計すると数千件の調査がありました。勧告に至ったものだけでも59件もあります。
-
堀内:
-
消費税といえば、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が導入されることになっています。インボイス制度に関しては、先日(本年10月1日)、インボイスを発行するための適格請求書発行事業者としての登録申請の受付が始まりました。
-
井本:
-
インボイス制度について簡単にご説明いただけますか。
-
堀内:
-
消費税は、売上取引に関して受領した消費税から仕入取引に関して支払った消費税を控除することで納付すべき消費税額が算定されます。この仕入取引に関して支払った消費税を控除する制度が、仕入税額控除になります。仕入税額控除が得られれば、納める消費税額が減り、所得として手元に残るお金も増えるわけです。今回のインボイス制度では、発注者が仕入税額控除を得る要件として、「インボイス(適格請求書)」の保存を求められることとなり、その結果、サプライヤーはインボイスを発行できるよう「適格請求書発行事業者」として登録をしなければならなくなります。

CHAPTER
02
サプライヤーに対する
適格請求書発行事業者としての登録要請が独占禁止法上の問題を引き起こす可能性
-
井本:
-
仕入税額控除を得たい発注者からすれば、当然サプライヤーには適格請求書発行事業者の登録を受けて欲しいということになりますね。登録を受けることでサプライヤーに何かデメリットはありますか。
-
堀内:
-
現在消費税を納めている課税事業者については大きな問題はないと思います。一方で、現在消費税を納めていない免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには課税事業者になる必要があります。課税事業者になれば、サプライヤーが発注者への売上に際して、発注者から受け取っていた消費税を納める必要が出てきますので、サプライヤーには大きな金銭的インパクトがある可能性があります。
-
井本:
-
そうすると、発注者が、一方的に免税事業者であるサプライヤーに適格請求書発行事業者としての登録を要請したり、その要請を応諾しないサプライヤー側との取引を直ちに停止したりすると、独占禁止法に違反する可能性がありますね。
-
堀内:
-
適格請求書発行事業者の登録の是非を検討するサプライヤーだけの問題ではないということですね。インボイス制度の導入に関して、先ほど言及のあった消費税転嫁対策特別措置法のような特別法の制定は予定されていないですよね。
-
井本:
-
少なくとも2021年11月末現在では予定されていないと思います。そのため、独占禁止法のような一般法の問題となり、具体的には優越的地位濫用の問題となります。

CHAPTER
03
具体的な対応策の指針
-
堀内:
-
免税事業者であるサプライヤーは、今までは発注者から消費税を受領するものの、納付はしていませんでした。これは益税と呼ばれて、国家財政上は問題視されてきました。発注者が、免税事業者であるサプライヤーに対して、適格請求書発行事業者の登録を行うよう要請することは、国の観点からみれば益税の解消に繋がり、インボイス制度導入の趣旨と合致する側面があると思います。この点は優越的地位濫用か否かという独占禁止法の観点からは考慮されますか。
-
井本:
-
益税自体は違法なものではないですし、インボイス制度の導入後も免税事業者という制度は残ります。また、益税の吐き出しの強制はサプライヤー側にとって大きな悪影響があるのは事実ですので、益税の解消や縮小がインボイス制度導入の趣旨と合致するとしても、それを根拠に、発注者の一方的な要求による優越的地位濫用を正当化するのは困難だろうと思います。
-
堀内:
-
それでは、免税事業者であるサプライヤーに適格請求書発行事業者として登録してもらい、従前同様に仕入税額控除を得たい発注者としてはどのようにすべきでしょうか。
-
井本:
-
発注者とサプライヤーの関係は千差万別ですが、最も大切なことは、発注者が一方的に登録の要請を強いていると取られないようにすることだと思います。「一方的」であるという非難を避けるためには、発注者が、①サプライヤーの事情についても配慮を示すこと、②サプライヤーに発注者の状況を把握してもらった上でサプライヤーに判断の時間を十分に与え、拙速に登録の意向確認を求めないことが重要な視点といえます。
-
堀内:
-
インボイス制度の導入に際しては、現行法の仕入税額控除のための要件を充足すること等を要件として、インボイス制度の導入後3年間は免税事業者からの仕入取引に係る消費税額の80%、その後の3年間については50%の限りで仕入税額控除が認められる経過措置が定められています。この経過措置の活用も考慮に値しそうですね。
-
井本:
-
そのとおりだと思います。経過措置と組み合わせる形で、発注者と免税事業者であるサプライヤーの双方が納得して軟着陸できる地点を、丁寧に時間もかけつつ探っていくことが大切だと思います。
-
堀内:
-
そういう意味では、免税事業者のままであることを望むサプライヤーについては、適格請求書発行事業者として登録してもらうのではなく、発注者が得られなくなる仕入税額控除相当分を双方が納得いく形で負担するように取引価格を調整するという方向性もあり得ますか。
-
井本:
-
あり得ると思います。実際にも、ニュースレター(「消費税インボイス制度導入に伴うサプライヤーとの取引設計と独占禁止法遵守の課題」)の脱稿後に、そのような方向性の考え方がまだ成案ではないようですが内閣官房から公表されています(第2回 消費税軽減税率制度の円滑な運用等に係る関係府省庁会議の資料4「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(案)」のQ7)。双方が納得して軟着陸できる地点を、丁寧に探っていくことに変わりはありません。
-
堀内:
-
免税事業者のままでいくか、登録に進むのか、最終的にどちらの方向性で行くとしても、インボイス制度が導入される2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには原則として同年3月31日までに登録申請をする必要がありますので、検討や交渉に残された時間は必ずしも長くないですね。今まで独占禁止法についてお話ししてきました。最後に、そもそも論ですが、下請法で何か規制がされることはないのでしょうか。
-
井本:
-
サプライヤーとの取引が下請法上の下請取引に該当する場合であっても、先ほどのような発注者の一方的な登録要請行為は下請法で規制するのは難しいと思います。下請法の親事業者の禁止行為となっている、「買いたたき」や「購入強制」といった類型に当てはめるのが難しいためです。もちろん、インボイス制度の導入の機会に、「買いたたき」や「購入強制」、一度決めた契約金額を一方的に「減額」するようなことが発生すれば別ですけど。
-
堀内:
-
このインボイス制度問題については、租税法と独占禁止法の両方に目配りが必要になりそうですね。租税法の面からのタックスプラニングと、それをどう発注者とサプライヤーの間の取引に反映していくかという交渉の視点、そうした交渉の内容や過程が独占禁止法に反しないかという独占禁止法遵守の視点を俯瞰しつつ、それぞれの分野を担当する弁護士が協働することが求められますね。本日は、ありがとうございました。
※本対談に関連して、以下のニュースレターもご覧ください。
「消費税インボイス制度導入に伴うサプライヤーとの取引設計と独占禁止法遵守の課題」

本対談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。