
井本吉俊 Yoshitoshi Imoto
パートナー
東京

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター
NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター
本ニュースレターに関連して、井本吉俊弁護士と堀内健司弁護士による対談記事を掲載しています。
「消費税インボイス制度導入に伴うサプライヤーとの取引設計と独占禁止法遵守の課題」
また、本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、いわゆる「インボイス制度」が導入される。このインボイス制度に関連して本年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まった。
経過措置が設けられているものの、インボイス制度は、商品・サービスの発注者側、そうした商品・サービスのサプライヤーとなる受注者側の双方にとって大きな金銭的インパクトをもたらす可能性が高い。
まず、発注者側へのインパクトを検討する。例えば、課税事業者(適格請求書発行事業者)である発注者が税込220万円(消費税20万円)の部品を免税事業者であるサプライヤー10名から購入し、加工の上で税込5,500万円(消費税500万円)の商品として販売する場合を想定する。インボイス制度が導入され、最終的に免税事業者からの仕入取引に係る消費税について仕入税額控除を取れなくなった場合、発注者がその消費税相当分の200万円を負担することになり、発注者の所得金額は200万円分減少することとなる。
| 現行法 | インボイス制度下 | |
|---|---|---|
| 売上げ | 55,000,000円 | 55,000,000円 |
| 仕入れ | 22,000,000円 | 22,000,000円 |
| 租税公課(消費税) | 3,000,000円※1 | 5,000,000円※2 |
| 所得金額 | 30,000,000円 | 28,000,000円 |
| 影響額 | ▲2,000,000円 |
次に、サプライヤー側へのインパクトを検討する。上記の例において、免税事業者であるサプライヤーが税込110万円(消費税10万円)の部品を課税事業者(適格請求書発行事業者)から購入していたとする。ここで、サプライヤーがインボイス制度の導入を理由に課税事業者(適格請求書発行事業者)になることを選択した場合、従前は納付義務を負っていなかった消費税10万円を納付しなければならなくなる(次頁の表参照)。この結果、サプライヤーの所得金額は10万円分減少することになる。
| 現行法 | 課税事業者となった場合 | |
|---|---|---|
| 売上げ | 2,200,000円 | 2,200,000円 |
| 仕入れ | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| 租税公課(消費税) | 0円※3 | 100,000円※4 |
| 所得金額 | 1,100,000円 | 1,000,000円 |
| 影響額 | ▲100,000円 |
そうした中で、発注者側が、サプライヤー側に対して一方的な税務対応を要請したり、その要請を応諾しないサプライヤー側との取引を直ちに停止したりするなど、発注者側の行動次第では、独占禁止法(優越的地位濫用)に違反するおそれもあり、発注者側においても周到な準備と慎重な対応が必要となる。
例えば、プラットフォーム事業者の中には、消費税の納税を行っていない免税事業者と推測される多くのフリーランスやギグワーカーと同一内容の継続的な取引を行っている者もいると思われる。そのようなプラットフォーム事業者側ではこれらのフリーランス等との取引(仕入取引)に課される消費税について段階的に仕入税額控除が取れなくなるため、これらフリーランス等との取引の在り方について検討を要する。プラットフォーム事業者側が仕入税額控除を取れなくなることを理由に、フリーランス等に対して、インボイス制度が導入される2023年10月1日までに課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を完了することを取引継続の条件として一方的に要求するとなれば、フリーランス等に対する金銭的インパクトは大きく、こうした要求は、独占禁止法上の優越的地位濫用の問題を生じさせることになる。これはプラットフォーム事業者とフリーランス等との取引特有の問題ではなく、とりわけ免税事業者からの仕入取引の多い発注者はおよそ避けて通れない問題である。発注者側では事業のコスト構造に関わる重要な問題として慎重な検討が必要であり、サプライヤーへの説明や交渉に要する時間を踏まえると、発注者側に残された時間は必ずしも長くない。
そこで、以下では、インボイス制度の概要を説明した上で、優越的地位濫用のおそれが生じる仮想事案を紹介し、考えられる対応策について簡単に言及する。
※2021年12月1日付けの本ニュースレターの公開後に、内閣官房「消費税軽減税率制度の円滑な運用等に係る関係府省庁会議」の第2回会議(令和3年11月18日付)の議事概要が公表された。第2回会議の資料の「資料4」として、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(案)」が公表されており、そのQ7において優越的地位濫用等のリスクへの留意点が記載されているのでそちらも参照されたい。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keigen_kaigi/index.html
まず、消費税制度とは、ごく簡単に述べると、事業者が自社の商品やサービスを販売・提供した際に受け取った消費税(売上げに係る消費税)から、その自社の商品やサービスを販売・提供するにあたって行った仕入取引に関して支払った消費税(仕入れに係る消費税)を控除した差分の消費税を納付する制度である。例えば、税込55万円(消費税5万円)の部品を購入し、加工の上で税込165万円(消費税15万円)の商品として販売する場合に支払うべき消費税は受け取った消費税15万円から支払った消費税5万円を差し引いた差分の10万円ということになる。この仕入取引に関して支払った消費税(上記の5万円)を納付すべき消費税の算定に際して控除する制度を仕入税額控除という。
2023年10月1日からインボイス制度が導入される結果、仕入税額控除を受けるためには、事業者(発注者)は、サプライヤーから仕入取引に対応するインボイス(適格請求書)の交付を受けて、保存することが求められる(消費税法30条1項、7項)。そして、インボイスにおいては、①消費税の計算に必要な事項である、対象取引の年月日、対象取引の内容、税率毎の対価の合計額・適用税率、消費税額に加えて、②インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)の氏名又は名称及び登録番号の記載が求められることになる(同法30条9項、57条の4第1項、2項)。そのため、下記(2)に述べる、適格請求書発行事業者としての登録をせず、登録番号を有しない事業者(サプライヤー)からの仕入れに係る消費税については、下記(3)で述べる経過措置を経て、発注者において仕入税額控除を受けることができなくなることが予定されている。
インボイス制度が導入される2023年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要がある(平成28年改正法附則44条1項)※5。また、適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、課税事業者である必要があるため(消費税法57条の2第1項)、課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納税義務を負わない免税事業者(同法9条1項)は、課税事業者となることを自ら選択した上で(同法4項)、登録申請を行うことになる※6。
現行法においては、免税事業者からの仕入取引に課された消費税についても仕入税額控除が認められている(現行の消費税法30条1項、7項)。これは、免税事業者からの仕入取引に課された消費税について仕入税額控除を認めないこととすると、仕入税額控除が得られないことを理由に免税事業者が取引から排除され、課税事業者よりも競争上不利な地位に置かれる事態を防ぐことを1つの理由とするものである※7。しかしながら、現行法の下では、発注者は免税事業者であるサプライヤーに支払った消費税について仕入税額控除を得つつ、サプライヤーは受領した消費税を納付する義務を負わないこととなる結果、実質的には、国から免税事業者に対して、消費税相当分の援助をしている、という指摘もされてきた※8。こうした状況は「益税」と呼ばれ、消費税の税率が引き上がれば上がるほど益税が大きくなり国庫からの消費税の流出を招く関係にあるため、国家財政の観点から、従前より問題視されてきた※9。
インボイス制度の導入によっても免税事業者自体はなくならない。そして、適格請求書発行事業者としての登録をしない免税事業者が直ちに取引から排除されることがないよう、激変緩和策として、免税事業者からの仕入取引についても、現行法の仕入税額控除のための要件を充足すること等を要件として、インボイス制度の導入後3年間は当該仕入取引に係る消費税額の80%、その後の3年間については50%の限りで仕入税額控除が認められる経過措置が定められている(平成28年改正法附則52条、53条)。最終的には適格請求書発行事業者としての登録をしない免税事業者からの仕入れに関しては仕入税額控除を得られなくなるため、免税事業者が取引減少のおそれも踏まえて適格請求書発行事業者の登録をする流れとなれば「益税」問題は縮小に向かうものと見られる。
以上のとおり、免税事業者においては、今後導入されるインボイス制度を踏まえて、今後も免税事業者であり続けるのか、あるいは、課税事業者となることを選択した上で、適格請求書発行事業者として登録するのか、また、登録するとしていつから登録するのか、適格請求書発行事業者とならないことによる発注者側からの取引の減少のリスクや金銭的インパクトも踏まえて、検討する必要があるといえる。
このような検討において、簡易課税制度は重要な意義を有するといえる。簡易課税制度は、中小事業者の事務処理負担を考慮して、実際の仕入取引に係る消費税額に代えて、課税期間における課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を掛けることによって得られるみなし消費税額を、仕入控除税額として用いる制度であり、基準期間(個人については前々年、法人については前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者の選択によって認められている(同法37条1項)。したがって、事務処理負担の軽減という本来の制度趣旨とは異なるものの、みなし仕入率(みなし消費税額)が実際の課税仕入率(課税仕入れに係る実際の消費税額)よりも高率・高額であることが見込まれる免税事業者においては、免税事業者から課税事業者になることを選択する際に、併せて簡易課税制度を選択することによって※10、上記差分の消費税が手元に残るという利益を得られることになり※11、免税事業者から課税事業者への変更に伴う益税の減少を緩和することが可能になる。
したがって、インボイス制度の導入に伴って課税事業者への変更を検討する免税事業者においては、併せて簡易課税制度の選択の要否についても検討を要するといえる。
なお、みなし仕入率は、事業の種類毎に以下のとおりである(同法37条1項1号、同施行令57条1項)。
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%
以下では、特に影響の大きい、サプライヤーが免税事業者である場合を念頭に、消費税インボイス制度の導入後のサプライヤーとの取引条件の設計につき、独占禁止法上の問題点・留意点を検討する。
発注者側としては、インボイス制度の導入後はサプライヤーに対し、適格請求書発行事業者として登録してもらい、従前通りの仕入税額控除を得られるようにするのが最も望ましい。このため、発注者としては、サプライヤーに対し、適格請求書発行事業者としての登録を要請したいところであろう。他方、サプライヤー側としては、既に課税事業者となっている場合には適格請求書発行事業者の登録をしても適格請求書発行に伴う各種の作業負担はあれインボイス制度の導入前と税負担の面において変わるところはないが、サプライヤーが免税事業者である場合には、課税事業者となることに伴う「益税」の喪失又は減少といった大きな税務上の悪影響が発生する。
こうした状況のもとで、発注者側が免税事業者であるサプライヤーに対して、適格請求書発行事業者としての登録を要求し、登録に応じないサプライヤーに対して、直ちに契約解除や契約単価の引き下げを示唆したり、実際に契約解除や契約単価の引き下げを行ったりする場合には、発注者側の行為は、優越的地位にある者による相手方への一方的な取引条件の設定として、独占禁止法上の優越的地位濫用※12に該当するおそれが高い。また、発注者が、免税事業者である多数のサプライヤーに対して拙速かつ一律にこうした要求をすることは、行為の広がりやサプライヤー側の不利益の程度も大きく※13、公取委が優越的地位濫用の違反被疑事件として大々的に取り上げる可能性も否定できないであろう。
なお、サプライヤー側が免税事業者である場合、インボイス制度の導入後、発注者側では仕入税額控除が段階的にゼロになる一方、サプライヤー側では「益税」が残るのであるから、発注者側の目線でみればサプライヤーは「益税」を吐き出して当然と考えるかもしれない。しかしながら、2で説明した「益税」は何ら違法なものではなく、また、インボイス制度の導入後も免税事業者というステータス自体は残ること、「益税」部分の吐き出しの強制はサプライヤー側にとって大きな悪影響があるのが通常である。これらからすれば、「益税」問題の存在やインボイス制度の導入に伴う「益税」問題の縮小にも整合的であることを理由に発注者側が自身の行為には正当化理由があると主張して優越的地位濫用を否定することは困難であろう。
他方、取引の自由は、資本主義経済の大原則である。発注者が免税事業者であるサプライヤーとの取引を、インボイス制度導入後も従前通りの取引条件で必ず継続しなければならない義務は、優越的地位濫用規制を前提としても存在しないというべきである。免税事業者のままのサプライヤーと従前通りの取引条件で取引を継続することは、発注者側にとっては、仕入税額控除の段階的廃止の税効果も勘案すれば、実質的にみて取引単価の上昇を意味し、発注者自身の事業の収益性確保の上で死活問題となりうる。よりよい取引条件を提示可能なサプライヤーとの取引関係を強化し、そうでないサプライヤーとの取引関係を縮小・終了させていくことは競争の原理の帰結でもあり、免税事業者に対して、適格請求書発行事業者としての登録を要請すること自体が違法となるわけではない。また、免税事業者であるサプライヤーの中には、あえて課税事業者となることで仕入税額控除を従前通り受けられる発注者側の便宜にも配慮し、取引の拡大や自身の競争力強化を図る者が出てくることもありえ、免税事業者が状況を的確に把握した上で自ら適格請求書発行事業者になることを過度に抑え込むことはかえって競争の促進にも資さない。したがって、発注者としては、サプライヤー側の立場や状況にも理解を示しつつ、インボイス制度の下で発注者側とサプライヤー側の双方が納得のいく妥結の余地を丁寧に探っていくことが優越的地位濫用のリスクを避けるために有用である。
免税事業者に対して、適格請求書発行事業者としての登録を要請する場合、最も大切なことは、発注者が一方的に登録の要請を強いていると取られないようにすることである。この「一方的」との非難を避けるためには、発注者が、①サプライヤー側(特に免税事業者)の事情についても配慮を示すこと、②サプライヤー側に発注者側の状況を把握してもらった上で判断の時間を十分に与え、拙速に登録の意向確認を求めないことが重要と思われる。
サプライヤーの数、属性(副業的な個人事業者か否か)、発注者との力関係・依存度など、発注者側とサプライヤー側の関係性は千差万別にならざるを得ず、優越的地位濫用にならないためのバランスの良い丁寧な妥結の模索に関して答えは一様ではない。このため、あくまで例示であるが、発注者としては以下のような対応指針が考えられる。すなわち、まずは発注者から消費税法上の経過措置も含めた制度説明を免税事業者側に積極的に行い、免税事業者との仕入取引に関する仕入税額控除の段階的廃止が発注者側においても大きなインパクトをもたらすことをサプライヤーに周知すること、現在免税事業者であるサプライヤーが自発的に課税事業者として登録するとなればサプライヤー側にも痛みが発生することにも十分配慮を示しつつ、時間的な余裕を与えて登録に向けた検討を要請することがベストプラクティスと考えられる。また、可能であれば、経過措置とも組み合わせる形で、発注者とサプライヤーとで痛み分けを行えるような単価・取引条件のパッケージ案や免税事業者から課税事業者に切り替えた者への一定のインセンティブ案を準備し、そうしたパッケージ案、インセンティブ案をベースに一定の時間をかけて交渉、妥結を目指すことが考えられる。それでも妥結が困難なサプライヤーとは一定年限のもとでサプライヤーとの取引を縮小、終了するといった手続を踏んでいくのであれば、優越的地位濫用に問われるリスクは比較的抑えられたものになると考えられよう。
消費税の税率上昇の際には、時限立法として消費税転嫁特別措置法が制定され、免税事業者であるか否かを問わず、仕入取引先に対して消費税上昇分の対価の引き上げを行わないことが同法上の買いたたきに該当するとして仕入取引先への保護が行われた。インボイス制度に関連して仕入取引先への保護のための特別措置法は制定されない予定である。
しかしながら、2021年3月、公取委は他の省庁と連名で立て続けにガイドラインを公表している。すなわち、「スタートアップとの事業連携に関する指針」(公取委及び経済産業省)及び「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(内閣官房、公取委、中小企業庁及び厚生労働省)である。これらはいずれも現行の下請法や独占禁止法の規律を変更するものではないが、スタートアップやフリーランスの保護のために、下請法に類似する新たな立法が検討されており、インボイス制度に伴う課税事業者の登録の要請にあたっても、こうした新法制定の内容も注視していく必要があると考えられる。
以上のとおり、インボイス制度は、商品・サービスの発注者側、そうした商品・サービスのサプライヤー側の双方にとって大きな金銭的インパクトをもたらし得る。そのような中、発注者側が免税事業者であるサプライヤーに対して、一方的に、適格請求書発行事業者としての登録を要求したり、その要求を応諾しないサプライヤー側との取引を直ちに停止したりするといった拙速な対応をする場合には、優越的地位にある者による相手方への一方的な取引条件の設定として、独占禁止法上の優越的地位濫用に該当するおそれが高い。したがって、2023年10月1日のインボイス制度の施行に向けて、免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録の要否を検討することに加えて、発注者側においても、とりわけ免税事業者であるサプライヤーとの取引について、サプライヤー側の事情にも配慮しつつ、一定の時間をかけて交渉し、双方が納得のいく妥結の余地を探っていくという慎重な対応が求められるといえる。
※1
売上げに係る消費税5,000,000円-仕入れに係る消費税2,000,000円
※2
売上げに係る消費税5,000,000円
※3
免税事業者のため、納付する消費税はゼロ円である。
※4
売上げに係る消費税200,000円-仕入れに係る消費税100,000円
※5
適格請求書発行事業者は、国税庁のウェブサイトで公表される
(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)。
※6
もっとも、2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合については、免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出しなくとも、登録申請書を提出すれば、課税事業者(適格請求書発行事業者)になることができる(平成28年改正法附則44条4項、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達5-1)。
※7
例えば、望月俊浩「消費税の複数税率化を巡る諸問題」『税務大学校論叢』42号(2003.6)231頁から233頁。
※8
免税事業者が負担するものの仕入税額控除を得ることのできない自らの仕入取引に係る消費税(同法30条1項)を経済的に補填する側面はある。
※9
例えば、佐藤良「インボイス方式導入をめぐる経緯と課題」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』949号(2017.3.23)9頁から10頁に引用された議論参照。
※10
脚注6記載の経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされる(平成30年改正令附則18条)。したがって、例えば、2023年10月1日から適格請求書発行事業者としての登録を受けた免税事業者については、2023年10月1日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署長に提出した場合には、同登録日から簡易課税制度の適用を受けることができることになる。
※11
これも「益税」の一種である。会計検査院の調査では、簡易課税制度適用者について事業区分毎にみなし仕入率と課税仕入率の平均を比較すると、みなし仕入率が全ての事業区分において課税仕入率の平均を上回っていたほか、同一の事業者において比較しても、多くの簡易課税制度適用者において、簡易課税制度を適用した課税期間の消費税納付率の方が、本則課税を適用した課税期間の消費税納付率より低くなっていたと指摘されている(2012年10月会計検査院「消費税の簡易課税制度について」に関する会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書(要旨)6頁・7頁)。
※12
なお、下請法については、サプライヤー側との取引が下請法上の下請取引に該当する場合であっても、上述のような発注者側の行為は必ずしも「買いたたき」や「購入強制」といった下請法上の親事業者の禁止行為に当てはまらない。別途、発注後の「減額」などの禁止行為がない限り、サプライヤー側が発注者の下請法違反を主張することは難しいと思われる。
※13
公取委「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」第1 1参照
()
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
伊藤伸明
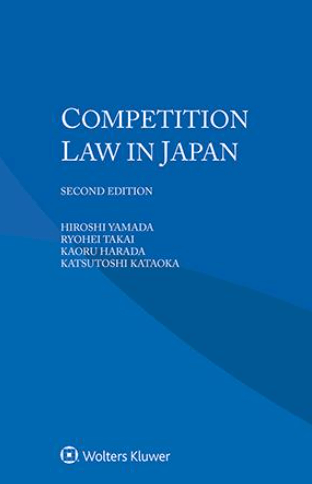
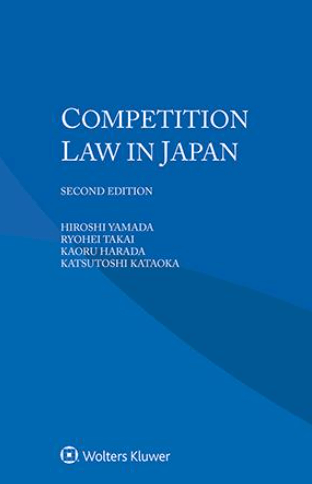
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2024年10月)
井本吉俊


服部薫、柳澤宏輝、一色毅、清水美彩惠(共著)


小川聖史


服部薫、柳澤宏輝、一色毅、清水美彩惠、田口涼太(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)
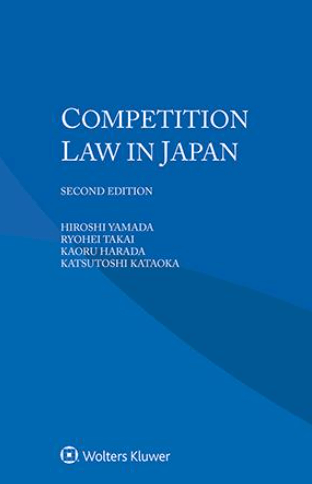
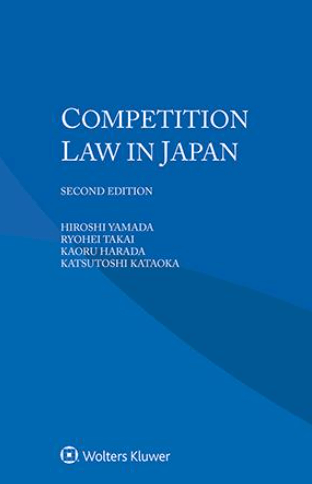
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


遠藤努、中村日哉(共著)


(2025年5月)
宰田高志


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2025年5月)
吉村浩一郎


遠藤努、中村日哉(共著)


(2025年5月)
宰田高志


(2025年5月)
吉村浩一郎


(2025年5月)
南繁樹


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


遠藤努、中村日哉(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
井上皓子


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
井上皓子


宮城栄司、井柳春菜(共著)


(2025年6月)
三笘裕、江坂仁志(共著)