
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
本ニュースレターでは、全3回に分けて内容をご紹介しています。第2回及び第3回は以下をご覧ください。
第2回:No.2(2022年3月)「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の内容(2) ―為替取引分析業に係る規制―」
第3回:No.3(2022年4月)「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の内容(3) ―高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制―」
2022年3月4日、金融庁は、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本改正法案」といいます。)を国会に提出しました※1。
本改正法案は、2022年1月11日に公表された「金融審議会『資金決済ワーキング・グループ』報告」※2(以下「WG報告書」といいます。)で示された方向性を踏まえ、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)、銀行法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)その他の関係法令を改正しようとするものです。
本改正法案の主な内容は、①電子決済手段等への対応、②銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応、③高額電子移転可能型前払式支払手段への対応の3点です。いずれも実務上重要な改正ですので、未成立の法案の段階ではありますが、本ニュースレターでは全3回に分けてその内容をご紹介したいと思います。
まず、本稿では、①電子決済手段等への対応を取り上げます。
近時、米国等の海外では、いわゆるステーブルコインの発行・流通の増加が見られます。ここでいうステーブルコインには明確な定義は存在しませんが、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定を目的とするデジタルアセットで分散台帳技術(又はこれと類似の技術)を用いているものをいうと考えられています※3。暗号資産は価値が乱高下しやすく、ボラティリティが高いことが一つの問題として認識されており、その価値を、特定の資産と関連付けることで安定(ステーブル(stable))にすることを目的としたものが、ステーブルコインです。
しかし、日本の法制度上、ステーブルコインをどのように分類することができるかは必ずしも明確ではありませんでした。また、日本の法制度上は、発行者が責任を負う形でのサービス提供を想定しており、ステーブルコインのように発行等の機能(主として利用者から資金を預かり、運用する機能)を担う「発行者」と、移転・管理等の機能(主として顧客管理(AML/CFT規制の遵守やシステム管理等))を担う「仲介者」が分離したスキームへの関係法令の適用関係が明確ではなく、流通に関する具体的な法的枠組みが整備されていません。
そこで、本改正法案は、ステーブルコインを、その価値を安定させる仕組みによって、以下の2つに分類した上で(WG報告書第2章1.(3)(17頁)参照)、そのうち(i)デジタルマネー類似型について、「電子決済手段」を新たに定義するなどして規制を及ぼすこととしました。具体的には、仲介者規制として、登録制の「電子決済手段等取引業」及び「電子決済等取扱業」を導入することとしています。これにより、すでに発行されたデジタルマネー類似型ステーブルコインの移転・管理等を行う「仲介者」に対する規制が新たに整備されることになります。
| 名称 | 概要 | 具体例 | |
|---|---|---|---|
| (i) | デジタルマネー類似型 | 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額での償還を約するもの(及びこれに準ずるもの) | 米ドルに連動したステーブルコインであるTether(USDT)、USD Coin(USDC)、Binance USD(BUSD) |
| (ii) | 暗号資産型 | 上記(i)以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等) | 暗号資産イーサリアム(ETH)を基盤とするDai(DAI) |
WG報告書においては、利用者の発行者に対する償還請求権が明確に確保され、発行者又は仲介者の破綻時において利用者の償還請求権が適切に保護されることが重要であるとの見解が示されており、発行者と仲介者が分離するステーブルコインのスキームにおいてかかる要請を満たす構成として、以下の3つの仕組みが例示されました。
本改正法案は、かかる3つの構成を軸に作られており、②と③は資金決済法において「電子決済手段等取引業」として、①は銀行法において「電子決済等取扱業」として、それぞれ規律されることになります※4。
なお、WG報告書※5では、現在米国で流通しているステーブルコインについて、発行者に対する償還請求権の保有者、償還のタイミング等が不透明であることや、かかるステーブルコインを扱う暗号資産取引プラットフォームは、一般的に、顧客のステーブルコインを分別管理していないウォレットで管理しており、オフチェーンの内部の帳簿に取引を反映しているといった取引実態を前提とすると、我が国の法制では、仲介者破綻時に利用者が発行者に対する償還請求権を円滑に行使できるとは言えないと考えられるという点や海外で発行されたステーブルコインについては、現行法上、発行者が日本で流通させる場合には、発行者に銀行業免許又は資金移動業登録が求められるという点が指摘されていることには留意が必要です。また、市場で流通している主要なデジタルマネー類似型ステーブルコインは、パーミッションレス型分散台帳を用いるものであるため、後述の仲介者に対する改正法の規制を踏まえると、本改正法案では、現在、日本国外で発行されている主要なステーブルコインをそのまま日本で取り扱うことは実務上困難であると考えられ、政令・内閣府令を含む今後の議論の状況を注意する必要があります。
本改正法案は、改正資金決済法2条で、以下のとおり「電子決済手段」の定義を新設しています。
5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
この定義の主な留意点は以下のとおりです。
1号と2号の文言は、現行法上の「暗号資産」の定義※6と類似していますが、「暗号資産」の定義における財産的価値からは「通貨建資産」が除外されているのと反対に、1号と2号における財産的価値はいずれも「通貨建資産」に限定されています。
「通貨建資産」とは、「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの・・・が行われることとされている資産」をいいます※7。暗号資産型のステーブルコインは通貨建資産に該当しないと考えられることから、1号と2号の「電子決済手段」に該当しないと考えられます。なお、暗号資産型のステーブルコインは、資金決済法上の「暗号資産」又は金商法上の「有価証券」に該当し得ると考えられます※8。
WG報告書では、既存のデジタルマネーについても、「発行者」と「仲介者」が分離し得ることを前提に仲介者規制を及ぼす必要があることが示唆されていました※9。この点、例えば銀行が発行している既存のデジタルマネーは、基本的に他人に譲渡する場合に「移転」という形式ではなく、銀行の譲渡人に対する債務の「消滅」及び受取人に対する債務の「発生」という構成を取るため、1号の電子決済手段の定義に該当しないものと思われます。本改正法案は、仲介者に係る業規制である「電子決済手段等取引業」の定義や「電子決済等取扱業」等において、電子決済手段に該当しないデジタルマネーについてもその対象に含め(改正資金決済法2条10項4号、改正銀行法2条17項1号)、規制が及び得るようにしているものと考えられます。
「通貨建資産」は、上記のとおり通貨をもって表示されるもののみならず、「本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの・・・が行われることとされている資産」を含みますので、銀行預金、国債、社債、前払式支払手段等もこれに該当し得ると考えられます。
もっとも、改正資金決済法では、通貨建資産のうち、「有価証券、・・・電子記録債権、・・・前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)」が、1号と2号の「電子決済手段」から除外されています。
但し、括弧書きのとおり、有価証券、電子記録債権、前払式支払手段等であっても、その全てが除外されるわけではなく、「流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるもの」については、「電子決済手段」に該当し得ることに注意が必要です。
WG報告書では、一般的に広く送金・決済手段として利用され得る状況には至っていないと評価されるものについては「電子決済手段」から除外しつつ、例外的にその流通性等に鑑み送金・決済手段としての機能が強いと認められるものを「電子決済手段」に含めることが考えられるとされていますので※10、このような点を踏まえて内閣府令が定められることが予想されます。例えば、WG報告書では、発行者がパーミッションレス型の分散台帳で不特定の者に対して流通可能な仕様で発行し、発行者や加盟店以外の不特定の者に対する送金・決済手段として利用できる前払式支払手段については、仲介者規制を及ぼすことが示唆されています。前払式支払手段は、現状、発行者に対してAML/CFTの観点からの規律(犯収法に基づく取引時確認等の義務)が課されていませんが、電子決済手段に該当する場合には、後述の通り、電子決済手段等取引業者に、犯収法に基づく取引時確認等の義務が課されることになります。
3号の「特定信託受益権」は、「金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの」と定義されており、信託受益権を用いる仕組みも「電子決済手段」に含まれることとしています。上記の3つの構成のうち、「信託受益権構成」に対応するものです。
これを受けて改正金商法では、信託受益権のうち、「資金決済に関する法律第2条第5項第3号又は第4号に該当する電子決済手段であって有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの」を、みなし有価証券から除外する改正が加えられています。
特定信託会社は、資金移動業者の登録拒否事由である改正資金決済法40条1項7号及び8号に該当しない場合には、銀行業免許を受けることなく特定資金移動業※11を営むことができるとされています(改正資金決済法37条の2第1項)。同条は特定信託会社について規定していますが、信託銀行については銀行法上、「為替取引」を業として営むことができますので、銀行法を根拠に、特定信託受益権の発行による為替取引である「特定信託為替取引」(改正資金決済法2条28項)も営むことができると考えられます。
4号では内閣府令への委任が行われています。また、同号は、文言上、「通貨建資産」に限定していません。そのため、本改正法案が成立した場合は、内閣府令の内容にも注視する必要があります。
この点、WG報告書では、「準ずるもの」の例として、形式的には発行者が償還を約していないものの、発行者又は発行者から買取資金の提供を受けた第三者が、実質的に発行者が償還を約しているのと同視できるような形でステーブルコインの買取りを行うものを挙げていることから※12、このような例を含む形で内閣府令が定められる可能性があると思われます。
以上のほか、現行資金決済法の「暗号資産」や「前払式支払手段」の定義で使用されている「物品」という文言が「物品等」に置き換えられ、改正資金決済法で新たに定義された「電子決済手段」でも「物品等」という文言が使用されています。そして、「物品等」は、「物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)」と定義されています。
現行法上、「物品」は「通常有体物を指し、債権などの無体物は含まれない・・・が、無体物の購入を除外する趣旨ではない」※13と考えられていましたが、「物品等」はその定義上無体物を除外するものではないと思われます。
もっとも、これまでも「物品」という要件が実質的な限定機能を果たしていたわけではないため、この改正の実務上の影響は小さいと考えられます。
本改正法案では、電子決済手段の仲介者に対する業規制として、「電子決済手段等取引業」に係る規制が導入されていますが、その概要は以下のとおりです。
「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義されており、かかる電子決済手段等取引業を行うには内閣総理大臣の登録を受けることが必要とされています※14。
このうち、1号、2号、3号は、現行資金決済法の暗号資産交換業の定義(2条7項)の1号、2号、4号に対応するものです。4号は、電子決済手段等取引業に特有の行為類型で、上記の3つの構成のうち、「資金移動業者の未達債務構成」に対応するものです。
なお、かかる登録は、外国法人にも認められていますが※15、外国法令に基づき電子決済手段等取引業の登録と同種類の登録を受けていること※16が必要とされています。さらに、国内の営業所及び国内における代表者(国内に住所を有するもの)を有しないことが登録拒否要件とされていることに留意する必要があります。
また、銀行等又は資金移動業者が電子決済手段の発行者である場合であって、一定の要件を満たす場合には、電子決済手段等取引業の登録を得ずに、その発行する電子決済手段について、自ら電子決済手段等取引業(1号から3号までに掲げる行為に関するものに限る。)を行うことができることとされています※17。なお、この場合、電子決済手段等取引業者に及ぶ規制の一部が適用されることに留意する必要があります。
電子決済手段等取引業者は、犯収法上の取引時確認等の義務を含む、主に以下の事項に関する規制を受けることとされています。
現行法上、電子決済手段(デジタルマネー類似型のステーブルコイン及び既存のデジタルマネー)を発行・償還する行為は、基本的には為替取引に該当し、銀行業免許又は資金移動業登録が求められることになり、暗号資産型のステーブルコインを発行・償還する行為について発行者としての規律はなく、暗号資産の売買、交換、それらの媒介等、管理を行う場合には暗号資産交換業者として規制されることになります。WG報告書では、発行者と仲介者が分離し得るステーブルコインの「発行者」に対する規制の在り方についても検討されていましたが※20、本改正法案に関する金融庁の説明資料※21では、デジタルマネー類似型については「発行者に係る規制の在り方は引き続き検討」する、暗号資産型については「利用実態や諸外国の動向も踏まえ、日本においても規制の在り方について引き続き検討」することとされています。そのため、ステーブルコインの「発行者」に対する規制に関する今後の議論の動向にも引き続き注視する必要があります。
WG報告書では、日本国外で発行されたデジタルマネー類似型ステーブルコインを、発行者が自ら日本で流通させるため(例えば、発行者が日本語のホームページを作る等して勧誘する行為)には、発行者が銀行業免許又は資金移動業登録を取得する必要があることが指摘されています※22。
もっとも、銀行業免許や資金移動業登録を取得するためには、国内に発行者の拠点が置かれていることや資産保全等がなされることが求められており、これらの要件は、日本国外のステーブルコイン発行者が日本市場に参入する上では高いハードルになると考えられます。
この点については、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会がWG報告書に対して反対意見を含む提言書を公表しており※23、今後の議論動向が注目されます。
※3
WG報告書第2章1.(2)(16頁)
※4
本ニュースレターでは、主として資金決済法上の「電子決済手段等取引業」について解説します。
※5
WG報告書第2章1.(6)①脚注74(22頁)、77(23頁)
※6
資金決済法2条5項(改正資金決済法2条14項)
※7
資金決済法2条6項(改正資金決済法2条7項)
※8
WG報告書第2章1.(3)(18頁)参照
※9
WG報告書第2章1.(4)(20頁)
※10
WG報告書第2章1.(4)(20頁)
※11
資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいいます(改正資金決済法36条の2第4項)。
※12
WG報告書第2章1.(3)脚注59(17頁)
※13
高橋康文編著「新逐条解説資金決済法」47頁(金融財政事情研究会、2021)
※14
改正資金決済法62条の3
※15
「外国電子決済手段等取引業者」という定義が新設されています。
※16
但し、外国法令に準拠して4号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者も「外国電子決済手段等取引業者」に該当します。
※17
改正資金決済法62条の8
※18
通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいうものとされています。
※19
改正犯収法上、電子決済手段等取引業者が特定事業者に加えられています(改正犯収法2条2項31号の2)。
※20
WG報告書第2章1.(6)①(22~25頁)
※22
WG報告書第2章1.(6)①脚注74(22頁)
(更新)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
淺野航平(共著)


斉藤元樹、大島岳(共著)


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
清水音輝(インタビュー)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(監修)、糸川貴視、大野一行(共著)
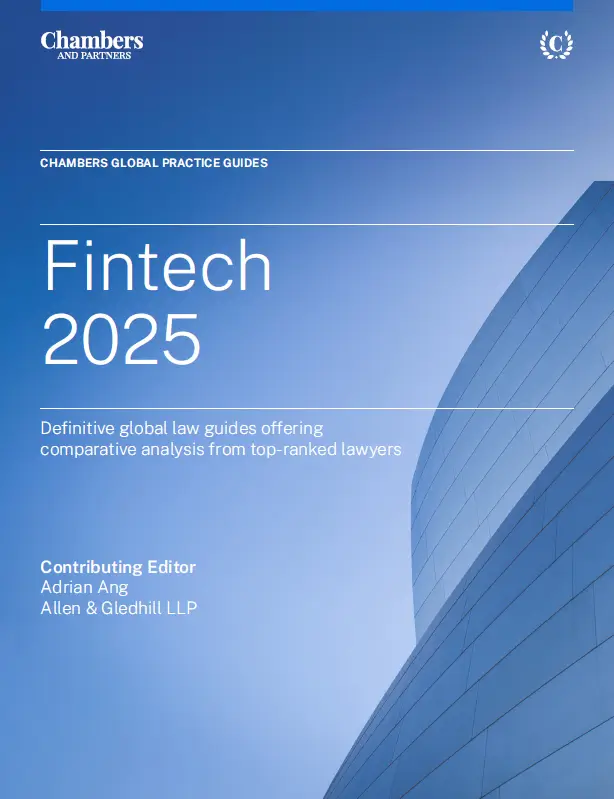
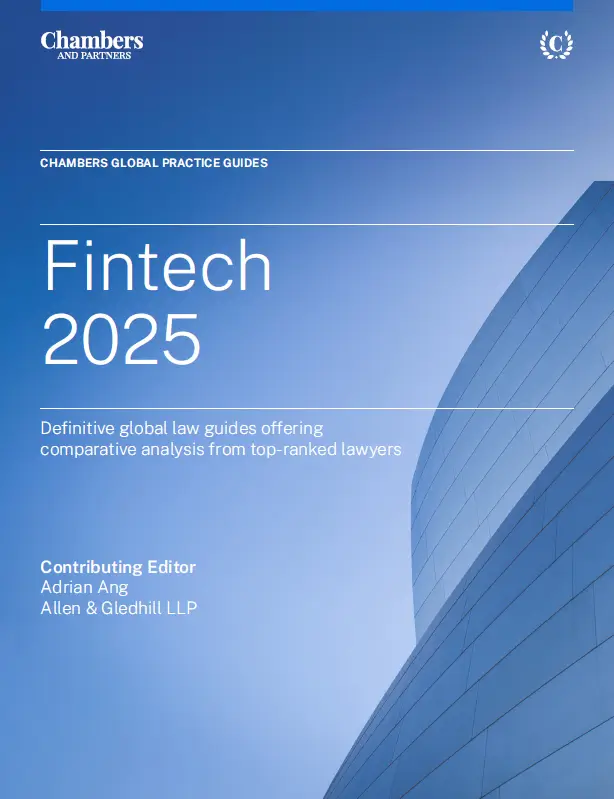
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)