
伊藤伸明 Nobuaki Ito
パートナー
東京

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
公正取引委員会(以下「公取委」といいます。)及び経済産業省(以下「経産省」といいます。)は、2022年3月31日、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を策定し公表しました※1。本指針は、2021年3月29日に公表された「スタートアップとの事業連携に関する指針」(以下「旧指針」といいます。)※2を基に、成長戦略実行計画(2021年6月18日閣議決定)※3においてスタートアップと出資者との契約の適正化に向けて新たなガイドラインを策定することとされたことを受け、旧指針に「スタートアップへの出資に関する指針」を追加する形で策定されました。
近年、オープンイノベーションによる生産性の向上が期待され、中でもスタートアップと大企業等との事業連携が重要視されているところ、公取委による「スタートアップの取引慣行に関する実態調査」(以下「本実態調査」といいます。)※4や旧指針の策定など、スタートアップが公正かつ自由に競争できる環境の確保に向けた取組が行われています。スタートアップへの出資に携わる関係者は、スタートアップ及びベンチャーキャピタルの他にも、大企業及び大企業の投資部門・投資子会社であるコーポレートベンチャーキャピタルなど多様化しており、関係者の皆様においては、本指針において新たに追加された出資契約に係る問題に対する独占禁止法上の考え方を理解しておくことが重要と考えられますので、本ニュースレターではその概要についてご説明します。
本指針による改正前の旧指針においては、スタートアップと連携事業者との間のNDA(秘密保持契約)、PoC(技術検証)契約、共同研究契約等において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、問題の背景及び解決の方向性を示していました。
本指針では、下表のとおり「第3 スタートアップへの出資に関する指針」という項目を旧指針に追加し、スタートアップと出資者との間の出資契約において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法・競争政策上の考え方を整理し、問題の背景及び解決の方向性を示しています。
本指針の構成
第1 スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針の必要性と構成
第2 スタートアップとの事業連携に関する指針
第3 スタートアップへの出資に関する指針
第4 参考情報
青文字が新規追加項目
以下では、本指針により新たに追加された「第3 スタートアップへの出資に関する指針」の概要についてご説明します。
スタートアップへの出資に関する指針は、出資契約に係る問題として、(1)営業秘密の開示、(2)NDA違反、(3)無償作業、(4)出資者が第三者に委託した業務の費用負担、(5)不要な商品・役務の購入、(6)株式の買取請求権、(7)研究開発活動の制限、(8)取引先の制限、及び(9)最恵待遇条件の9つを挙げ、それぞれについて問題事例とその事例に対する独占禁止法・競争政策上の考え方を整理し、問題の背景及び解決の方向性を示しています。
各項目について、問題事例とその事例に対する独占禁止法・競争政策上の懸念事項、及び解決の方向性の概要は、下表のとおりです。
| 項目 | 問題事例 | 独占禁止法・競争政策上の懸念事項 | 解決の方向性 |
|---|---|---|---|
| (1) 営業秘密の開示 | 正当な理由なく、NDAを締結せず営業秘密の無償開示を要請 | 優越的地位の濫用 |
|
| (2) NDA違反 | 出資者がNDAに違反してスタートアップの営業秘密を他の出資先に漏洩し、当該他の出資先にスタートアップの商品・役務と競合する商品・役務を販売させる行為 | 競争者に対する取引妨害 |
|
| (3) 無償作業 | 正当な理由なく、契約に定められていない無償での作業等を要請 | 優越的地位の濫用 | 双方がスタートアップの経営状態に応じて発生する作業等※5を調整 |
| (4) 出資者が第三者に委託した業務の費用負担 | 一方的に、出資者が第三者に委託して実施した業務に係る費用※6の全ての負担を要請 | 優越的地位の濫用 |
|
| (5) 不要な商品・役務の購入 | スタートアップが事業遂行上必要としない商品・役務の購入を要請 | 優越的地位の濫用 |
|
| (6) 株式の買取請求権 | (ア)正当な理由なく、不利益な要請を行い、当該要請に応じない場合に株式の買取請求権の行使を示唆 | 優越的地位の濫用 |
|
| (イ)一方的に出資額よりも著しく高額な価格での買取請求が可能な買取請求権の設定を要請※8 | 優越的地位の濫用 | 上記(ア)と同じ | |
| (ウ)買取請求権の行使条件が満たされているなどの正当な理由なく、出資者の保有株式の一部買取りを請求 | 優越的地位の濫用 | 上記(ア)と同じ | |
| (エ)スタートアップの経営株主等の個人に対し買取請求が可能な買取請求権の設定を要請 | スタートアップの起業意欲・オープンイノベーションを阻害 | 買取請求権は発行会社のみに限定※9 | |
| (7) 研究開発活動の制限 | 出資者自ら又は他の出資先が有する技術の競争技術に関し、スタートアップが自ら又は第三者と共同して研究開発を行うことを禁止 | 拘束条件付取引 | 研究開発活動の制限は事業拡大の障害になる可能性が高く、基本的に望ましくない |
| (8) 取引先の制限 | 市場における有力な事業者である出資者が、合理的な範囲を超えて、他の事業者との取引を禁止※10 | 排他条件付取引又は拘束条件付取引 | 取引先の制限は事業拡大の障害になる可能性が高い※11 |
| (9) 最恵待遇条件 | 市場における有力な事業者である出資者が、最恵待遇条件を設定 | 拘束条件付取引 |
|
以下では、出資契約における論点として関心の高い株式の買取請求権、及び近時の公取委の動向が注目される最恵待遇条件について補足します。
日本におけるスタートアップへの出資契約には、表明保証の違反、出資契約その他の出資関連契約上のスタートアップ又は経営株主の義務違反等があった場合に、出資者がスタートアップに株式の買取りを求めることができる旨の定めが置かれることが一般的であり、創業者その他の経営株主個人に対しても請求が可能とされることも多くあります。特に米国におけるスタートアップへの投資実務ではこのような定めが置かれることは極めてまれである(補償条項すら置かれないことが多い)こととの比較からも、株式の買取請求権については日本におけるスタートアップ投資実務における重要な検討事項と捉えられてきたものの、今日に至るまで大きな変化は見られないように思われます。
2020年11月に報告された本実態調査でも問題点が指摘されており、出資契約の問題を取り扱う本指針において、本実態調査において指摘されていた問題点を踏まえた指針が示されました。その概要は上記1における表(6)のとおりですが、ここではそのうち(ア)の買取請求権の行使を示唆した不利益要請と(エ)の経営株主等の個人に対する買取請求権の設定について取り上げたいと思います。
まず、(ア)では、大きく、①買取請求権を背景に出資者がスタートアップに対して不当な要求をするような場合があることと、そして、②そもそも買取請求権の発生事由が広く設定される場合があること、の2点が指摘されています。実務上は買取請求権は安易に行使するべきものではなく、また、安易に又は不当に行使した場合には投資家としてのレピュテーションに悪影響を及ぼすことは共通の認識になっていると思われますが、買取請求権が行使された場合、スタートアップ及び経営株主の負担は大きなものとなります。様々な事象が発生し、時にはスタートアップと出資者の間で緊張関係が生じるスタートアップの経営の中で、特に発生事由が広範に設定される場合には、(出資者側にその意図がなかったとしても)スタートアップ及び経営株主にとってのプレッシャー、出資者にとってのレバレッジになっている可能性は否めず、本指針が示すように、発生事由を一定の重要な事由に限定する、できるだけ明確に規定するという方向性は、スタートアップと出資者の間の関係をより健全なものにするための正しい方向性であるように思われます。本指針は、解決の方向性において「買取請求権の行使が正当と認められる重大な表明保証違反、重大な契約違反」の内容を例示していますが、出資者とスタートアップは、スタートアップの事業内容、デューディリジェンスの結果等を踏まえ、(例示されている事項を広げる方向にも狭める方向にも)案件の事情に適した内容を、できるだけ明確に合意するよう努めるべきでしょう。
(エ)では、買取請求権の行使の対象は発行会社のみに限定し、経営株主等の個人は対象から除いていくことが競争政策上望ましいとされています。しかし、例えば、スタートアップの収益性(が得られる具体的見込み)も確立しておらず、また内部管理体制も未整備で経営株主の持分や会社の経営についてのコントロールが大きいステージにおける出資においては、経営株主等の個人を対象にすることで出資が促進される面があるとすると、一律に個人を対象から除いていくことが競争政策上望ましいとは必ずしもいえないようにも思われます。また、本指針は「経営者保証に関するガイドライン」(2013年12月 経営者保証に関するガイドライン研究会)が「法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めない」ことを示し、融資慣行としてこれが浸透・定着していることも個人を対象から除くことが望ましいことの根拠として引き合いに出していますが、同ガイドラインは「法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る」ことを、経営者保証を求めないことを検討するための前提としており、一律に個人保証を求めるべきではないとするものではありません。経営株主等の個人を不必要に対象にしない方向性に進むべきことに異論はありませんが、経営株主等の持分や会社の経営についてのコントロールの大きさ、会社の規模や収益性(の見込み)の確立の程度、内部管理体制を含む会社の成熟度、買取請求権の発生事由等の個別のスタートアップの事情・ステージ・買取請求権の内容を踏まえ、経営株主等の個人を買取請求の対象とすることが適切なのか、対象とする個人の範囲は適切なのか、段階的な議論をしていくことが現時点の日本の実務の実情には合っているようにも思われます※12。
最恵待遇条件とは、通常、契約当事者の一方が相手方に対して最も有利な条件で取引を行うことを確約する契約条件をいいます。最恵待遇条件には不確実性が高い状況下で取引を行いやすくするなど競争促進的な側面もあり、最恵待遇条件を設定することが直ちに独占禁止法上問題になるとは考えられていません。
もっとも、例えば、市場における有力な事業者Aが、取引の相手方B等に対し、最恵待遇条件を設定することによって、Aの競争者Cがより有利な条件でB等と取引することが困難となり、Cが市場から排除されるような場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあると考えられています。実際に独占禁止法違反との認定には至りませんでしたが公取委が審査を行った案件として、アマゾンジャパン合同会社が、Amazonマーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約において価格等の同等性条件を定めていた件※13や、Booking.com B.V.が、「Booking.com」に宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者との間の契約において、Booking.comに掲載する宿泊施設に係る宿泊料金及び部屋数について他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件を定めていた件※14などがあります。
本指針においても、出資者が最恵待遇条件(出資者の取引条件を他の出資者の取引条件と同等以上に有利にする条件)を設定することが当然に独占禁止法上問題になるわけではないとしつつ、市場における有力な事業者である出資者が最恵待遇条件を設定し、それによって、例えば、出資者の競争者がより有利な条件でスタートアップと取引することが困難となり、市場閉鎖効果が生じるおそれがある場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるとされています。しかし、(理論上そのような場合に独占禁止法上問題になるおそれがあることは否定しませんが、)スタートアップ等に対して投資を行う出資者は極めて多数存在すると思われ、実際には本指針が述べる「市場における有力な事業者※15である出資者」というものを想定することは現時点では難しいようにも思われます。
したがって、出資契約において最恵待遇条件を定めることが拘束条件付取引として独占禁止法上問題となる可能性は比較的低いと思われますが、特にスタートアップにとって影響が大きい契約条件であるため、本指針に示されているように、出資者・スタートアップ間で慎重に協議した上で定めるべきものと考えられます。
本指針の策定は、スタートアップにとっては出資者から不当な要求を受けた場合に本指針の内容を踏まえ対応することができることとなった面で重要であり、他方で、出資者側にとってもスタートアップとの協議において本指針の内容を参照することで独占禁止法上の懸念をコントロールできるという観点で重要です。本指針における独占禁止法上の考え方に抵触した場合には、潜在的に公取委から調査を受けるおそれがあることに加え、個々の民事訴訟において本指針が援用され、裁判所の判断に一定の影響を与える可能性があることにも留意が必要です。また、独占禁止法の違反が問題になるような場面以外でも、スタートアップ及び出資者双方が、本指針が示している競争政策や起業意欲の向上等から望ましいとされている考え方への理解を深め、スタートアップの成長につながる健全な関係を築いていくことが期待されます。
公取委は、本指針の公表に先立ち、「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の設置を発表し、大企業とスタートアップとの取引に関する調査などの取組を進め、優越的地位の濫用の未然防止をより一層図ることとしています※16。今後も、公取委及び経産省による大企業とスタートアップとの取引に対する取組を注視することが必要となります。
※5
PoCを例に、PoCのゴール・対価設定・出資への移行条件の共通認識などが挙げられています。
※6
例として、スタートアップへの出資検討におけるデューディリジェンスに係る費用が挙げられています。
※7
表明保証違反の例として、知的財産権などの企業の競争優位性に関する事項の虚偽表明、粉飾決算、反社会的勢力との関係が明らかとなった場合が挙げられており、重大な契約違反の例として、投資資金の資金使途以外での使用、事前承認事項への違反、重大な法令違反が生じた場合が挙げられています。
※8
なお、パブリックコメントに対する考え方において、出資者・スタートアップ間で十分な交渉が行われた結果、双方の利害の調整として設定された契約条件に基づき価額が合理的な範囲にて計算される場合は、通常、優越的地位の濫用としては問題にならないと記載されています。
※9
他方で、発行会社からの買戻しを確保するための減資プロセスへの経営者の協力義務や、経営株主が会社に損害を与えたことが明確な場合の株主代表訴訟プロセス、法人格否認の法理の適用の考え方などの実務上の整理は進めていく必要がある旨付言されています。
※10
前提として、スタートアップの商品・役務に使用された出資者のノウハウ等の秘密性を保持するために必要な場合に、取引の相手方であるスタートアップに対し、出資者が他の事業者との取引を制限することは、原則として独占禁止法上問題とならないとされています。
※11
他方で、出資後の共同事業が予定される場合において、スタートアップに共同事業の成果物の知的財産権を単独で帰属させる一方で、出資者が競合他社との関係で競争優位性を保てるように、スタートアップに対し、出資者の競合他社との取引を制限することは一定の合理性を有する場合もある旨付言されています。
※12
もっとも、公取委・経産省は、パブリックコメントにおいて、「一律に経営株主等への買取請求権の設定を避ける必要はなく、買取請求権の設定の余地を残しつつ、個人に対する買取請求権の行使という事情や、起業・企業経営へのインセンティブの阻害を防止する観点から、買取請求権の行使が不当とみられる類型を明確化して頂きたい。」という意見に対し、起業意欲の向上、オープンイノベーション・雇用促進、及び海外投資の呼び込みが政策課題となっている観点から、「経営株主等の個人を除いていくことが競争政策上望ましい」との考え方を示していますので、一律に対象から除いていくことが望ましいとの立場をとっていると思われます。
※15
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針上、市場における有力な事業者と認められるかどうかは、市場シェア20%を超えることが一応の目安になるとされています。(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


糸川貴視、北川貴広(共著)


(2025年5月)
大久保涼(コメント)


内海健司、門田正行、山中淳二(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2025年4月)
鈴木明美、西村修一、真野光平(共著)


糸川貴視、鈴木雄大(共著)


斉藤元樹、堀内健司(共著)


斉藤元樹、堀内健司(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
伊藤伸明
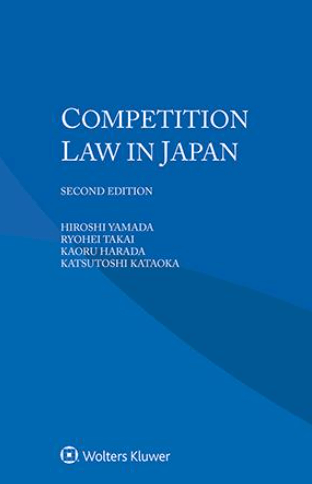
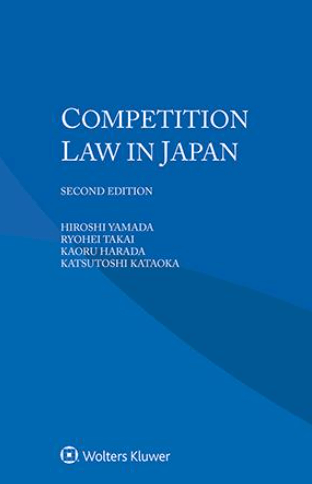
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2024年10月)
井本吉俊


服部薫、柳澤宏輝、一色毅、清水美彩惠(共著)


小川聖史


服部薫、柳澤宏輝、一色毅、清水美彩惠、田口涼太(共著)