
緒方絵里子 Eriko Ogata
パートナー
東京

NO&T Labor and Employment Law Update 労働法ニュースレター
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
企業がシステム開発を行う過程でシステム開発業務を外部業者(ベンダー)に委託する場合、当該外部業者の従業員(外部業者従業員)が企業に常駐して開発を行うケースも見られます。このような形で外部業者を活用する場合、発注者側が外部業者従業員と直接コミュニケーションをとることも多いことから、外部業者従業員が発注者の指揮命令下にあり、当該委託が労働者派遣事業に該当しないか(すなわち、いわゆる「偽装請負」に該当しないか)という点が問題になることがあります※1。
特に、近時のシステム開発においては「アジャイル型開発」※2という手法が使われることが多いところ、アジャイル型開発には、発注者側と受注者側の担当者が緊密なコミュニケーションを取り合いながらシステム開発を行っていくという特徴があり、従来の偽装請負におけるガイドラインや質疑応答集で示されているような、発注者から受注者側の担当者に直接指示は行わずに受注者の責任者を通して指示を行う、あるいは、受注者の責任者も会議に同席すべきであるといった規律をそのまま適用してしまうと、アジャイル型開発の強みであるスピーディーさが失われてしまうという問題があります。
「偽装請負」に該当するか否かは、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準※3」(昭和61年労働省告示第37条告示。以下「37条告示」といいます。)にしたがって判断がなされていますが、上記のようなアジャイル型開発における問題意識を踏まえて、アジャイル型開発における37条告示の運用については、2021年9月に厚生労働省から「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第3集)※4」(以下「本Q&A」といいます。)が公表されました。本Q&Aにおいて、アジャイル型開発を含むシステム開発においても37条告示の基準が適用されることが明らかにされたとともに、アジャイル型開発が偽装請負とみなされないようにするための現場における留意点が示されました。
そこで本稿では、アジャイル型開発における偽装請負に該当しないように運用するための留意点及び偽装請負と判断された場合のサンクションについて解説します。
適正な請負ないし業務委託といえるためには、発注者と受注者の労働者との間に指揮命令関係を生じさせないようにする必要があります。受注者の労働者が発注者の直接の指揮命令下にあるとされた場合には、労働者派遣事業に該当するとみなされる可能性があります。
受注者の労働者が発注者の直接の指揮命令下にあるか否かを判断するために、厚生労働省は、前述のとおり、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準として37条告示を示しており、①受注者が、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること、②受注者が、請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること、という2つの要件を満たしていなければ労働者派遣業(いわゆる偽装請負)に該当するとされています(①及び②の要件の詳細については37条告示をご参照ください。)。
また、アジャイル型開発における偽装請負の判断基準についても37条告示で示された内容が基本的に維持されています。具体的には、本Q&A・A2で以下のように示されました(下線は筆者らによります。)。
アジャイル型開発においても、実態として、発注者側と受注者側の開発関係者(発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者を含みます。以下同じ。)が対等な関係の下で協働し、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合には、受注者が自己の雇用する労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、また、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理しているものとして、適正な請負等と言えます。・・・
他方で、実態として、発注者側の開発責任者や開発担当者が受注者側の開発担当者に対し、直接、業務の遂行方法や労働時間等に関する指示を行うなど、指揮命令があると認められるような場合には、偽装請負と判断されることになります。
このように、従来の判断枠組みは維持されているものの、アジャイル型開発の特色を踏まえて、発注者側の開発責任者と受注者側の開発担当者のコミュニケーションや、開発チーム内のコミュニケーションがあることをもって直ちに偽装請負と判断されるわけではなく、実態として、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っていると認められる場合には適正な請負・業務委託等であることが明確になりました。
本Q&Aに照らして、アジャイル型開発における発注者から受注者とのコミュニケーションが請負や業務委託が労働者派遣(偽装請負)に該当しないための留意事項を列挙すると、以下のとおりです。
上記で挙げられている事項の他には、作業場所や勤怠管理の方法、機材の貸し出し等について、事前に発注者と受注者の間で認識を共有し、合意しておくことが考えられます。
以上の留意点を踏まえ、アジャイル開発においては、発注者から受注者の労働者に対する指揮命令関係が認められず、かつ、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行うことが可能となるような仕組みを構築しておくことが考えられるところです。
請負契約や準委任契約を締結してシステム開発を外部に委託した委託者と受託者の従業員との間に指揮命令関係があると認められた場合、労働者派遣業が行われたものとみなされ、発注者・受注者それぞれに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)に基づくサンクションが課される可能性があります。
まず、発注者(労働者派遣を受け入れたと扱われる事業主)との関係では、許可のある事業主以外からの派遣を受け入れることは禁止されており(派遣法第24条の2)、厚生労働大臣または厚生労働省の都道府県労働局長による行政指導(第48条第1項)、改善命令(第49条)、勧告及び企業名の公表(第49条の2)がなされ、また派遣先事業者としての法的義務(派遣先責任者の選任、適切な管理台帳の作成等)の懈怠に基づいて罰則(例えば適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金(第61条第3号))が課され、さらに、派遣労働者に対する雇用申込みが擬制(第40条の6)される可能性があります。実際に、大阪高判令和3年11月4日労判1253号60頁では、偽装請負の実態及び目的を認定の上、派遣法第40条の6第1項第5号に基づき発注者から受注者の労働者に対する雇用申込みが擬制され、派遣労働者との間の労働契約の成立が認められました。
また、受注者(労働者派遣を行ったと扱われる事業主)との関係では、当該企業が労働者派遣事業の許認可を取得している企業か否かでサンクションの内容が異なります。すなわち、当該企業が労働者派遣事業の許可を取得していない企業の場合、無許可で労働者派遣事業を行ったとして1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第59条第2号)が課される可能性があります。また、労働者派遣事業の許可を取得している企業の場合でも、派遣法上の義務を遵守できていないとして、厚生労働大臣または厚生労働省の都道府県労働局長による行政指導(第48条第1項)、許可取消しや事業停止命令(第14条)、改善命令(第49条)、勧告(第49条の2第1項)、罰則(例えば適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金(第61条第3号))の対象となる可能性があります。
システム開発においては、一般的に二重の専門性(システムに関するベンダーの専門性と業務に関するユーザーの専門性)があるとされています。そして、アジャイル型開発は、まさしくユーザー側の自らの業務に関する専門性とベンダー側のシステムに関する専門性を掛け合わせて、双方向かつ対等なコミュニケーションがなされて、ユーザーのニーズに則った迅速なシステム開発を行うことを主な目的としています。当該アジャイル型開発の目的を踏まえたシステム開発の現場が実現されるよう、これらを支援する法務・人事担当者としては、社内ガイドラインの策定等の方法によって、偽装請負とならないような、本来のアジャイル型開発のシステム開発の実現をサポートする仕組みを構築することが期待されます。
※1
「偽装請負」という講学上の概念については、請負契約の場合に限られず、準委任契約その他の法的性質の契約に基づいて業務を外部に委託する場合であっても同様に問題となり得ます。
※2
アジャイル型開発とは、開発要件の全体を固めることなく開発に着手し、市場の評価や環境変化を反映して開発途中でも要件の追加や変更を可能とし、短期間で開発とリリースを繰り返しながら機能を追加してシステムを作り上げていくもので、発注者側の開発責任者と発注者側及び受注者側の開発担当者が対等な関係の下でそれぞれの役割・専門性に基づき協働し、情報の共有や助言・提案等を行いながら個々の開発担当者が開発手法や一定の期間内における開発の順序等について自律的に判断し、開発業務を進めることを特徴とするものです。このように、アジャイル型開発には、従来型の請負や業務委託にて想定されている従来の発注者・受注者の関係性とは異なる面があります。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)


安西統裕、一色健太(共著)


(2025年9月)
神田遵


(2025年7月)
森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)


清水美彩惠、菅紀世美(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
犬飼貴之


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
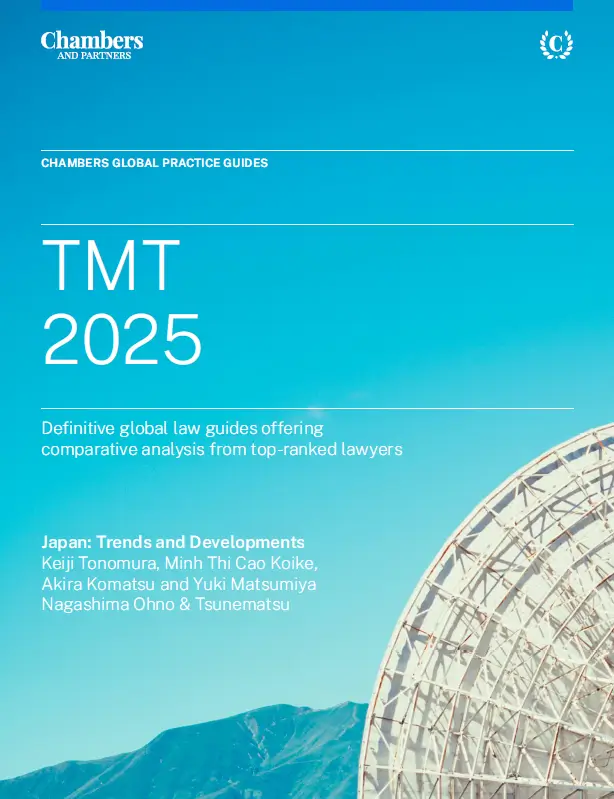
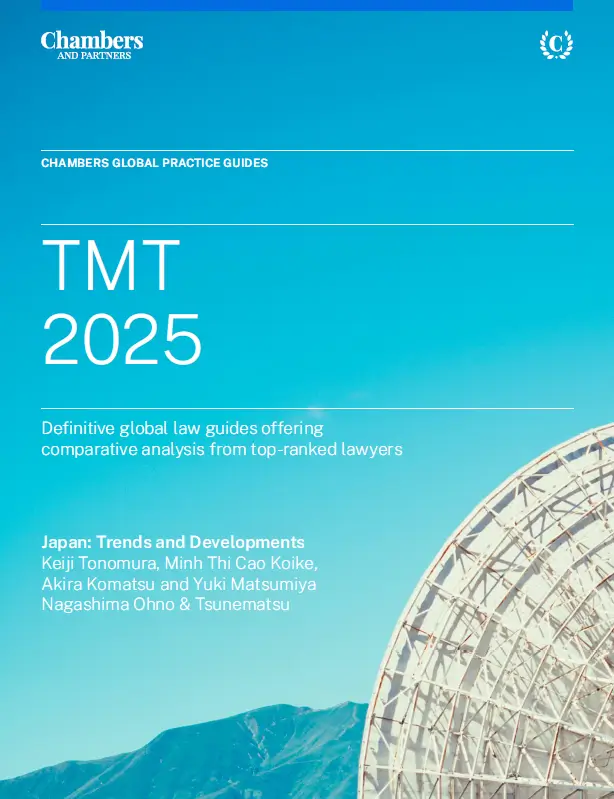
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


殿村桂司、丸田颯人、小宮千枝(共著)