
佐々木修 Shu Sasaki
パートナー
東京

NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
2021年11月22日、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年5月26日法律第46号)(以下「本改正」といいます。)が施行されました。本改正の内容は多岐にわたりますが、本ニュースレターでは銀行による銀行業高度化等会社への出資規制の改正について取り上げます。
また、2022年8月9日、金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を実施し、他業銀行業高度化等会社の認可審査に係る考え方を示しました※1。
大きなポイントは以下の3点で、各類型の概要の比較については図表のとおりです。
| 他業銀行業高度化等会社 | 一定の銀行業高度化等会社 | 特例銀行業高度化等業務 | |
|---|---|---|---|
| 業務内容 |
以下の業務を営む会社
|
|
|
| 手続の種類・タイミング | 5%超※8の議決権取得について事前認可 | 50%超の議決権取得(子会社化)について事前認可 | 認定銀行持株会社による50%超の議決権取得(子会社化)について事前届出 |
| 認可におけるいわゆる全損要件※9 | 全損要件あり | 全損要件なし | 認可不要 |
2022年8月9日、主要行等向けの総合的な監督指針及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針が改正されました。この改正には、他業銀行業高度化等会社に関する改正が含まれており、子会社認可に際しての収支要件について、3年以上の期間を収支予想期間とすることが可能である旨の明示などがなされていますが※15、他業銀行業高度化等会社の認可審査に関しても、以下のような規定が追加されています。
(主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-3-3-4(2)③に以下追記※16)
「他方、他業銀行業高度化等会社の業務については、当庁所管以外の一般事業会社が行う業務であることが多く、また、同会社の認可審査事項に全損規定(施行規則第17条の5の2第2項第2号)があることに鑑み、当該業務の実現可能性や実施予定の業務に係るリスク等の詳細を確認することまでは求められていないことに留意すること。」
他業銀行業高度化等会社については、2021年11月の本改正により業務の外縁が広がったと考えられるところ、他業銀行業高度化等会社が営む業務は、金融庁が従来から所管する事業者の業務範囲を超える可能性があることを踏まえて、審査において、「当該業務の実現可能性や実施予定の業務に係るリスク等の詳細を確認することまでは求められていない」ことを明確化するため、上記の改正が行われたものと思われます。
本改正を受けて銀行業高度化等会社の業務範囲は着実に広がりをみせています。2020年12月22日に公表された銀行制度WGの報告書※17においても言及されているように、銀行は、自らが持続可能なビジネスモデルを構築した上で、日本経済の回復・再生を支える「要」としての役割を果たすべく、創意工夫を凝らした新しいビジネスにチャレンジすることが期待されていると思われます。
2022年8月9日に改正された監督指針では、特に他業銀行業高度化等会社に関して、その性質に鑑みた審査上の着眼点が規定されており、また、多様な他業銀行業高度化等会社の認可事例が出てきていることなどを踏まえると、銀行にとっては、新しいビジネスにチャレンジしやすい制度・環境が整いつつあると考えられます。
※1
2022年8月9日金融庁「「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について)(https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220809/20220809.html)
※2
銀行法16条の2第1項15号、52条の23第1項14号
※3
銀行法施行規則17条の4の3、34条の18の2参照
※4
なお、「一定の銀行業高度化等会社」には、障害者雇用促進法上の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社も含まれます(図表参照)。
※5
銀行法施行規則17条の5第3項
※6
銀行法52条の23の2第6項
※7
特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社は、銀行持株会社の子会社である銀行の子会社ではないことが必要となります。
※8
銀行持株会社の場合には15%超
※9
銀行法施行規則17条の5の2第2項2号は「当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であっても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。」とのいわゆる全損要件を定めています。銀行法施行規則17条の5第2項が定める通常の子会社認可の要件では全損要件は要件とされておらず、銀行業高度化等会社に係る認可取得において、全損要件は重要なポイントとなります。
※10
2021年11月10日金融庁「令和3年銀行法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について」パブリックコメント回答No.108参照(https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211110/01.pdf)
※11
銀行法施行規則17条の4の3第2号
※12
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-7-4
※13
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-7-5(4)
※14
銀行法施行規則34条の19の9第2項、「銀行法施行規則第三十四条の十九の七第二項第一号並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める比率等を定める件」(金融庁告示第百号)第3条
※15
主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-3-3(注1)及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-7(注1)
※16
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-7-5(2)③にも同内容が追加されています。
※17
2020年12月22日「金融審議会 銀行制度等ワーキング・グループ報告‐経済を力強く支える金融機能の確立に向けて‐」(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20201222/houkoku.pdf)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


遠藤努、中村日哉(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)


(2025年6月)
松尾博憲


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


(2025年5月)
吉良宣哉


(2025年5月)
井上聡、大野一行(座談会)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒、糸川貴視、大野一行(共著)
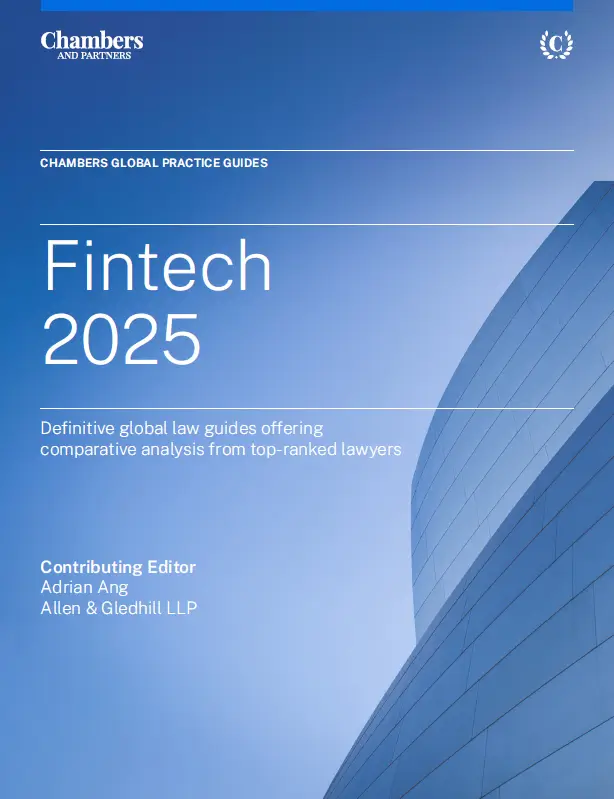
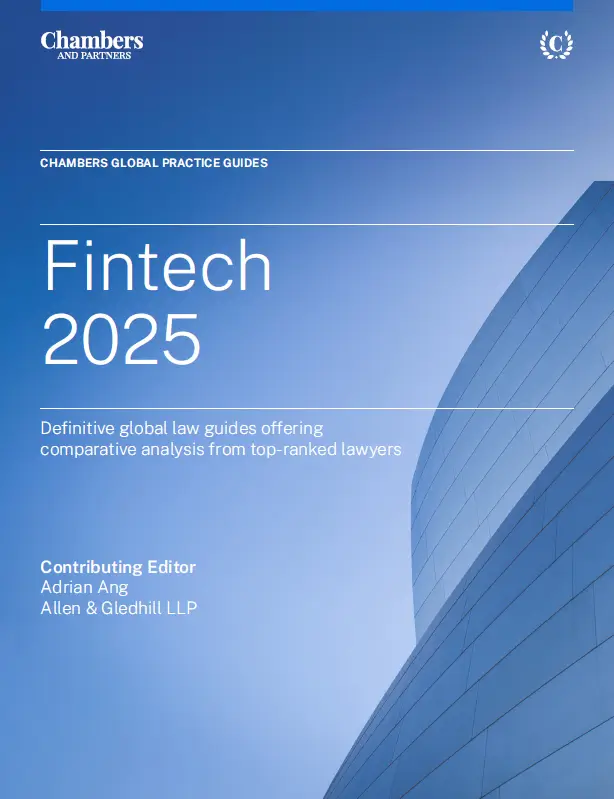
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)


(2024年12月)
清水音輝