
鹿はせる Haseru Roku
パートナー
東京

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター
本ニュースレターでは、2回に分けて内容をご紹介しています。第2回は以下をご覧ください。
NO&T Asia Legal Update No.121/NO&T Competition Law Update No.12(2022年9月)
「改正中国独禁法の要点―どこが日本企業にとって重要か(下)」
本ニュースレターの概要をPodcastで配信しています。
The NO&T Podcast – JP
「中国独禁法の最近の動向 Part1」
「中国独禁法の最近の動向 Part2」
目次:
1.中国独禁法の改正及び施行
2.中国独禁法改正の要点
(1) 処罰の厳格化
(2) 企業結合規制に関する改正の要点
<以上、本号(アジア最新法律情報No.120/独占禁止法・競争法ニュースレターNo.11)>
(3) 独占的協定(取引制限)規制に関する改正の要点
(4) 市場支配的地位の濫用規制に関する改正の要点
中国独禁法の改正が2022年6月24日に成立し、8月1日から施行された。同法の改正については2020年1月には競争当局である国家市場監督管理総局(SAMR)から、2021年10月には全国人民大会常務委員会から相次いで改正案が公表されていたが、ようやく正式に成立・施行できる運びとなった。また、2022年6月27日には、企業結合届出、独占的協定及び市場支配的地位の濫用等に関する下位法令の改正案も一挙に公表され、日本企業に大きな影響を与えてきた中国の独禁法典及び実務は重要な変化を迎えることとなる。もっとも、改正法(案)は従来の実務を明文化したものも多く、本稿では、成立した中国独禁法本文と改正案が公表されている下位法令を併せ、①何が従来から実質的に変わったのか、及び、②何が日本企業にとって重要な改正か、という視点から要点解説を試みる※1。
以下のとおり、中国独禁法の改正法では法令に違反した場合の制裁金が旧法から大幅に上昇し、特に日本企業にとっては、企業結合※2届出義務違反に対する制裁金が10倍以上となったことが重要である。また、改正法では違反があった場合の原則としての制裁金と、情状が悪質な場合の制裁金規定が分けて規定されており、情状が悪質な場合は原則の5倍以下の制裁金が課され得る※3。更に、独占的協定(カルテル)※4については、協定の当事者となる事業者だけでなく、事業者内で独占的協定を主導した個人についても、制裁規定が設けられた点が重要な改正である。
| 違反行為 | 旧法 | 改正法・原則 | 改正案法・情状が悪質な場合 |
|---|---|---|---|
| 企業結合届出義務違反 | RMB50万元以下の制裁金 |
競争の制限・排除効果が認められる場合:直近年度の売上高の10%以下の制裁金 競争の制限・排除効果が認められない場合:RMB500万元以下の制裁金 |
原則の5倍以下の制裁金 |
| 中国独禁法に関する当局の調査・審査の拒絶・妨害等 |
個人:RMB10万元以下の制裁金 事業者:RMB100万元以下の制裁金 |
個人:RMB50万元以下の制裁金 事業者:直近年度の売上高の1%以下の制裁金(売上がない場合:RMB500万元以下の制裁金) |
|
| 水平・垂直の独占的協定の合意・実施 | 合意を実施した場合:直近年度の売上高の1-10%の制裁金 | 直近年度の売上高の1-10%の制裁金(売上がない場合:RMB500万元以下の制裁金) | |
| 合意があったものの実施しなかった場合:RMB50万元以下の制裁金 | RMB300万元以下の制裁金 | ||
| 事業者内の個人責任:規定なし | RMB100万元以下の制裁金 | ||
| 市場支配的地位の濫用 | 直近年度の売上高の1-10%の制裁金 | 直近年度の売上高の1-10%の制裁金 |
中国独禁法の三大規制類型である企業結合規制、独占的協定規制、市場支配的地位の濫用規制のうち、とりわけ企業結合規制は、企業結合当事者グループに一定の中国売上があれば、企業結合の対象に中国エンティティが含まれていない場合(典型的には日本でしか事業を行わないJVを新規に設立する場合)も中国の競争当局に対して企業結合届出を行う必要がある点で、M&A取引を行う日本企業にとって影響が大きく、改正に対する関心も高い。企業結合規制について、改正中国独禁法及び下位法令の改正案で見込まれる改正の要点は以下のとおりである。
① 届出基準の変更(下位法令※5の成立待ち)
企業結合が国務院令で定める届出基準のいずれかを満たす場合には、企業結合当事者に競争当局であるSAMRに対する届出を行う義務が生じる。6月27日に公表された国務院令の改正案では、届出基準となる売上高が現行令に比べ引き上げられており、従来は容易に届出義務が発生してしまう企業結合につき若干ながら届出義務が発生しにくくなった一方で、別個の届出基準が一つ追加されたことにより、届出義務の発生原因は増えたことになる。
改正案のうち、日本企業との関係で特に重要なのは、現行令では企業結合当事者について、それぞれ中国国内でRMB4億元(約80億円)以上の売上高があれば届出義務が発生する可能性が高かったところ、国務院令の改正案が成立すれば、倍額となるRMB8億元(約160億円)が必要となるため、届出要件を満たす可能性が低くなることである。現行令における届出基準と改正案の比較については、以下の表の(i)及び(ii)を参照されたい。
他方、改正案で追加された届出基準(下記表の(iii))は、主にアリババ、テンセント等の中国国内大手企業によるスタートアップ買収を想定した規定であり、日本企業が買収者として基準を満たす可能性は低いと思われるが、中国の現地法人等が買収対象となる場合は留意する必要がある。
この届出基準に関する国務院令の改正はまだ成立・施行されていないため、当面は現状の届出基準によって届出の要否を判断せざるを得ないが、企業結合のクロージング時点までに国務院令が施行されれば届出が不要となる案件も考えられ、立法の動向にも気を配る必要がある。
|
現行国務院令第3条 (以下の(i)(ii)のいずれかを満たす場合に要届出) |
改正案第3条 (以下の(i)(ii)(iii)のいずれかを満たす場合に要届出) |
|---|---|
| (i) 企業結合を行う全ての事業者の,直近会計年度における全世界の売上高の合計がRMB100億元を超え,かつ,そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれRMB4億元を超える場合 | (i) 企業結合を行う全ての事業者の,直近会計年度における全世界の売上高の合計がRMB120億元を超え,かつ,そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれRMB8億元を超える場合 |
| (ii) 企業結合を行う全ての事業者の,直近会計年度における中国国内での売上高の合計がRMB20億元を超え,かつ,そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれRMB4億元を超える場合 | (ii) 企業結合を行う全ての事業者の,直近会計年度における中国国内での売上高の合計がRMB40億元を超え,かつ,そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれRMB8億元を超える場合 |
|
(iii) 上記(i)(ii)を満たさない場合であり,かつ,同時に以下の要件を満たす場合 (a) 企業結合を行う当事者のいずれかの直近会計年度の中国国内での売上高がRMB1000億元を超える場合,かつ (b) 企業結合の対象となる企業(支配権を取得される企業)の市場価値(又はその概算)がRMB8億元以上であり,かつ,直近会計年度の中国国内での売上高が全世界の売上高の3分の1を超える場合 |
② 審査期間の中断(8月1日から施行済み)
旧中国独禁法において、企業結合の審査期間は一次審査(30日)、二次審査(90日)及び三次審査(60日)に分けられ、旧法の下では一度審査がスタートすれば中断することはなく、「最大180日」とされている。これに対して、改正中国独禁法では、(i)事業者が規定に従った書類、資料を提出しない場合、(ii)企業結合審査に重大な影響を与える新しい事実及び状況が生じた場合、(iii)問題解消措置に関し更に検討が必要な場合で、事業者の同意が得られる場合のいずれかの場合に、競争当局が事業者に書面通知により審査期間を中断することができる条項が追加された(改正法第32条)。
本改正により、これまで時計が止まらなかった審査期間が中断できるようになり、中国独禁法の企業結合審査が長期化するおそれがないか懸念される。しかし、現在でも一次審査前には届出の受理に関する事実上の審査(立案前審査と呼ばれる)が行われ、特に通常審査案件では複雑な案件の場合には2か月超に及ぶこともある。また、複雑な案件で審査が長期化し、三次審査に至っても審査日数が足りなくなった場合には、一旦事業者に届出を撤回させて再提出させるいわゆるpull and refileも行われてきたため、旧法の下でも「最大180日」は絶対的なものではなかった。実務上、審査期間がどの程度長期化するかは、当該企業結合案件自体の複雑さの他に、競争当局であるSAMRのその時々の処理件数及び人員の多寡や、企業結合の関わる事業分野のセンシティビティ、SAMRや欧米当局等で並行して審査されている同一分野の案件の有無等によって異なり※6、法令上審査期間の中断が認められるか否かだけでは決まらない。本改正が審査期間の長期化をもたらすものかどうかは、改正後の実務運用を見守る必要がある※7。
③ 届出基準を満たさない企業結合の届出・調査(8月1日から施行済み)
旧中国独禁法では、企業結合の当事者である各事業者について、上記①で記載した中国国内売上高及び全世界売上高が届出基準を満たした場合に届出義務を課しているが、改正法では、届出基準を満たさない案件についても、「当該企業結合が競争を制限、排除する効果を有する又は有するおそれがあると認められる証拠がある場合」には、当局は当事者に対して届出を求めることができ、当事者が応じない場合調査を行うことができるとする条項が追加された(改正法第26条第2項及び第3項)。
この点、企業結合届出の売上基準を満たさない場合でも、当局が競争を実質的に制限するおそれがあると認めるものについて調査し、場合によって阻止できるのは、日本の独禁法も同様である。そのため、日本の独禁法実務では、関連市場の売上規模が小さいといった理由で届出基準を満たさないものの、市場シェアが高く、競争を実質的に制限するおそれがあるとしてクロージング後に公正取引委員会からの介入を招きかねない企業結合案件について、事業者が公取委に事前相談を行い、「準ずる届出」と呼ばれる届出類似の手続を行うことがあるほか、近時では公正取引委員会が積極的に企業結合当事者に連絡をとり、届出義務がなくとも実質的な審査を行う例も散見される。中国独禁法においても、改正成立後は、届出基準を満たす・満たさないの判断に加え、競争当局に対する積極的な事前相談を行うことの得失を含め新たに検討する必要があると思われる。
改正法では、旧法にはない企業結合の重点審査分野が法定されることとなり、「生活関連、金融、科学技術、メディア等の分野」の企業結合に関して審査を強化すると定められている(改正法第37条)。これらの分野と全く関係のない企業結合は想定しづらく、本規定は確認的なものと思われるが、列挙された分野については、過去の届出義務違反についても摘発されるリスクがより高く、また届出後の審査がより慎重になる傾向が示唆されていると思われ、留意を要する。
④ 簡易審査に関する届出・審査機関の変更(8月1日から施行済み)
これまで企業結合届出・審査はいずれも中国・北京の市場監督管理総局(「中央総局」)が担当していたところ、同総局は2022年7月8日に、同年8月1日から企業結合審査のうち、試験的に簡易審査を各地方の市場監督管理局(「地方管理局」)に委託することを公表した※8。概要は以下のとおりである。
| 委託先 | 北京、上海、広東、重慶、陝西の各省(直轄市)の地方管理局 |
|---|---|
| 委託案件 | 簡易審査要件を満たす届出のみ |
| 委託要件:(i)から(iv)のいずれかを満たす場合 |
(i) 企業結合の届出者の所在地が委託先関連地域内 (ii) 企業結合の対象者(支配権を取得される企業)の所在地が委託先関連地域内 (iii) 企業結合の対象となる合弁企業の所在地が委託先関連地域内 (iv) 企業結合の関連市場が地域市場であり、全部又は主要の一部が委託先関連地域内 |
| 委託先関連地域 |
北京:北京市、天津市、河北省、山西省、内モンゴル自治区、遼寧省、吉林省、黒竜江省 上海:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省 広東:広東省、広西省、海南省 重慶:河南省、湖北省、湖南省、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区 陝西:陝西省、甘粛省、青海省、寧夏省、新疆自治区 |
| 届出先 | 中央総局に対して届出を行う |
| 事前相談先 | 中央総局又は委託先の地方管理局のいずれでも可 |
| 届出・審査手続 |
(i) 中央総局は届出受領後、委託要件を満たす場合、委託先の地方管理局に届出資料を転送する。 (ii) 各地方管理局が届出者に通知の上、受理及び審査を行う。 (iii) 最終的な審査の決定は中央総局が地方管理局の報告・意見を踏まえて決定し、公表する。 |
| 委託の中止 | 委託案件が簡易審査要件を満たさない場合、届出義務違反がある場合、取引が中止又は重大な変更があり、届出者が届出を撤回した場合などの場合は、委託先の地方管理局が中央総局に報告し、中央総局が委託の中止を決定する。 |
上記改正により、今後簡易審査は原則として各地方の市場監督管理局に委託されることとなる。試験的措置のため、委託案件は簡易審査案件のみとされ、中央総局の関与も予定されているが、中国は各地域により法執行の傾向が異なることがしばしば指摘され、地方管理局の担当官は競争法の審査実務に不慣れな者も多いことが予想されるため、本改正による届出の審査実務への事実上の影響は小さくないと思われる。
(次号に続く)
※1
本稿を執筆する過程では井本吉俊弁護士から有益な示唆を多くいただいており、心より御礼を申し上げたい。
※2
中国語:经营者集中
※3
何をもって情状が「悪質」と見るかは法令の文言上から明らかではないが、これまでの中国独禁法上の処罰及び中国の他法令の行政処罰の先例を踏まえると、事業者が義務違反を明確に認識し、当局から調査・指摘を受けたにもかかわらず義務違反を積極的に是正しなかった場合がこれに該当する可能性がある。
※4
中国語:垄断协议
※5
国務院の企業結合の届出基準に関する規定(「国務院令」)。中国語:国务院关于经营者集中申报标准的规定
※6
半導体などいわゆる米中対立に影響を受ける事業や、レアアースなど戦略的重要性の高い物資が関連する事業の審査は、事実上長期化するおそれがあると思われる。
※7
なお、改正法第32条では、審査期間の中断及び再開について、いずれも競争当局が書面により当事者に通知すると定められており、結合当事者にとって審査期間が中断・再開しているかどうかは、当局からの書面により判断できる仕組みが採られている。
※8
中国語:市场监管总局关于试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查的公告
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


(2025年8月)
前川陽一


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
若江悠


(2025年8月)
前川陽一


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
井本吉俊


小川聖史


深水大輔、Simon Airey(McDermott Will & Emery)(共著)


(2024年2月)
佐々木将平


(2024年2月)
服部薫、柳澤宏輝、井本吉俊、森大樹、田中亮平、一色毅、小川聖史、鹿はせる、伊藤伸明、山口敦史、山田弘(共著)


佐々木将平


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
若江悠


若江悠


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
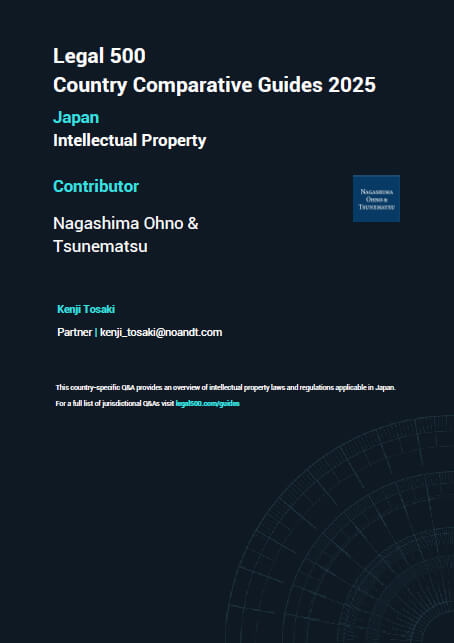
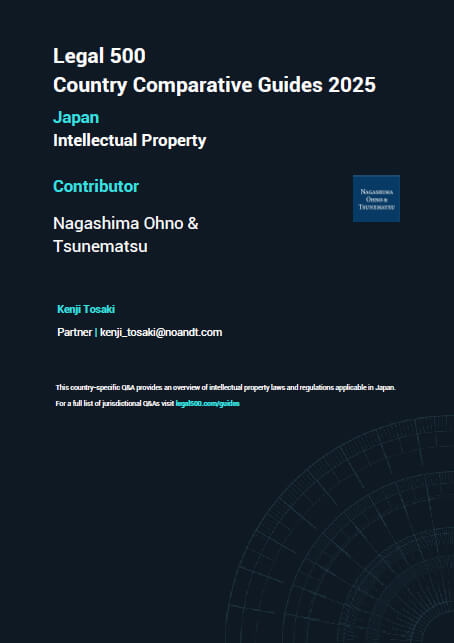
(2025年9月)
東崎賢治


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
髙取芳宏


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


(2024年9月)
柳澤宏輝


(2024年2月)
服部薫、柳澤宏輝、井本吉俊、森大樹、田中亮平、一色毅、小川聖史、鹿はせる、伊藤伸明、山口敦史、山田弘(共著)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2022年9月)
鹿はせる


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


山本匡


梶原啓


箕輪俊介


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


川合正倫


川合正倫、王雨薇(共著)


(2025年9月)
若江悠