
粂内将人 Masato Kumeuchi
パートナー
東京
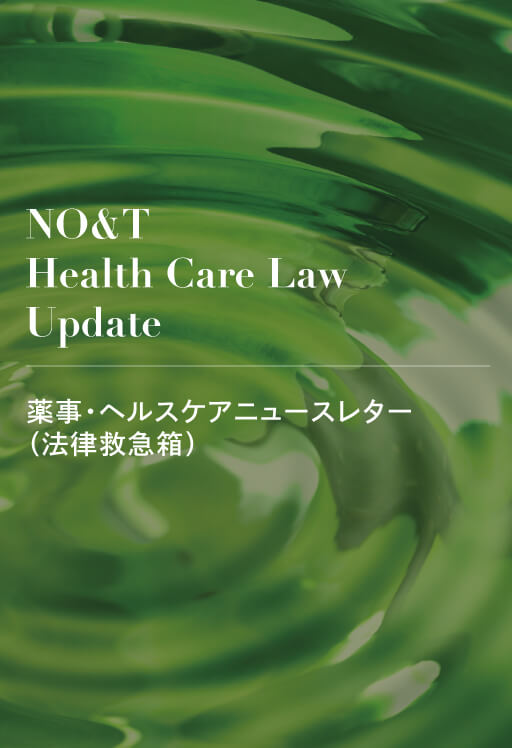
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
ニュースレター
医療広告を巡る規制動向・執行状況のアップデート ~ウェブサイト等事例解説書の改訂、ステマ規制の処分事例~(2024年8月)
2024年1月31日に医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改正案(以下「本改正案」といいます。)が公表されました。医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(医療広告)については、原則として、医療法及び厚生労働省の告示に規定されている一定の事項(広告可能事項)以外は広告することができませんが、医療法及び同法施行規則に定める広告可能事項の限定解除の要件を満たした場合には、例外的に広告可能事項以外の事項であっても広告できるものとされています。医療広告ガイドラインにおいては、そうした限定解除の要件の解釈が示されていますが、本改正案では、特に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)において承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品や、承認等された効能・効果又は用法・用量とは異なる効能・効果又は用法・用量にて使用する医薬品・医療機器・再生医療等製品(未承認医薬品等)を自由診療で使用する場合において、限定解除の要件として明示すべき内容が、新たに追記されています。
最近、もともと2型糖尿病治療薬等として承認されているGLP-1受容体作動薬について、適応外で美容・痩身・ダイエット目的で使用すること(GLP-1ダイエット)等、美容・痩身目的での医薬品等の適応外使用に関する違反広告やそれに起因する消費者トラブルが問題となっており、本改正案はこのような問題に対処することを念頭に置いたものであると考えられます。
薬機法上、製薬会社等が未承認医薬品等を流通させることは禁止されており、また、未承認医薬品等の広告を行うことも禁止されています(薬機法14条1項、同法68条等)。他方で、薬機法上も、医師法や医療法等の各種関連法規制上も、医師が自らの責任の下で未承認医薬品等を医療行為の中で使用すること自体は禁止されていません。そのため、従来から、一定の要件を満たす場合に限り、医療機関等が、未承認医薬品等を用いた医療行為についての広告を行うことも可能となっていました。
今回の改正については、2024年1月29日に開催された厚生労働省の分科会(第2回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会)において議論がなされており、当該分科会において使用された資料(「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて」の改正について)から、今回の改正の背景・経緯等を読み取ることができます。
当該資料では、本改正案の背景として、以下の2点が記載されています。
医療広告については、前述のとおり、医療法及び厚生労働省の告示(「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)」)により、原則として、診療科名、病院の名称・所在場所、診療日・診療時間等の一定の事項(広告可能事項)のみ広告をすることが可能とされていますが、下記の4要件を満たした場合には、例外的に広告可能事項の限定解除が認められ、広告可能事項以外の事項の広告が可能とされています。なお、③及び④については、自由診療について情報を提供する場合にのみ必要とされています。
この点に関連して、本改正案では、未承認医薬品等を自由診療で使用する場合には、広告可能事項の限定解除の要件として、以下の各事項についても十分に記載する必要がある旨が追記されています。
上記(i)から(iv)の要件は、これまでも「医療広告ガイドラインに関するQ&A」において未承認医薬品等を自由診療に使用する場合における広告可能事項の限定解除の要件として必要となることが示されていましたが、本改正案では、同じ内容が明記されています。
他方で、上記(v)の要件は、「医療広告ガイドラインに関するQ&A」では示されていない要件であり、本改正案において、新しく追加されたものです。従前より上記(i)から(iv)の各事項を明示していた医療機関等についても、本改正案によれば、新たに(v)の事項を明示する必要があるため、対応の要否・内容について確認しておく必要があります。(v)の要件について、より具体的には「国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る。(v)において同じ。)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で万が一健康被害があったとき、公的な救済制度(医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度)があるが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済対象にならないこと、また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量及び使用上の注意に従って使用されていない場合は救済対象にならないことを明示すること」が求められています。
なお、医療広告ガイドラインの改正と併せて、厚生労働省による通知(「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて」)についても、「わが国で承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品を用いた治療(承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品等を用いた治療も含む。)に係る説明に当たっては、①未承認医薬品等であること、②入手経路等、③国内の承認医薬品等の有無、④諸外国における安全性等に係る情報及び⑤未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象にはならないことについて、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする者に対して、丁寧に説明しなければならないこと。」という内容を追記することが検討されています(前掲 第2回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会資料「「医療広告ガイドライン」及び「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて」の改正について」)。厚生労働省の通知は、一般市民との関係において、それ自体が直接的に法的拘束力を持つものではありませんが、民事訴訟において説明義務違反の有無が争われた際等に、通知の内容に従っていたか否かが考慮要素の一つとして参酌される可能性もあり得ますので、上記通知の改正との関係においても、対応について検討しておく必要があると思われます。
今回公表された医療広告ガイドラインの改正内容について、再考を促したい場合や、疑義を解消したい場合、その他規制当局に意見を述べたい場合には、パブリックコメントを提出することが可能です。コメントの受付締切期限は2024年2月29日23時59分に設定されています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


(2025年6月)
小池晨


(2025年5月)
小池晨
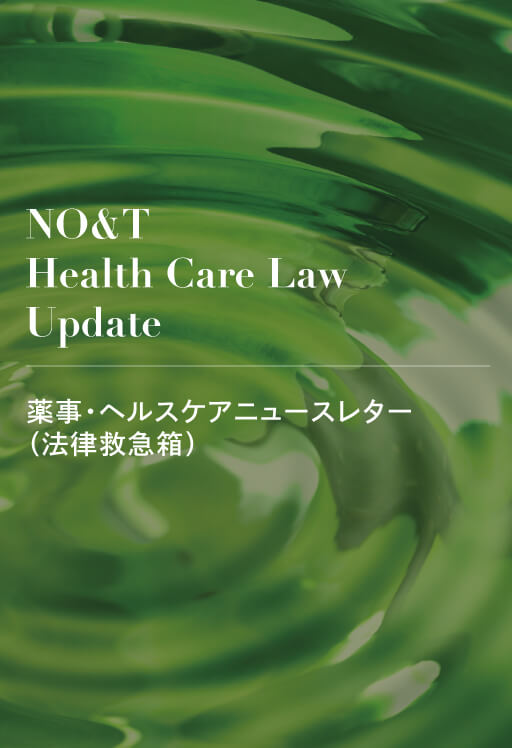
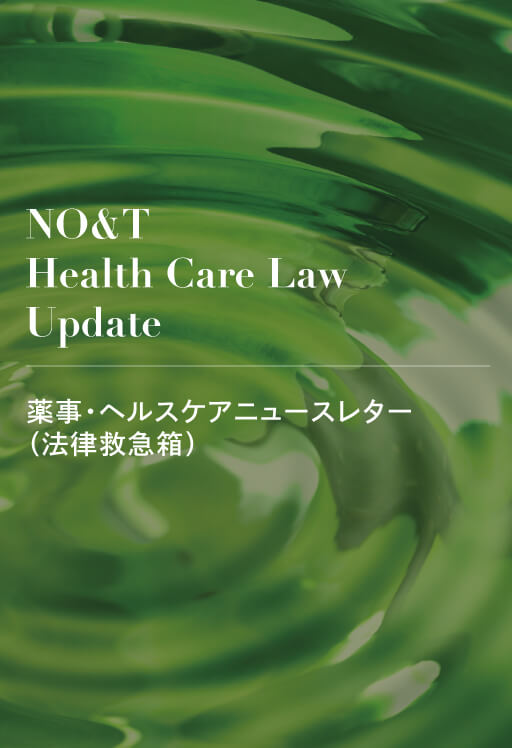
鈴木謙輔、中本優介(共著)
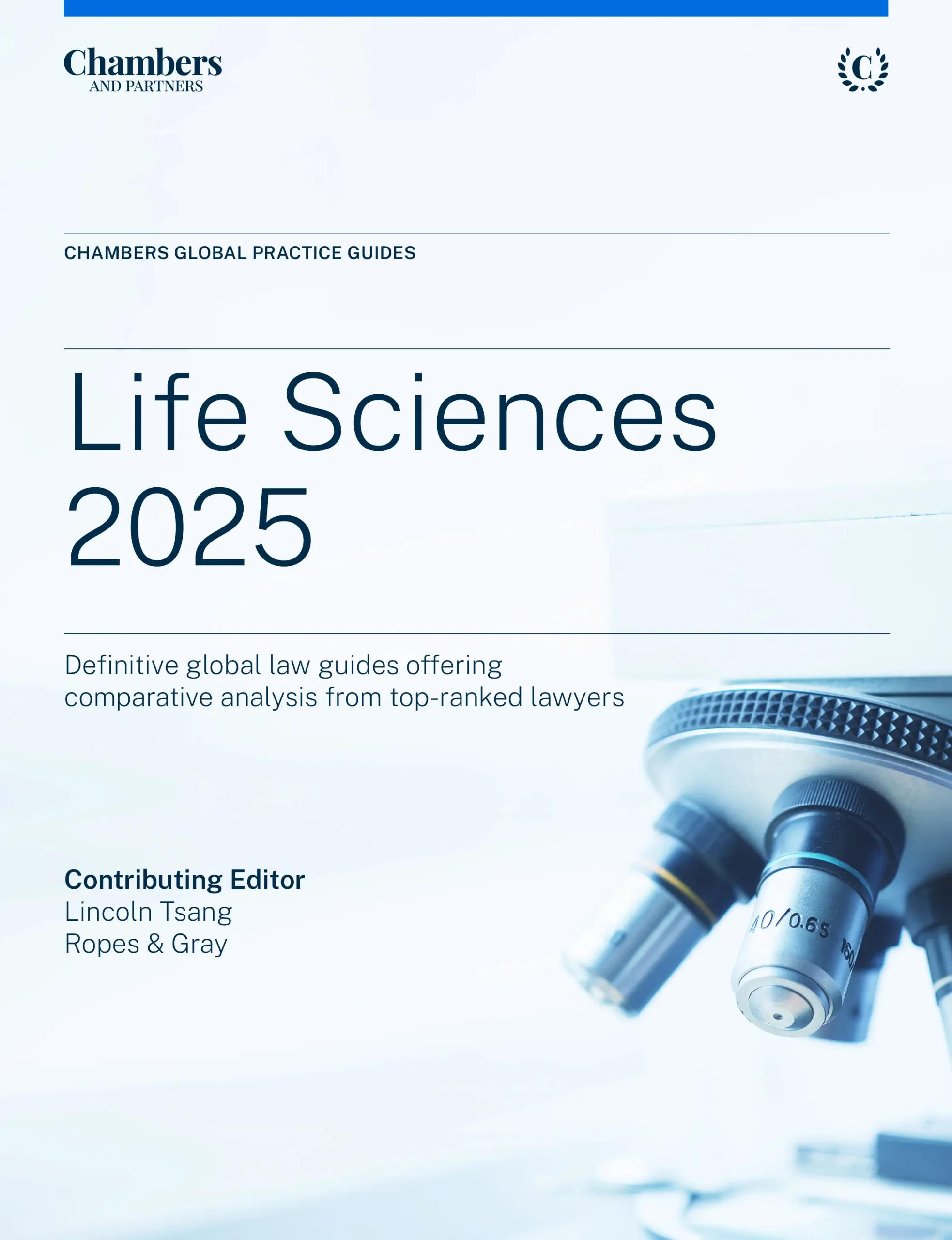
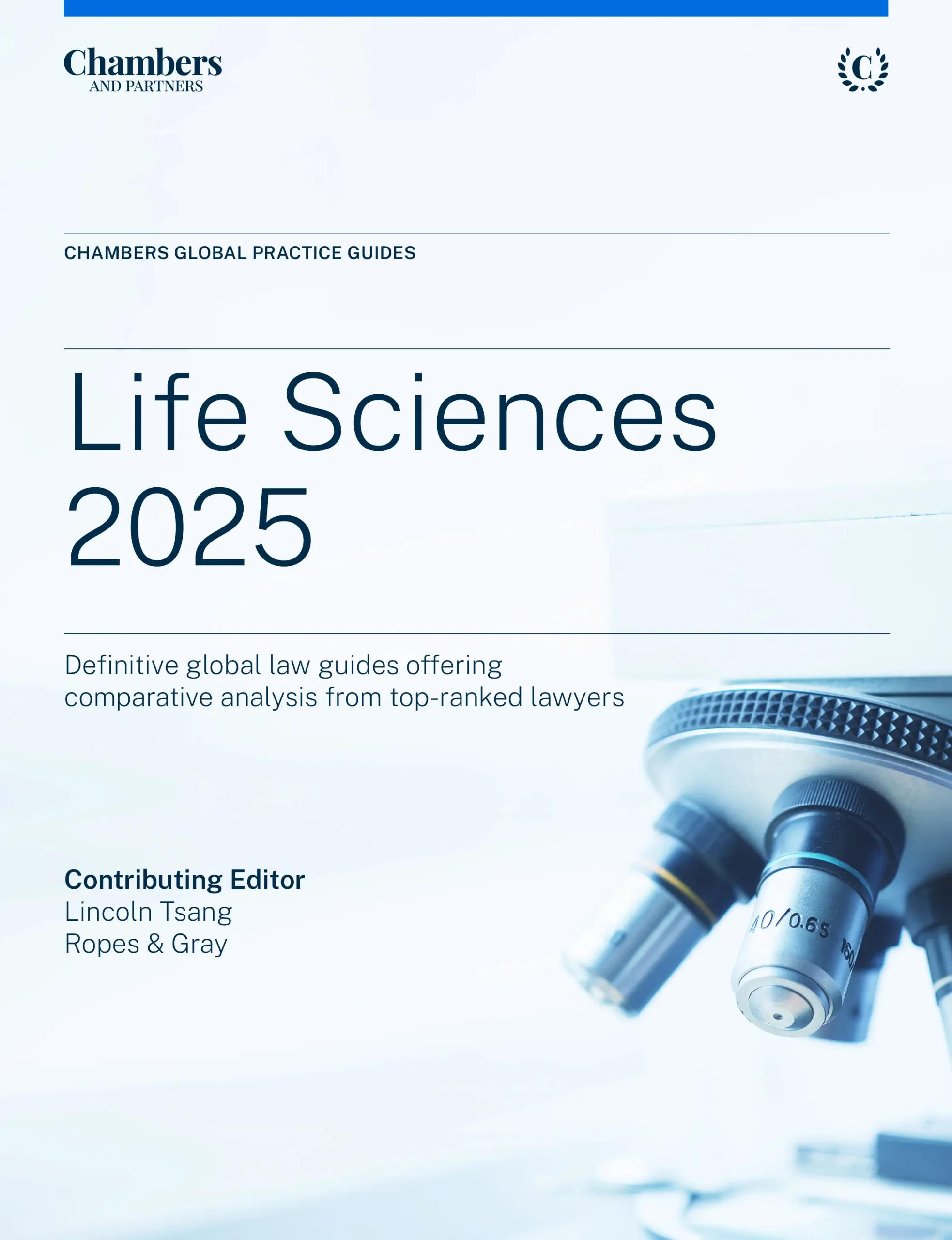
(2025年4月)
内海健司、鈴木謙輔(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


東崎賢治、羽鳥貴広、加藤希実(共著)


情報機構 (2025年9月)
澤山啓伍、前川陽一、箕輪俊介、坂下大、クレア・チョン、リー・ユエン・ヤオ、ズン・パイ(共著)


民事法研究会 (2025年8月)
北島東吾(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
森大樹、井上皓子(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年7月)
森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


宮城栄司、井柳春菜(共著)