
清水美彩惠 Misae Shimizu
パートナー
東京

NO&T Labor and Employment Law Update 労働法ニュースレター
NO&T Dispute Resolution Update 紛争解決ニュースレター
令和6年4月26日、最高裁判所第二小法廷は、労働者と使用者との間に当該労働者の職種等を特定のものに限定する旨の合意(いわゆる職種限定合意)が認められる場合における配転命令の有効性が争われた事案において、職種限定合意がある場合には、使用者は、当該労働者の個別的同意なしに配転する権限を有しないと判示し、(労働者と使用者との間の黙示の職種限定合意の存在を認めながらも、)当該配転が、当該労働者が従事していた業務が廃止されるという状況下において、当該労働者の解雇を回避するために行われたこと等の事情を考慮して、当該配転は配転命令権の濫用に当たらないと判断した原審を破棄し、原審に差し戻す旨の判決(以下「本判決」といいます。)を下しました(最高裁判所第二小法廷令和6年4月26日(令和5年(受)604号))。本判決は、職種限定合意が認められる場合における配転命令の有効性について明確な判断を示した初めての最高裁判決であり、実務への影響が注目されています。
本ニュースレターでは、企業の配転命令権及び職種限定合意について概説した上で、本判決の概要について説明します。
日本においては、使用者による解雇規制が厳しい反面、使用者の配転命令権が広範に認められています。日本の会社の就業規則や従業員との労働契約において、「業務上の必要性がある場合には配転を命ずることができる」という趣旨の規定が設けられていることが一般的であり、このような定めがある場合には、当該社員と、職種や勤務地を限定する合意をしている場合でない限り、使用者は、従業員の個別の同意がなくとも配転を命じることができます。企業の配転命令権は権利濫用法理により制限される余地はありますが、判例は、企業の配転命令権を広範に認め、濫用の有無の判断を厳しく行う立場をとっており、配転命令権の濫用が認められるのは限定的な場合に限られます。具体的には、①配転命令について業務上の必要性がない場合、②業務上の必要性はあるものの、配転命令が他の不当な動機・目的によってなされたものであるとき、③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような場合についてのみ、配転命令権の濫用になると解されています(東亜ペイント事件判決(最判昭和61年7月14日(昭和59年(オ)1318号)))。
一般に、使用者と労働者が職務内容や勤務場所を特定する特別な合意(職種・勤務地限定合意)をした場合には、使用者は当該労働者に対して、一方的に配転を命ずることはできず、配転に当たっては労働者の個別同意が必要であると解されています。もっとも、日本では、職務内容や勤務場所を特定する明示的な合意なしに労働契約を締結する場合が多いため、裁判の中で、職種・勤務地限定合意の存否の認定自体が問題となることも少なくありません。後記4のとおり、本判決の事案においても、労働契約締結時に、労使間で明示的な職種限定合意はなく、職種限定合意の存否が争いになりました(第一審及び原審において、黙示の職種限定合意が認められています。)。
本件の原告は、平成13年3月、福祉用具の改造・制作、技術の開発等の業務を行う滋賀県福祉用具センター(以下「福祉用具センター」といいます。)を運用していた財団法人滋賀県レイカディア振興財団を当初の雇い主として、福祉用具センターで福祉用具の改造・制作、技術の開発に係る技術職として雇用されて以降、滋賀県社会福祉協議会(被告)が上記財団法人の権利義務を承継した後も、平成31年3月末まで、18年間、当該業務を行っていました(その間、原告は福祉用具センターにおいて、溶接のできる唯一の技術者でした。)。
そのような中で、被告は、福祉用具のセミオーダー化により、既存の福祉用具を改造する需要が年間数件までに激減し、福祉用具センターにおける福祉用具改造・製作の実施件数が大きく減少していたこと等を理由に、同センターにおける福祉用具改造・製作業務の廃止を決定し、原告に対して、上記業務を行う技術職から総務課の施設管理担当への配転を命じました(以下「本件配転命令」といいます。)。
これを受けて、原告は、被告に対して、本件配転命令は、原告と被告との間の職種限定合意に反し違法であるか又は配転命令権の濫用であり、これにより原告が精神的苦痛を被った等と主張して、労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償等を請求しました。
第一審(京都地判令和4年4月27日(令和元年(ワ)3532号))は、以下のとおり、原告と被告との間での黙示の職種限定合意の存在を認めつつも、本件配転命令に関する具体的な諸事情を考慮して、本件配転命令の有効性を認めました。
第一審は、原告と被告との間で、原告の職種を技術者に限るとの書面による合意はないが、原告が技術系の資格を多数保有していること、溶接ができることを見込まれて採用された経緯、採用後18年間にわたって福祉用具の改造・製作、技術開発を行う技術者として勤務してきたこと、福祉用具センターの指定管理者である被告が、福祉用具の改造・製作業務を外部委託化することは想定されていなかったこと、原告は福祉用具センターにおいて、溶接のできる唯一の技術者であったこと等の事情を考慮して、原告と被告との間には、原告の職種を、福祉用具の改造・製作、技術開発を行う技術者に限定するとの黙示の職種限定合意があったと認定しました。
本件配転命令の有効性については、(i)福祉用具のセミオーダー化により、既存の福祉用具を改造する需要が年間数件までに激減する中で、その程度の改造の需要のために原告を専任の技術者として配置することに経営上の合理性がないとの判断に至ることもやむを得ないこと、(ii)本件配転命令当時、総務担当者の病気による退職があり、総務課が欠員状態であったことから、総務担当者を補填する必要があったこと、(iii)施設管理担当の業務内容は特別な技能や経験を必要とするものではなく、負荷も大きくないこと等の事実を認定した上で、福祉用具の改造・製作業務が廃止されることに伴って、(当該業務を行う技術職として職種を限定された)原告を解雇するという事態を回避するためには、原告を総務課の施設管理担当に配転することにも業務上の必要性があり、また、本件配転命令は原告に甘受すべき程度を超える不利益をもたらすものではなく、不当な動機・目的があるとは認められないとして、本件配転命令が権利の濫用として違法・無効であるということはできないと認定しました。
原審である控訴審(大阪高判令和4年11月24日(令和4年(ネ)1373号))も、第一審の判断を維持し、本件配転命令は、技術者として職種を限定して採用された原告につき、解雇もあり得る状況のもと、これを回避するためになされたものであり、本件配転命令当時、総務課が欠員状態であったことや、原告が過去にも見学者対応等の業務を行っていたこと等からすれば、配転先を総務課とすることについても合理的な理由があるといえ、本件配転命令に不当目的があるとも言い難いと述べ、本件配転命令が違法・無効であるとはいえないと判断しました。
本判決は、上告人(原告)と被上告人(被告)との間には、上告人(原告)の職種及び業務内容を福祉用具センターにおける福祉用具の改造・製作業務等を行う技術職に限定する旨の合意があったこと等の、原審において確定した事実関係を前提に、「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかった」と判示して、当該配転は配転命令権の濫用に当たらないと判断した原審を破棄し、原審に差し戻しました。
前記2(2)のとおり、本判決の判断が示される前から、一般に、労使間で職種限定合意の成立が認められる場合には、使用者による配転命令権は制限され、労働契約に基づく合意の範囲を超える配転を一方的に命じることはできず、配転に当たっては労働者の個別同意が必要であると解されていましたが、裁判例の中には、労使間における職種限定合意の存在を認めつつも、他の職種への配転を命ずることについて正当な理由があるとの特段の事情が認められる場合には、使用者に他の職種への配転命令権が認められると述べるものもありました(東京海上日動火災保険事件(東京地判平成19年3月26日(平成18年(ワ)2001号、平成18年(ワ)15394号、平成18年(ワ)16906号)))。本判決は、職種限定合意が認められる場合には、使用者は配転命令権を有しないことについて明確な判断を示した初めての最高裁判決として意義を有すると考えられます。
本判決によって、職種限定合意が認められる場合には使用者は配転命令権を有しないことが明らかにされましたが、そもそも、明示的に職種を限定する合意がなされることは少なく、黙示の職種限定合意の有無が争われるケースが少なくありません。特に高い専門性やスキルを持つ社員を他の職種に配転させた場合に職種限定合意の有無が争われるケースが多く見られます。近時は、高い専門性やスキルを持つ社員を獲得することや社員のエンゲージメント向上を期待して、ジョブ型雇用への転換を検討している企業も少なくありませんが、職種限定合意の有無との関係では、ジョブ型雇用は、それ自体が必ずしも職種を限定した雇用を意味するわけではなく、就業規則の定めや個別の労働契約の定め方次第では、使用者の配転命令権を認めることも可能であると考えられます。
本判決及び令和6年4月1日施行の改正法により、労働契約の締結時に就業場所・業務の変更の範囲を明示することが義務付けられました(令和6年4月1日施行の労働条件明示義務の強化については、NO&T Labor and Employment Law Update ~労働法ニュースレター~ No.6「労働条件明示義務の強化」にて紹介しています。)ことも踏まえ、企業としては、労使間の認識違いからトラブルに発展することを回避する観点から、(特に、高い専門性やスキルを持つ社員を採用する場合や、ジョブ型雇用で社員を採用する場合には)就業規則や労働契約の規定を点検し、また、採用時における説明を工夫することが望ましいでしょう。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年6月)
壱岐祐哉(講演録)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年5月)
福井信雄、山内建人(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
壱岐祐哉(講演録)


(2025年3月)
神田遵


清水美彩惠、伊藤菜月(共著)
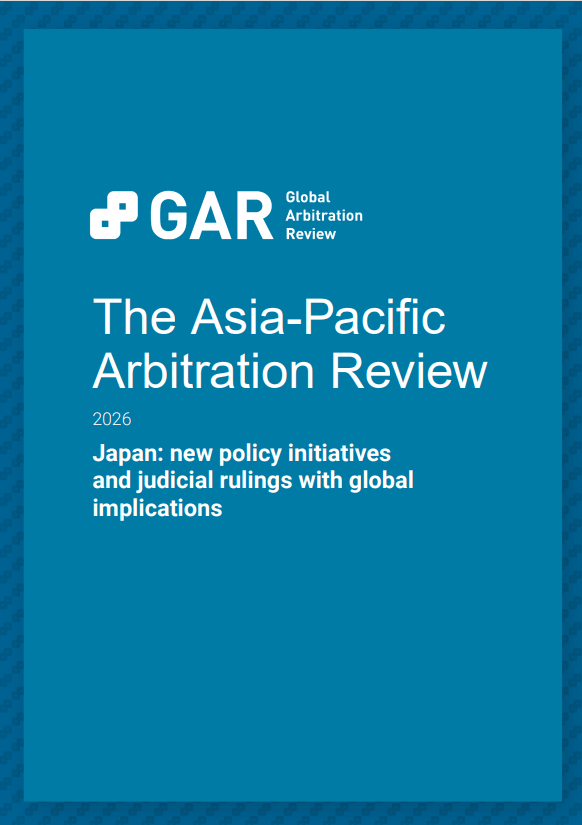
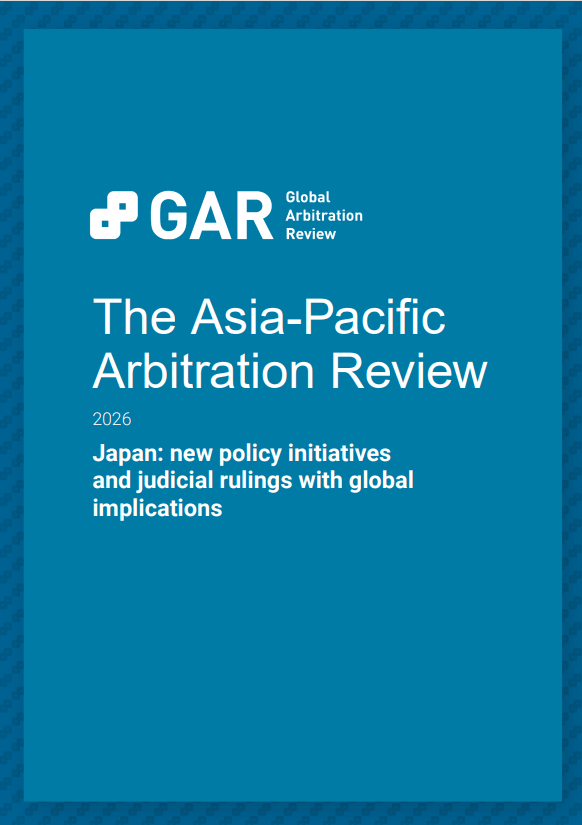
(2025年5月)
小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年6月)
壱岐祐哉(講演録)
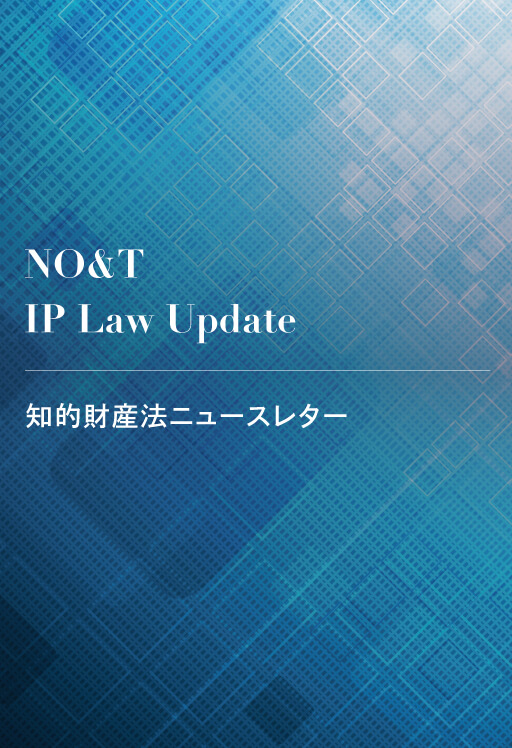
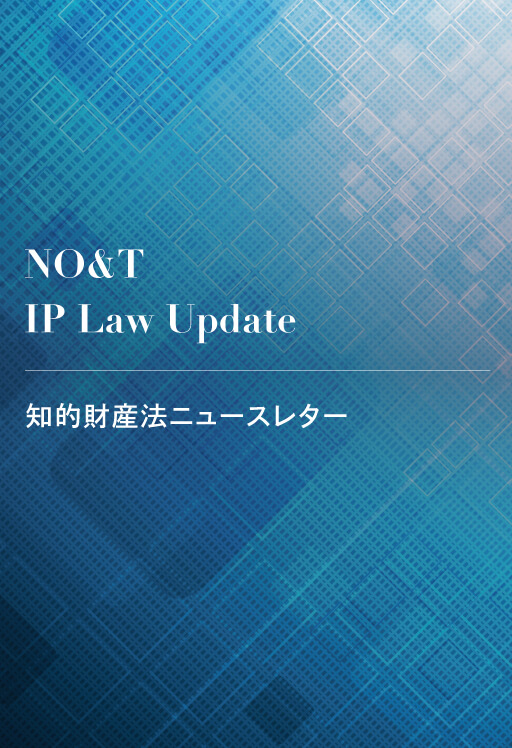
東崎賢治、平山貴仁(共著)


(2025年6月)
神田遵


梶原啓


(2025年4月)
杉本花織


(2025年4月)
伊藤眞