
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
ニュースレター
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を踏まえた法改正の議論の現状と展望(2024年7月)
政府におけるメタバースに関する議論は、2024年も引き続き行われています。例えば、総務省では、昨年開催された「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」で示された課題解決の方向性を踏まえ、メタバースに関する国際的な理念の確立を見据え、日本国内での議論を推進することを主目的に「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」を開催し、2024年10月31日付で、「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会 報告書2024」(以下「本報告書」といいます。)を取りまとめました。
上記研究会では、2023年10月から、ユーザにとって安心・安全なメタバースの実現に向けて、メタバースの民主的価値に基づく原則等の検討やメタバースに係る技術動向等のフォローアップを行うとともに、国際的なメタバースの議論にも貢献することを目的として議論を重ねており、2024年9月11日には素案が公表されました。2024年9月19日から同年10月8日にかけて、上記素案に関する意見募集が実施され、提出された意見を参考に素案を修正したものが、本報告書となります。
本報告書は、メタバースに関する国内外の最近の動向や技術動向・利活用事例に触れつつ、「メタバースの原則(第1.0版)」や今後の検討事項を紹介するものであり、メタバースに携わる関係者には重要なものといえます。本ニュースレターでは、本報告書の概要について紹介いたします。
本報告書は、以下の5つの章から構成されています。
本報告書の構成
第1章では、国内の政府・業界団体等の動向、米国・EUなど諸外国の動向、国際機関における国際的な議論の状況などが紹介されています。第2章では、メタバース関連サービス提供者の取組として期待される項目に関する原則である「メタバースの原則」の検討経緯及び原則の内容が紹介されています。第3章ではVR・AR等のデバイスの動向や利活用状況が、第4章では生成AIとの連携や利活用における課題解決が紹介されています。最後に、第5章では今後の検討課題として、国際的な議論の状況フォローやVR・AR等も含めたメタバースの利活用促進に係る課題等の検討が紹介されています。
本ニュースレターでは、本報告書の中心的な内容であり、特にメタバース関連サービス提供者や利用者に影響がある第2章(メタバースの原則(第1.0版)の検討)及び第5章(今後の検討事項)について、以下でより詳しく紹介します。
本報告書は、メタバースにおける民主的価値の主な要素を示した上で、これを実現するため、仮想空間そのものの提供を担うメタバース関連サービス提供者が果たす役割が特に重要であることに注目して、メタバース関連サービス提供者の取組として期待される項目に関する原則を、「メタバースの原則(第1.0版)」(以下単に「メタバースの原則」といいます。)と定義しています。このメタバースの原則に法的拘束力があるわけではありませんが、メタバース関連サービス提供者が事業を展開する上で遵守すべき項目を示す一つの指針として参考にすべきものといえます。なお、本報告書では、メタバースの原則はメタバース関連サービス提供者の取組を対象としたものであるものの、ユーザ、コンテンツの創作や提供を行う者(クリエイターを含みます。)、メタバースに関するルール整備に関わる者、メタバースに関するユーザのリテラシー向上に関わる者を含む全てのステークホルダーの取組においても参照されることが期待されるとも述べられており、メタバースに関係する全ての方が参照すべきものといえます。
<前文>
メタバースの原則は、大きく分けて前文と原則に分けて規定されています。前文では、「民主的価値を踏まえたメタバースの将来像の醸成」、「原則の位置付け」、「各原則についての考え方」、及び「補足」について述べられています。
「民主的価値を踏まえたメタバースの将来像の醸成」においては、民主的価値の主な要素として国際的な共通認識となるものに以下の3つを挙げ、メタバースの将来像の醸成を図ることが重要であるとしています。
そして、ユーザが安心・安全にメタバースを利用するためにメタバース関連サービス提供者(プラットフォーマー及びワールド提供者※1)の役割が重要であるとした上で、メタバースの原則として以下の2つを提示し、それぞれについて考え方が示されています。
以下、メタバースの各原則を構成する項目とその内容を紹介し、メタバースのサービスを提供するに当たって法的観点から特に留意すべきと考えられる事項について説明いたします。
<原則①:メタバースの自主・自律的な発展に関する原則>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オープン性・イノベーション |
|
| 多様性・包摂性 |
|
| リテラシー |
|
| コミュニティ |
|
法的な観点からは、「知的財産権等の適正な保護」が重要な要素の一つとして挙げられます。メタバース関連サービス提供者には、メタバースサービスの開発・運営等に当たり、知的財産権をはじめとする諸権利の適正な保護に努めることが期待されることはもちろん、利用規約やコミュニティガイドライン等を通じて、知的財産権をはじめとする諸権利の適正な保護の重要性についてユーザへの浸透を図るとともに、例えば、二次利用の可否をはじめ、UGCの創作・利用に関するルール等についてこれらの文書に明示することが期待されています。具体的な対応策としては、利用規約やコミュニティガイドライン等において、ユーザによるUGC等に関する知的財産権の帰属を明確にし、また、かかるUGC等の利用可能範囲を明確にすることが望ましいといえます。利用規約やコミュニティガイドライン等の策定に当たっては、内閣府知的財産戦略推進本部による「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理」(2023年5月)(以下「論点整理」といいます。)における法的な整理に加え、業界団体によるガイドライン(例えば、日本デジタル空間経済連盟「メタバース・リテラシー・ガイドブック」(2024年1月)※2)が参考になります。
<原則②:メタバースの信頼性向上に関する原則>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 透明性・説明性 |
|
| アカウンタビリティ |
|
| プライバシー |
|
| セキュリティ |
|
本報告書では、「メタバースの利用に際してのユーザへの攻撃的行為や不正行為への対応の説明」(透明性・説明性)として、メタバース関連サービス提供者は、メタバース上でのユーザ間のトラブルを抑制するとともに、コミュニケーションが円滑に行われるよう、提供するメタバースサービスにおいて、どのような行為が他のユーザへの攻撃的行為や不正行為に該当するかについて説明し、また、それらの行為を行ったユーザに対して取り得る対応についても説明することが期待されています。具体的な対応策として、他のユーザへの攻撃行為や不正行為に該当する行為類型や行為態様を可能な限り具体的に定めること、攻撃的行為や不正行為を行ったユーザにどのような対応を取る可能性があるのか可能な限り具体的に記載することが述べられており、利用規約やコミュニティガイドライン等において明示することが望ましいといえます。
また、アカウンタビリティにおいては「他のユーザやアバターに対する誹謗中傷及び名誉毀損の抑制」が要素の一つとして挙げられています。趣旨としては、自由で開かれた場であるメタバースにおいて、他のユーザやアバターに対する誹謗中傷、また名誉毀損につながり得る行為を抑制するために、メタバース関連サービス提供者は、利用規約やコミュニティガイドライン等を通じてユーザ間、ユーザとメタバース関連サービス提供者の間で当該メタバースサービスに関する共通的な理念を形成し、これに基づき必要な措置を講じることが期待されています。具体的な対応策として、利用規約等に禁止行為としてこれらの行為を列挙し、これに違反した場合の対応を明記したり、コミュティガイドライン等に禁止行為としてこれらの行為を明記することが考えられます。
これらに関連する重要な動向として、2024年5月に成立した「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(いわゆる「情プラ法」)が挙げられます。情プラ法において、「大規模特定電気通信役務提供者」に該当する場合、当該事業者は、権利侵害情報への対応の迅速化義務(例えば、侵害情報送信防止措置の申出方法の整備・公表、権利侵害の調査義務、申出に対する一定期間内の判断・通知)と、運用状況の透明化義務(例えば、侵害情報送信防止措置の実施基準の策定・公表、運用状況についての公表)を負うこととなります。同法は公布日(2024年5月17日)から1年以内に施行されるため、メタバース関連サービス提供者のうち特にプラットフォーマーは、「大規模特定電気通信役務提供者」に該当しないか注意する必要があります。
本報告書では、メタバースの利用において、ユーザの様々な行動に関する履歴が大量にデータとして記録され、蓄積され得る状況を踏まえ、メタバース関連サービス提供者は、ユーザのプライバシーに十分配慮した取扱いを行うことが期待されています。行動履歴それ自体は特定の個人を識別する情報ではないため個人情報保護法における「個人情報」(個人情報保護法第2条第1項)に直ちに該当するものではありませんが、本報告書では、行動履歴を利用する場合には利用目的を明示してユーザから同意を得ることや、取得する行動履歴は利用に必要な範囲にとどめることに留意されたい旨が述べられています。
また、法的な観点からは、「メタバースの利用に際してのデータ取得、メタバースの構築に際しての写り込み等への法令遵守等による対処」や「アバター(実在の人物を模したアバターを含む)の取扱いへの配慮(知的財産権、名誉毀損及びパブリシティの観点を含む)」といった内容は当然に重要なものといえます。これらの内容については、論点整理の内容が参考となります。
個人情報に関連して重要な動向としては、個人情報保護法の「いわゆる3年ごと見直し」が挙げられます。中間整理で挙げられた検討項目の中には、「不適正な利用の禁止」「適正な取得」の規律の明確化やこどもの個人情報等に関する規律の在り方があり、メタバース関連サービスへの影響が考えられます。3年ごとの見直しの内容については議論が続いており、「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会」の検討内容を注視する必要があります※3。
本報告書では、メタバースに関する今後について、VRだけでなく、AR・MRの実装が進む中でこれらの没入型技術全般を活用したメタバースも多く見られ、リアル(物理空間)とバーチャル(仮想空間)は相互に作用しつつその融合が一層進展することが見込まれるところ、同一の見え方が共有されない事態も起こり得るところであり、ある空間が持つ公共性をめぐる議論にも影響する可能性があると述べられています。また、産業面においても没入型技術全般を用いたメタバースの利活用が活発になされていることを踏まえ、改めてメタバースに関連する様々なステークホルダーを整理して把握するとともに、国内外の市場や技術、制度(ソフトローを含みます。)等の動向に関する調査のほか、インダストリアルメタバースや行政、医療、教育現場等での利活用事例などを含むユースケースを幅広く調査し、没入型技術全般をユーザが主体的に活用したメタバースのメリットや普及に向けた課題を整理することが求められるとも述べられており、VRだけでなく、ARやMRの発展にフォーカスした検討も今後求められることが示唆されています。法的な観点でも、AR・MRによってリアルに変更を加えることが、例えば著作権や商標権の問題を生じさせるか等、AR・MR特有の法的な検討も必要となります。
加えて、VRゴーグルやARスマートグラス等の没入型技術を用いたメタバースについては、様々な活用方法が期待され、また、近年、青少年を含めて利用が増加している傾向にある一方、文献調査においては、軽微なものを含め身体的、精神的な影響・課題があることが指摘されていることに触れ、リスクの有無を明らかにすることが望ましいことが述べられており、リスクの程度やその責任の所在が今後の検討課題となっていると考えられます。
本報告書は、メタバース関連サービス提供者が、メタバース関連サービスの制度設計を行う上で、参照すべきものであるといえます。記載内容は多岐にわたりますが、上記のとおり法的な観点からも重要な記載が含まれており、利用規約やコミュニティガイドライン等を整備するに当たり留意が必要となります。また、本報告書の中で触れられているメタバースの原則は、コンテンツのクリエイターやメタバースに関するルール整備に関わる者を含む全てのステークホルダーの取組においても参照されることが期待されています。
加えて、メタバース関連サービスに関しては、情プラ法や個人情報保護法といった重要な法改正があるため、最新動向を注視する必要があります。また、今後AIを活用する場面が増えてくることを踏まえると、国内外のAIに関する動向にも注意してビジネスの設計を行う必要があるといえます。
※1
本報告書では、プラットフォーマーと契約(有償・無償を問わず、利用規約への同意等も含まれます。)し、プラットフォーム上にワールドを構築して提供する者を指しています。
※2
事業者向けとユーザ向けに分けて策定されており、メタバース関連サービス提供者は「事業者向け」が参考になります。
※3
3年ごと見直しの概要については、NO&T個人情報保護・データプライバシーニュースレターNo.47「「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を踏まえた法改正の議論の現状と展望」もご参照ください。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年9月)
関口朋宏(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年9月)
関口朋宏(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
関口朋宏(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)


有斐閣 (2025年8月)
小川聖史(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
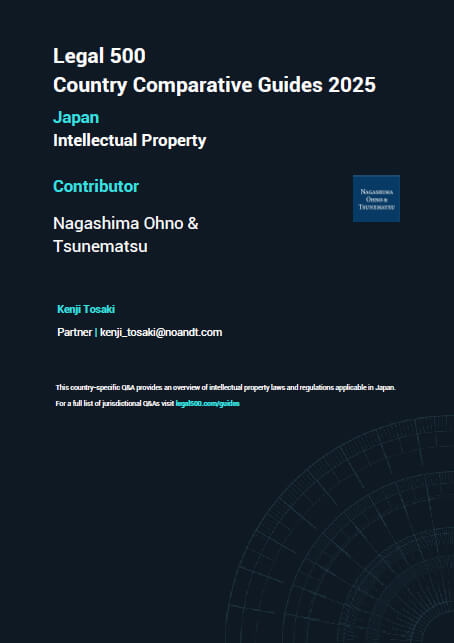
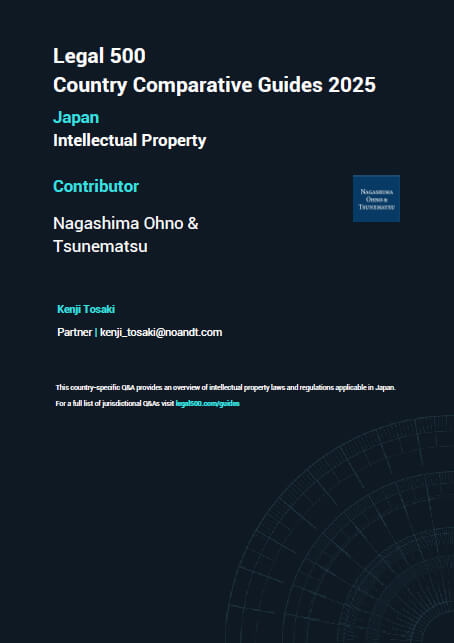
(2025年9月)
東崎賢治


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


(2025年9月)
酒井嘉彦


川合正倫