
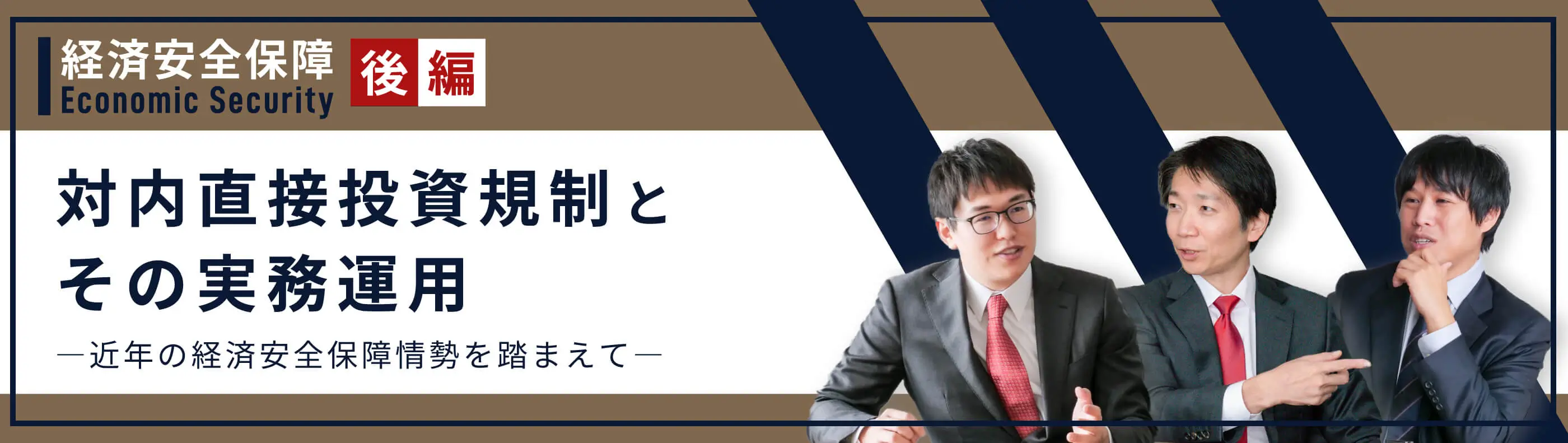

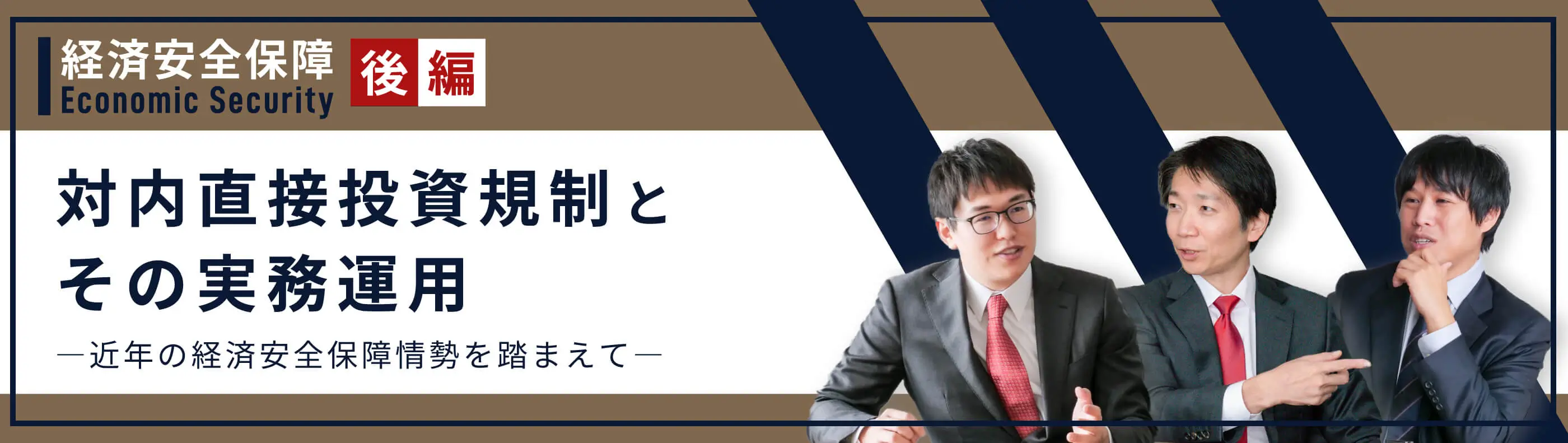


主な取扱分野は、M&A、企業再編、コーポレートガバナンス、敵対的買収対応等。海外での経験を活かし、国内外の企業を代理して、数多くのクロスボーダー案件に携わっている。とりわけ、戦略的M&A・提携に数多くの経験を有している。

企業法務一般に加え、クロスボーダーの複雑なM&A取引、輸出入貿易、外為法等経済安全関連法務に関するアドバイスを提供している。米国、中国の法律事務所での執務経験を踏まえ、貿易摩擦・紛争関連案件、国際間取引の紛争案件、海外法令のコンプライアンス関連、中華圏企業との買収・合弁等の交渉案件に関して幅広い経験・知見を持つ。

M&A・企業再編、コーポレートに関わる業務を中心に、企業法務全般に関するアドバイスを提供している。2021年12月から2022年11月まで経済産業省に出向(貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理政策課、同課国際投資管理室、大臣官房経済安全保障室等に所属)、外為法に基づく対内直接投資規制の政策・運用・執行を中心に、経済安全保障に関わる業務を担当した経験を持つ。

濱口

鹿

大澤

濱口

大澤

鹿

大澤

鹿

大澤

鹿

大澤

濱口

大澤

鹿

大澤


鹿

大澤

鹿

大澤


濱口

大澤

濱口

大澤

濱口

大澤

濱口

※1
大澤大「外国資本の受入れと経済安全保障〔上〕 ─日本企業に求められる検討─」旬刊商事法務 2022年12月15日号(No.2313)。
※2
大澤大「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく投資管理と実務上の諸論点」旬刊商事法務 2022年5月5・15日号(No.2294)。
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。