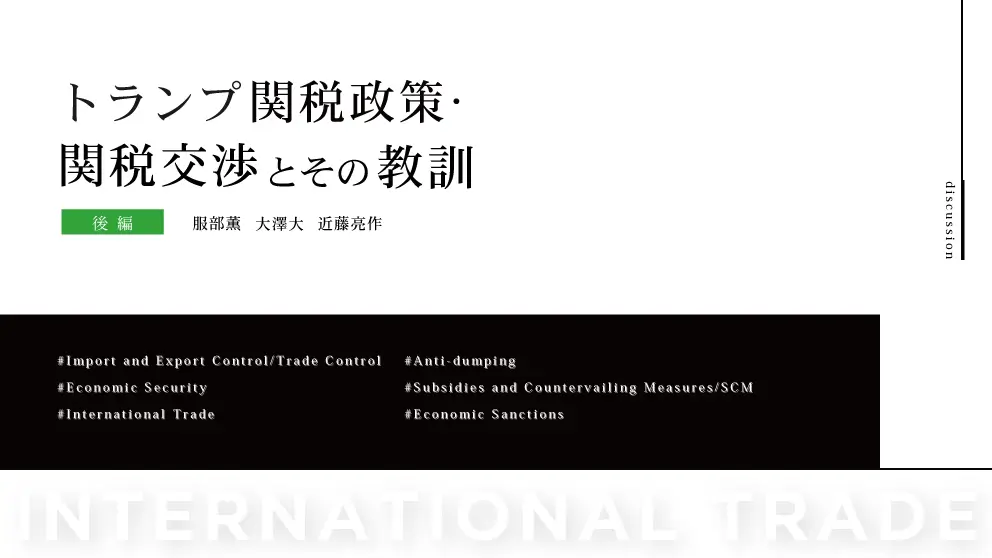
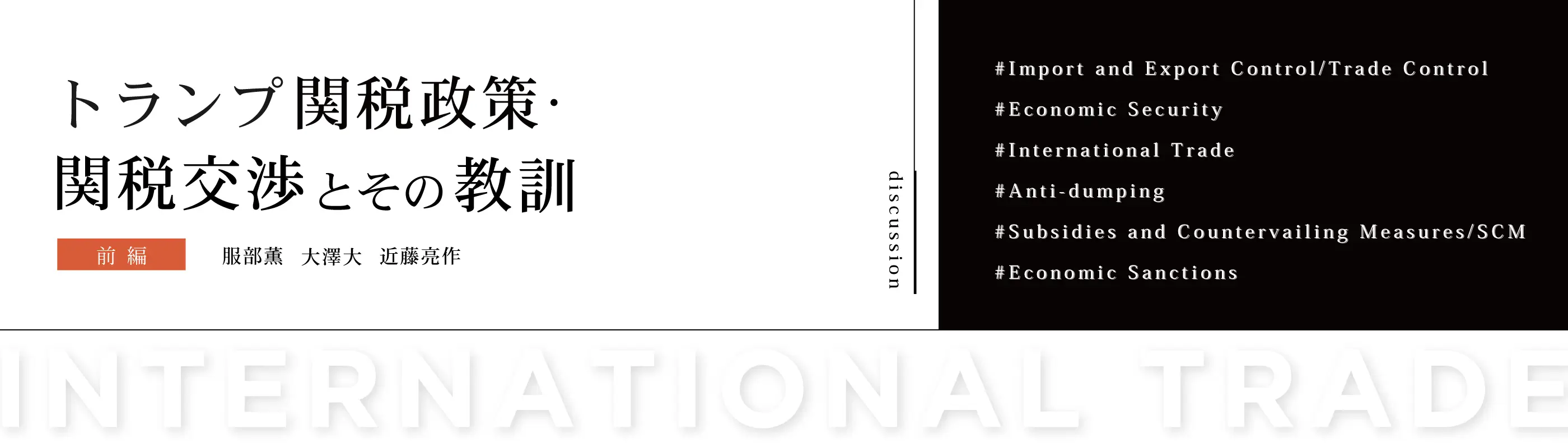

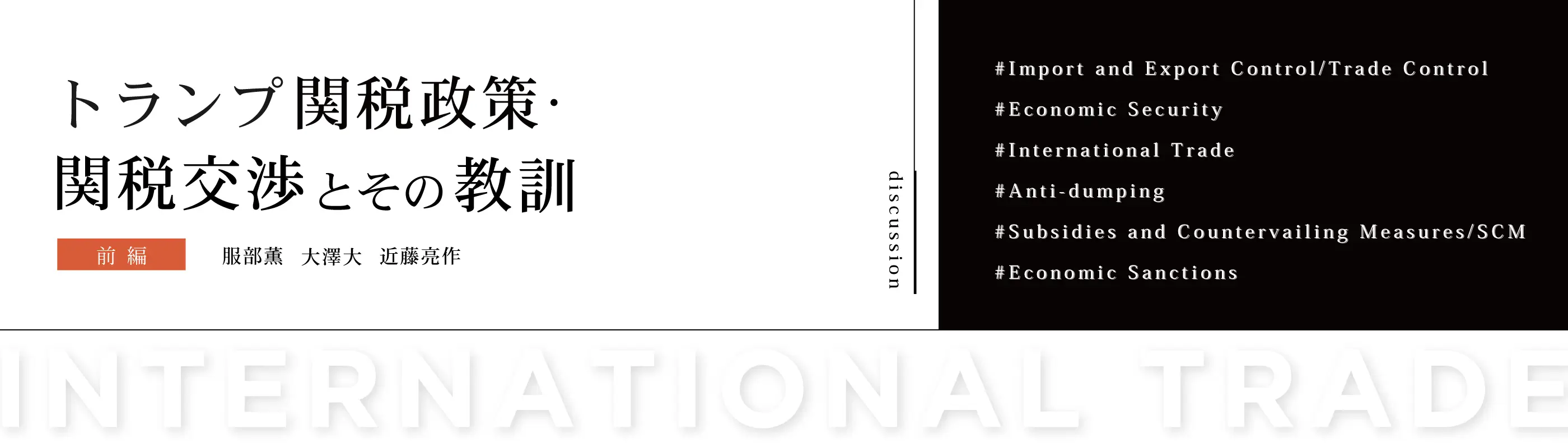

「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ大統領は、2025年1月の大統領再任直後、全ての国からの輸入品に対する関税の大幅な引き上げを発表しました。さらに、米国の貿易赤字が大きい国を対象に、「相互」関税の導入を宣言し、世界経済に大きな波紋を広げました。その後、各国との間で関税交渉が相次ぎ、日本も例外ではありませんでした。赤沢亮正担当大臣が複数回にわたり渡米して米国側と協議を行い、2025年7月には日米間で関税措置に関する合意が成立したことが発表されました。こうした第2次トランプ政権下での関税政策は、日本企業にとって重大な影響を及ぼすものでありながら、事前に内容を予測することが難しく、また、一度打ち出した施策も状況次第で見直されてしまうため、対応に苦慮した日本企業も多かったのではないかと思います。本座談会では、通商・関税実務に精通した服部薫弁護士・近藤亮作弁護士と、安全保障・経済安全保障の観点から企業実務に精通する大澤大弁護士が、トランプ政権下での関税政策とその交渉の経緯を振り返るとともに、それらを教訓として日本企業が何を学ぶべきかについても議論します。
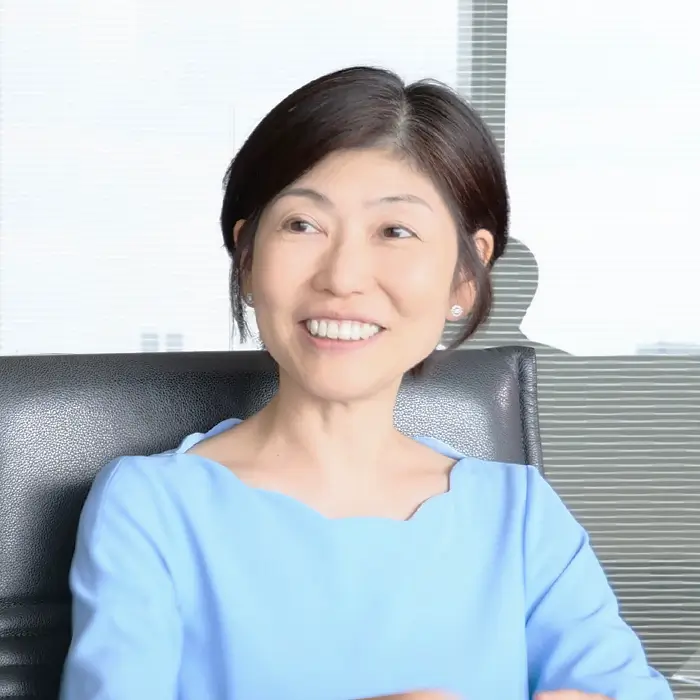
独占禁止法/競争法、下請法等の経済法、国際通商法(各国通商関連措置、アンチ・ダンピング等の貿易救済事案、サプライチェーン、経済安全保障ほか)に知見が深い。

M&A・コーポレートを中心に企業法務全般の助言を提供するほか、経済産業省にて外為法等に関わる立案、審査、規制執行、各国との連携強化等に関与した経験を活かし、経済安全保障全般のサポートを行う。近年は輸出管理や経済制裁の社内管理体制の構築支援も行う。

国際通商法・国際投資法、各国レギュレーション対応、競争法、紛争解決、コーポレート・M&A、労働法などの助言を提供。経済安全保障の分野での支援も行う。政府機関において内外での国際通商実務経験があり、追加関税問題にも詳しい。

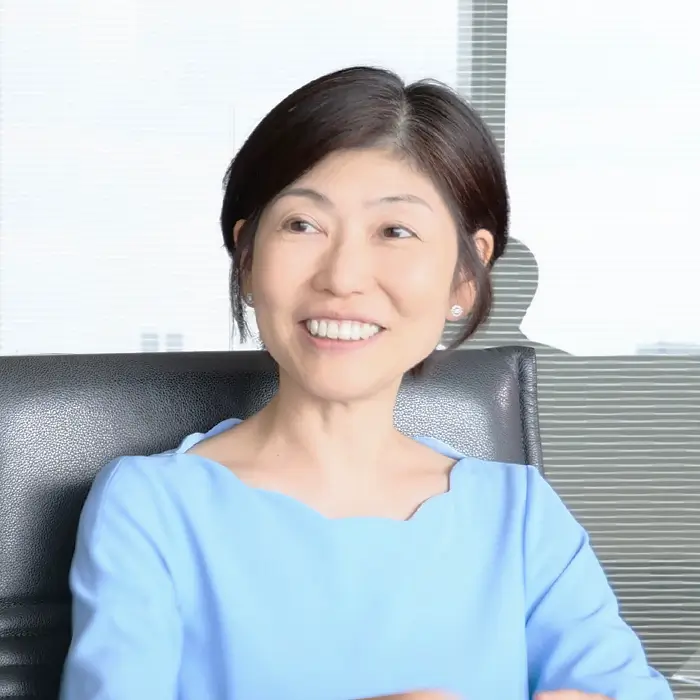
服部

近藤

大澤

近藤

大澤
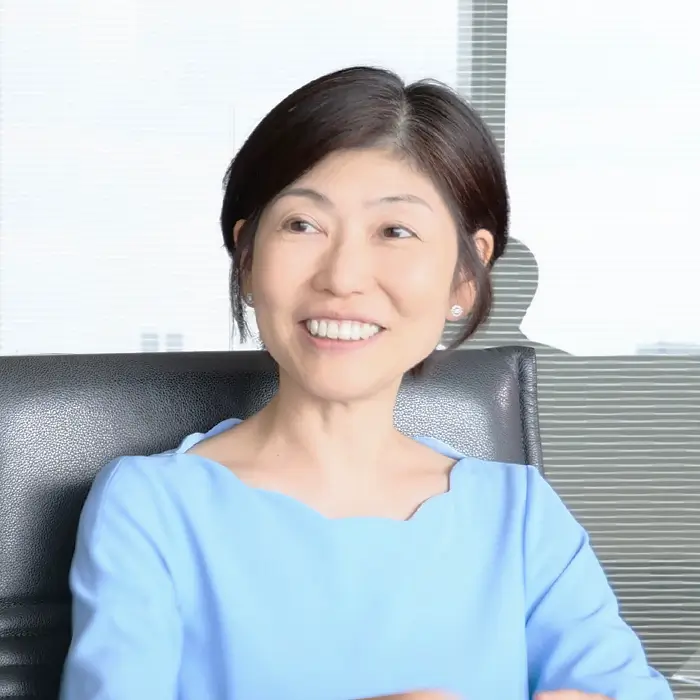
服部

近藤

大澤

近藤
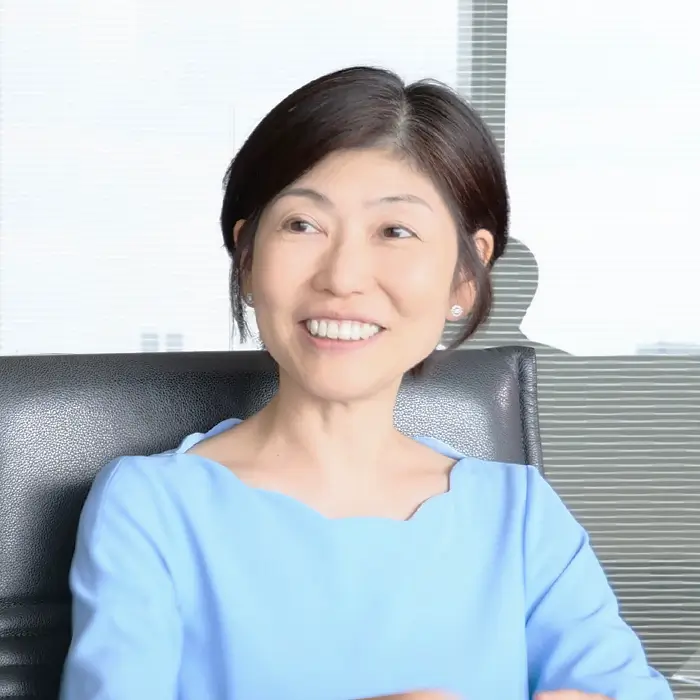
服部

大澤

近藤
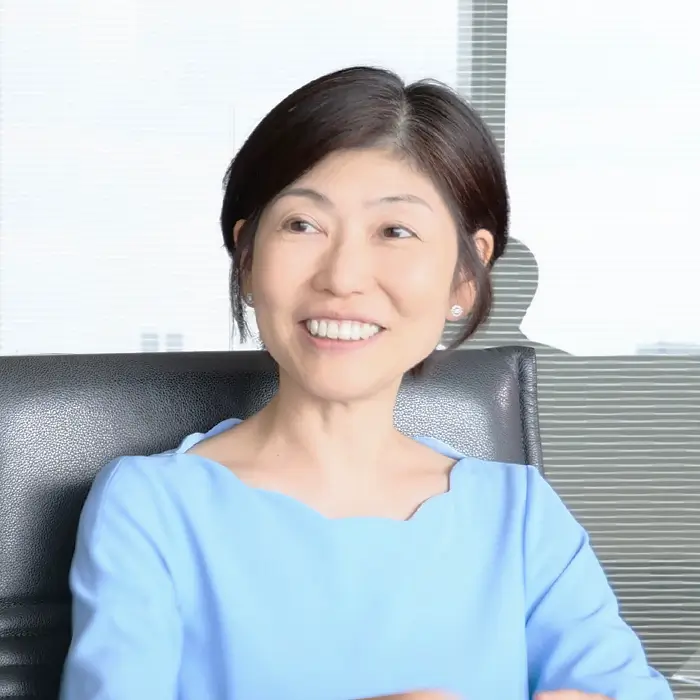
服部
各国との「合意」のタイムライン
| 相手国 | 合意日等 |
「相互」関税 修正後税率 |
主な内容 |
|---|---|---|---|
| 英国 |
5月5日 (大枠合意) 6月30日 (米英貿易協定発効) |
10% |
米国:自動車関税を10%に引き下げ(年間10万台まで)。鉄鋼・アルミ追加関税の引き下げ交渉を継続させる等。 英国:50億ドルの英国への輸出機会を創出等。 |
| ベトナム | 7月2日 | 20% |
米国:「相互」関税を20%にする一方、第三国からの積み替え品には40%を課す。 ベトナム:対米関税をゼロに。 |
| 7月8日 当初の交渉期限 | |||
| インドネシア | 7月15日 | 19% | インドネシア:対米関税をゼロに。 |
| 日本 | 7月22日 | 15%以下(*) | (下記参照) |
| フィリピン | 7月22日 | 19% | フィリピン:対米関税をゼロに。 |
| EU | 7月27日 | 15%以下(*) |
米国:自動車追加関税を含めて、追加関税を15%に引き下げ。 EU:重要な米国産品について関税を撤廃。今後3年間で米国から7500億ドル相当のエネルギーや半導体等の購入。6000億ドル相当の対米民間投資等。 |
| 韓国 | 7月30日 | 15% |
米国:「相互」関税、自動車追加関税ともに、15%へ引き下げ。 韓国:3500億ドル相当の対米投資(うち1500億ドルは造船)。1000億ドル相当のエネルギー購入。 |
| タイ | 7月30日 | 19% | 米国:「相互」関税を19%に。 |
| カンボジア | 7月30日 | 19% | 米国:「相互」関税を19%に。 |
| 7月31日 延長後の交渉期限 | |||
(*)既存MFN税率が15%を超える品目については、「相互」関税はゼロ。既存MFN税率が15%以下の品目については、「相互」関税は15% – 既存MFN税率。

近藤
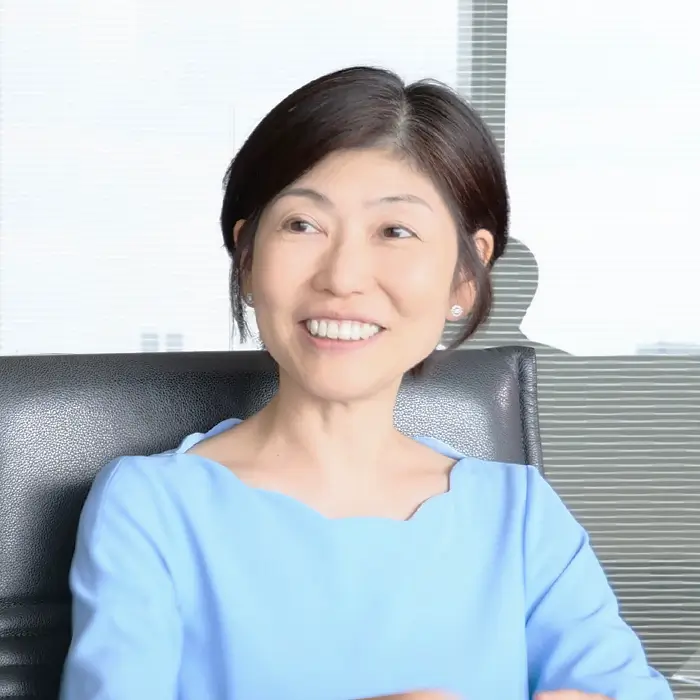
服部

近藤

大澤

近藤
| トピック・分野 |
日本側の発表 (内閣官房関税事務局) |
米国側の発表 (ホワイトハウスFact Sheet仮訳) |
|---|---|---|
| 半導体・医薬品 | 「仮に分野別関税が課される場合も日本を他国に劣後する形で扱わない。」 | (言及自体なし) |
| 日本による投資規模・方法・目的 |
「日本は、・・・政府系金融機関が最大5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供する。」 「日米がともに利益を得られる強靱なサプライチェーンを米国内に構築していくため。」 |
「5500億ドル以上の新たな日米投資ビークル」 「日本は、米国の指示に基づき、アメリカの基幹産業の再構築と拡大のために5500億ドルの投資を行う。」 |
| 日米がサプライチェーンを強靱化する分野等 | 「・・・鉄鋼、航空、自動車、AI・量子等」を含む分野等 | (これらの分野に言及なし) |
| 米国産米の輸入 | 「MA米制度の枠内で、日本国内のコメの需給状況等も勘案しつつ、必要なコメの調達を確保。」 | 「日本は米国産米の輸入を75%即時増加し、輸入割当を大幅に拡大する。」 |
| その他各種米国産品の購入 | 「バイオエタノール、大豆、トウモロコシ及び肥料等を含む米国農産品、及び半導体、航空機等の米国製品の購入の拡大。」 |
「日本はコーン、大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料を含む米国製品を80億ドル購入する。」 「日本は、ボーイング社製商用航空機100機を含む、米国製商用航空機を購入する。」 |
| 米国メーカー製乗用車の規制 | 「日本の交通環境においても安全な、米国メーカー製の乗用車を、追加試験なく輸入可能とする。」 | 「米国製の自動車及びトラックに対する長年の輸入制限が解除。米国自動車メーカーが日本の消費者市場にアクセスできるようになる。米国の自動車基準が日本で史上初めて許可される。」 |
| その他米国産工業品への非関税障壁の撤廃 | (言及自体なし) | 幅広い工業製品および消費財の市場開放により、米国生産者の競争条件が平等になる。 |

大澤


(服部薫弁護士、大澤大弁護士、近藤亮作弁護士)
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。