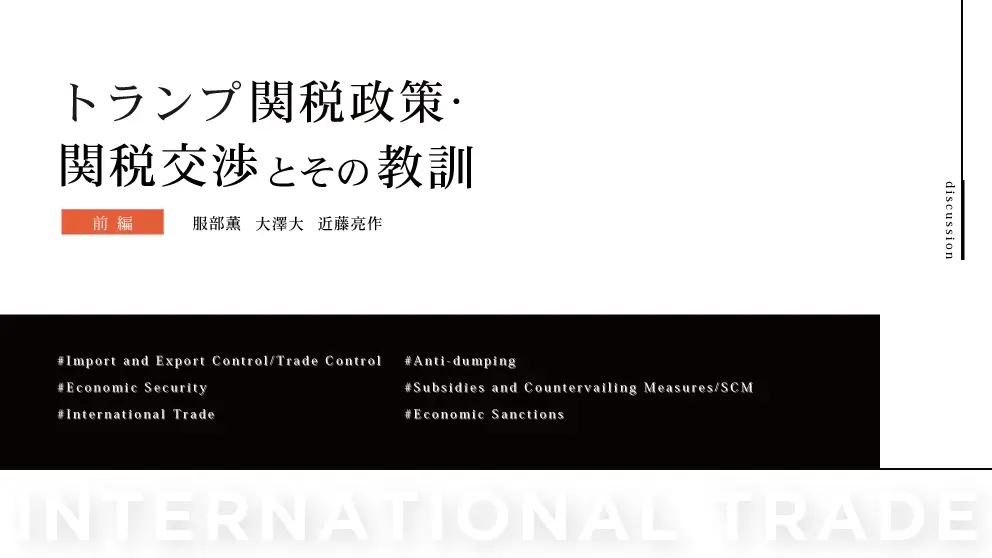
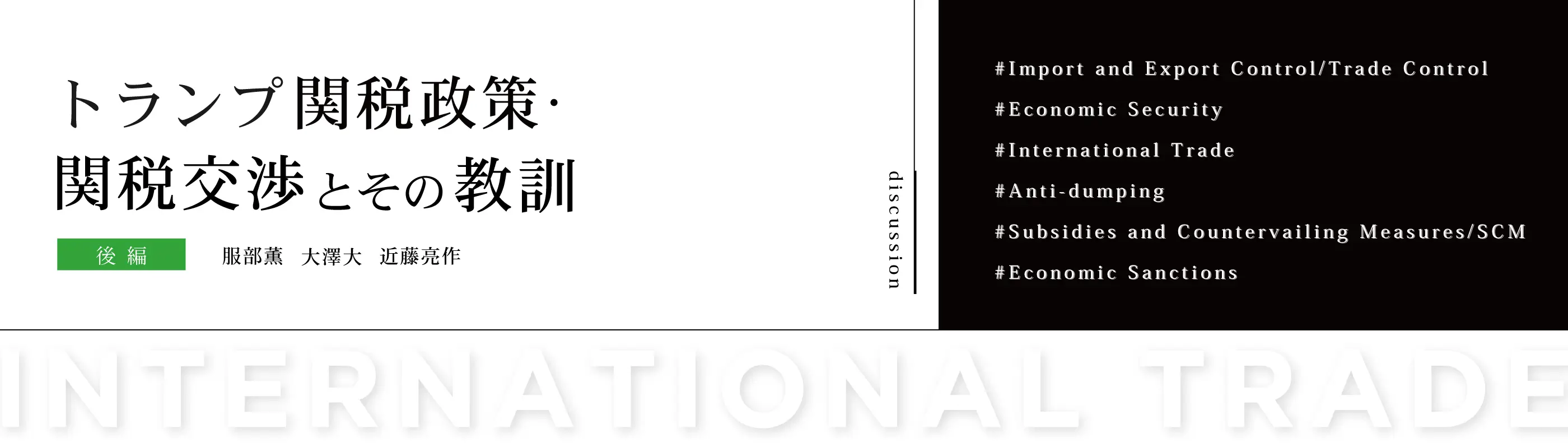

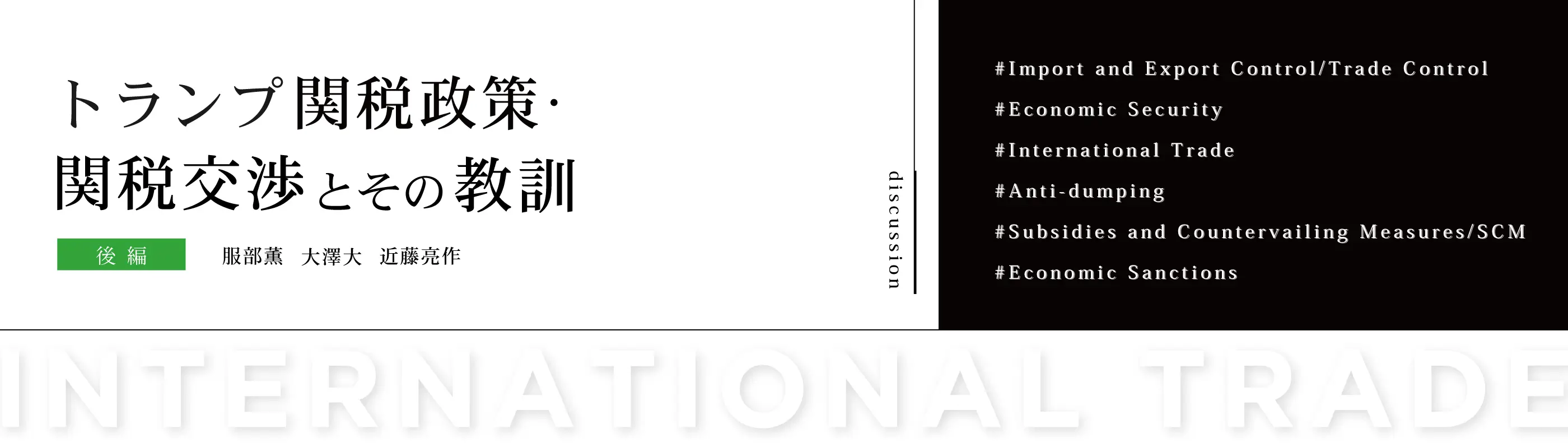

「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ大統領は、2025年1月の大統領再任直後、全ての国からの輸入品に対する関税の大幅な引き上げを発表しました。さらに、米国の貿易赤字が大きい国を対象に、「相互」関税の導入を宣言し、世界経済に大きな波紋を広げました。その後、各国との間で関税交渉が相次ぎ、日本も例外ではありませんでした。赤沢亮正担当大臣が複数回にわたり渡米して米国側と協議を行い、2025年7月には日米間で関税措置に関する合意が成立したことが発表されました。こうした第2次トランプ政権下での関税政策は、日本企業にとって重大な影響を及ぼすものでありながら、事前に内容を予測することが難しく、また、一度打ち出した施策も状況次第で見直されてしまうため、対応に苦慮した日本企業も多かったのではないかと思います。本座談会では、通商・関税実務に精通した服部薫弁護士・近藤亮作弁護士と、安全保障・経済安全保障の観点から企業実務に精通する大澤大弁護士が、トランプ政権下での関税政策とその交渉の経緯を振り返るとともに、それらを教訓として日本企業が何を学ぶべきかについても議論します。
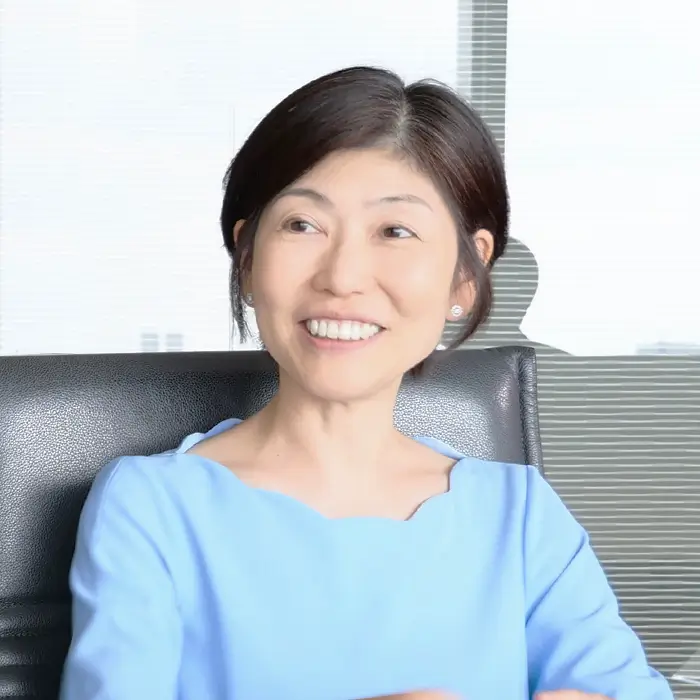
独占禁止法/競争法、下請法等の経済法、国際通商法(各国通商関連措置、アンチ・ダンピング等の貿易救済事案、サプライチェーン、経済安全保障ほか)に知見が深い。

M&A・コーポレートを中心に企業法務全般の助言を提供するほか、経済産業省にて外為法等に関わる立案、審査、規制執行、各国との連携強化等に関与した経験を活かし、経済安全保障全般のサポートを行う。近年は輸出管理や経済制裁の社内管理体制の構築支援も行う。

国際通商法・国際投資法、各国レギュレーション対応、競争法、紛争解決、コーポレート・M&A、労働法などの助言を提供。経済安全保障の分野での支援も行う。政府機関において内外での国際通商実務経験があり、追加関税問題にも詳しい。
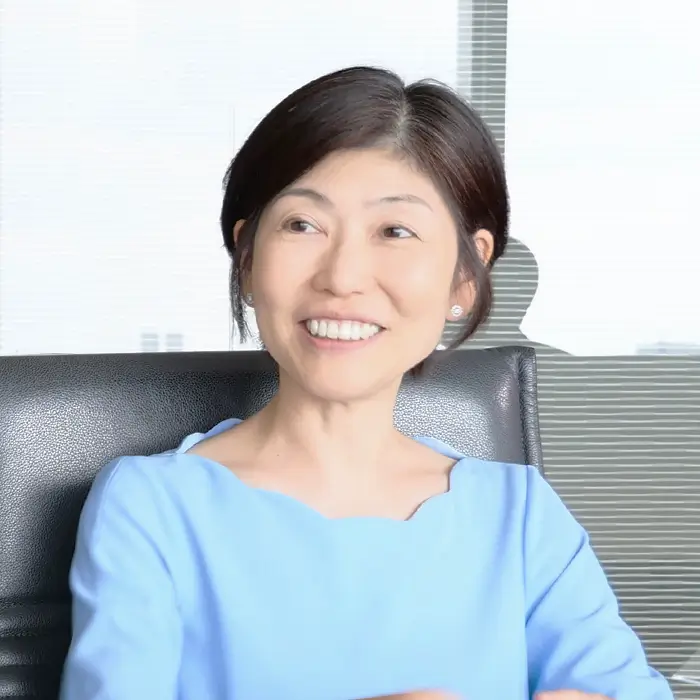
服部

近藤

大澤

大澤

近藤

大澤

近藤
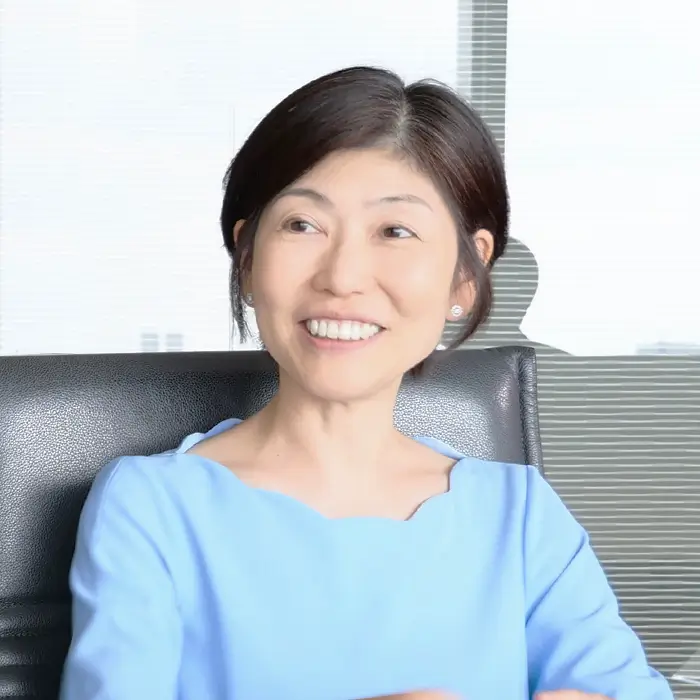
服部

近藤
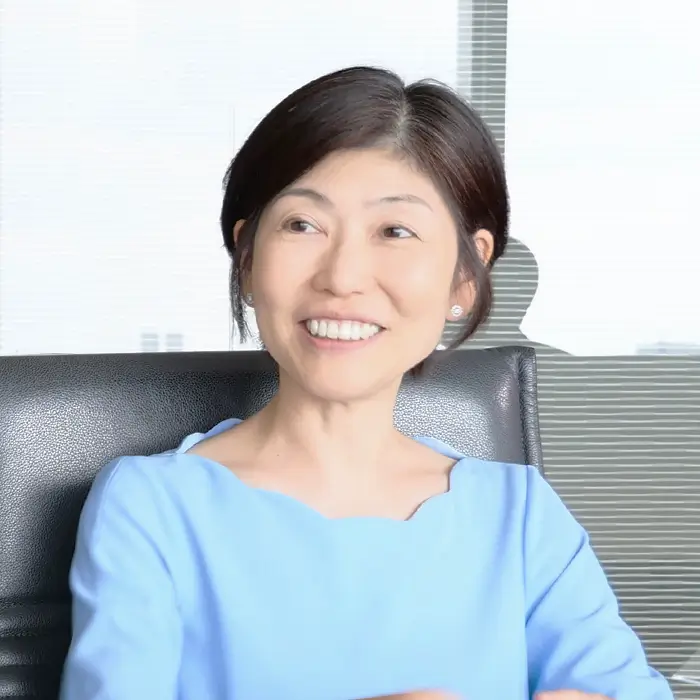
服部

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

大澤

近藤
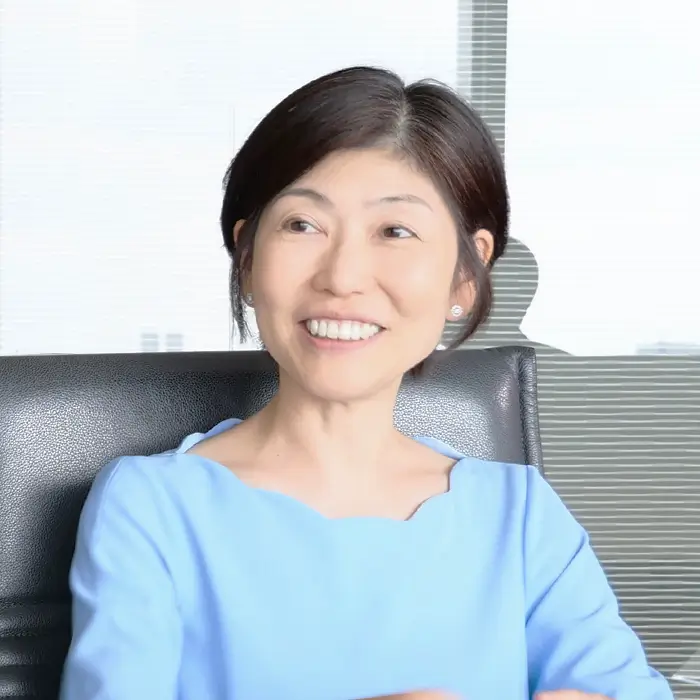
服部

近藤
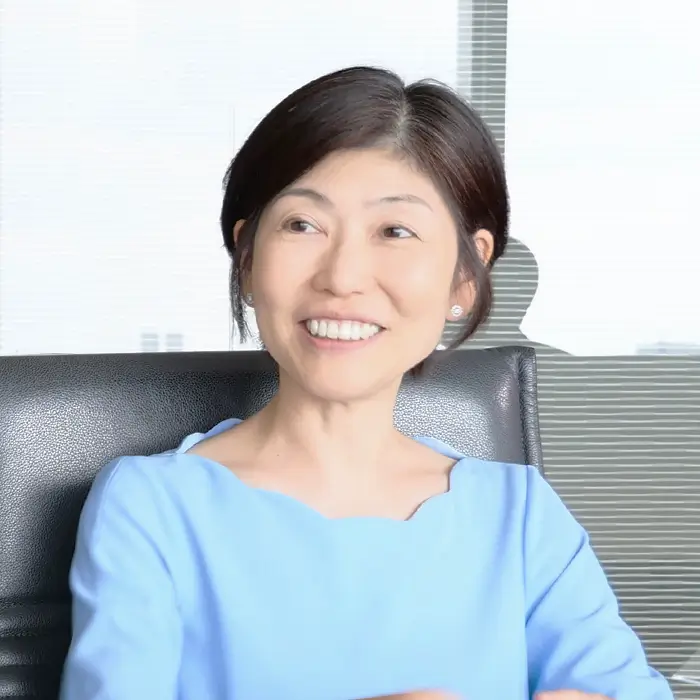
服部


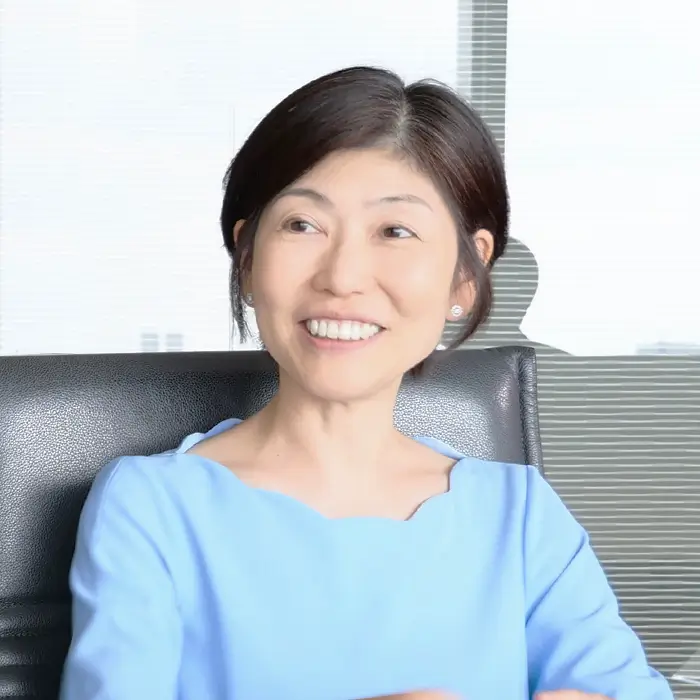
服部

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤
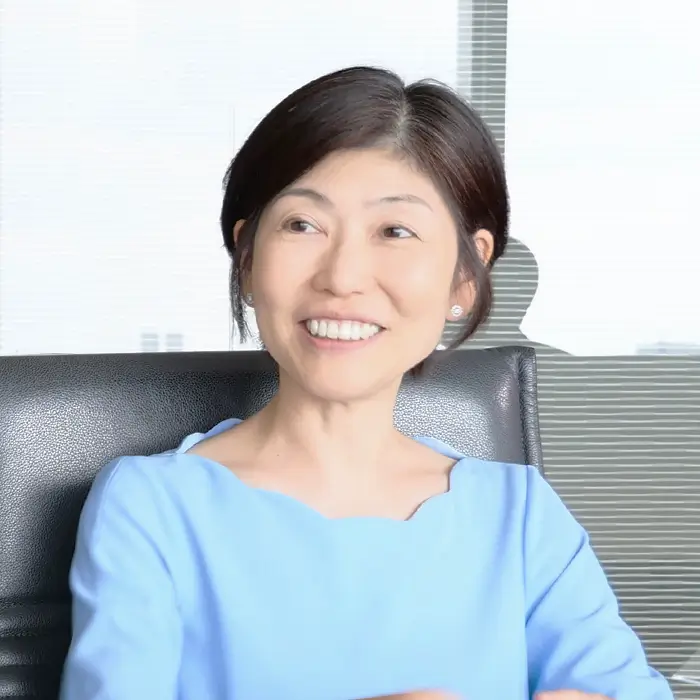
服部

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤

大澤

近藤
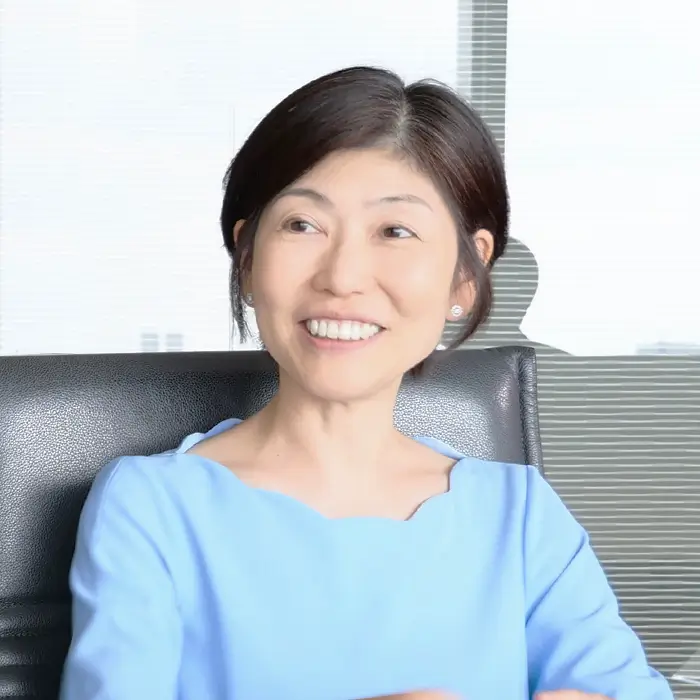
服部

大澤
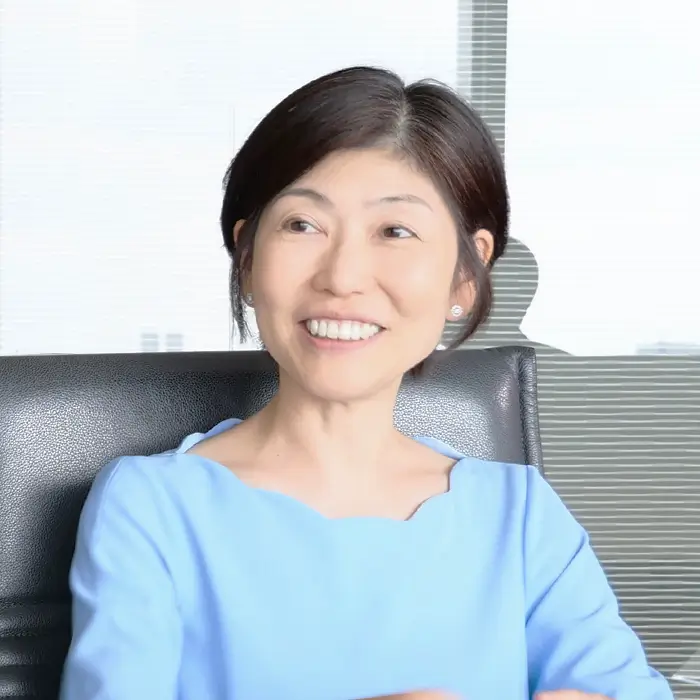
服部

大澤
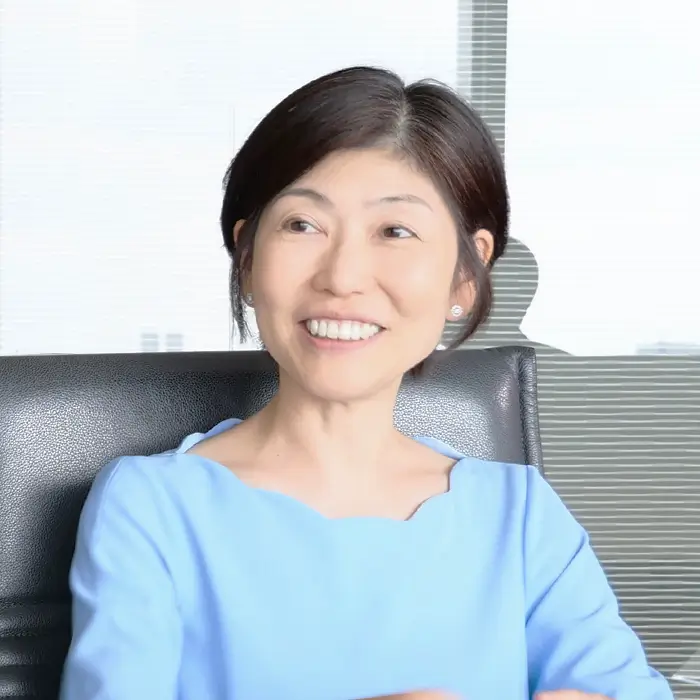
服部



本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。