
佐々木修 Shu Sasaki
パートナー
東京

NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
本ニュースレターでは、全3回に分けて内容をご紹介しています。第1回及び第2回は以下をご覧ください。
第1回:No.1(2022年3月)「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の内容(1) ―ステーブルコインの仲介者等に関する規制―」
第2回:No.2(2022年3月)「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の内容(2) ―為替取引分析業に係る規制―」
2022年3月4日、金融庁は、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本改正法案」といいます。)を国会に提出しました※1。
本改正法案は、2022年1月11日に公表された「金融審議会『資金決済ワーキング・グループ』報告」※2(以下「WG報告書」といいます。)で示された方向性を踏まえ、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)、金融商品取引法、銀行法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)その他の関係法令を改正しようとするものです。
本改正法案の主な内容は、①電子決済手段等への対応、②銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応、③高額電子移転可能型前払式支払手段への対応の3点であり、本稿では、③高額電子移転可能型前払式支払手段への対応を取り上げます。
①及び②については、すでに当事務所より配信しておりますニュースレターにて取り上げておりますので、①についてはこちら※3、②についてはこちら※4をご覧ください。
WG報告書は、IC型・サーバー型の第三者型前払式支払手段について大きく以下のように分類しています※5。
| 分類 | 概要 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | 小口決済型 |
電子的に譲渡・移転できず、少額のチャージ上限の下で、小口決済に使われる前払式支払手段 例:交通系ICカード |
| Ⅱ | 電子移転可能型 | 電子的な譲渡・移転が可能な前払式支払手段 |
| (1)残高譲渡型 | 発行者が管理する仕組みの中でアカウント間での前払式支払手段の残高譲渡が可能なもの | |
| (2)(広義の)番号通知型 |
(ア)(狭義の)番号通知型: 発行者が管理する仕組みの外で前払式支払手段である番号等の通知により、電子的に価値を移転することが可能なもの 例:メール等で通知可能な前払式支払手段(ID番号等)を用いてアカウントにチャージする電子ギフト券 |
|
|
(イ)(ア)に準ずるもの: 残高譲渡型及び(狭義の)番号通知型以外のものであって、発行者が管理する仕組みの外で、チャージ済のアカウント残高(前払式支払手段)の利用権と紐づくものとして発行者から付与された番号等を他者に通知することにより、当該他者に対し、当該残高(前払式支払手段)を容易に利用させることが可能であり、かつ、その利用範囲が多数かつ広範囲に及ぶものとして法令に個別に規定するもの 例:国際ブランドのクレジットカードと同じ決済基盤で利用することができるプリペイドカード(いわゆる国際ブランドの前払式支払手段) |
現在、前払式支払手段については、犯収法に基づく取引時確認(本人確認)義務や疑わしい取引の届出義務等は課されていませんが、前払式支払手段についてAML/CFT規制の観点から問題が指摘されていることを受けて、本改正法案では、上記の電子移転可能型を対象として、「高額電子移転可能型前払式支払手段」という分類を設け、取引時確認(本人確認)や疑わしい取引の届出義務等の対象とすること、及び、その発行者に対して、資金決済法上の登録申請書への記載や、業務実施計画の届出を求めることとしています。本改正法案の具体的な内容を以下で解説いたします。
本改正法案は、改正資金決済法3条で、以下のとおり「高額電子移転可能型前払式支払手段」の定義を新設しています(※下線等による強調は筆者らにて追加)。
8 この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
9 この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
上記の定義を踏まえますと、「高額電子移転可能型前払式支払手段」の要件は以下のとおりであると考えられます。
前払式支払手段のうち、第三者型のものが対象になります。
「未使用残高」は、金額表示型の前払式支払手段(改正後資金決済法3条1項1号)については、その金額(代価の弁済に充てることができる金額)、また、物品・役務の数量表示型の前払式支払手段(同項2号)については、「給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額」を意味します。
また、その未使用残高は、改正後資金決済法3条9項に定める「前払式支払手段記録口座」に記録される必要があります。「前払式支払手段記録口座」とは、上記規定のとおり、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座であって、かつ、当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものとされており、その詳細は今後内閣府令において定められることになります。なお、未使用残高の上限額は、WG報告書では「例:30万円以内」とされていますので※6(同48頁)、30万円程度となることが予想されます。また、WG報告書では、「アカウントは繰り返しのチャージ(リチャージ)が行えるものに限る」との要件も提案されていますので※7、「その他内閣府令で定める要件」として、同要件が内閣府令に定められることが予測されます。
ここでは、前払式支払手段自体が電子情報処理組織を用いて移転可能であることが要件となっていますので、上記の分類における(1)残高譲渡型及び(2)(ア)(狭義の)番号通知型が対象となるものと考えられます。なお、規約等において譲渡等を禁止している場合でも、利用者がこれに反して事実上譲渡等を行うことが可能である場合には、この要件に該当するものと考えられます※8。
これに対して、いわゆる国際ブランドの前払式支払手段等の上記(2)(イ)(狭義の)番号通知型に準ずるもので、前払式支払手段自体を電子的に譲渡できるものではない場合には※9、本③の要件は充足しないものと考えられます。もっとも、そのような前払式支払手段についても、改正資金決済法3条8項2号に定める同項1号に「準ずるものとして内閣府令で定めるもの」として規制の対象となる可能性があるものと思われます。
「移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件」を満たすものが対象となります。
この具体的な内容については、内閣府令で定められることになりますが、(1)残高譲渡型及び(2)(ア)(狭義の)番号通知型についてのWG報告書の提案内容※10が参考になりますので、その内容を紹介します。
| 分類 | 提案された要件案 |
|---|---|
| (1)残高譲渡型 | 他のアカウントに移転できる額が一定の範囲を超えるもの(例:1回当たりの譲渡額が10万円超、又は、1か月当たりの譲渡額の累計額が30万円超のいずれかに該当) |
| (2)(ア)(狭義の)番号通知型 | メール等で通知可能な前払式支払手段(ID番号等)によりアカウントにチャージする額が一定の範囲を超えるもの(例:1回当たりのチャージ額が10万円超、又は、1か月当たりのチャージ額の累計額が30万円超のいずれかに該当) |
改正資金決済法3条8項2号に定める同項1号に「準ずるものとして内閣府令で定めるもの」も、「高額電子移転可能型前払式支払手段」に該当するとされています。具体的な定義の内容は内閣府令に委任されており、明らかではありませんが、上述のとおり、いわゆる国際ブランドの前払式支払手段等の(2)(イ)(狭義の)番号通知型に準ずるものがその対象に含まれる可能性があるものと思われます。(2)(イ)(狭義の)番号通知型に準ずるものについては、WG報告書で以下のとおりアカウントへのチャージ額・利用額について一定の要件を定めることが提案されていますが、かかる点は、改正資金決済法3条8項2号に基づき「高額電子移転可能型前払式支払手段」として規制対象となる要件として参考になると思われます。
| 分類 | 提案された要件案 |
|---|---|
| (2)(イ)上記(ア)に準ずるもの | アカウントへのチャージ額・利用額が一定の範囲を超えるもの(例:1か月当たりのチャージ額の累計額、1か月当たりの利用額の累計額のいずれもが30万円超) |
改正資金決済法11条の2は、前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、以下に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣総理大臣に届け出なければならないこととし(第1項)、また、届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届けなければならないこととしています(第2項)。なお、当該届出を行わなかった又は虚偽の届出をしたときには、30万円以下の罰金の対象になります※11。
具体的な内容については、内閣府令で定められることになりますが、WG報告書では、「利用者保護等の観点を踏まえ、商品性、システムによる対応事項、モニタリング手法、不正利用等が生じた場合の利用者に対する対処方針等」の記載を求めることが提言されていますので※12、それらの事項が内閣府令に具体化されることが予想されます。
高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する事業者について取引時確認(本人確認)や疑わしい取引の届出義務等の対象とするため、犯収法についても、本改正法案の対象とされ、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する者として上記の届出をした者は、「特定事業者」に該当するものとされました※13。そのため、現在、前払式支払手段の発行者は犯収法の規制対象となっていませんが、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する場合には、犯収法上の規制を受けることになります。
本改正法案は、その施行日について、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」としていますが※14、本改正法案の施行の際に高額電子移転可能型前払式支払手段を現に発行している者については、改正資金決済法11条の2の規定を施行日から起算して2年間は適用しないものとしています※15。したがって、既存の前払式支払手段の発行者が、高額電子移転可能型前払式支払手段に該当する前払式支払手段を発行している場合であっても、改正資金決済法に基づき業務実施計画を定め、内閣総理大臣に届け出るまでには相応の猶予が設けられているといえます。そして、猶予を受けている間は、その事業者は上記届出を行っていないため、(高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する者として上記の届出をした者と定められた)「特定事業者」に該当せず、犯収法上の規制対象とならないものと思われます。
WG報告書においては、上記の点以外に、(広義の)番号通知型について、対象を高額のものに限るのではなく、少額の取引を含めた上でリスクベースでの取り組みが求められると考えられるとし、不正利用防止等の観点から、(1)の残高譲渡型と同様に価値移転に焦点を当てた体制整備等を求める趣旨で、以下の提言も行っています※16。
上記の点については、本改正法案に明示的には含まれていないようですが、かかる点の規制動向についても引き続き注意する必要があります。
本改正法案では高額電子移転可能型前払式支払手段に対する規制強化がなされており、現在犯収法の規制対象となっていない前払式支払手段の発行者についても、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する場合には、犯収法上の規制を受けることとなる点で実務上も重要な改正であると思われます。もっとも、その具体的な内容については内閣府令に委任された箇所も多く、内閣府令がどのような内容となるかは注視する必要があります。
※5
WG報告書36頁~38頁参照。
※6
WG報告書48頁
※7
WG報告書47頁
※8
WG報告書47頁注154
※9
WG報告書48頁注159
※10
WG報告書48頁
※11
改正資金決済法114条1号
※12
WG報告書51頁
※13
改正犯収法2条2項30号の2
※14
本改正法案附則第1条
※15
本改正法案附則第2条
※16
WG報告書39頁、40頁
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


工藤靖


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
犬飼貴之


(2025年7月)
清水音輝(インタビュー)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(監修)、糸川貴視、大野一行(共著)
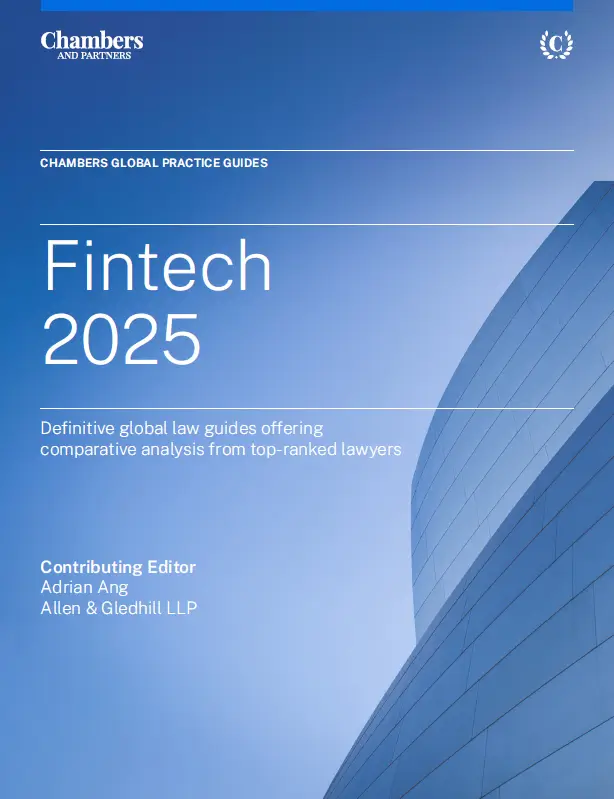
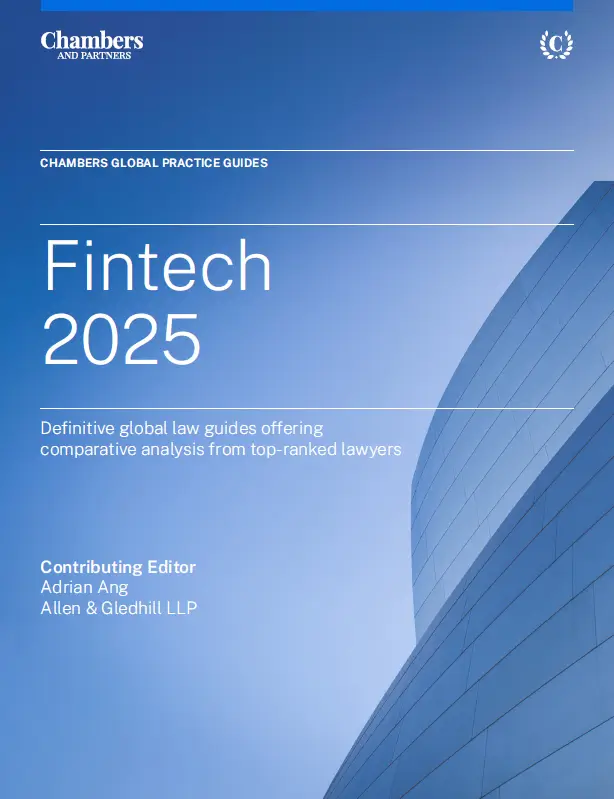
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)