
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
今年3月の当事務所ニュースレター※1でも取り上げた通り、2020年にNBAがスポーツ業界ではいち早くサービスを開始して以降、世界中の多くのプロスポーツリーグ・チームやスポーツ団体等に関係するNFTが販売されています。現時点では、例えば日米の主要なリーグだけでも、下表のものがあげられます。
【日米の主要なリーグに関するデジタルコレクティブル】
| サービス名 | リーグ | サービス運営者 | コンテンツの内容 |
|---|---|---|---|
| NBA Top Shot | NBA/WNBA | Dapper Labs | 選手のプレー・ハイライト動画等 |
| NFL ALL DAY | NFL | Dapper Labs | 選手のプレー・ハイライト動画等 |
| ToppsNFTs | MLB | Topps | 選手の画像やスタッツ等 |
| J.LEAGUE NFT Collection Players Anthem | Jリーグ | 楽天グループ | 選手のプレー・ハイライト動画等 |
| B.LEAGUE PARK | Bリーグ | ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | 選手の画像やプレー・ハイライト動画等 |
|
パ・リーグ Exciting Moments β※2 |
パ・リーグ (日本プロ野球) |
パシフィックリーグマーケティング / メルカリ | 選手のプレー・ハイライト動画等 |
リーグ・チーム等のライツホルダーが特定のサービス運営者に対して独占的なライセンスを与える等しない限り、同一のリーグ・チーム等に関して複数のサービス運営者から異なるNFTが販売されるケースもあります。例えば、MLBに関しては、上表のTopps以外に、Candy Digitalも選手のプレー・ハイライト動画等のNFTを取り扱っています。
また、スノーボードのショーン・ホワイト選手、平野歩夢選手、クロエ・キム選手等、ウィンタースポーツのスター選手の画像・動画等のNFTを販売するnWayのApex Athleteのように、リーグ・チームスポーツのみではなく、個人競技の選手に関するNFTも取引されています。特に、スノーボード、スケートボード等のアクションスポーツは、クールなトリックの瞬間等を短い動画で収めやすく、ファンもデジタルネイティブの若い世代が多い等、NFTと非常に相性がよいスポーツといえます。今後も、リーグ・チーム単位のものに限らず、個々の選手やイベント等に関するNFTも増えていくことが予想されます。
NFTの法的性質や取引をめぐる法律関係が現在の法令上は自明ではないこと等から、プラットフォームの利用規約等による補完を含め、選手やリーグ・チーム等、プラットフォーム、購入者等の関係者間の権利関係の整理が重要であることは冒頭記載のニュースレターでも触れた通りです。本稿では、その中でも、選手やリーグ・チーム等がNFTを発行するサービス運営者との間で締結するライセンス契約について、一般的な権利関係を説明した上、具体的な契約上のポイントを取り上げたいと思います。
選手の画像・動画等のNFTを制作・発行するにあたっては、選手や(後述のようにリーグ・チーム等に権利が与えられている場合には)リーグ・チーム等が自ら制作者・発行者となるケースもありますが、選手やリーグ・チーム等が、NFTの制作・発行を取り扱うサービス運営者等とライセンス契約を締結して、そのサービス運営者等がNFTの制作・発行を行うケースも多いと考えられます。この場合のライセンス契約は、伝統的な紙ベースのトレーディングカードやビデオゲーム、グッズ等の商品化の場合と同様に、商品化権のライセンス契約の一種であると考えることができます。
商品化権とは、選手やチーム・リーグ等の氏名・名称、肖像、ロゴ、マスコット等を利用した商品を製造・販売する権利です。もっとも、商品化権は、商標権や著作権のように特定の法律に基づき認められる固有の権利というわけではなく、その具体的な法的性質としては、主に、商標権、肖像権・パブリシティ権、著作権等であると考えられます。
すなわち、商品化権のライセンスとは、ケースに応じて、通常これらのいずれかの権利のライセンスであり、選手やチーム・リーグ等からライセンスを受けずに無断でNFTの制作・発行を行った場合には、これらの権利の侵害として違法となる可能性があります※3。
これらを踏まえ、選手の画像・動画等のNFTに係るライセンス契約は、選手の画像・動画等に係る商品化権をライセンスする権限を有する者(以下「ライツホルダー」といいます。)と、当該NFTの制作・発行を行おうとする者(以下「ライセンシー」といいます。)との間で締結される必要があります。
ライツホルダーについて、具体的には、選手の画像・動画の使用許諾は、通常、選手の肖像権・パブリシティ権のライセンスであると考えられるところ、これらの権利は原則として選手個人に帰属します。もっとも、選手契約やリーグ・大会の規約等によって、チーム・リーグや大会主催者等にライセンス権限が与えられている場合もあります。また、チーム・リーグのユニフォームやチームロゴ等を使用する場合にはチーム・リーグからのライセンスが必要になり、実際にNFTに使用する画像・動画自体の著作権については著作権者からのライセンスが必要になります。
一般論として、NFTの制作・販売のライセンスについては、NFTの法的性質や取引をめぐる法律関係が法令上自明ではなく、また、関係者間でも必ずしも共通理解があるとは限らないことから、誤解やトラブルが生じないよう、ライセンス契約上で明確にしておくべきポイントが多いといえます。すなわち、単に「選手等の画像・動画を使用したNFTの制作・販売をライセンスします」という一言だけでは、その具体的な意味や範囲が法令上も実務上も必ずしも定まっておらず、法律関係が不明確になるリスクがあるということです。
特に、NFTの特殊性も踏まえて、NFTの具体的な内容や使用方法、NFTを販売するプラットフォーム、二次流通時の取扱い等については、明確化しておく必要性が高いと考えられます。
この点、一般的に、利用者との関係では、プラットフォーム上でのNFTの購入や売却に関しては、プラットフォームの定める利用規約において、利用者とプラットフォームの間の法律関係のみならず、利用者に対するライセンス条件の他、利用者相互間の二次流通時の売買に係る法律関係についても規定されることになると考えられます。これに対して、ライツホルダーとプラットフォーム(ライセンシー)の間では、通常、個別にライセンス契約が締結されるケースが多いでしょう。
もっとも、後者のようにライツホルダーには直接に利用規約が適用されないケースであったとしても、前者の通り、プラットフォーム上でのNFTの販売・流通や使用は利用規約に定める条件に従うことからすれば、ライツホルダーとしても、プラットフォームの利用規約には一定の利害を有するものといえます。
例えば、NFTの購入者がどのような権利を持つのかという点は、通常、利用規約において明確化が図られますが※4、その内容は、そもそも当該NFTがどのような「商品」なのか、すなわちライセンス対象の商品は何なのかという点と密接に関連すると考えられます。また、NFT一般の特徴であり、ライツホルダーにとって重要なメリットとなりうる、二次流通時に発行者に利益の一部が還元される仕組みに関しても、その採否や具体的な内容についてプラットフォームの利用規約に定められることが通常です。いずれも詳しくは下記3.で説明しますが、一般論としては、ライツホルダーとしても、ライセンス契約と利用規約との関係には留意した方がよいといえるでしょう。
伝統的な紙ベースのトレーディングカード等とNFTのいずれの場合でも、商品化ライセンスの具体的な対象製品の明確化が重要であることに変わりはありません。しかし、NFTの場合、単に画像・動画を見て楽しんだりコレクションしたりという用途に限らず、オンラインゲームやメタバース内でのアイテムやアバターとしての使用等、他のサービスと連携して様々な形で使用される可能性があります。そのため、ライセンス契約においては、対象のNFTがどのようなサービス・用途に使用されうるものかを踏まえて、ライセンス対象製品を明確化すること(例えば、ライセンス対象製品を単に「NFT」と定めるのみではなく、「ゲーム内アイテムとしても使用可能なNFT」又は「NFT及びこれを使用したゲーム内アイテム」と定めること等)も考えられます。
また、上記2.(2)で述べた通り、プラットフォームの利用規約上でNFTの購入者に与えられる権利の内容は、ライセンス契約上で対象製品とされるNFTの具体的な内容と密接な関係にあると考えられます。その観点からは、ライセンス契約に定めるライセンス対象製品の内容や範囲と、利用規約に定めるNFTの購入者に与えられる権利の内容や範囲には、齟齬が生じないようにすることが望ましいでしょう。
商品化ライセンス契約の場合、ライセンス対象製品の範囲に含まれさえすれば自由に制作・販売が可能というわけではなく、具体的な製品の仕様・デザイン等については、ライセンシーから提出されたサンプルの確認等を経て、ライツホルダーの承認が必要とされるケースが通常です。NFTの場合、例えば動画等であればその編集・装飾等の余地が大きいことに加えて、上記の通り用途が多様になりうることからも、ライツホルダーとしては、自己のイメージやブランディング等の観点から、具体的な仕様・デザイン等について承認権を持ち、十分なコントロールを及ぼしたいケースは多いといえるでしょう。
伝統的な紙ベースのトレーディングカード等の場合には、その具体的な販路についてまではライツホルダーの関心が高くないケースも多いと考えられます。しかし、NFTの場合、NFTがライセンシーにより当初に販売され、さらに二次流通の場ともなるプラットフォームをどこにするかは、ライツホルダーにとっても重要な関心事となりえます。上記2.(2)で述べた通り、二次流通時に発行者に利益の一部が還元される仕組みの採否や内容を含め、プラットフォーム毎にNFTの取扱いに関する具体的条件が異なりうるためです。また、ライツホルダーのイメージやブランディング等の観点から、プラットフォームの利用規約の内容等に限らず、プラットフォームの信用、人気、仕様等についても一定の考慮をすべき場合もありえます。
これらを踏まえると、ライツホルダーの立場からは、ライセンス契約において、少なくともNFTがライセンシーにより当初に販売されるプラットフォームについては、具体的に特定し、又はその選択についてライツホルダーの承諾を必要としておくことが考えられます。これに対して、二次流通の当事者はいずれもライツホルダーと直接の契約関係に立たない者ですので、二次流通に利用するプラットフォームについて、ライツホルダーが当該当事者を直接に拘束することは困難と考えられます。もっとも、ライツホルダーとしては、ライセンシーが当初に販売を行うプラットフォームの利用規約やNFT・サービスの仕様等を通じて、特定のプラットフォーム上での二次流通のみ可能とするよう、ライセンス契約上でライセンシーに約束させることは検討しうると思われます。
商品化ライセンス契約の場合、ライツホルダーは、通常、ライセンシーによる対象製品の制作・販売についてロイヤリティを受け取ることになりますが、NFTの場合、ライツホルダーは、これに加えて、二次流通時にもロイヤリティを受け取れる可能性があります。NFTの特徴を活かして、二次流通時に発行者に利益の一部が還元される仕様にすることが可能であり、この場合には、その利益の還元を受けた発行者であるライセンシーからライツホルダーに対する一定のロイヤリティの支払が合意されることが通常であるためです。
その場合、ライセンス契約上は、ライセンシーによる当初の販売に係るロイヤリティと二次流通に係るロイヤリティについて、区別して整理することが有益と考えられます。前者に係る販売価格・規模はライセンシーがコントロールでき、かつ、その売上の全額をライセンシーが収受する一方、後者の二次流通の価格・規模は市場において決せられ、また、ライセンシーが収受する利益はあくまで売買価格の数%程度の手数料のケースが多い等、両者は経済的なメカニズム等が異なるためです。
この二次流通時の発行者、ひいてはライツホルダーへの利益の還元が行われるか否かは、繰り返し述べた通り、基本的には二次流通が行われるプラットフォームによります。この観点からも、上記(2)末尾で述べた二次流通時のプラットフォームに関する取り決めは、ライツホルダーにとって重要になりうると考えられます。
この点はNFTの場合に限りませんが、NFTに使用する画像・動画等をライツホルダーからライセンシーに提供する場合、ライツホルダーとしては、その画像・動画等について自らが権利を有しており、第三者の知的財産権等の権利を侵害しないか、十分に留意する必要があります。例えば、選手自ら撮影した画像・動画であったとしても、他人が写り込んでいないか(第三者の肖像権等を侵害しないか)、大会中の画像・動画である場合には大会のルール等でその提供が制限されていないかといった点は、確認する必要があります。
ライツホルダーが提供した画像・動画等について、ライツホルダーが権利を有しており、第三者の権利を侵害しないものであることは、ライセンス契約上、ライツホルダーによる表明保証を求められることも一般的です。これに対応して、当該画像・動画等の使用により第三者の権利を侵害し、当該第三者からライセンシーに対して損害賠償請求等がなされたような場合には、ライツホルダーがライセンシーの損害等を補償する義務が課せられることも珍しくありません。これらのことからも、ライツホルダーとして、自ら提供する画像・動画等の権利関係については、事前の確認を尽くすことが重要となります。
NFTに限らず、スポーツビジネスにおける商品化ライセンス契約一般の観点からは、相互に、相手方の著しいイメージ低下を招く不祥事等が発覚した場合の対応を規定しておくことも検討に値します。ライツホルダーの不祥事等が発覚した場合には、ライセンシーとして、期待していた売上が達成困難となることが想定されますし、ライセンシー(又は関連するプラットフォーム)の不祥事等が発生した場合、ライツホルダー自らのイメージやブランドにも悪影響が及びうるためです。
その他、本稿で個別に解説はしませんが、商品化ライセンス契約においては、一般的に、ライセンス期間、対象地域、ロイヤリティの計算・支払方法や最低保証の有無、契約終了後に在庫を販売できるsell-off期間、販売数等の報告、帳簿の作成・保管と監査権、著作権等の表示、PL保険の有無、独占的なライセンスか否かといったポイントが重要となります。スポーツNFT/デジタルコレクティブルに係るライセンス契約の交渉に際しては、これらの一般的なポイントとNFT特有のポイントの両観点からの検討が必要といえるでしょう。
※1
当事務所のテクノロジー法ニュースレター2022年3月No.11 松尾博憲=宮城栄司=加藤志郎著「<NFT/Web3 Update> スポーツビジネスにおけるNFT・トークンの活用方法と法的な留意点」
※2
但し、本サービスについては、現時点ではブロックチェーンを使用しておらず、今後、ブロックチェーンを活用したサービスを提供予定とされています。
※3
他に不正競争防止法による保護も及ぶ場合があります。
※4
典型的には、NFTが表彰する画像・動画等のデータを一定の範囲で私的に利用する権利のみが与えられます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
関口朋宏(共著)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒、糸川貴視、大野一行(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
関口朋宏(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
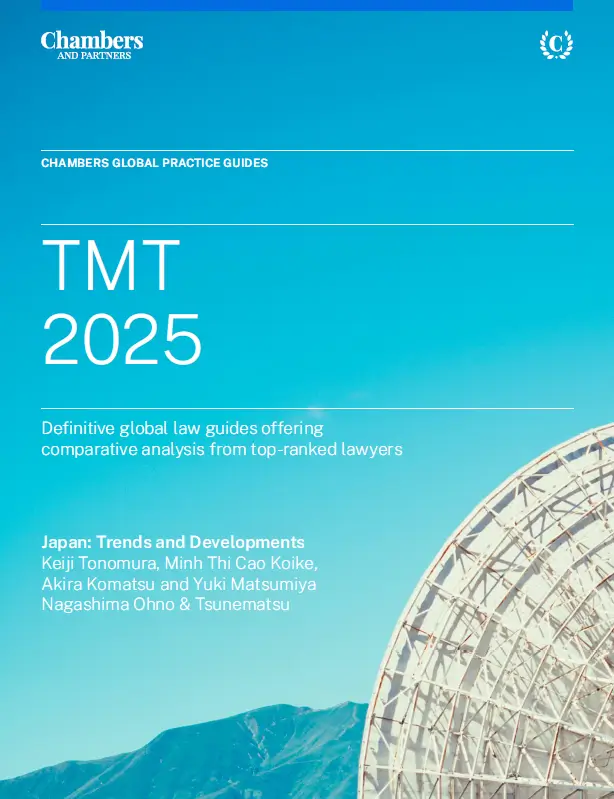
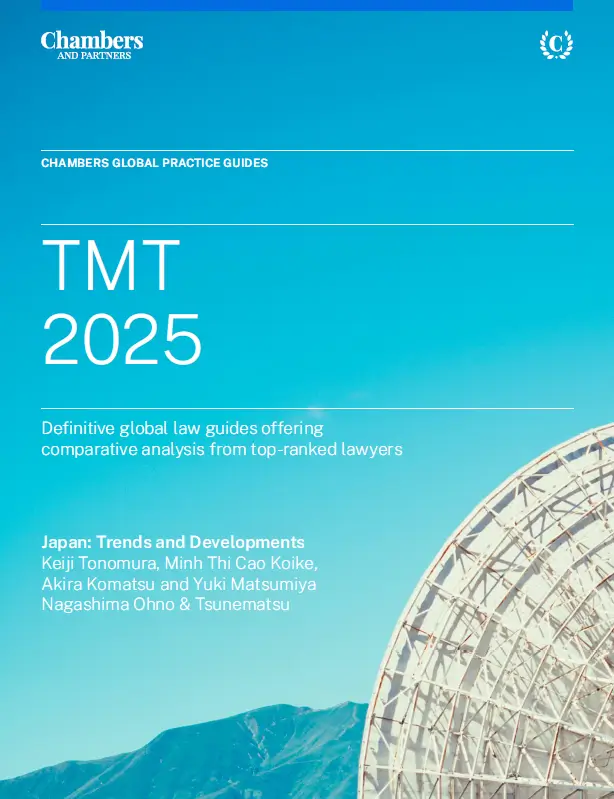
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)


殿村桂司、近藤正篤、丸田颯人、小宮千枝(共著)


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年6月)
近藤正篤(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
今野庸介


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(共著)


(2025年3月)
殿村桂司、小松諒、加藤志郎(共著)


(2024年10月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ(共著)
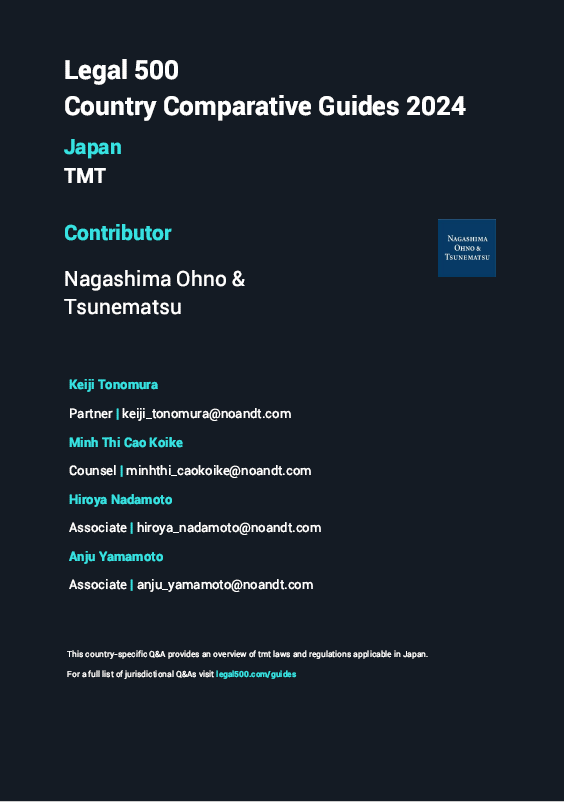
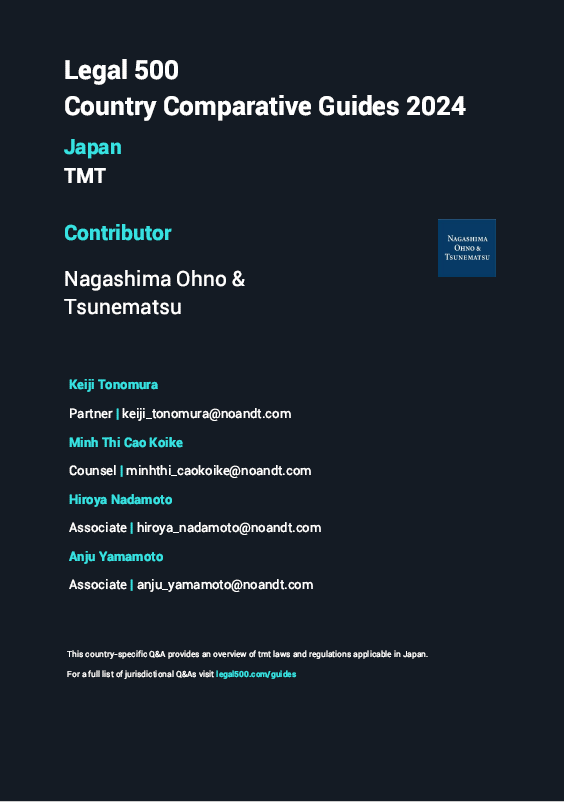
(2024年8月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、灘本宥也、山本安珠(共著)


(2025年7月)
加藤志郎、鈴木雄大(共著)


(2025年6月)
近藤正篤(共著)


(2025年5月)
東崎賢治、近藤正篤(共著)


(2025年5月)
今野庸介