
佐々木修 Shu Sasaki
パートナー
東京

NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
2022年6月30日、金融庁は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」といいます。)の改正案を公表し、パブリックコメントを実施しました※1。かかる改正案が施行されると、信託銀行による暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受け(ただし、後述のとおり、管理型信託業に限られます。)が解禁されることになります。
また、2022年7月22日、金融庁は、「信託会社等に関する総合的な監督指針」(以下「信託会社等指針」といいます。)についても、信託銀行が暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けをする際の留意点を示した改正案を公表し、パブリックコメントを実施しています※2。
なお、2022年8月29日現在、上記のいずれのパブリックコメントについても結果が公表されておらず、改正案の内容は今後変更される可能性がある点にご留意ください。
2020年4月3日公表のパブリックコメント※3によると、暗号資産は、マネー・ローンダリングに利用されるリスクや暗号資産の管理等にかかるシステムリスク等を有することから、これらのリスクの顕在化により、信託銀行の固有業務に悪影響を与えることを避けるため、信託兼営金融機関が暗号資産を受託財産とする信託業を営むことは適当でないと整理され、2020年5月1日に施行された兼営法施行規則の改正により、信託銀行を含む信託兼営金融機関による暗号資産の受託は禁止されました(兼営法施行規則3条1項6号の新設)。また、銀行の子会社である信託会社及び銀行又はその子会社が合算して5%超の議決権を保有する国内の会社については、実施可能な信託業務の範囲を信託銀行の業務範囲に合わせるという建付になっていたため、銀行傘下の信託会社では暗号資産を信託財産に含む信託の引受けが認められていませんでした(銀行法16条の2第1項6号、16条の4第1項)。
一方で、銀行傘下ではない信託会社では、こうした銀行の固有業務への影響を考慮する必要がなく、暗号資産を信託財産に含む信託の引受けが認められていました。
今般の兼営法施行規則3条1項6号の改正案が施行されると、信託銀行は※4、管理型信託業に限って、暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けが認められることになります※5。また、これに伴い、銀行の子会社である信託会社及び銀行又はその子会社が合算して5%超の議決権を保有する国内の会社についても、管理型信託業に限って暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けが可能となります。
改正後において認められる暗号資産に関連する信託の業務範囲をまとめると、大要以下のとおりとなります。
| 信託業の類型 | 信託財産の内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理型 | 運用型 | 暗号資産 |
暗号資産関連 デリバティブ |
|
| 信託銀行 | ○ | × | ○ | × |
| 信託銀行以外の兼営金融機関 | × | × | × | × |
| 銀行傘下の信託会社 | ○ | × | ○ | × |
| (銀行傘下でない)信託会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
信託銀行が新たに暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けをするためには、業務方法書において、「引受けを行う信託財産の種類」として、暗号資産及びその細目を追加する必要がありますので、業務方法書の変更認可を受ける必要があります(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律3条、兼営法施行規則4条1項3号イ、2項11号)。なお、信託銀行が暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けをする場合の規制については、基本的には信託会社に対する規制と同様のものとする兼営法施行規則の改正案が公表されましたが、後述のとおり、履行保証暗号資産の保有に関する監督指針上の留意点など、信託銀行固有の点も存在するこることに留意が必要です。
信託銀行が暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けをする場合、原則として信託財産に属する暗号資産は「常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法」(いわゆるコールドウォレット)で管理する必要がありますが、例外的にコールドウォレット以外で管理することが必要な最小限度の暗号資産(ただし、その管理する信託財産に属する暗号資産の5%が上限)に関しては、いわゆるホットウォレットによる管理も認められています(兼営法施行規則21条3項)。ホットウォレット管理をする場合、信託銀行は、流出時の弁済に充てるため、ホットウォレットで管理をしている暗号資産と同種・同量の暗号資産(履行保証暗号資産)を自己の固有の財産として保有する必要があります(兼営法施行規則21条4項)。
この点、信託銀行は、銀行として、主要行等向けの総合的な監督指針又は中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(併せて、以下「銀行等監督指針」といいます。)の適用を受けますが、銀行等監督指針は、暗号資産のリスクに鑑み、「銀行グループによる暗号資産の取得は必要最小限度の範囲とする必要」があると規定しています※6。信託銀行が暗号資産をホットウォレットで管理した場合、上記のとおり、自己の固有の財産として、履行保証暗号資産を保有する必要がありますが、履行保証暗号資産の保有は銀行等監督指針の規定との関係で整理が必要となります。
こうした点を踏まえ、信託会社等指針11-2についても改正案が公表されたものと考えられます。具体的には、兼営法施行規則の改正に合わせた修正に加え、以下の記載が追加され、銀行等監督指針の規定との関係が明確化されることになりました。
「暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託を営む場合、銀行である信託兼営金融機関による履行保証暗号資産の保有は、主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-6-1及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-13-1に規定する「必要最小限度の範囲」に含まれるが、銀行勘定に与えるリスクに鑑み、特に主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-6-2③及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-13-2③に記載の点に留意する。」
なお、上記信託会社等指針が言及している主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-6-2③は以下のとおり定めており、下記の点については引き続き留意する必要があります。
「③ 財務の健全性確保を図るための措置
銀行グループの業務において暗号資産の取得が必要となる場合であっても、健全性の確保の観点から、取得する暗号資産の量については当該業務のために必要最小限度の範囲とする等、適切な方針が定められているか。 また、暗号資産の保有についても、当該暗号資産の市場リスク、流動性リスク等を考慮の上で、速やかに売却する等により適切な処分を図ることが可能な態勢となっているか。
なお、銀行グループにおいては、投資の目的をもってする暗号資産の取得等を行わないこととしているか。」
また、信託会社等指針には、信託会社が暗号資産を信託財産に含む信託の引受けをする際の着眼点が記載されていますが※7、信託銀行にも当該留意点が準用される点についても留意が必要となります※8。
本改正により信託銀行による暗号資産を含む信託財産の管理又は処分を行う信託の引受けの可能性が広がりました。管理型信託業に限られるとはいえ、信託を活用した新たな暗号資産サービスも検討の俎上に上がる可能性があり、今後の活用が期待されます。
※1
2022年6月30日金融庁「「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」
※2
2022年7月22日金融庁「「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について」
※3
2020年4月3日金融庁「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」別紙1 68頁No.253~256回答では、以下のように説明されています。
「信託銀行等の信託兼営金融機関が暗号資産を受託財産とする信託業を営む場合のリスクとしては、マネー・ローンダリング等に利用されるリスクや暗号資産の管理等にかかるシステムリスクのほか、これらが顕在化した場合のレピュテーショナル・リスク等が想起されます。これらのリスクを完全にコントロールすることは容易ではないところ、これらのリスクが顕在化した場合には、信託勘定に留まらず、信託銀行等の固有業務への影響も考えられます。こうした点を踏まえ、信託兼営金融機関が暗号資産を受託財産とする信託業を営むことは適当でないと考えます。」
※4
兼営法施行規則3条1項6号の改正案においては、「令第二条第一号に掲げる金融機関にあっては、」と規定しているため、今回の改正により管理型の暗号資産の受託が認められるのは銀行に限られ、従前どおり、銀行以外の兼営金融機関には暗号資産の受託は認められません(信託会社等指針11-2(注)参照)。
※5
なお、信託銀行は引き続き暗号資産デリバティブ取引を行う信託を受託することはできません。
※6
主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ-6-1、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-13-1
※7
信託会社等指針3-5-1(5)参照
※8
信託会社等指針11-5により、信託会社に係る信託会社等指針3-5の内容は、一部を除き、信託銀行に準用される構成になっています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
淺野航平(共著)


斉藤元樹、大島岳(共著)


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


工藤靖


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
清水音輝(インタビュー)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(監修)、糸川貴視、大野一行(共著)
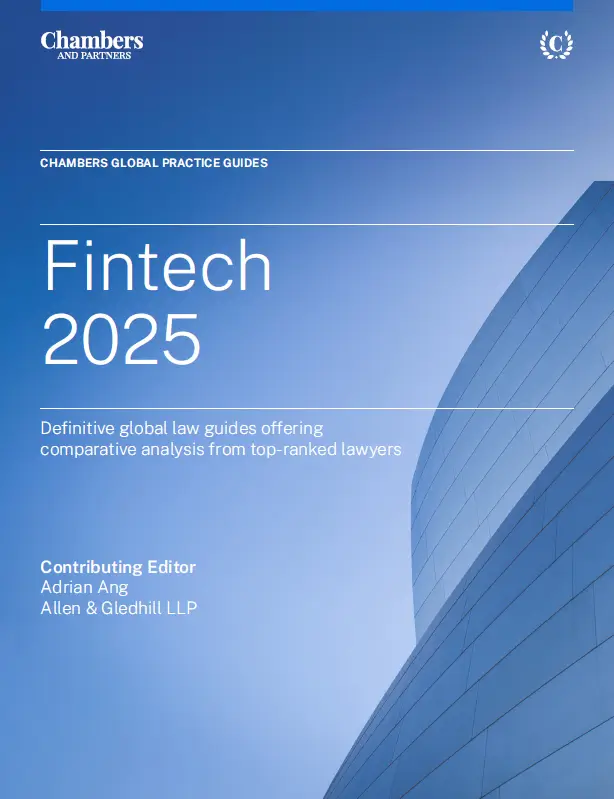
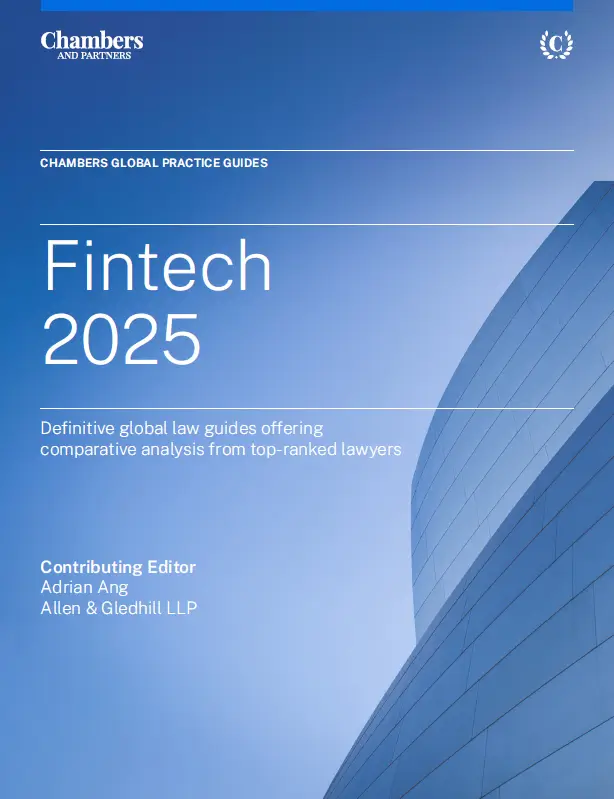
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


(2025年5月)
井上聡、大野一行(座談会)


(2025年4月)
松本岳人