
鹿はせる Haseru Roku
パートナー
東京

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター
本ニュースレターでは、2回に分けて内容をご紹介しています。第1回は以下をご覧ください。
NO&T Asia Legal Update No.120/NO&T Competition Law Update No.11(2022年8月)
「改正中国独禁法の要点―どこが日本企業にとって重要か(上)」
本ニュースレターの概要をPodcastで配信しています。
The NO&T Podcast – JP
「中国独禁法の最近の動向 Part1」
「中国独禁法の最近の動向 Part2」
目次:
1.中国独禁法の改正及び施行
2.中国独禁法改正の要点
(1) 処罰の厳格化
(2) 企業結合規制に関する改正の要点
<以上、アジア最新法律情報No.120/独占禁止法・競争法ニュースレターNo.11>
(3) 独占的協定(取引制限)規制に関する改正の要点
(4) 市場支配的地位の濫用規制に関する改正の要点
<以上、本号(アジア最新法律情報No.121/独占禁止法・競争法ニュースレターNo.12)>
① 垂直的取引制限に関するセーフハーバー規定(下位法令※1の成立待ち)
独占的協定とは、「競争を排除し若しくは制限する合意、決定又はその他の協調行為」(第16条)であり、中国独禁法では競争関係にある事業者の間で、価格、生産数量又は販売数量等に関する独占的協定(いわゆる水平的取引制限)、取引関係にある事業者との間では、再販売価格及びその最低価格等に関する独占的協定(いわゆる垂直的取引制限)がそれぞれ禁止対象とされている。
改正中国独禁法においても、上記規制の枠組み自体は変わっていないが、取引当事者間の垂直的取引制限については、(i)「事業者が競争排除・制限効果がないと証明できる場合」は禁止されず(改正中国独禁法第18条第2項)、(ii)「関連市場における市場シェアが競争当局の定める基準を下回り、かつ競争当局が定めるその他の要件を満たす場合」も禁止されないとする規定(同法第18条第3項)がそれぞれ新設された。このうち、(i)は従来の実務を追認した確認的な規定であるが、(ii)は新たに垂直的取引制限に関するセーフハーバーを定めた規定として注目されている。
この点、同規定を具体化した下位法令(独占的協定禁止規定)改正案によれば、セーフハーバーは以下の場合に満たされる(独占的協定禁止規定第15条)。
(a) 事業者及び取引の相手方の関連市場における市場シェアが15%未満であること
(b) 協定が競争を排除・制限する効果があることを示す証拠が存在しないこと
この(a)(b)のセーフハーバーと改正中国独禁法第18条第2項に定められた(i)の規定を併せて読めば、下位法令成立後の垂直的取引制限規制は、取引当事者の市場シェアが15%未満である場合は、原則違反とならず(当局が違反とする場合は、競争の排除・制限効果を要立証)、15%以上の場合は、原則違反となる(事業者が違反なしを主張するためには、競争の排除・制限効果がないことを要立証)であろう。
この点、従来の中国独禁法実務では、垂直的取引制限のうち、取引相手方の再販売価格の固定など価格を直接制限する行為は、(販売場所・方法の規制など非価格制限行為と異なり)当事者の市場シェアにかかわらず原則違反とされていた※2。とりわけ日系企業を含む外資企業の製品については、垂直的取引制限によって中国での販売価格が不当に高く維持されており、消費者の利益が害されているとして、摘発・処罰を受けるリスクの高い違反類型であった。
本セーフハーバー規定は、規定の文言上価格制限行為等のいわゆるハードコア制限行為を適用対象から排除していない。仮に、取引相手方の再販売価格を拘束しても当事者の市場シェアが15%未満の場合に原則違反とならないことを定めたものであれば、従来の実務を変えるものとして大きなインパクトがあると思われるが、現状この点に関する当局の明確な説明はない。下位法令の改正案も正式に成立していないため、価格制限行為についてはひとまず旧法の実務に従い、市場シェアにかかわらず原則違法になることを前提に慎重に判断し、今後の解釈の明確化を待つのが賢明と思われる※3。
なお、垂直的制限に関して上記セーフハーバー規定が設けられたことの副次的効果として、別の下位法令(知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定)に定められていた独自のセーフハーバー規定は削除されており、独占的協定禁止規定に一本化されることが明らかとなった。
② 独占的協定の組織・ほう助を処罰する規定の新設(8月1日から施行済み)
旧中国独禁法ではカルテル等の取引制限行為を組織・ほう助する行為を直接禁止する規定がなく、いわゆるハブアンドスポークと呼ばれる、仲介者を介したカルテルを処罰することが法令上困難であった※4。例えば川上の事業者単体が川下の事業者群の再販売価格を制限した場合は、川上・川下事業者間の垂直的取引制限及び川下事業者同士の水平的取引制限と構成する必要があった※5。改正中国独禁法では、「事業者は他の事業者の独占的協定を組織し又は他の事業者による独占的協定に対して実質的ほう助を提供してはならない」との規定が新設され(改正中国独禁法第19条)、処罰の間隙を埋めている。
① プラットフォーム規制の強化(8月1日から施行済み)
中国独禁法本文では、市場支配的地位の濫用規制について基本的に旧法の枠組みが維持されており、改正法による変更は、市場支配的地位の濫用行為の類型を定めた第22条に、「市場支配的地位を有する事業者がデータ、計算方法、テクノロジー及びプラットフォームルール等を用いて、前項に定める市場支配的地位の濫用行為を行ってはならない」(改正中国独禁法第22条第2項)と条項が一つ新設されたのみである。
同項の新設は明らかに近年のアリババ、テンセント等の中国の巨大IT企業に対する処罰強化を踏まえたものであり、その背景としては世界的な潮流として、GAFA等の巨大IT企業に対する競争当局の執行活動の厳格化と軌を一にする側面もあれば、中国独自の事情として、大手IT企業がアリババ及びテンセントを頂点に寡占化している現状への対応という側面もあり、安易に単純化できない。もっとも、少なくとも日系企業を含む外資企業は、外資規制の関係で、中国で市場支配的地位を有するほどのプラットフォーム事業者となる可能性は低く、むしろE-Commerceの勃興によってプラットフォームに対する依存度が高まっているため、規制強化を追い風として生かす道を探るべきであろう※6。
② 標準必須特許権者の権利行使規制の強化(下位法令※7の成立待ち)
市場支配的地位の濫用規制に関し、日系企業の立場から注目すべき改正はむしろ、下位法令のうちの知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定(「知財濫用禁止規定」)における、標準必須特許に関する以下の改正と思われる(下線部分が実質的追加)。
| 現行知財濫用禁止規定第13条第2号 | 改正案第16条第2号・第3号 |
|---|---|
|
市場支配的地位を有する事業者は…以下の競争を排除・制限する行為を行ってはならない。 (1) 略 (2) 保有する特許が標準必須特許となった後に、公平、合理的かつ非差別的な原則に反し、実施許諾の拒絶、抱き合わせ又は取引時その他の不合理な取引条件を付加するなど競争を排除・制限する行為。 |
市場支配的地位を有する事業者は…以下の行為を行うことにより競争を排除・制限してはならない。 (1) 略 (2) 保有する特許が標準必須特許となった後に、公平、合理的かつ非差別的な実施許諾の承諾に反し、不当に高い価格での実施許諾、正当な理由のない実施許諾を拒否し、抱き合わせ、差別的条件、又はその他の不合理な制限的条件を付加すること。 (3) 標準必須特許の実施許諾の過程において、公正、合理的かつ非差別的な実施許諾の承諾に反し、誠実な交渉手続を経ずに、裁判所又は関連当局に対して関連知的財産権の使用を禁止する判決、裁定又は決定を下すよう不当に要求し、被許諾者をして不当に高い価格又はその他の不合理な制限条件を受け入れさせること。 |
標準必須特許(Standard Essential Patent “SEP”)は、標準規格に準拠した商品役務を製造・供給するために回避できない特許を意味し、特許権者は、公正、合理的かつ非差別的な条件(いわゆるFRAND条件)で他社にライセンスすることが求められる。しかし、何がFRAND条件にあたるかは解釈の問題であり、特許権者とライセンシーの間で紛争となりやすい。
近年では、中国のメーカーがライセンシーとして、日系企業を含む海外企業が保有する通信、自動車、レアアース等の標準必須特許のロイヤリティが不当に高額である等と主張することによる、知財紛争が頻発している。こうした知財紛争はひとたび起きれば、ライセンシー及びライセンサーはそれぞれ自社にとって有利な判決を得ようとして、世界各地で訴訟を提起し合うことがしばしば起きる。
しかし、最近では中国の裁判所が、ライセンシーである中国メーカーの申立てに応じて、日系企業を含む海外のライセンサー(標準必須特許権者)に対して、係属事件の審理期間中、他国の裁判所に類似訴訟を提起することを禁じ、既に提起された訴えでライセンサーに有利な判決又は処分が下されている場合であっても、その判決及び処分の撤回を求めるか、執行の禁止を求める仮処分(いわゆる禁訴令。Anti-Suit-Injunction “ASI”とも呼ばれる。ライセンサーが仮処分に違反した場合には一日につきRMB100万元といった高額な制裁金を課す間接強制条項が含まれることも特徴的である。)を頻発していることが世界的に問題となっている※8。2022年2月18日には、EUが中国の裁判所が発令する禁訴令はEU企業の知的財産権を侵害しているとしてWTOに調査の申立てを行っており、その後米国、カナダ、日本も同様の調査の申立てを行っている。
これに対して、上記知財濫用禁止規定の改正は、第2号で標準必須特許権者に対して「不当に高い価格での実施許諾」を禁じ、更に第3号でライセンシーと誠実な交渉を経ることなく裁判所に特許権に基づく差止請求等の訴えを提起することを禁じる条項を新設するなど、標準必須特許のライセンシーとなることが多い中国メーカーの主張を後押しする姿勢が明確に取られている。
現在でも標準必須特許を保有する日系企業を含む海外企業にとっては、中国のライセンシーとなるメーカーから、標準必須特許のロイヤリティ等実施許諾条件に関する交渉を申し込まれることが頻繁にあるが、今後交渉の仕方及び提示条件次第では、中国独禁法との関係で市場支配的地位の濫用であるとの判断を受けるリスクが高まったことを意味し、十分に留意すべきである。
※1
独占的協定禁止規定(中国語:禁止垄断协议暂定规定)
※2
公表されている再販売価格拘束に関する処罰決定書を読むと、価格を拘束した事実のみが認定されており、当事者の市場シェアは認定されていない。
※3
価格制限行為が行われる場合には、セーフハーバー規定の(b)の要件(協定が競争を排除・制限する効果があることを示す証拠が存在しない)を満たさないと判断される可能性もあると思われる。
※4
事業者団体が加入者である事業者をして独占的協定を行わせてはならないとする条項は旧独禁法にも制定されているが(旧法第16条、改正法第21条)、事業者団体ではない者がハブ(仲介者)となる場合を処罰する規定が欠けていた。また、水平的な独占的協定については、「競争関係を有する事業者間」で実施してはならないと条文上規定されているため(旧法第13条、改正法第17条)、競合者ではない仲介者を直接独占的協定の当事者として処罰することが条文上困難であった。
※5
例として、国家発展改革委員会(当時の執行当局)の2014年9月12日付中国第一汽車集団及びBMWに対する処罰決定書参照
※6
中国の競争当局のIT企業に対する厳罰化傾向及び日系企業に対する影響についての詳細は、筆者執筆の「近時の中国独禁法の厳罰化傾向と日系企業への影響(上・下)」で紹介している。
(商事法務ポータル(会員制サイト)SH3906(上)https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=17398916及び同3907(下)https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=17419807)
※7
知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定(「知財濫用禁止規定」)(中国語:关于禁止滥用知识产权排除,限制竞争行为的规定)
※8
禁訴令の問題点及び日本企業の考えられる対応については、筆者執筆の「EUがWTOに提訴した中国の新しい知財戦術「禁訴令」(上・下)」で紹介している。
(商事法務ポータル(会員制サイト)SH3916(上)https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=17497651及び同3918(下)https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=17517720)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


(2025年8月)
前川陽一


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
若江悠


(2025年8月)
前川陽一


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年8月)
井本吉俊


小川聖史


深水大輔、Simon Airey(McDermott Will & Emery)(共著)


(2024年2月)
佐々木将平


(2024年2月)
服部薫、柳澤宏輝、井本吉俊、森大樹、田中亮平、一色毅、小川聖史、鹿はせる、伊藤伸明、山口敦史、山田弘(共著)


佐々木将平


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)


(2025年9月)
若江悠


若江悠


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
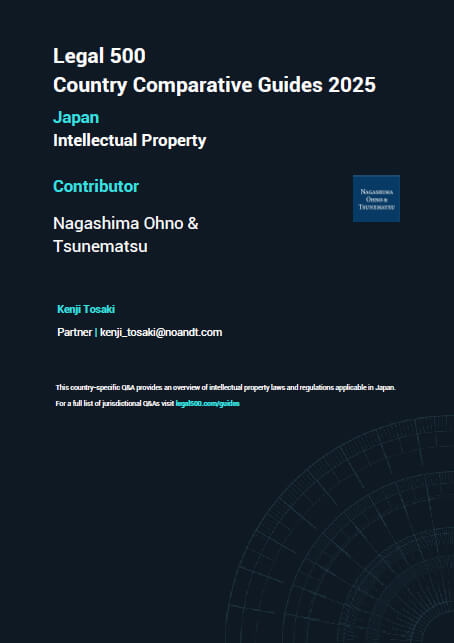
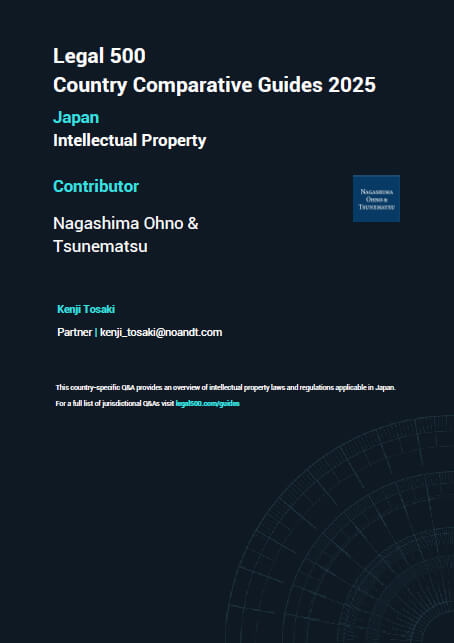
(2025年9月)
東崎賢治


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治


東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
髙取芳宏


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治


(2024年9月)
柳澤宏輝


(2024年2月)
服部薫、柳澤宏輝、井本吉俊、森大樹、田中亮平、一色毅、小川聖史、鹿はせる、伊藤伸明、山口敦史、山田弘(共著)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2022年9月)
鹿はせる


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


山本匡


梶原啓


箕輪俊介


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


川合正倫


川合正倫、王雨薇(共著)


(2025年9月)
若江悠