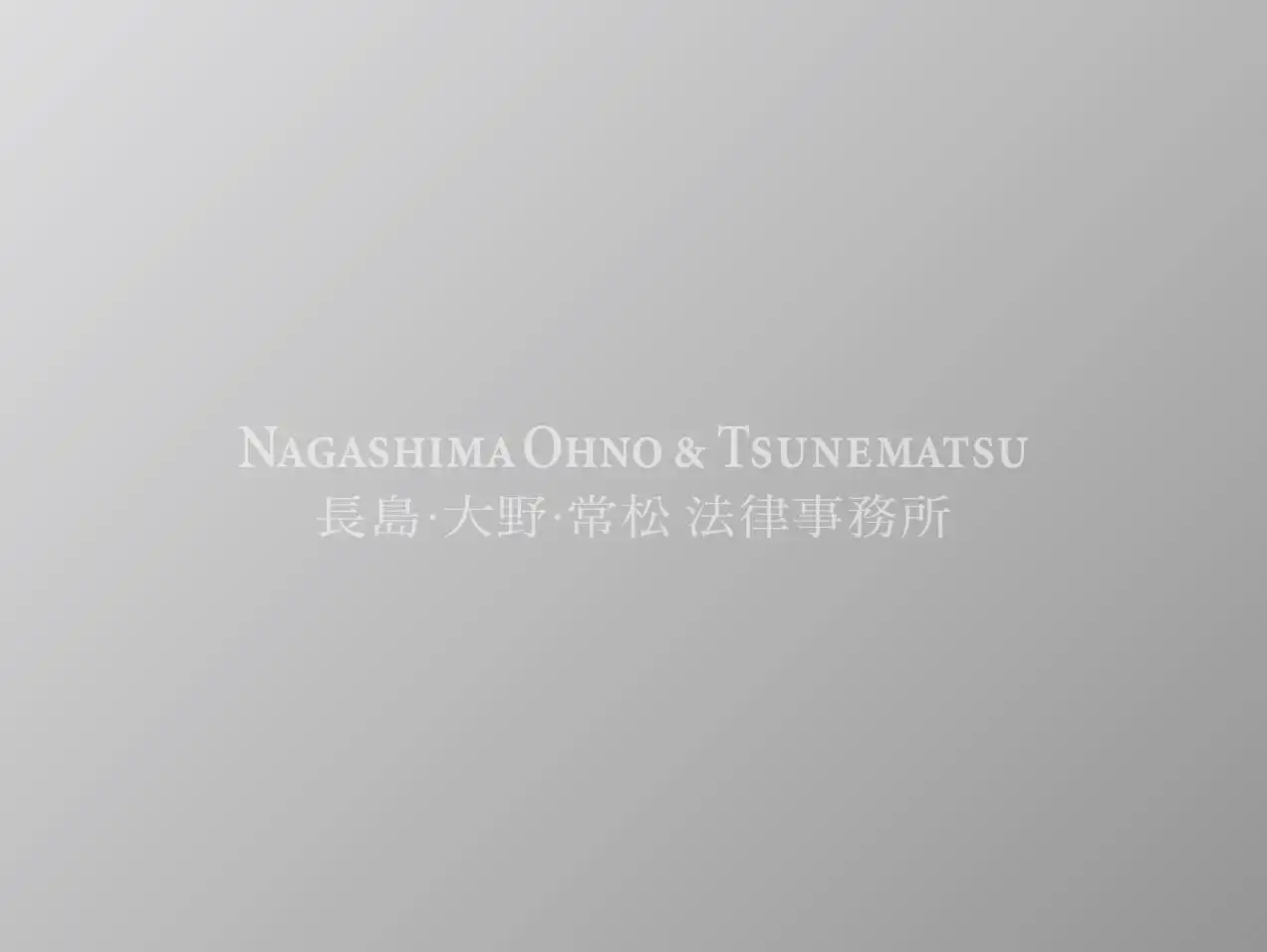
山本匡 Tadashi Yamamoto
パートナー
東京

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター
本ニュースレターの概要をPodcastで配信しています。
The NO&T Podcast – JP
「競争法改正法案(インド)」
インドの2002年競争法(Competition Act, 2002)(以下「インド競争法」という。)は、反競争的協定及び市場支配的地位の濫用行為に関する条項が2009年に、企業結合に関する条項が2011年に施行された。特に企業結合に関する条項の施行前には、施行後の日本企業のM&Aの実行に混乱が生じるのではないか懸念されていた。同法が全面的に施行されてから約10年が経過した現在においては、幸い、施行当時懸念されていたほどの混乱は生じていないように思われる。
インド競争法は全面的に施行されてからこれまで一度も改正されてこなかったが、2022年競争法改正法案(Competition (Amendment) Act, 2022)(以下「改正法案」という。)が2022年8月に議会に提出された。最終的な改正内容は今後の議会での審議次第であるが、企業結合の届出基準として取引価値基準が導入されること、日本企業が届出不要と整理する際に利用してきた小規模取引の除外(de minimis exemption)が取引価値基準を充足する場合には使えなくなることが想定されることなど、実務上影響が大きい改正となる可能性がある。以下では、改正法案中の企業結合に関する改正点について概説する。
現在、インド競争法に基づく企業結合の届出の要否は、企業結合の当事者及びそのグループのインド国内外における資産額及び売上高を基準として判断される※1。
改正法案では、既存の資産額及び売上高基準に加えて、新たに取引価値基準が導入された。すなわち、企業結合(支配権、株式、議決権もしくは資産の取得又は合併等)に関連する取引価値(value of transaction)が200億ルピーを超える場合において、取引の当事者である企業がインドで実質的な事業(substantial business operations in India)を行っている場合には、インド競争委員会(Competition Commission of India、通称「CCI」)への届出が必要となる。
上記の通り、取引価値基準の閾値は200億ルピーである。取引価値(value of transaction)には、直接又は間接、後払いを問わず全ての対価が含まれる。インドの取引価値基準における金額の閾値は、非常におおまかにいえば、同じく取引価値基準を導入している国と比較して同程度、あるいは最近の著しい為替レートの変動の影響もあろうが現時点ではやや低いという印象である。例えば、ドイツの取引価値基準における取引価値の閾値は4億ユーロ超、オーストリアの閾値は2億ユーロ超、(法定の取引価値基準ではないものの)日本の閾値※2は400億円超で、インドの閾値200億ルピーのユーロ換算・円換算はそれぞれ約2.5億ユーロ、約360億円である。
どのような場合に「取引の当事者である企業がインドで実質的な事業を行っている」という要件に該当するか(「substantial business operations in India」に該当するか)は、改正法案においては定義されておらず、今後インド競争委員会が規則で定めることになるため現段階でその内容は不明であるが、取引価値基準に該当する場合は下記の通り小規模企業結合の除外が適用されないことが想定されている。そのため、同基準に基づく届出の要否は、この要件の内容に大きく影響されることが想定され、どのような場合にこれに該当するか注目される。
なお、改正法案の文言を見る限り、買収会社のインド国内売上高に関する要件は見当たらない。この点、例えばドイツの取引価値基準においては、一方の当事会社(被買収会社を除く。)のドイツ国内売上高が5,000万ユーロ超であることが要件とされている。また、日本では「被買収会社の国内売上高等に係る金額のみが届出基準を満たさない」企業結合計画が「届出不要企業結合計画」と定義されていることから、買収会社は国内売上高等に係る金額基準(例えば株式取得であれば200億円超)を満たす必要がある。このように、ドイツの取引価値基準や日本の手続対応方針上の基準においては買収会社等が相応の国内売上高を有することが要件とされているところ、改正法案自体にはかかる要件が存在しない。改正法施行時にインド競争委員会が定める規則の内容次第ではあるが、買収会社側のインド国内売上高等に係る要件が規定されない場合には、取引価値基準を満たすケースが増える可能性もあると考えられる。
現在の企業結合規制では、インド競争委員会が通達により定めた、企業結合の対象会社の資産・売上高の規模による除外(de minimis exemption)が存在し、現在の基準では、対象会社のインド国内の資産が35億ルピー以下又はインド国内の売上高が100億ルピー以下である場合には事前届出が不要とされている。日本企業はこのde minimis exemptionを多用してきたと理解しており、de minimis exemptionはインドでの届出を不要と整理する際の非常に重要な拠り所となってきた。
しかしながら、改正法案では、取引価値基準に該当する場合はde minimis exemptionは適用されないことが想定されているようである。仮に、改正法案の方針通り、取引価値基準に該当する場合にde minimis exemptionに依拠できなくなる場合には実務上の影響は大きいと考えられ、今後の改正法案の動向を注視する必要がある。
現在のインド競争法の規定では、支配権(control)は以下の通り規定されている。
「(a) "control" includes controlling the affairs or management by—
(i) one or more enterprises, either jointly or singly, over another enterprise or group;
(ii) one or more groups, either jointly or singly, over another group or enterprise」
改正法案では以下の通り規定されている(下線部が現在の規定と異なる部分で筆者が付したもの)。
「(a) "control" means the ability to exercise material influence, in any manner whatsoever, over the management or affairs or strategic commercial decisions by—
(i) one or more enterprises, either jointly or singly, over another enterprise or group; or
(ii) one or more groups, either jointly or singly, over another group or enterprise」
もっとも、現状の実務においても、インド競争委員会が支配権の有無を判断するに当たっては「重大な影響」(material influence)の有無を考慮しており、改正法案はこの実務を法文に反映させようとするものといえる。また、競争者間の企業結合であれば、インド競争法上は「control」の取得がないようなマイノリティの議決権株式取得のみでも届出対象取引に該当するとされてしまうことから、この定義の変更の影響はさほど大きなものではないと思われる。
現在、企業結合の届出が行われた場合、インド競争委員会は30営業日以内に当該企業結合が競争に対する重大な悪影響を及ぼす可能性があるかの初期的(prima facie)な判断を行い、210日以内に企業結合を承認するかの判断を行うことになっている(210日以内にインド競争委員会が必要な命令を行わなければ承認されたものとみなされる。)。
改正法案では、これらがそれぞれ20暦日及び150日(更に30日延長可能)に短縮されている。これら以外にも企業結合に関する様々な期間の短縮が提案されている。
法定の審査・待機期間が短縮されるという方針自体は好ましいことではある。もっとも、現在のインド競争委員会の規則において、企業結合の届出後に同委員会から質問や追加情報リクエストが出された場合、これに対する回答を完了するまで法定の審査・待機期間の進行は停止するとされており、改正法案施行後も現在の規則と同様の取扱いが継続される可能性はある。この点の取扱い次第では短縮された審査・待機期間内においてインド競争委員会からの質問や情報提供要請にタイムリーに回答しなければならない等、企業結合の当事者の実務的な負担が大きくなる可能性もあるため、今後の改正法案・関連規則及び実務上の運用の動向を注視する必要がある。
現在、インドの対象会社(上場会社)の買収で株式を取得する場合において、例えば市場での取得と既存株主からの取得を組み合わせる場合、先行する市場での取得が少数の株式の取得でありそれ自体は届出要件に該当しない場合であっても、インド競争委員会は、市場での取得とそれに続く既存株主からの取得を一体の取引とみなし、後続の取得について企業結合の届出を行っても、先行する市場での取得自体にインド競争委員会が必要であったという立場をとっており、実際にかかる取引を行った企業に対して(先行する市場での取得に係る届出義務違反による)ガンジャンピングとして制裁金を課している。そのため、市場での取得を組み合わせた買収が極めて困難となっていた。
改正法案では、一定の条件の下、市場での取得について届出が不要とされた。すなわち、公開買付け又は市場での株式又は転換証券の取得を事前のインド競争委員会への届出及びクリアランスなく行うことが(待機義務(standstill obligation)からの除外という形で)認められている。これにより、市場において適時に株式等を取得することが可能となるが、この場合でも、同委員会が規則で定める期間内に所定の方法で取得の届出を行い、かつ、同委員会で別途規定される場合を除き、同委員会の承認が得られるまで取得者は議決権や配当の受領その他の権利や受益権等を行使してはならないことが条件とされている。
現在、企業結合の届出が必要であるにもかかわらずこれを怠った場合又はインド競争委員会の承認前に企業結合を実行した場合(ガンジャンピング)、インド競争委員会は、当該企業結合の売上高合計又は資産合計のいずれか高い方の1%以下の制裁金を課すことができる。
改正法案では、上記に加えて、インド競争委員会が自ら企業結合について探知して情報提供を要請したにもかかわらず要求を受けた者が情報を提供しなかった場合にも、当該企業結合の売上高合計、資産合計又は取引金額のいずれか高い方の1%以下の制裁金を課す権限を同委員会に付与することが提案されている。取引価値基準が導入されたことに伴う改正であるが、インド競争委員会が法文上制裁金を課すことができる場合が拡大されている点が注目される。
インド競争委員会がガンジャンピングを理由として制裁金を課すケースは決して珍しいことではなく、年に数件の制裁金納付命令が出されているなど、世界的にみてガンジャンピングに対する執行が比較的多い国といえる。また、前記の通り、取引価値基準が施行されればインド競争委員会への届出が必要となる企業結合が増加する可能性があることから、実務上、制裁金の観点からもインドでの届出の要否に留意すべきであろう。
なお、現在のインド競争法上、企業結合の当事者が、重要な事項について虚偽の報告を行った場合もしくは知りながら虚偽の報告を行った場合、又は重要な事項についてそれが重要であると知りながら報告しなかった場合、インド競争委員会により500万ルピー以上1,000万ルピー以下の制裁金が課される。改正法案では、制裁金の金額の上限を5,000万ルピーに引き上げる提案がなされており、この点も併せて留意が必要であろう。
※1
インドでの届出の要否は、企業結合の当事者及びそれが属するグループ(「group」)がインド国内外において一定の資産額又は売上高を有するかにより判断されるが、ある企業がグループの範囲に含まれるか否かを判断するための基準の1つとして、インド競争法上、議決権の26%以上を直接又は間接に行使することができるかという基準が定められている。そのため、親子会社の関係にはなくても、ある企業が他の企業の議決権の26%以上を直接又か間接に行使することができれば、両社は同一グループに属するとされ、インドでの届出の要否を判断する上では両社の資産額及び売上高を合算しなければならない。
この点、インド競争委員会が2011年3月に出した通達により、上記の法定の基準(すなわち、ある企業が他の企業の議決権の26%以上を直接又は間接に行使することができる場合)にかかわらず、行使することができる議決権の割合が50%未満であればグループから除外するとされていた。そのため、行使することができる議決権の割合が50%未満であれば、企業結合を行う企業と他の企業は同一グループに属しないことになり、他の企業の資産額及び売上高を合算する必要がなかった。この通達による除外の有効期間は当初5年間とされ、同委員会が2016年3月に出した通達により5年間延長されていたものの、2021年3月にこの有効期間は再延長されなかった。
したがって、現在、グループの範囲に係る有効な基準は法定の26%であり、グループに含まれる企業の範囲が、通達による除外が有効であった2021年3月までと比べて拡大している。
今回の改正法案では、法定のグループの定義に基本的には変更ない(議決権に基づく基準としては、現在の基準と同じく、議決権の26%以上の行使がグループ該当性の基準とされている)ものの、「exercise twenty-six per cent. or such other higher percentage as may be prescribed, of the voting rights in the other enterprise」(下線筆者)として下線部の文言の追加が提案されている。上記の経緯及び改正法案の文言からすると、改正法案が原案のまま議会で承認され改正法が施行されれば、改正法施行時にあわせて改正されることになる関連規則(Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011)において、グループの範囲に関する議決権行使基準が、例えば既に失効した通達と同様の基準(50%)に引き上げられる可能性はある。ただし、現時点では、インドの企業結合規制におけるグループの範囲は広く、議決権の26%以上を基準としてグループ該当性を判断する必要がある点には留意されたい。
※2
日本では、法的な届出義務を発動する基準ではなく、事実上のものである。公正取引委員会の「企業結合審査の手続に関する対応方針」において、当事会社のうち実質的に買収される被買収会社の国内売上高等に係る金額のみが届出基準を満たさないために届出を要しない企業結合計画(届出不要企業結合計画)のうち、買収に係る対価の総額が400億円を超えると見込まれ、かつ、国内の需要者に影響を与えると見込まれる場合(被買収会社の事業拠点や研究開発拠点等が国内に所在する場合など)には、当該届出不要企業結合計画の当事会社は公正取引委員会に相談することが望まれ、当事会社から相談がない場合には、公正取引委員会は当事会社に対して各種の資料等の提出を求め、企業結合審査を行うとされている。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年7月)
森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)


清水美彩惠、菅紀世美(共著)


(2025年5月)
小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)


(2025年6月)
神田遵


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)


(2025年6月)
伊藤伸明
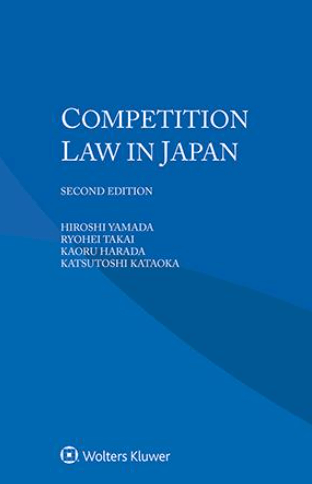
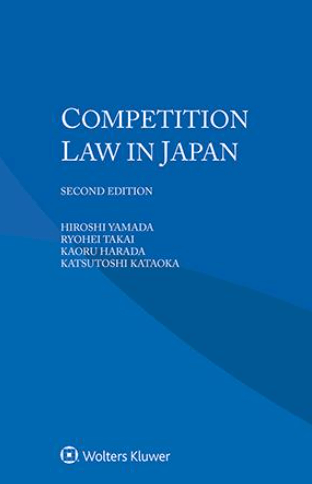
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


(2024年9月)
柳澤宏輝


(2024年2月)
服部薫、柳澤宏輝、井本吉俊、森大樹、田中亮平、一色毅、小川聖史、鹿はせる、伊藤伸明、山口敦史、山田弘(共著)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2022年9月)
鹿はせる


(2025年6月)
伊藤伸明


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2025年2月)
大久保涼(コメント)


大久保涼、佐藤恭平(共著)


(2025年7月)
殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)
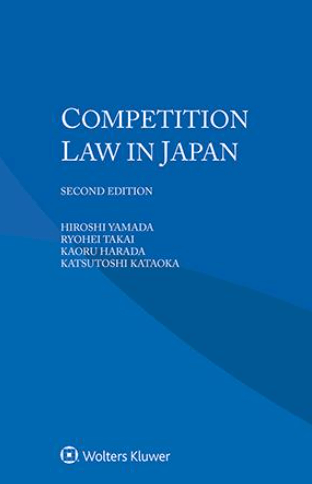
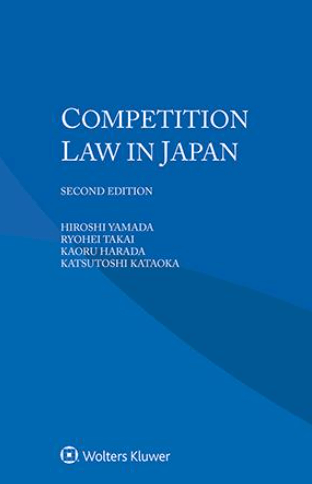
Kluwer Law International (2025年4月)
山田弘(共著)


中央経済社 (2025年5月)
長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)


大久保涼、田中亮平、佐藤恭平(共著)


(2025年7月)
德地屋圭治、李辛夷(共著)


深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


(2025年6月)
井上皓子


(2025年7月)
德地屋圭治、李辛夷(共著)


德地屋圭治、李辛夷(共著)


(2025年6月)
井上皓子


井上皓子


梶原啓


(2025年5月)
洞口信一郎


(2025年4月)
山本匡


(2025年3月)
安西統裕