
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
ニュースレター
<AI Update> 米国におけるAI大統領令発令後の取組みについてのアップデート(2024年3月)
AIの発明者性について判示した東京地裁判決 ―東京地判令和6年5月16日―(速報)(2024年5月)
<AI Update> 「欧州AI法」の概要と日本企業の実務対応(2024年6月)
<AI Update> 米国著作権局によるAI生成物の著作権保護に関する報告書の公表(2025年2月)
<AI Update> AIの学習データ利用について著作権侵害を認めた米国連邦地裁判決―Thomson Reuters v. Ross Intelligence事件―(2025年2月)
<AI Update> 欧州AI法「禁止されるAIプラクティス」に関するガイドラインの公表(2025年4月)
<AI Update> 米国AI規制の現在地―連邦及び州レベルによる規制の最新動向―(2025年4月)
令和7年1月30日、知財高裁第2部において、特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られるか等が争点となっていた事案につき、判決が言い渡されました(令和6年(行コ)第10006号)※1。
本判決は、上記争点に関し、知財高裁として初めて、AI発明(人工知能(AI)が自律的にした発明)については現行特許法に基づき特許を付与することはできないとする判断を示しました。生成AIの性能の飛躍的な向上やAIエージェントの発展等もあり、今後、発明の過程におけるAIの利用は益々活発に行われるようになることが想定されるため、本判決は重要な判断であると考えられます。本ニュースレターでは、この争点に関する本判決の判断の内容を紹介いたします。
本件において、原告は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」に関する発明について、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、国際出願を行い、その国内書面における発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載していました。なお、「ダバス(DABUS)」とは、Dr. Stephen Thaler が開発したとされるAIシステム「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字を取ったもので※2、DABUSを発明者とする特許出願は、これまで日本以外の国及び地域においても行われています。
これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者欄の氏名人を記載する補正を命じましたが(特許法185条の5第2項)、原告は、特許法にいう「発明」はAI発明(自然人が介在することなくAIが自律的に生成した発明)を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないことを理由にこれに応じなかったことから、特許庁長官は、出願却下処分(以下「本件処分」といいます。)を行いました(同法184条の5第3項)。
そこで、原告は、本件処分に対し審査請求を行ったものの、特許庁により上記審査請求を棄却されたことから、東京地方裁判所に本件処分の取消訴訟を提起しました。
東京地判令和6年5月16日(令和5年(行ウ)第5001号)※3(以下、単に「東京地裁判決」といいます。)は、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示し、原告の主張を斥けたことから、原告(控訴人)は、同判決に対し、控訴を提起していました。
知財高裁は、次の2点を、本件の争点として示しています。
争点1:特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られるか※4
争点2:国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項であるか
知財高裁は、特許法の性格(実体法及び手続法としての性格)を踏まえた上で、特許を受ける権利の発生及び原始的帰属に関する規定の解釈から、AI発明については現行特許法に基づき特許を付与することはできないと判断しました。また、この争点に関連して、AI発明について民法上の果実取得権に基づき特許を受ける権利を取得できるとの控訴人(原告)の主張も退けています。
まず、知財高裁は、特許法1条、66条1項を挙げた上で、「特許法は、特許権及び特許を受ける権利の実体的発生要件や効果を定める実体法であると同時に、特許権を付与するための手続を定めた手続法としての性格を有する」と判示しています。
次に、知財高裁は、特許法のうち「『特許を受ける権利』の発生及びその原始帰属者について定めた規定」として、自然人が発明をした場合の原始的帰属について定めた特許法29条1項柱書と職務発明の場合の使用者等への原始的帰属について定めた35条3項を概観した上で、これらの条項以外には、「『特許を受ける権利』の発生及びその原始帰属者について定めた規定・・・は存在しないから、特許法上、『特許を受ける権利』は、自然人が発明者である場合にのみ発生する権利である」と述べています。さらに、特許出願に関する各種書面において記載又は掲載されるものとされている「発明者の氏名」と、特許出願人、出願人又は特許権者についての「氏名又は名称」という文言を対比し、この観点からも、発明者が自然人であることを前提としていると判示しています。
知財高裁は、以上を踏まえて、次のとおり、特許法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られる旨判示しています(下線及び太字による強調は、筆者によります。以下、同様です。)。
そうすると、特許法は、特許を受ける権利について、自然人が発明をしたとき、原則として、当該自然人に原始的に特許を受ける権利が帰属するものとして発生することとし、例外的に、職務発明について、一定の要件の下に使用者等に原始的に帰属することを認めているが、これら以外の者に特許を受ける権利が発生することを定めた規定はない。また、同法に定める「特許を受ける権利」以外の権利に基づき特許を付与するための手続を定めた規定や、自然人以外の者が発明者になることを前提として特許を付与するための手続を定めた規定もない。したがって、同法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発明者となるものに限られると解するのが相当である。
また、知財高裁は、控訴人(原告)の主張に対応する形で、次のとおり、権利能力のない存在を発明者とする「発明」について、特許法に基づく手続により特許権を付与する余地がない旨判示しています。
・・・特許法が予定している「特許を受ける権利」の解釈は、特許法29条1項柱書の文言、同法の他の規定の文言との整合性を検討した上でされるべきものであり、検討した結果、同項柱書にいう「発明をした者」が自然人をいうものと解される・・・
・・・
・・・特許法2条1項の規定する「発明」の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)中には、発明者が誰であるかという点は明示的に含まれてはいないけれども、特許法上、特許を受けるための手続については、これまで検討したとおり、権利能力のない存在を発明者とする発明について特許を付与するための手続は定められていない。したがって、仮に、原告が主張するように特許法上の「発明」の概念自体は自然人を発明者とする場合に限られないと解したとしても、権利能力のない存在を発明者とする「発明」について、同法に基づく手続により特許権を付与する余地がないことに変わりはない。
・・・
・・・特許法の解釈として、自然人が発明者となる発明の場合に特許を受ける権利の発生及び原始的帰属が限定されていると解すべき・・・
そして、知財高裁は、小括として、争点1(特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られるか)について、次のとおり、AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく、特許法に基づきAI発明に特許を付与することはできない旨判示しています。
したがって、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、AI発明については、同法に基づき特許を付与することはできない。
そうすると、AI発明が特許法上の「発明」の概念に含まれるか否かについて判断するまでもなく、特許法に基づきAI発明について特許付与が可能である旨の原告の主張は、理由がない。
争点1に関連して、控訴人(原告)は、AIであるダバスを創作・管理する者として、民法上の果実取得権(善意の占有者(民法189条1項、205条)又は所有者(民法206条、89条1項)の果実取得権に基づき、本件出願に係る発明についての特許を受ける権利を有していると主張していました。これに対し、知財高裁は、次の3点を指摘して、控訴人(原告)の主張を退けました。
第1に、そもそもAIは有体物ではないため、所有権の対象とはならないとしました。
第2に、仮にAIの使用者が民法205条の規定にいう財産権を行使している者に該当すると考えた場合でも、「AI発明について特許を受ける権利」は、「物の用法に従い収取する産出物」又は「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」(民法88条1項及び2項)のいずれにも該当しないとしました。その理由として、AI発明について特許を受ける権利が発生する根拠規定自体が存在しないため、現行法上、これを財産権の行使に係る果実に該当するものと解することはできないとしています。
第3に、特許法が認めていない特許を受ける権利が民法の規定に基づいて発生すると解することはできず、本件において民法89条を適用又は準用することもできないとしました。
なお、この点に関し、東京地裁判決は、「同条(筆者注:民法205条が準用する同法189条)によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきである。」と判示していたことから、判断のアプローチの違いが注目に値するものと考えられます。
知財高裁は、特許法184条の5第1項柱書及び2号、同条2項柱書及び3号、特許法施行規則38条の5第1号の規定によれば、国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項として規定されていると判示しました。
その上で、「AI発明の出願において、発明者の氏名は必要的記載事項ではない」との控訴人(原告)の主張に対し、次のとおり判示しました。
・・・原告の主張は、権利能力のない存在が行ったAI発明について、特許法上、特許を付与することができると解することを前提とするものであって、この前提において誤っている・・・
・・・
現行特許法上、発明者は自然人であることが前提とされている以上、出願書類等に記載すべき「発明者の氏名」が自然人であることは当然の論理的帰結である。
控訴人(原告)は、発明者の氏名を必要的記載事項とした場合の実務上の問題点として、①発明者でない自然人を発明者として記載した出願(冒認出願)の増加を招くこと、②そのような冒認出願に係るAI発明の特許については、冒認を理由とする無効審判の請求権者である利害関係人が存在せず、無効とならないことを指摘していました。
これに対し、知財高裁は、次のとおり判示し、控訴人(原告)の主張は、自然人を発明者とする発明についてのみ特許付与が可能であるとの解釈を変更する理由にはならないと結論付けました。
原告が指摘するこれらの問題は、AI発明の存在を前提としていない現行法の問題点の一つといえるが、発明者の氏名欄の記載を必要的記載事項でないと解すれば解決するものではない・・・
原告指摘の冒認出願については、特許の拒絶の査定をする理由になる(特許法49条7号)ほか、侵害訴訟において特許無効の抗弁として主張することは可能である(同法104条の3第1項、3項)。
AI発明において同法123条2項の利害関係人(特許を受ける権利を有する者)として同条1項6号に該当することを理由に特許無効審判を請求する者が存在しないとしても、それは現行法が予定していなかった事態が生じたというだけで、特許法上、自然人を発明者とする発明についてのみ特許付与が可能である旨の前記解釈を変更する理由にはならない。
本件に関し、東京地裁は、「発明者」という概念について、知的財産基本法、特許法の各規定、及び、特許法における「発明者」にAIが含まれると解した場合の不都合性などの諸般の事情を考慮した上で、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である。」と判示し、この解釈を前提に、発明者として自然人の氏名の記載を欠く本件国内書面には形式要件違反があるとして、本件処分を適法と判断していました。
これに対し、本判決における知財高裁の判断には、以下の特徴が見られます。
すなわち、知財高裁は、特許法の手続法としての性格に着目し、現行特許法は自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めるものであると判示した上で、
これらの判断は、いずれも注目に値するものと考えられます。
本判決は、東京地裁判決においても同様の言及が見られたとおり、AI発明に特許権を付与するか否かは、発明者が自然人であることを前提とする現在の特許権と同内容の権利とすべきかを含め、AI発明が社会に及ぼすさまざまな影響についての広汎かつ慎重な議論を踏まえた、立法化のための議論が必要な問題であって、現行法の解釈論によって対応することは困難であり、立法政策についての議論の中で検討されるべき問題であるとの認識を示しています。
AIと発明を巡っては、あくまでAIを利用する自然人が「発明者」となることを前提に、発明の過程でAIを利用した場合でも特許の要件を満たすか否かも一つの論点ですが、本判決は、AIが自律的に行った発明についての特許付与の可否が問われたものであり、注目に値します。
どのような場合にAIが「自律的」に発明をしたと言い得るかはケースバイケースの判断になりますが、生成AIの性能の飛躍的な向上やAIエージェントの発展等もあり、今後、発明の過程におけるAIの利用は益々活発に行われるようになることが想定されます。日本においても、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許法の目的も踏まえ(若しくは、そのような目的を維持するか否かも含めて)、AIが自律的に発明した発明の保護の要否・方法等についてあらためて検討し、明確なルール形成を速やかに行うことが期待されます。
※1
令和7年2月12日現在、本判決の判決書は、裁判所ホームページで公開されています。(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=93757)
※3
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92981 なお、東京地裁判決については、殿村桂司・松﨑由晃「AIの発明者性について判示した東京地裁判決―東京地判令和6年5月16日―(速報)」(テクノロジー法ニュースレターNo.49・知的財産法ニュースレターNo.17合併号(2024年5月))もご参照ください (最終アクセス:2025年2月12日)。
※4
これに対し、東京地裁判決では、本件の争点は、「特許法にいう『発明』とは、自然人によるものに限られるかどうか。」とされています。
※5
現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているから、(本件における人工知能(AI)を含む)権利能力のない存在を発明者とする発明について特許権を付与する余地がないこと。
※6
また、その過程において、特許法における「発明」の概念自体が自然人を発明者とする場合に限られるか否か(ひいてはAI発明が特許法における「発明」に含まれるか否か)について明示的に言及ないし判断を避けている点も、注目に値するものと考えられます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年8月)
殿村桂司


(2025年8月)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
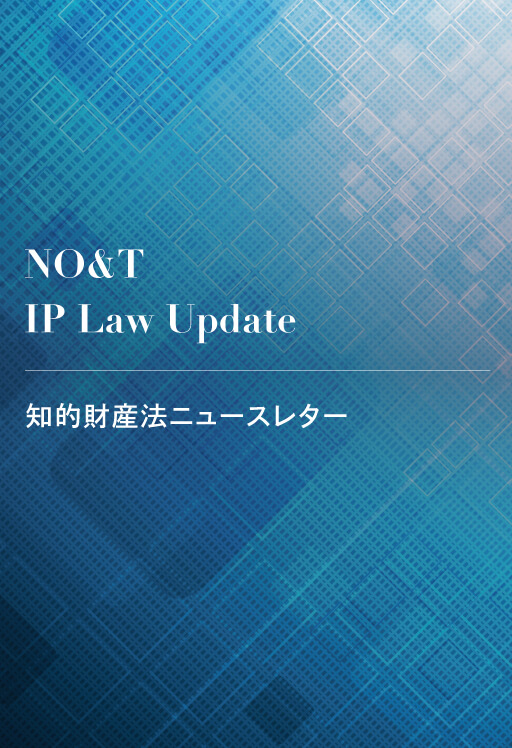
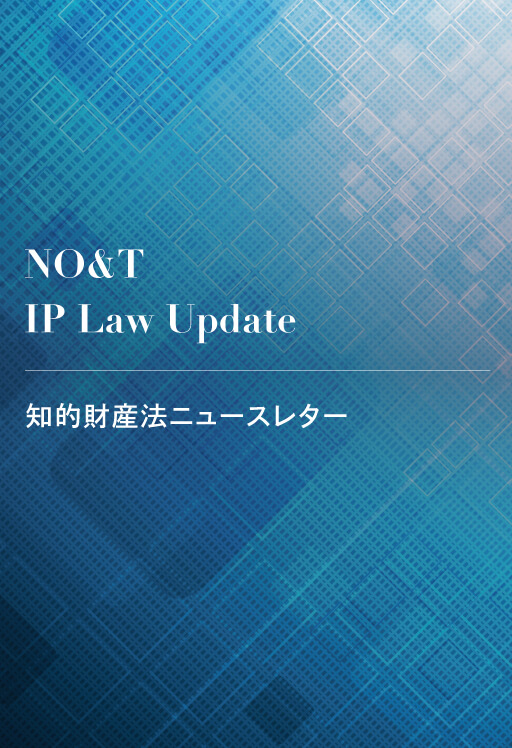
東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
東崎賢治
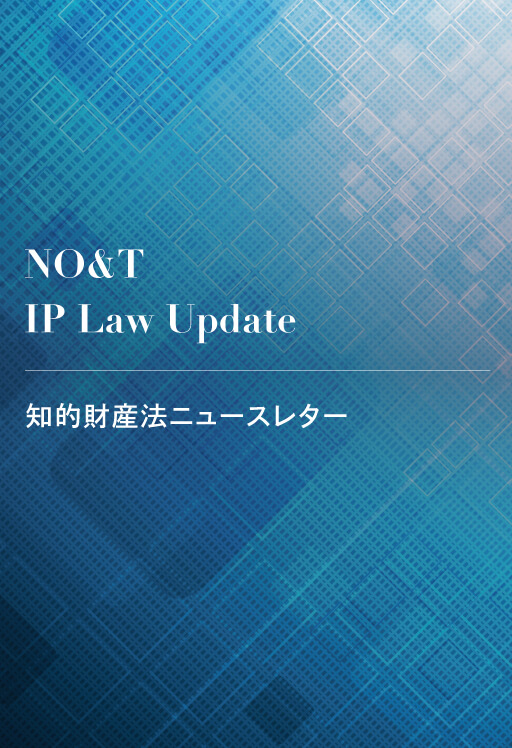
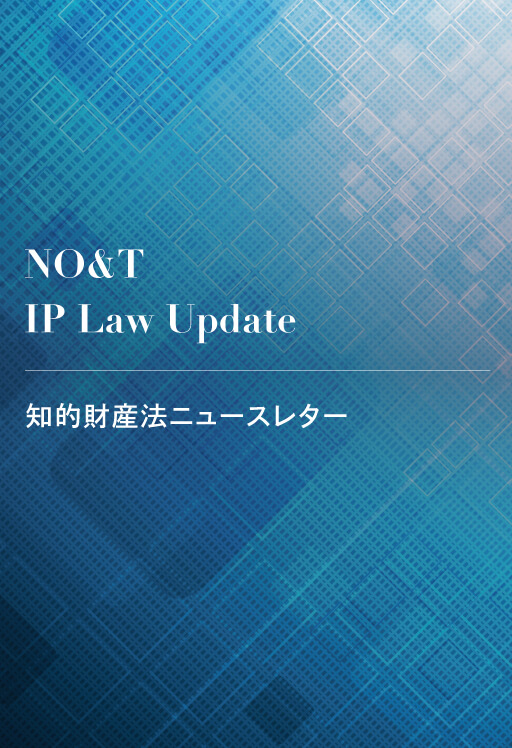
東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


(2025年10月)
髙取芳宏


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


梶原啓


(2025年10月)
東崎賢治