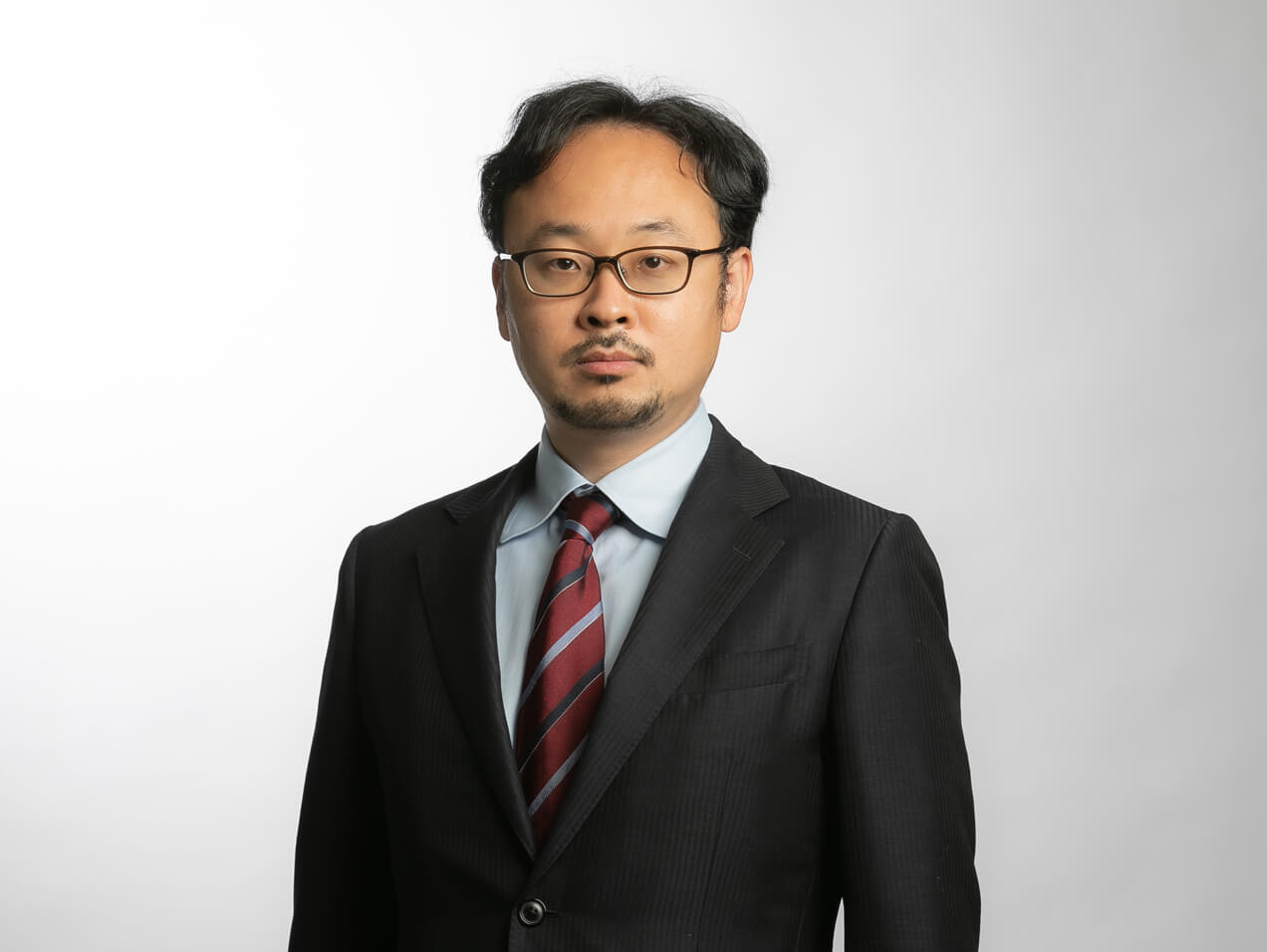
細川智史 Satoshi Hosokawa
パートナー
東京

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
ニュースレター
セキュリティ・クリアランス法案の概要(小林鷹之議員及び立法担当官と語る経済安全保障の最前線セミナーに向けて)(2024年5月)
セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理(後編) ~既存従業員の取扱い・業務委託時の留意点~(2025年3月)
特集
経済安全保障
2024年5月10日に成立した「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(以下「法」又は「重要経済安保情報保護活用法」といいます。)に基づく経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の運用が2025年5月16日に開始されることが決定しました。この制度の下、民間事業者は、日本国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報(法3条1項)の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合すること(法10条1項)等を条件に、日本政府が保有する重要経済安保情報の提供等を受けることができますが、重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業務「を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者」(法12条に基づく適性評価を受けてクリアランスを付与された者)をして行わせなければなりません(法11条1項)。
基本的な⼈権の尊重やプライバシー保護(憲法13条)の観点から、適性評価は従業者本人の同意を前提として行われることとされており(法12条3項)、民間事業者が従業者に適性評価を受けるよう命じることはできません。また、民間事業者は、適性評価の実施に当たって取得する個⼈情報を原則として重要経済安保情報保護以外のために利⽤・提供してはならず(法16条2項、2025年1月31日付「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準※1」(以下「運用基準」といいます。)4章4節3)、また、適性評価の結果等を適切に管理して、適性評価の結果を考慮して解雇・減給や⼈事考課上の不利益評価等を⾏ってはならないとされています。このように、今般のセキュリティ・クリアランス制度は、民間事業者にとって、重要経済安保情報の提供等というメリットを享受できる可能性がある制度である一方、民間事業者に対して、クリアランスが必要な業務に従事させる又はその予定の従業者について、労働法のみならず、重要経済安保情報保護活用法(及びその背景にある従業者の基本的人権・プライバシー等)まで考慮に入れた人事労務管理を行うことを求める制度であるともいえます。
当事務所では、このように経済安全保障法制と人事労務法制が交錯する場面においては、経済安全保障法に関してと、人事労務に関しての、それぞれに豊富な知見・経験を有する弁護士が協働しながらリーガルサービスを提供しております。本ニュースレターにおいても、経済安全保障法・労働法に詳しい弁護士が協働し、セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理に関する留意点を解説します。
上記のとおり、行政機関の長が適性評価を実施するためには、評価対象者の同意を取得することが必要とされています(法12条3項)。また、同意を得て適性評価が実施されても、その結果、重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められなかった(すなわち、クリアランスを取得できなかった)者は、当該情報を取扱う業務に従事することはできません(法11条1項)。そのため、適合事業者が重要経済安保情報を取扱う業務に従事させることを想定して新たに従業員を採用した場合でも、その後、当該従業員が適性評価の実施に同意せず、あるいは適性評価の結果、クリアランスを取得できなければ、当該業務に従事させることができなくなるという事態が生じます。このとき、当該従業員の職種が限定されていないのであれば、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事できない以上、それが必要となる業務からの配置転換それ自体は法的には通常許容されると考えられますが、かかる配置転換が不利益な配置の変更とならないようにすることが必要となる上(運用基準別添1の7参照)、そもそも適合事業者にとってそのような人材を雇用し続けるメリットが見出せないケースもないとはいえません。
そこで、重要経済安保情報を取扱う業務や職種に限定した上で従業員を募集及び採用することが考えられます。このような職種限定の合意を行う場合には、少なくとも、労働契約書や労働条件通知書等の書面で明示的に職種を限定するべきです。
では、職種限定の合意をした上で採用しようとしている従業員について適性評価が実施されたところ、クリアランスを取得できなかった場合、当該従業員の採用内定を取り消す又は解雇することはできるのでしょうか。
一般論として、採用内定の取消しや解雇が有効となるためには、取消事由や解雇事由があるだけでは足りず、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であることが必要です(労働契約法16条)。この点、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事させることに限定して募集し、採用対象者がクリアランスを取得できなかった場合は、(実務的にはまずは採用辞退や自主退職に係る当該対象者の個別的同意を得るべく説明・協議を行うのでしょうが、それでもなお対象者が雇用継続を望む場合)「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であると認められるべきと思われます※2。もっとも、これらの要件を充足するか否かに関しては、最終的に裁判所の判断に委ねられるため、裁判所の判断の予測可能性も踏まえて、採用内定前に求職者に適性評価を受けてもらい、適性評価の結果を確認してから内定を出すことが望ましい場合が多いと考えます。
なお、採用・内定前の者は、現に適合事業者の従業者であるわけではありませんが、以下のとおり、重要経済安保情報を取扱うという条件で採用する限り、「重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者」(法12条1項1号)として適性評価の対象となり得る旨を、今後のガイドライン又はQ&Aで明示することが予定されています。
「重要経済安保情報を取扱うことが見込まれる者」には、たとえば、求職者などは含まれるのか。(略)
(注)2024年11月26日付第5回重要経済安保情報保護活用諮問会議資料「運用基準の補足として今後定めていくもの」※3(以下「運用基準補足」といいます。)2(2)から引用
もっとも、適性評価調査の期間が長期にわたる場合、その結果が出るまで求職者を待たせることが現実的ではない場面もあるように思われます。この点、調査期間については、「適性評価の結果を通知するまでの間において、いたずらに時間を要すことのないようにしなければならない」(運用基準4章2節7(5))とされるにとどまっています。政府は今後のガイドライン又はQ&Aにおいて目安となる期間を示すことも検討していますが※4、そもそも、重要経済安保情報を漏えいするおそれの有無は、評価対象者の個別具体的な事情を考慮して判断されることから、調査期間は、かかる事情に応じて変わり得るものと考えられます。そのため、適合事業者としては、実際の運用の一般的な傾向は注視しつつも、個別の評価対象者に係る調査期間の想定は基本的に困難である前提で、対応を検討していく必要があるところ、(求職者に対する市場のニーズ等によるものの、)例えば、求職者の理解を得た上で、適性評価の結果が出るまでは求職者に待ってもらう等といった対応が安全であるように思われます。
重要経済安保情報の取扱いの業務に従事させることを念頭に採用を行う場合、適合事業者側で、適性評価において適性があると認められるかどうかを予測する目的で、求職者に関する情報を収集したいという場合が想定されます。このような対応は許容されるでしょうか。
この点について、適性評価調査の対象となる事項(法12条2項各号)に係る情報には、「要配慮個人情報」(個人情報保護法2条3項、個人情報保護法施行令2条)が含まれるところ、要配慮個人情報を取得するためには、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります(個人情報保護法20条2項)。さらに、求職者等の個人情報は、「業務の目的の達成に必要な範囲内で」(職業安定法5条の5)のみ収集することが許容されています。この点に関して、職業安定法に基づく指針によると、求職者等の個人情報の一部(社会的差別の原因となるおそれのある事項など)は、「特別な職業上の必要性」が存在するなど、個別に合理性、必要性がある場合に限り、収集することができるものとされています※5。
以上に加え、適性評価の実施者が「行政機関の長」であって(法12条1項)一定の裁量があるためいかなる情報を収集したとしても適性評価の結果自体を事前に確実に予測することはできないことに鑑みれば、今後この点に関してガイドラインやQ&A等で別段の解釈が示されない限り、適合事業者において求職者を対象とする適性評価の結果を事前に予測しようと試みることは、「特別な職業上の必要性」ではないと解される可能性があります。そのため、適合事業者においては、求職者に関する情報を積極的に収集した上で、適性が認められると予測される者を採用する、という対応をするのではなく、あくまで、適性評価の結果が出た後に、適性があると認められた者を採用することにならざるを得ないように思われます。
また、上記のとおり、求職者に関する情報の収集には法令上の制限があることに加えて、適性評価において適性があると認められるかどうかは、行政機関が独自に保有・収集する情報をも踏まえて判断する以上、適合事業者がどれだけの情報を収集しても、確実に予測することは困難です。このような観点からも、かかる情報の収集にコストをかけないという選択肢にも合理性があり、そもそも、仮に適性評価において適性があると認められなかった場合において、重要経済安保情報の取扱いの業務以外の業務に従事させてもよいような求職者に限って、採用の対象とするという対応もあり得るように思われます。
なお、適性評価調査において評価対象者が記載する質問票の記載事項には、本人及び家族の「日本国籍」、「帰化歴」及び「外国籍」、並びに「外国政府等との関係」、「海外への居住」等が含まれていますが(運用基準別添5)※7、適性評価を予想する目的で行う国籍の情報の収集は、「業務の目的の達成に必要な範囲内」(職業安定法5条の5)に含まれず、少なくとも適性評価の結果を予測する目的で求職者に外国籍か否かを尋ねることは許されないということになると考えられます※8。
次に、適合事業者が採用しようとする者が過去に行政機関の職員又は他の適合事業者の従業者としてクリアランスを保有していたケースについて考えてみましょう。
まず、当該採用予定者が直近で受けた適性評価が、当該適合事業者の取扱う重要経済安保情報の提供元である行政機関の長によって実施され、かつ当該適性評価において重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた場合(すなわち、採用予定者にクリアランスを付与した行政機関と適合事業者に重要経済安保情報を提供した行政機関が同じ場合)、当該適性評価の結果の通知日から10年※9を経過しておらず、「引き続き当該おそれがないと認められる」ときは、そもそも当該採用予定者は新たに適性評価を受ける必要がありません(法12条1項1号イ)。これに対し、当該採用予定者にクリアランスを付与した行政機関と当該適合事業者に重要経済安保情報を提供した行政機関が異なる場合、当該採用予定者は新たに適性評価を受ける必要がありますが、直近で受けた適性評価の結果の通知日から10年を経過していない限り、新たに適性評価のための「調査」を受ける必要はなく、前回の適性評価において行われた調査の結果に基づいて適性評価を受けることになります(法12条7項)。
このように、過去にクリアランスを取得した者については適性評価又は調査が不要とされる余地が相応にあることから、こうした者を採用することには、適合事業者側としてもスムーズな採用と業務配置が可能となるというメリットがあります。また、一般論としては、過去に行政機関においてクリアランスを取得した者は、当該行政機関において安全保障上重要な職務に関与し、安全保障関連分野に係る知見が豊富である可能性が高く、また他の適合事業者の従業者としてクリアランスを取得していた者についても、重要経済安保情報の取扱いに関する実務上のノウハウや経験を有することが期待されます。したがって、その者が担当していた具体的な職務内容等にもよりますが、企業等がクリアランス保有者を新たに採用することは、経済インテリジェンス能力や情報保全体制を強化させるという観点からも有益であり得る可能性があります。
その上で、過去にクリアランスを保有していた者を採用しようとする場合において、適合事業者において当該採用予定者が本当にクリアランスを保有していたか(過去の適性評価において「漏らすおそれがないと認められた者」であったか)否かをどのように確認するかという問題があります。
この点、クリアランス保有者であることの対外的な証明については、「証明書」の発行といった方法も想定されますが、本ニュースレターの執筆時において、具体的な検討がなされているか否かを含めて明らかではありません※10。仮にこのような証明書の発行が実現しない場合、単に行政機関への照会を行うだけでは回答はなされないため(法16条1項参照)、適合事業者側としては、まず当該採用予定者本人に対して、いずれの行政機関から適性評価をいつ受けたのかを質問することが考えられますが、本人の記憶が明確でないなどの理由により、正確な確認が必要となるケースも想定できます。この場合には、当該採用予定者について行政機関の長に対し適性評価の実施を求めた上、それに対する行政機関側の対応を通じてクリアランス保有の有無を確認せざるを得ないと思われます※11。このようなケースでは、採用や業務配置のタイミングを決めるにあたり、採用予定者がクリアランス保有者であることの確認に相応の時間を要することも考慮に入れる必要があるでしょう。
加えて、採用予定者がクリアランス保有者であったことを確認できた場合においても、採用予定者が過去の職場でどのような重要経済安保情報を取扱っていたか、又はどのような業務を行っていたか、といった点については、採用予定者の適性評価を実施しても明確にならない可能性があります。これらの点についても、採用予定者本人へのインタビューで確認することが考えられますが、その際、採用予定者本人に法23条1項の漏えい罪や国家公務員法等の守秘義務違反罪に当たる行為を求めることのないよう、質問の仕方等について注意が必要であるほか、求職者等の個人情報の収集に関する限界について、採用対象者に新たにクリアランスを取得させる場合と同様の留意が必要です。
(後編に続く)
※2
2025年1月31日に公示された、運用基準案のパブリック・コメントに対する回答(以下「運用基準案のパブリック・コメント」といいます。)においては、適性評価により適性が認められなかった者の採用・内定取消は可能かという質問に対し、内閣府から「少なくとも、重要経済安保情報保護活用法の観点からは、問題が生じるものではありません」との回答がなされています(164番)。
※4
運用基準補足2(5)
※5
「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」第五の一(二)参照https://www.mhlw.go.jp/content/001003997.pdf
※6
法12条2項各号に掲げる調査事項以外の調査は禁止されています(運用基準4章1節3)。
※7
運用基準案のパブリック・コメントにおいては「評価対象者の国籍が外国籍であることのみをもって、直ちに適性があると認められないと判断されるわけでな」いとされています(131番ないし133番)。
※8
外国人雇用管理指針の「事業主においても、職業紹介事業者等に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること」(第四の一の1ロ)とされております。
※9
直近で受けた適性評価が特定秘密保護法に基づくものであった場合、この期間は5年になります(法12条1項1号ロ)。
※10
運用基準案のパブリック・コメントにおいても証明書の発行を要望する旨の意見が出されていますが、これに対する政府の回答は「御意見は今後の参考とさせていただきます」というものにとどまっています(306番)。
※11
運用基準補足2(4)
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年9月)
鹿はせる、温可迪(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


(2025年9月)
若江悠


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


箕輪俊介


(2025年10月)
清水美彩惠


安西統裕、一色健太(共著)