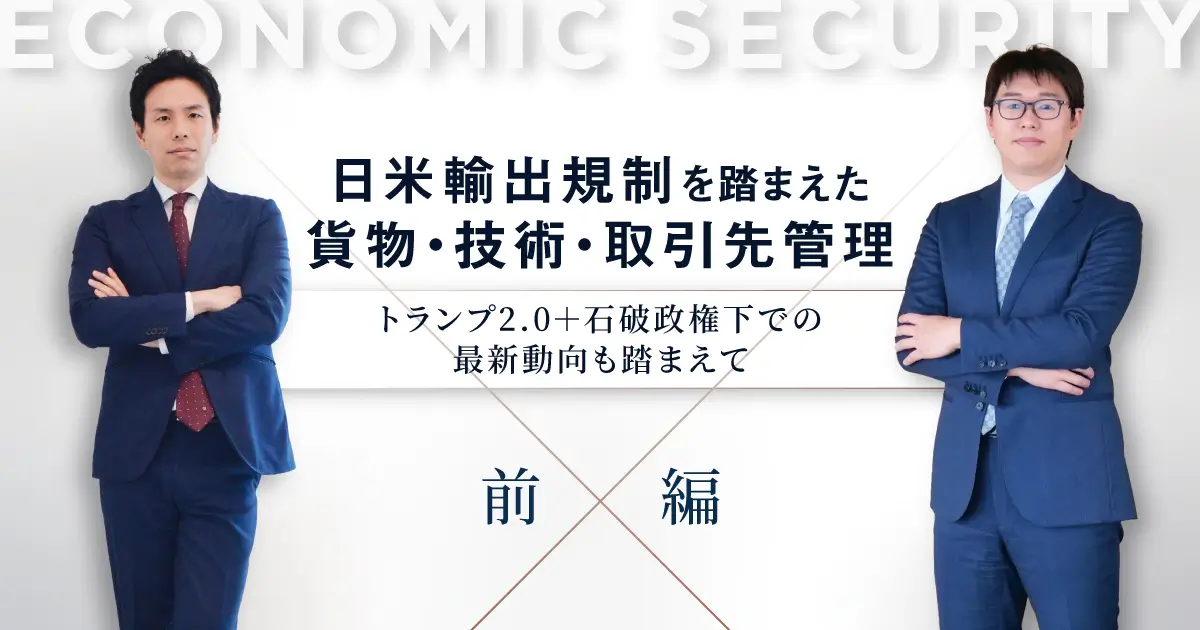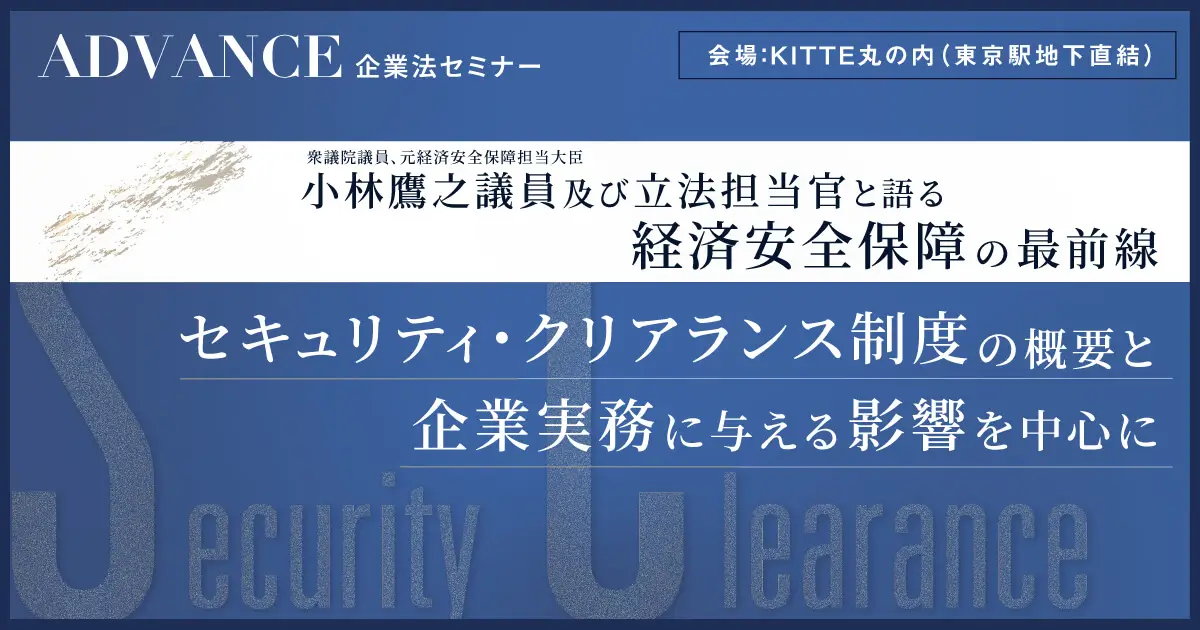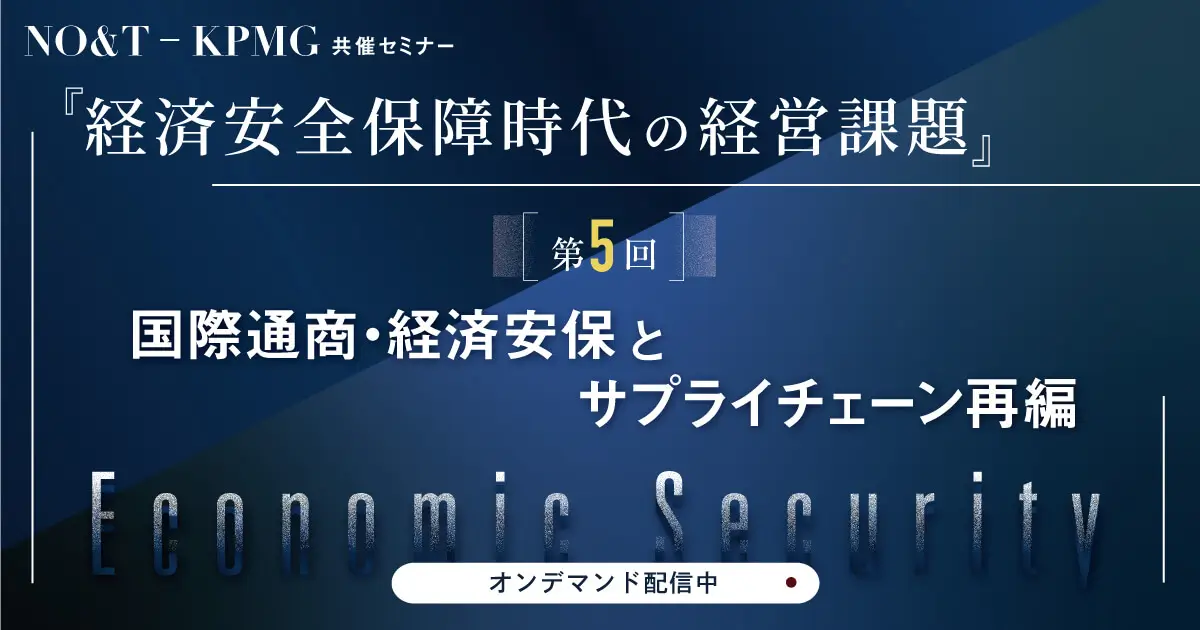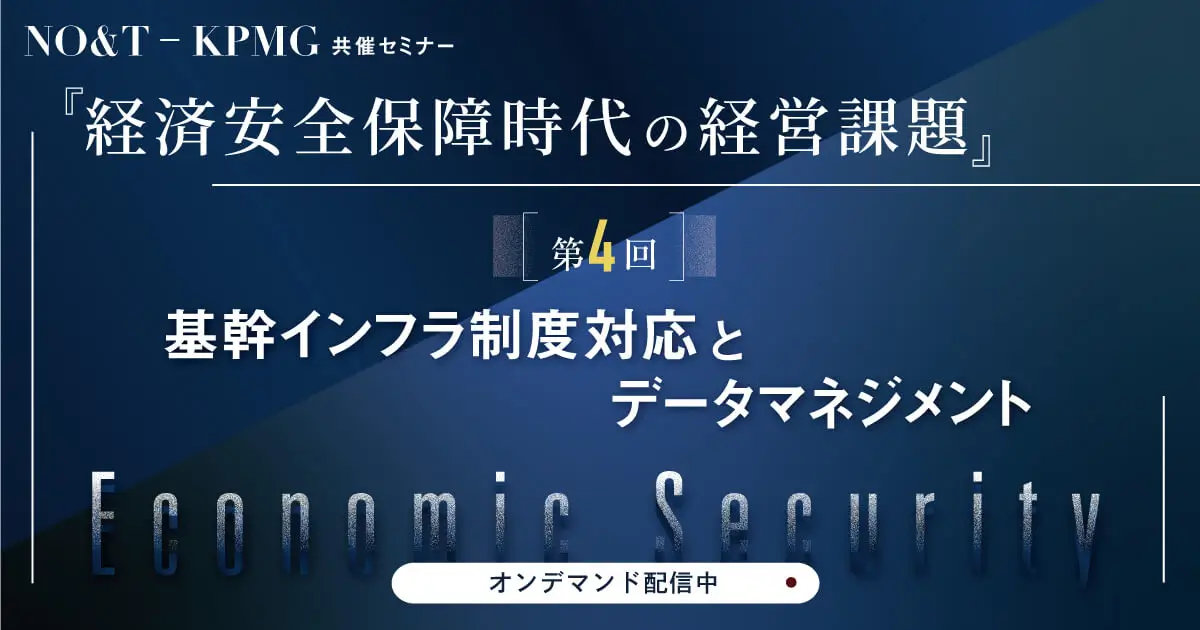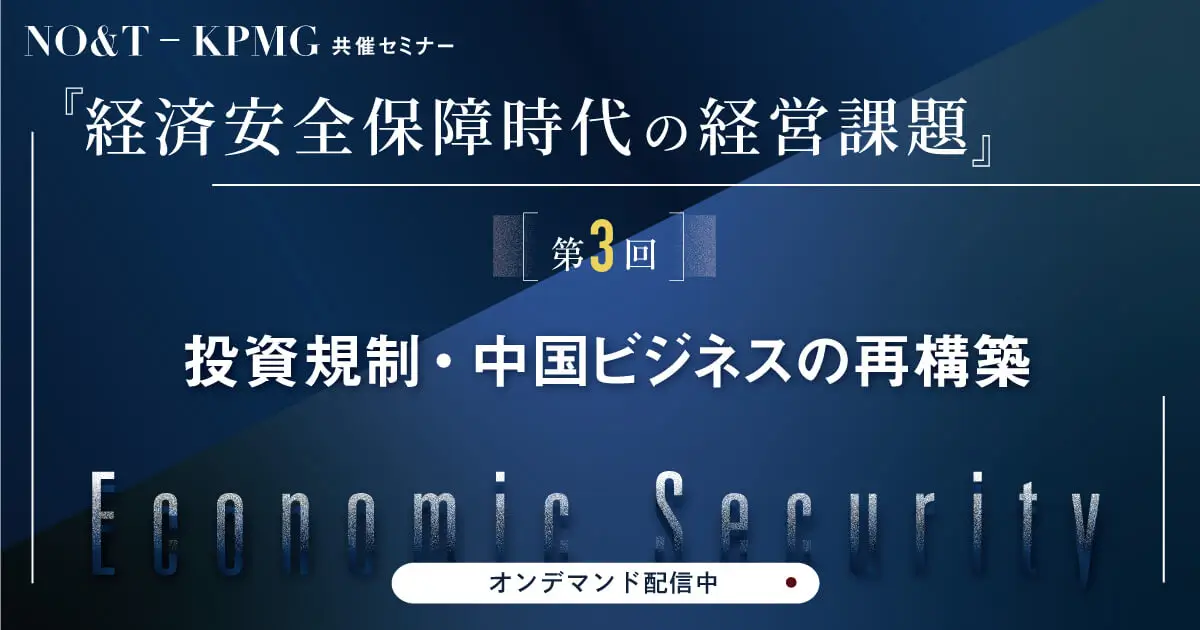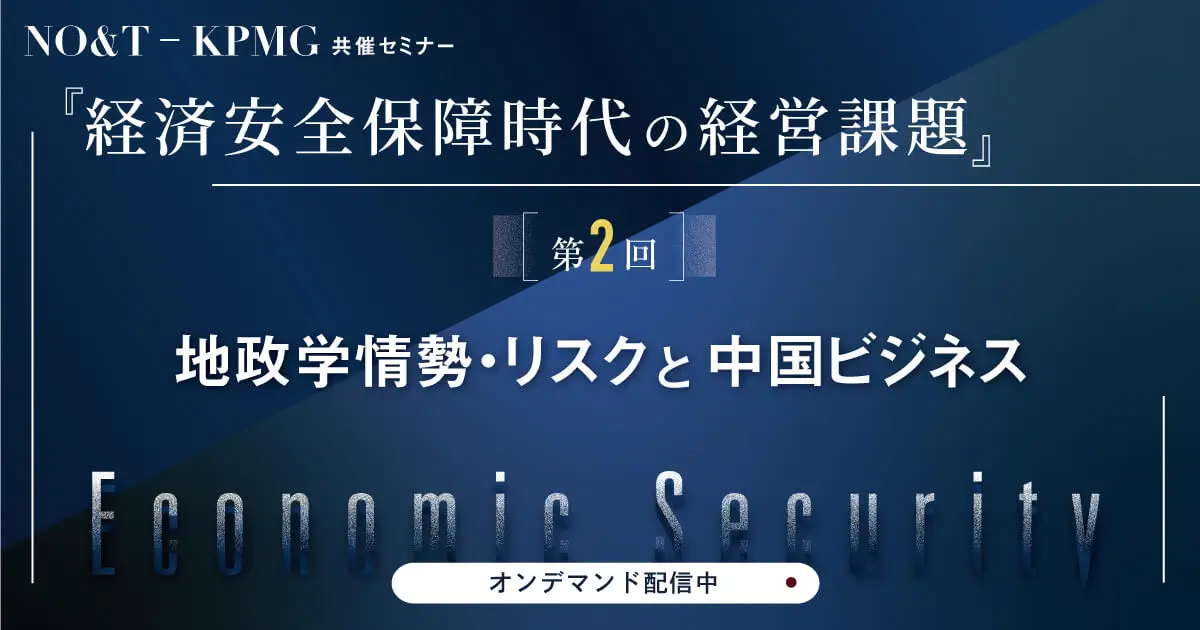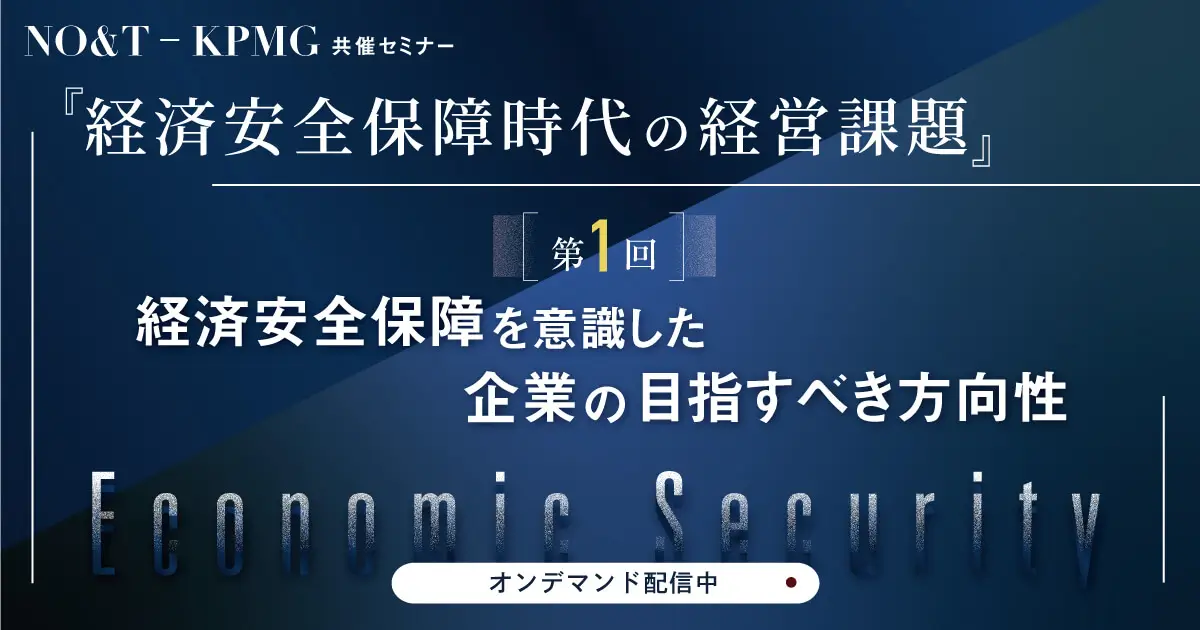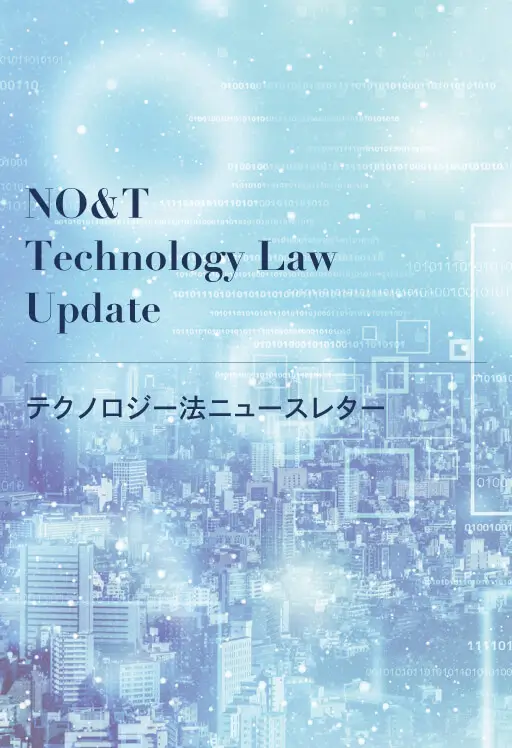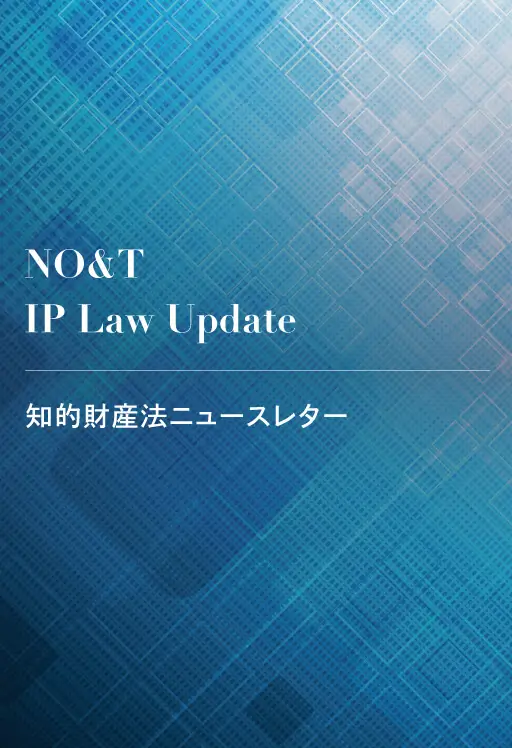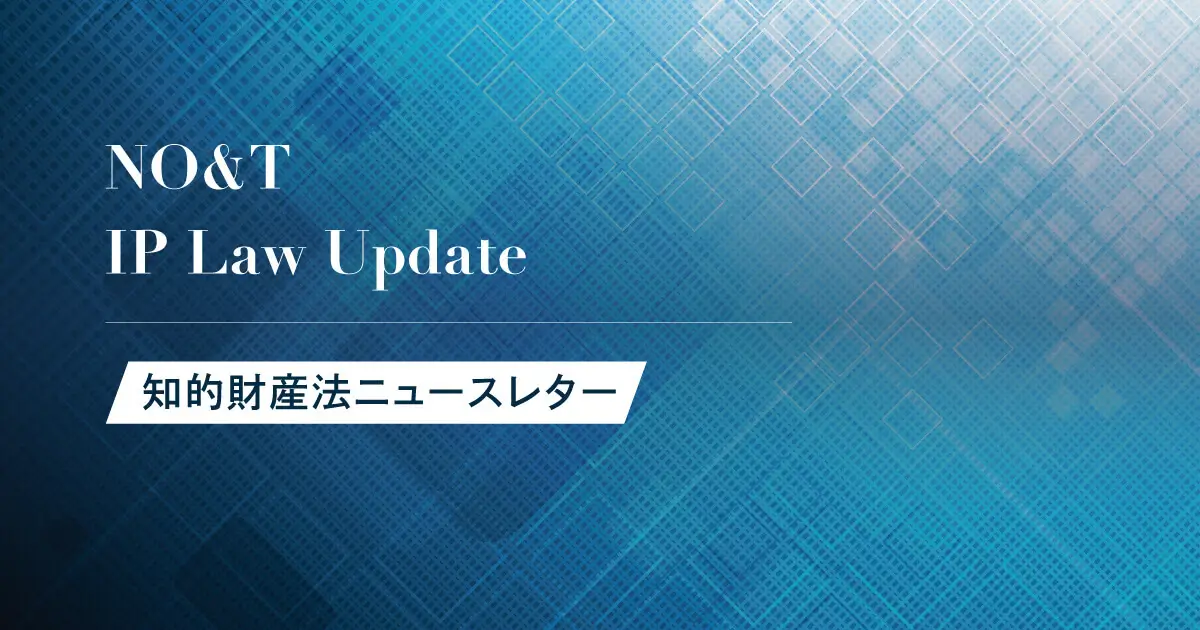経済安全保障
Economic Security
経済安全保障で求められる
法務対応
従来、防衛等ハードな側面を中心に捉えられてきた国家安全保障について、経済上の手段によっても侵害され得ることを前提に、経済活動の促進と規制等を通じて国益等を保護するという #経済安全保障 に関心がもたれ、各国において経済安全保障政策が積極的に採用されてきています。
また、ロシア・ウクライナ危機では、経済制裁が軍事行為への対抗手段として採られ、安全保障とは逆に、経済上の手段が外交的な目的を達成するために用いられることを現実的に示すこととなりました。他方で、経済のグローバル化が進んだ現在、全ての経済活動を国内で完結させることは現実的ではない中で、経済安全保障政策は、WTO体制のもとで保障されている自由かつ公正な経済活動を制約するものともなり得ます。このような世界経済、市場の動向を踏まえて、各国の経済安全保障に係る措置、規制が、企業の経済活動に及ぼす影響は、今後益々増えることはあっても、減ることはないでしょう。
経済安全保障に係る措置、規制や経済制裁につき、各国間での協調が進む一方で、米国など広範な域外適用を行う法域もあり、逆に、中国など、それら措置等に対抗する立法を行う動きも相次いでおり、各企業は、複数法域の規制を念頭におきつつ現実的な判断を行う必要があります。当事務所は、米国や中国等における拠点や、現地法律事務所等のネットワークをもいかし、企業が事業活動をグローバルに展開する上で、関連する国内及び国外の従来型の安全保障関連規制だけでなく、経済安全保障に関わる規制や最新の動向を踏まえてアドバイスを提供しています。
また、経済のグローバル化による世界規模で密接に関連したサプライチェーン、流通、金融の体制は、経済制裁の発動や感染症の流行等の突発的な事象によって多大な影響を受けることが現実的なリスクとして認識されるに至っています。当事務所は、有事における対処、有事により顕在化する法的リスクに対する予防的対応等についても、アドバイスを提供しています。
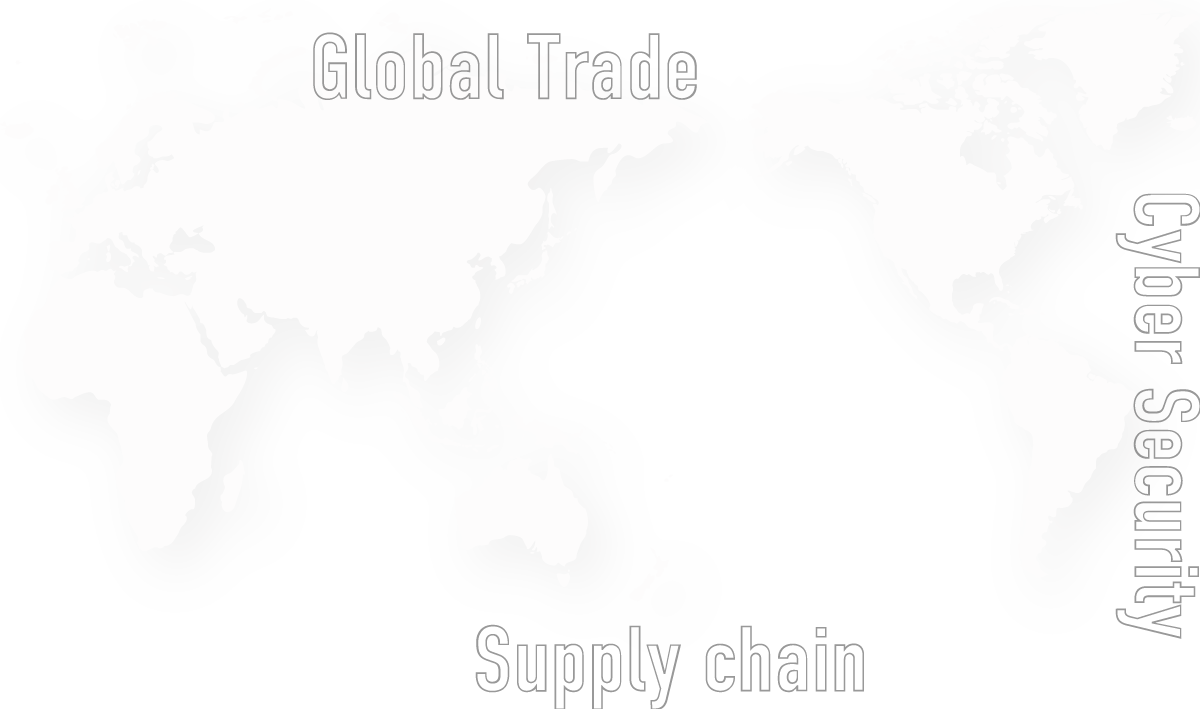
Focus
01日本
経済安全保障対応総論
経済的手段を用いた国家の戦略的目的の追求、技術領域における覇権争いの加速などを背景に、経済施策と安全保障の関わり合いが強まっています。日本政府も、経済安全保障推進法の制定、貿易管理・投資規制の強化など、経済安全保障に関わる施策を次々に打ち出しており、企業が経済安全保障に関わる法規制が自社に与える影響を考える必要性は、これまでにないほど高まっています。
当事務所では、経済安全保障対応に関する豊富な経験と最新の規制動向の知見を有しており、企業における経済安全保障関連法全般に関するアドバイス、経済安全保障の観点を踏まえた個別案件対応のサポート等を提供しております。
著書/論文/ニュースレター

セキュリティー・クリアランス始動 労務と安保の板挟みも

- 日本経済新聞電子版 2025年4月25日
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 労働法
- 労働法アドバイス

セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理(後編) ~既存従業員の取扱い・業務委託時の留意点~
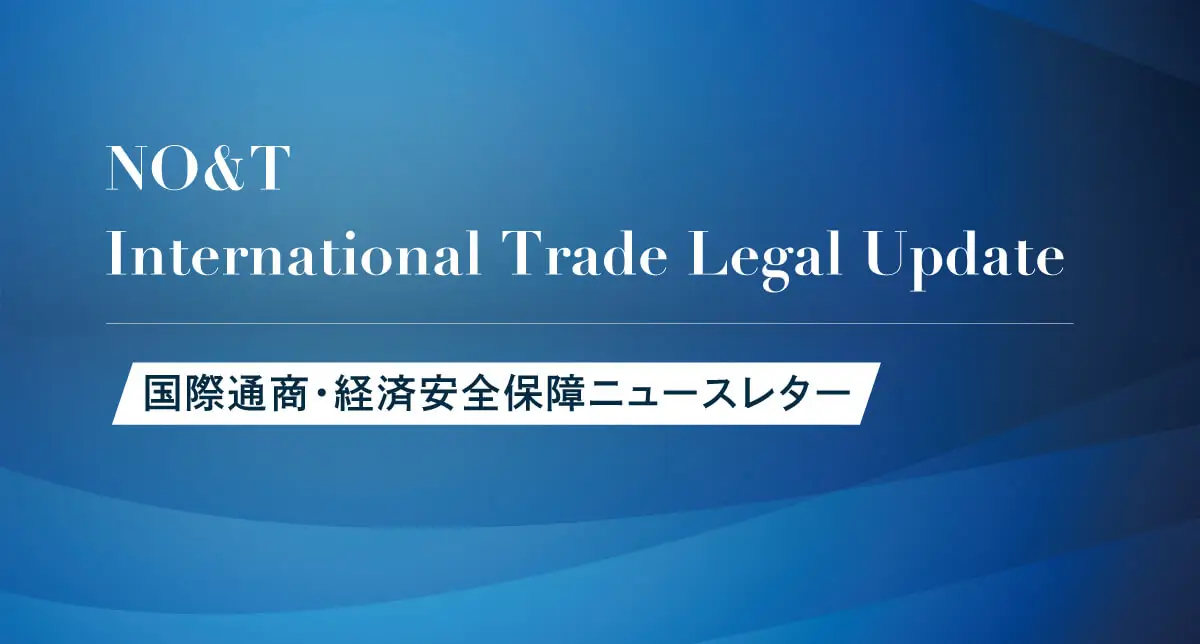
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2025年3月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 労働法
- 労働法アドバイス

セキュリティ・クリアランス制度下での人事労務管理(前編) ~従業員の新規募集・採用時の留意点~
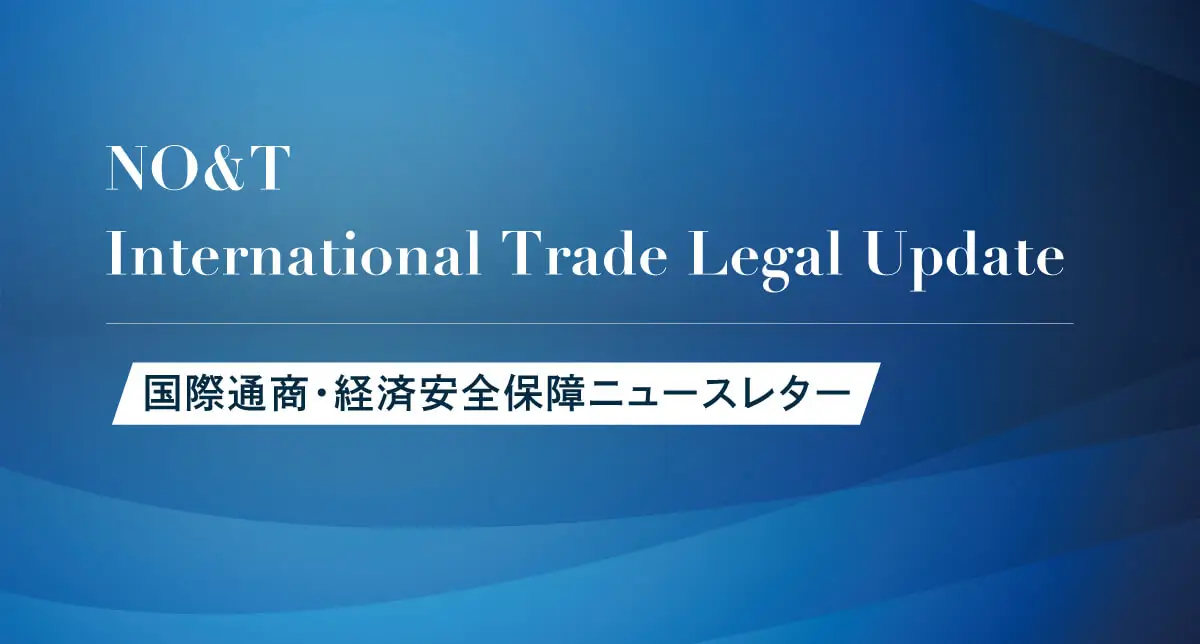
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2025年2月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 労働法
- 労働法アドバイス

経済安全保障法制と不動産業界への影響

- ARES不動産証券化ジャーナル Vol. 82 (December 2024)
- 不動産・REIT
- 不動産投資/証券化
- 不動産ファイナンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

経済安保・地政学リスクに備える攻めと守りのインテリジェンス機能とは(前編)(後編)

- KPMGコンサルティング
- コーポレート
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

セキュリティ・クリアランス法案の概要(小林鷹之議員及び立法担当官と語る経済安全保障の最前線セミナーに向けて)
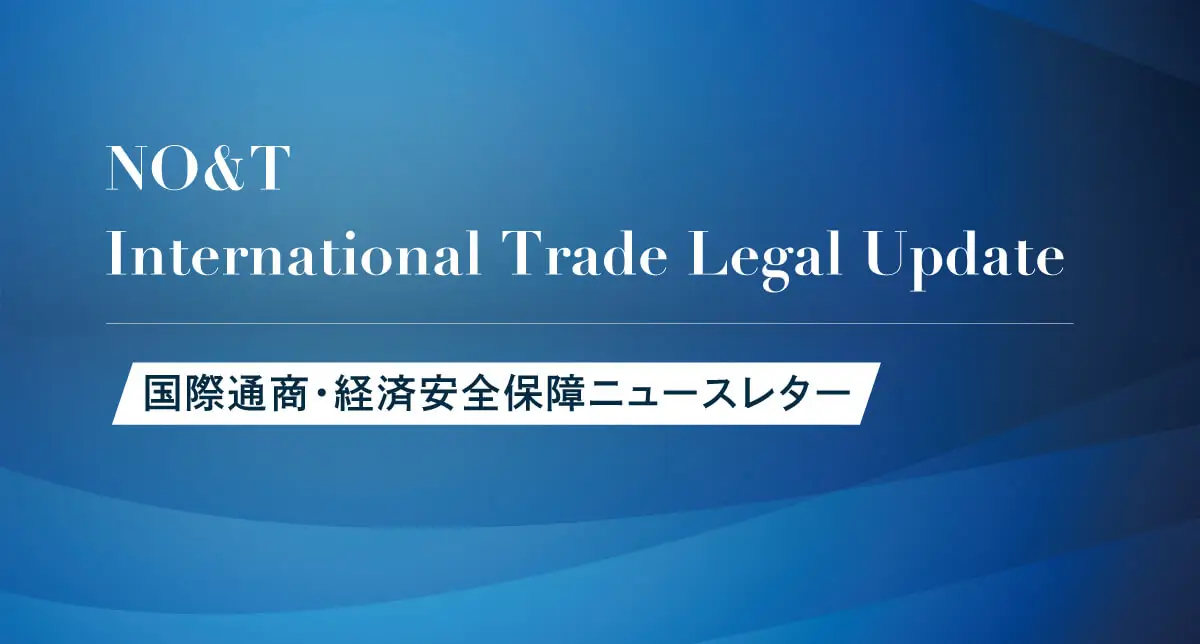
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 労働法
- 労働法アドバイス
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

Japanese security clearance bill likely to face implementation challenges

- Mlex
MLex News Articles
- コーポレート
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 労働法
- 労働法アドバイス
- 海外業務

LAWYERS GUIDE 2024(経済安全保障)

- Business & Law
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤役務(基幹インフラ役務)の安定提供確保に関する基本指針の決定と実務上の留意点
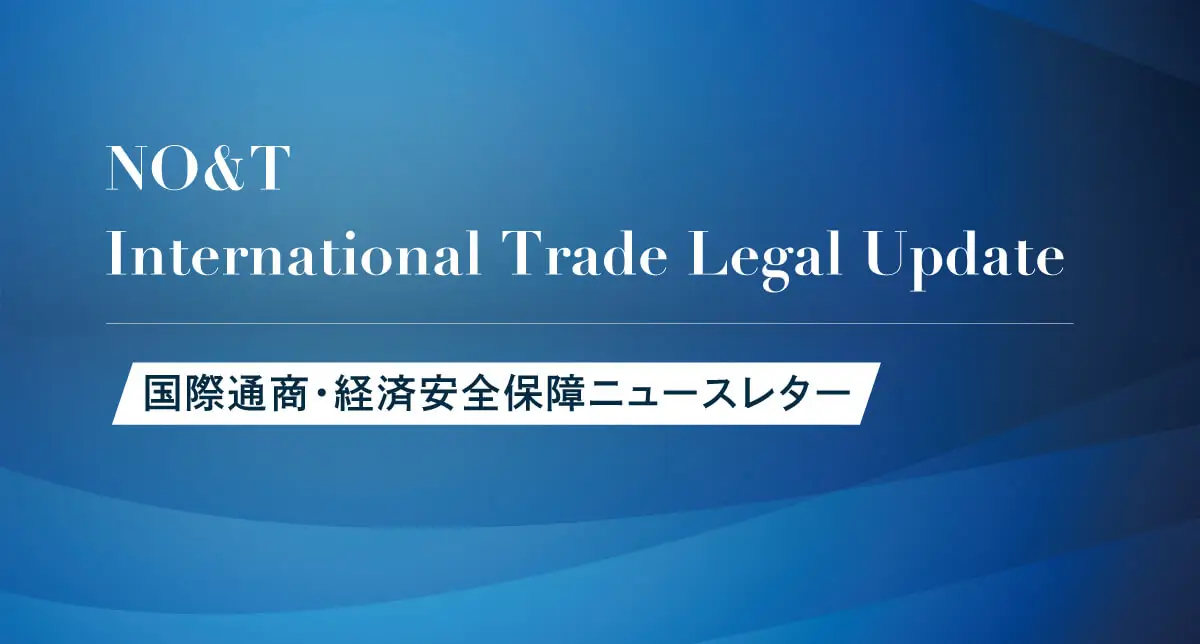
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
- Compliance Legal Update ~危機管理・コンプライアンスニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

日本企業の経済安全保障を考える

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2023年4月5日号(No.2323)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

外国資本の受入れと経済安全保障〔下〕 ─日本企業に求められる検討─

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2022年12月25日号(No.2314)
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

外国資本の受入れと経済安全保障〔上〕 ─日本企業に求められる検討─

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2022年12月15日号(No.2313)
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

経済安全保障推進法に基づく基本方針・基本指針の策定
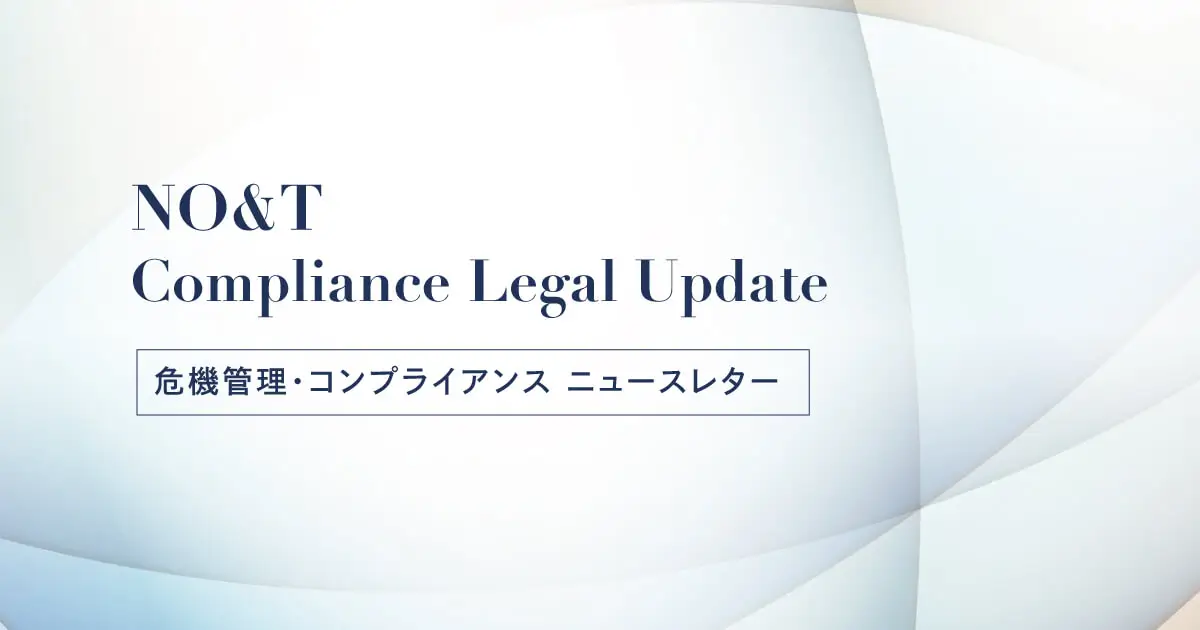
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2022年10月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

経済安全保障推進法の実務対応をさぐる 契約実務、企業コンプライアンスへの影響と対応

- 中央経済社
ビジネス法務 2022年9月号(Vol.22 No.9)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務

経済安全保障推進法の成立
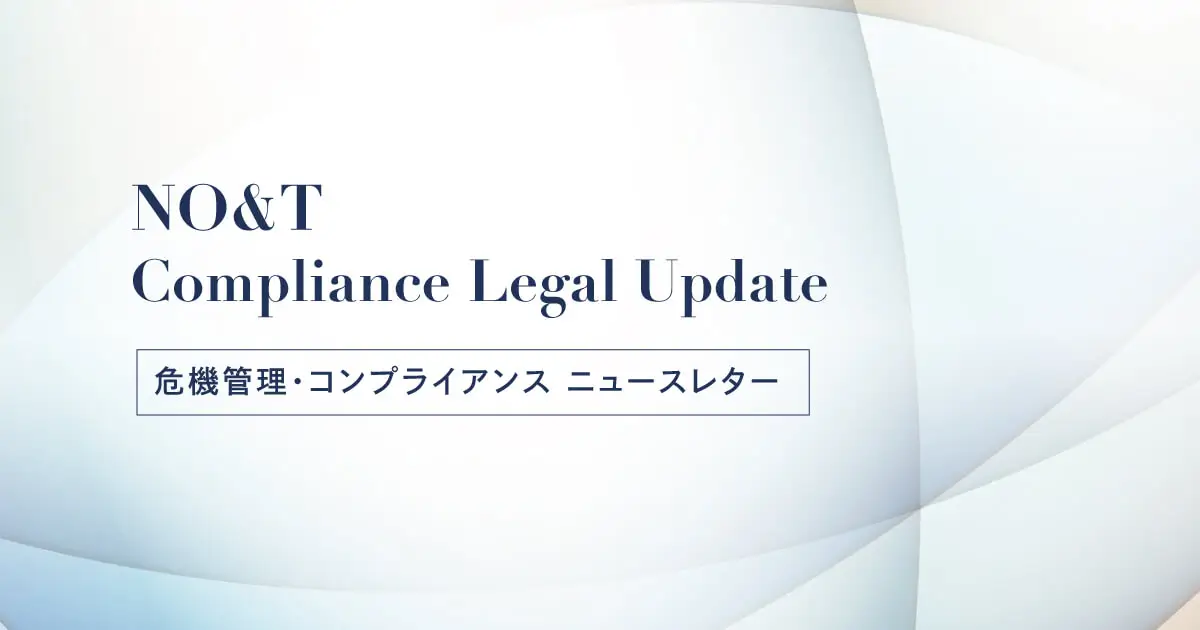
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2022年5月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
講演/セミナー

<緊急特別企画>米国関税措置に対して日本企業に求められる取組みと着眼点 ~関税措置の現状と企業対応を短時間で解説いたします~
企業研究会セミナールーム(オンライン受講もあり)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

【緊急開催】大関税時代に求められる日本企業の取組みと考え方 ~自国優先主義による自由貿易体制の危機に、法務部門を含めた全社でどう立ち向かうべきか~
オンライン(ライブ配信・オンデマンド配信)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

アジャイル・ガバナンス シンポジウム 4th
京都大学時計台記念ホール(両日ともオンライン参加可能)
- テクノロジー
- AI・ロボット
- デジタルプラットフォーム
- デジタルトランスフォーメーション(DX)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- コーポレート
- コーポレートガバナンス

場面で学ぶ 経済安全保障とリスクマネジメント ~法務部門は何ができるか、何をすべきか~
商事法務 会議室
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

セキュリティ・クリアランスを企業の力に~法施行前の準備と実務上の論点
オンライン
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
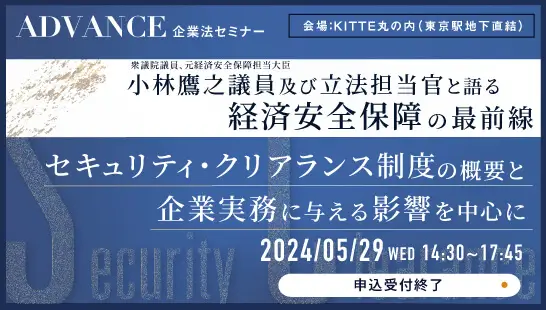
小林鷹之議員及び立法担当官と語る経済安全保障の最前線:セキュリティ・クリアランス制度(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)の概要と企業実務に与える影響を中心に
JPタワー ホール&カンファレンス(KITTE丸の内4階・東京駅 地下直結)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

アジャイル・ガバナンス シンポジウム 3rd
京都大学時計台記念ホール(両日ともオンライン参加可能)
- テクノロジー
- AI・ロボット
- デジタルプラットフォーム
- デジタルトランスフォーメーション(DX)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- コーポレート
- コーポレートガバナンス

経済安全保障推進法の概要と実務動向
東京都立産業技術研究センター 本部(東京イノベーションハブ)及びオンライン
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
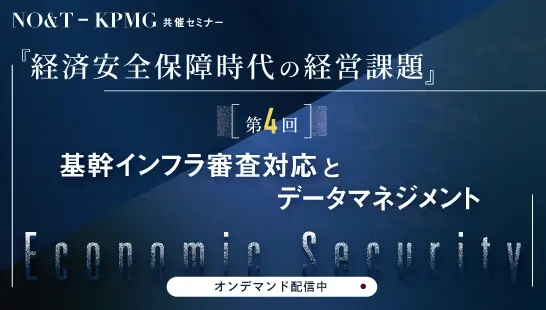
『経済安全保障時代の経営課題』第4回「基幹インフラ制度対応とデータマネジメント」
オンライン(オンデマンド配信)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- テクノロジー
- サイバーセキュリティ
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
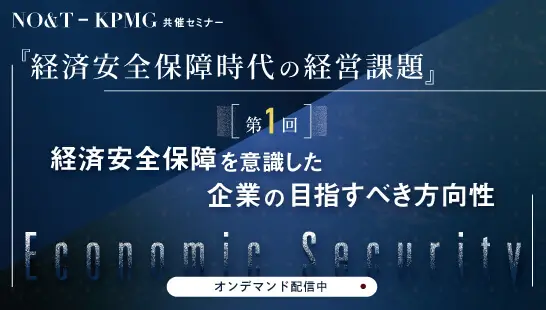
『経済安全保障時代の経営課題』第1回「経済安全保障を意識した企業の目指すべき方向性」
オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

企業価値の維持向上のための経済安全保障対応の実務 ~地に足付けた経済安全保障との向き合い方~
企業研究会セミナールーム(オンライン受講もあり)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

法務・総務担当者が抑えるべき経済安全保障の基礎と考え方 ~経済安保との付き合い方と期待される情報収集・分析・社内共有~
- 商事法務ビジネス・ロー・スクール
商事法務 会議室 / オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
安全保障貿易管理
外為法に基づく輸出入規制は、安全保障に関わる諸規制の中でも最も基本的な要素の一つであり、かつ日本企業の日常的な事業活動に密接に関わる分野です。貿易摩擦や国家間の軍事衝突等の国際情勢を背景に日本の輸出入規制も頻繁に改正が行われているほか、法令遵守を超えて、企業のレピュテーションリスクを管理する観点から取引の是非を判断する必要が生じる場面も増えています。当事務所は、国際取引及びコンプライアンス体制の構築についての豊富な経験と規制動向に関する最新の知見に基づいて、輸出入取引に関連する諸規制やコンプライアンスプログラム及びリスク管理体制についてのアドバイスを提供しております。
著書/論文/ニュースレター

2024年4月安保小委中間報告が示した安全保障貿易管理の見直しの方向性
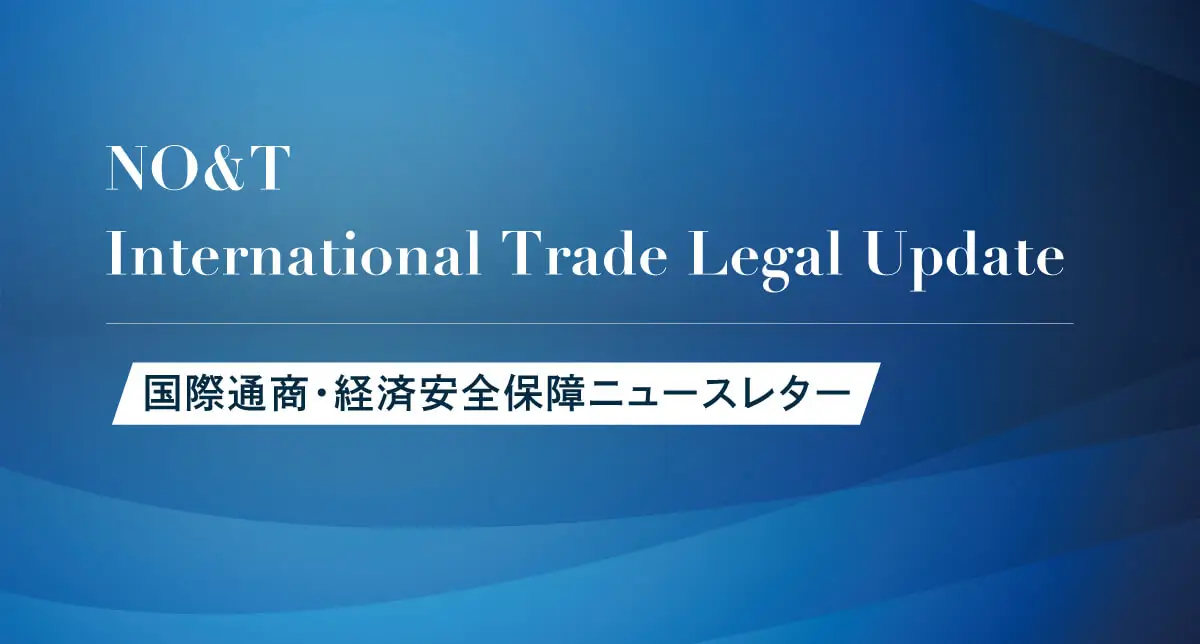
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年6月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

中国:対抗の時代(上)(下)―中国の半導体原材料及びドローン等の輸出制限の法的影響と対応策―

- 商事法務
商事法務ポータル「アジア法務情報」
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

Japan considers tightening export controls, amid reports of machine tools diverted to China (update*)

- Mlex
MLex News Articles
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

対抗の時代:中国の半導体原材料及びドローン等の輸出制限の法的影響と対応策

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年8月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

日本における重要土地等調査法の制定及び中国からの不動産投資に対する影響

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年3月)
- 不動産・REIT
- 不動産取引
- M&A
- M&A/企業再編
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

企業のリスク管理のために理解しておくべき「経済安全保障」のポイント

- 日本監査役協会
月刊監査役 2022年8月号(No.738)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

経済安全保障推進法の実務対応をさぐる 契約実務、企業コンプライアンスへの影響と対応

- 中央経済社
ビジネス法務 2022年9月号(Vol.22 No.9)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務

「みなし輸出」管理の明確化と実務対応
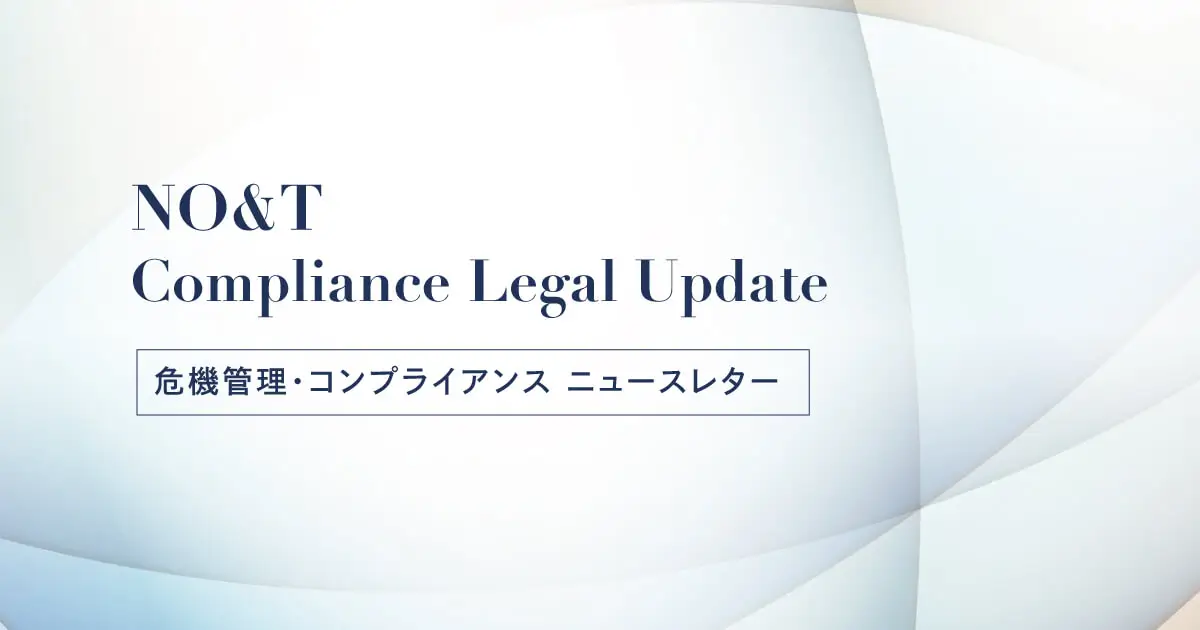
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2021年12月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 個人情報保護・プライバシー
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- 消費者関連法
- 製品安全/コンプライアンス・リコール・製造物責任
- 紛争解決
- 民事・商事争訟
- M&A
- プライベートエクイティ/ベンチャーキャピタル・スタートアップ
講演/セミナー

トランプ関税の現在地と実務対応 ~トランプ関税の正確な理解・見通しと短期的・中長期的な対応について~
- 第17471回 JPI特別セミナー
JPIカンファレンススクエア(オンラインライブ受講、後日動画視聴も可)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

経済安全保障を背景とした国際取引規制のコンプライアンス経済安保関連 ~最新動向と実務上の留意点の解説
- 第5025回 金融ファクシミリ新聞社セミナー
オンライン(後日動画視聴も可)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

5月1日施行!厳格化する「みなし輸出」管理のポイントと対策
- 大阪商工会議所
オンライン
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- コーポレート
- 一般企業法務

経済安全保障を背景とした国際取引規制のコンプライアンス ~規制の背景と実務上の留意点の解説
- 第4730回 金融ファクシミリ新聞社セミナー
金融ファクシミリ新聞社 セミナールーム(オンラインライブ受講、後日動画視聴も可)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
投資規制
我が国への投資規制も外為法の主な目的の一つです。世界的に強まる経済安全保障に対する関心・意識の高まりは我が国においても例外でなく、近年、外為法に基づく投資規制については、法改正が頻繁になされており、また、政府当局による投資案件の審査も以前と比較して入念・慎重に行われる傾向にあります。投資案件の審査をスムーズかつ迅速に進めるためには、最新の関連法令に関する正確な知識だけでなく、政府当局の関心・懸念事項を的確に把握してその反応を予測し、審査における政府当局への説明内容を事前に検討・準備することが肝要です。また、審査手続の具体的な進め方についても、個別の事案に応じ戦略的に検討する必要があります。当事務所は、これまで数多くの我が国に対する投資案件について助言する中で、外為法に基づく投資規制及びその審査実務に関する知見を豊富に蓄積しており、この分野についても柔軟かつ充実したアドバイスを提供できる体制を整えております。
著書/論文/ニュースレター

経済安全保障の観点を踏まえた技術情報ガバナンスの強化 ―国家的な技術調達活動の脅威を考慮した現地法人への技術共有の検討―

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2023年11月25日号(No.2343)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

Japan's tightening of foreign investment screening emerges as a deal risk

- Mlex
MLex News Articles
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

(速報)サプライチェーン保全等のための「コア業種」の追加に関する意見公募手続の開始 ―対内直接投資審査の対象業種が拡大される見通し―

- NO&T Corporate Legal Update コーポレートニュースレター
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年3月)
- M&A
- M&A/企業再編
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

外国資本の受入れと経済安全保障〔下〕 ─日本企業に求められる検討─

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2022年12月25日号(No.2314)
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

外国資本の受入れと経済安全保障〔上〕 ─日本企業に求められる検討─

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2022年12月15日号(No.2313)
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく投資管理と実務上の諸論点

- 商事法務研究会
旬刊商事法務 2022年5月5・15日号(No.2294)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- M&A
- M&A/企業再編
講演/セミナー

経済安全保障時代の各国外資規制の最新動向 〜日本企業同士のM&Aでも留意が必要〜
グリンヒルビル及びオンライン(後日動画視聴も可)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- M&A
- M&A/企業再編
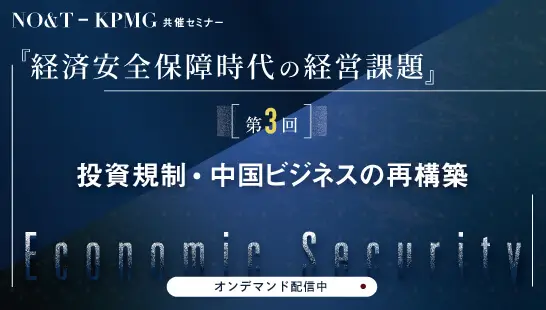
『経済安全保障時代の経営課題』第3回「投資規制・中国ビジネスの再構築」
オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- 南北アメリカ
- 米国
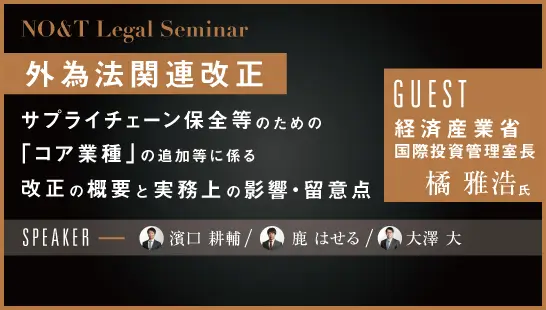
【外為法関連改正!】サプライチェーン保全等のための「コア業種」の追加等に係る改正の概要と実務上の影響・留意点
- NO&T Legal Seminar
オンライン(ライブ配信)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- M&A
- M&A/企業再編
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
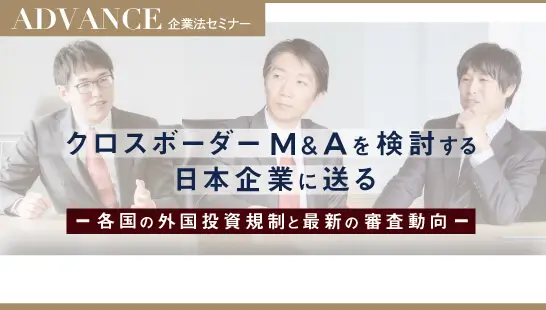
クロスボーダーM&Aを検討する日本企業に送る ー各国の外国投資規制と最新の審査動向
- ADVANCE企業法セミナー
オンライン(ライブ配信)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- コーポレート
- M&A
- M&A/企業再編
- 海外業務
テクノロジーその他産業振興
日本では、上記の伝統的な安全保障関連規制に加えて、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安全保障推進法)の制定に向けた動きを中心に、現政権下で経済安全保障に関する議論が活発化しています。同法の下では、半導体、医薬品等の重要物資に関するサプライチェーン強靱化や宇宙・海洋・量子・AI・バイオ等の先端的な重要技術の開発に対する政府の支援など、国内産業振興策と重なる施策も導入される予定であり、民間企業の側では、競争力強化のためにそれらの施策を利用していく視点も今後必要となってきます。
また、事業やイノベーションを支えるデータに関して、増大する外国からのサイバー攻撃やガバメントアクセス(外国政府による強制力を持った民間データへのアクセス)等のリスクへの継続的な対応も不可欠です。最近では、国際的な経済支援や経済制裁に暗号資産やNFT(非代替性トークン)が用いられるなど、テクノロジー分野を対象に含めなければ、経済安全保障関連施策は完結しなくなっていると言えるでしょう。当事務所では、テクノロジー関連法務やデータプロテクション、サイバーセキュリティ、さらには知財関連取引、M&A、スタートアップ支援など、様々な側面で先端技術を取り扱う企業にリーガルサービスを提供しており、経済安全保障関連施策の知見を反映することで、より一層充実したサービスを提供してまいります。
著書/論文/ニュースレター
講演/セミナー
知的財産・研究開発
産業基盤のデジタル化や高度化により、国家の安全保障にも影響し得る先端的な重要技術におけるイノベーションが進展しています。このため、重要技術の開発に対する政府による支援だけではなく、安全保障上重要な先端的技術の流出を防止することの重要性が増しており、各国がその対策を強化しています。我が国においても、今般、経済安全保障推進法において、公開により我が国の安全保障が著しく損なわれるおそれがある発明について、出願公開等による不用意な技術流出を防止するため、特許出願の非公開の制度が設けられ、また、我が国で行った発明のうち、一定の発明については、我が国への第一国出願義務が定められます。このような状況を踏まえて、今後、各国、各企業において、グローバルな共同研究開発等も含め、先端的な重要技術の研究開発を強力に推進する一方で、そのような重要な技術の流出防止のために十分かつ適切な知的財産・技術情報管理体制を構築し、運用することがより一層求められるものと思われます。また、外国において知的財産権を取得した場合であっても、当該外国政府によって強制実施権の対価が無償とされ、あるいは、当該外国政府によって特定された並行輸入品については知的財産権が及ばないとされるなど、知的財産権が外交上の目的を達成するための手段として用いられることも増加しており、外国において取得した知的財産権がそのように用いられることを想定することが必要になってきています。当事務所では、バイオ、化学、AI(人工知能)など、デュアルユースの先端技術を取り扱う企業にアドバイスを提供しており、国際的な共同研究開発、知的財産・技術情報の管理体制の構築・運用、知的財産戦略などについての豊富な経験に、経済安全保障に関する最新の動向・知見を加味し、充実したリーガルアドバイスを提供してまいります。
著書/論文/ニュースレター
02米国
安全保障貿易管理
貨物や技術の移転を規制する輸出入規制は、安全保障に関わる諸規制の中でも最も基本的なものですが、米国の安全保障貿易管理関連規制は諸国の中でも最も複雑で厳格なものの一つです。当事務所では、International Traffic in Arms Regulations (ITAR)、Export Administration Regulation (EAR)、Office of Foreign Assets Control (OFAC) Regulations、National Defense Authorization Actを含む米国の様々な安全保障貿易管理関連規制について、安全保障貿易管理に明るい米国法律事務所とのネットワークも活用しつつ、関連規程の作成・レビュー、デュー・ディリジェンス、当局対応等様々な形で日本企業の皆さまに継続的に助言をしております。
著書/論文/ニュースレター

トランプ政権による相互関税の導入
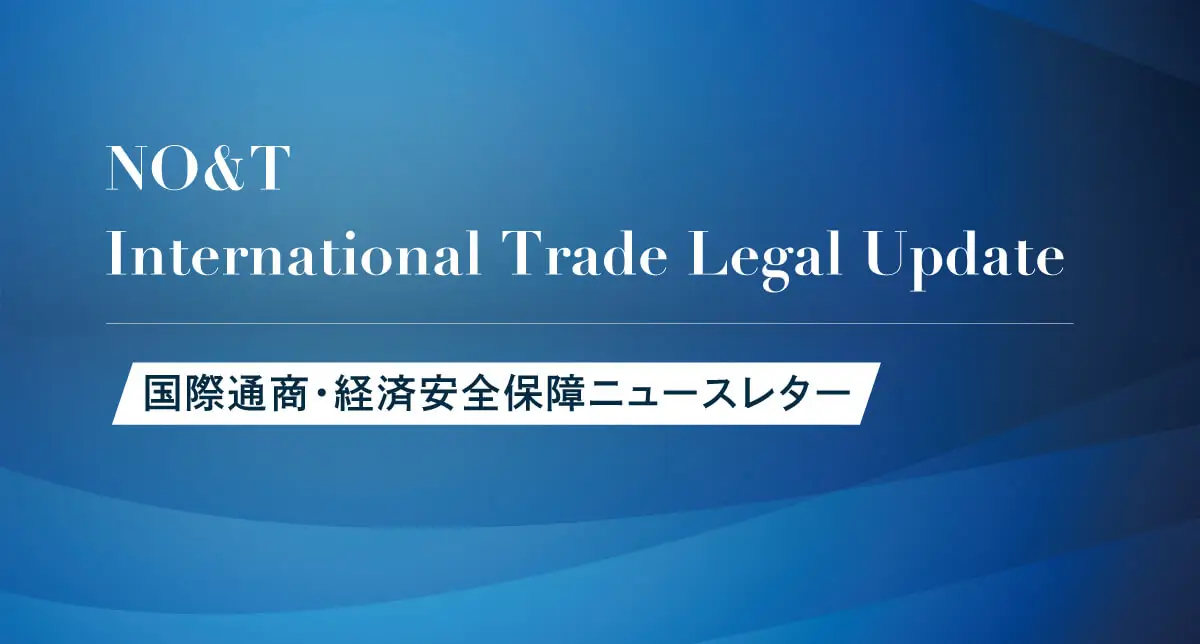
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Client Alert
長島・大野・常松法律事務所(2025年4月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国輸出管理規制アップデート~2024年12月対中国向け半導体輸出規制の拡大~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2025年3月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

CFIUSの調査・法執行権限を強化する最終規則の公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年12月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国輸出管理規制アップデート ~先端半導体、量子コンピュータ等の先端技術に関する追加規制の導入~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年12月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

CFIUSの活動に関する年次報告書(2023年度)の公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年10月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国輸出管理規制アップデート~エンドユース・エンドユーザー規制の拡大~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年9月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国による1974年通商法301条追加関税の維持及び強化
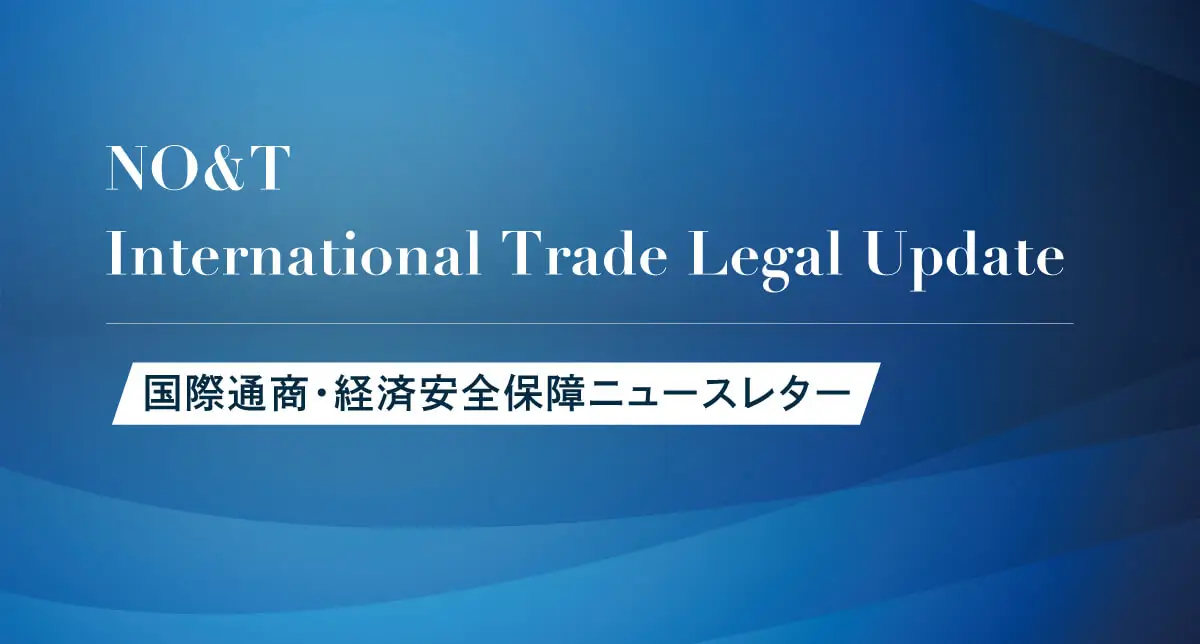
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

CFIUSの調査・法執行権限を強化する規則案の公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国による対ロシア追加制裁の公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年4月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

米国外の者による米国制裁法及び輸出管理規則の遵守に関するコンプライアンスノートの公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年4月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国輸出管理規制アップデート~2023年度の執行状況等について~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2024年3月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国輸出管理規制アップデート~先端コンピューティング及び半導体製造装置関連の輸出管理規制の強化~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年12月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国制裁法・輸出管理規則等の安全保障関連法令違反の自主的な報告に関するコンプライアンスノートの公表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年8月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国政府による中国製半導体製品等の排除~国防権限法5949条の成立~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2023年3月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

米国連邦通信委員会による一部の通信機器の輸入・販売の禁止措置

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年12月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

ウイグル強制労働防止法の制定

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年1月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- コーポレート
- 一般企業法務

米国輸出管理規制アップデート~エンティティ・リストの更新~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年1月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- コーポレート
- 一般企業法務

米国輸出管理規制アップデート ~サイバーセキュリティ関連の輸出管理強化~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2021年11月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- コーポレート
- 一般企業法務

米国輸出管理規制アップデート ~ファーウェイとSMIC向け輸出許可申請の運用状況~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2021年11月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- コーポレート
- 一般企業法務

米国輸出管理規制アップデート~エンティティ・リストの更新~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2021年7月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

米国輸出管理規制アップデート~エンティティ・リストの更新とFAQsの公表~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2021年1月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- コーポレート
- 一般企業法務

米国政府によるHUAWEI製品等の排除~国防権限法889条の施行~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2020年7月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
- テクノロジー
- テレコム

米国輸出規制と日本企業における対応実務

- 中央経済社(2020年2月)
ビジネス法務 2020年4月号(Vol.20 No.4)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
講演/セミナー
投資規制
対米外国投資委員会(CFIUS)は、国家安全保障上の観点から対米投資の審査・調査を行う権限を有しており、外国投資家が対米投資を行う場合には、事前届出の要否の検討等が必要になりますが、CFIUSの姿勢にはその時々の国際情勢や政治的情勢が色濃く反映されるため、専門的かつ慎重な対応が必要になります。当事務所は、CFIUS対応に明るい米国法律事務所と緊密に連携して、日本企業による米国投資、米国M&A案件におけるCFIUS対応をサポートしています。
著書/論文/ニュースレター

米国半導体補助金をめぐる動向 ~CHIPS及び科学法の申請手続と制約上の留意点~

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2023年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

CFIUS審査に関する新たな大統領令及びガイドラインの対米投資に与える影響

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年11月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

CFIUSに対する義務的届出要件の改正

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2020年6月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

FIRRMA施行にかかるCFIUS最終規則の発表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

FIRRMA施行にかかるCFIUS新規則案の発表

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2019年12月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

FIRRMAパイロットプログラム対応の実務とCFIUSによる最近のエンフォースメント

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2019年6月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
講演/セミナー

米国宇宙ビジネスと法的課題~米国国内法動向と米国における資金調達
- 2024年度「先端的な宇宙活動に関する法的課題研究会」第2回研究会
慶應義塾大学法学研究科宇宙法研究センター、宇宙航空研究開発機構(JAXA)
- テクノロジー
- 宇宙
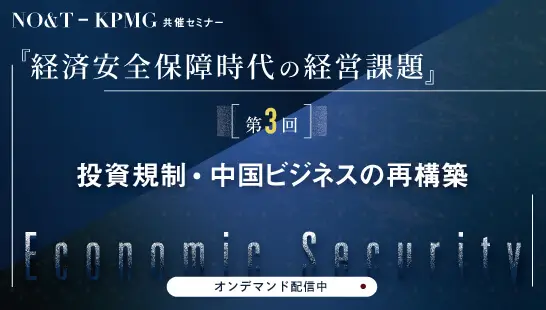
『経済安全保障時代の経営課題』第3回「投資規制・中国ビジネスの再構築」
オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- 南北アメリカ
- 米国

輸出管理規制セミナー「米中摩擦を背景とした諸規制の最新動向と法務対応」
- ADVANCE企業法セミナー
長島・大野・常松法律事務所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- アジア・オセアニア
- 中国
03中国
日本や米国、欧州等の経済安全保障関連規制は、事実上中国ないし中国企業を標的として強化が進むものも少なくない反面で、日本企業にとって、中国は日本の最大の貿易相手国であり、また重要な研究開発、製造、販売の拠点でもあります。それら経済安全保障関連規制の遵守においては、中国の法令や実務運用もあわせ検討し、現実的な判断を行う必要があります。特に近時、中国では外国による制裁や規制の域外適用等を対象に対抗措置をとりうる各種制度を整備しており、その判断を難しくしています。
さらに、中国でも、国家安全法、国家情報法、輸出管理法、外商投資安全審査弁法、いわゆるデータプロテクション関連三法(ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法)等の経済安全保障の観点に基づく立法や法令改正が急速に行われている反面、具体的な細則及び実務運用は不明確な点も多く、実際の対応はその時点での情報に基づく現実的対応が必要となります。
当事務所では、中国の法令及び規制実務や中国に関連する取引に精通した弁護士が、必要に応じ中国現地法律事務所とのネットワークも活用しつつ、これらの問題に関し日本企業及びその現地法人に対し最新の動向を踏まえたアドバイスを行っています。
著書/論文/ニュースレター

Japan to tighten foreign investment rules amid national security concerns

- Mlex
MLex News Articles
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- M&A
- M&A/企業再編

両用品目輸出管理条例の施行について(追記:12月3日付け米国向け両用品目輸出管理強化の商務部公告)(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年12月)
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

EUの外国補助金調査の近況と中国の関税法改正(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- ヨーロッパ

中国:対抗の時代(上)(下)―中国の半導体原材料及びドローン等の輸出制限の法的影響と対応策―

- 商事法務
商事法務ポータル「アジア法務情報」
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

対抗の時代:中国の半導体原材料及びドローン等の輸出制限の法的影響と対応策

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
- NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター
長島・大野・常松法律事務所(2023年8月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国版CFIUS(外商投資安全審査弁法)の概要と運用の現状

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年11月)
- M&A
- M&A/企業再編
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

特集/米中の規制等を巡る諸動向 〈1〉標準必須特許(SEP)に関する中国の禁訴令と企業の対応・留意点

- 安全保障貿易情報センター
CISTECジャーナル 2022年9月号 No.201
- 知的財産
- 知財関連取引
- 知財争訟
- 独占禁止法/競争法
- 独禁争訟
- 紛争解決
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

オフィス設備の国産優先戦略の動き(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年8月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国:『反外国制裁法』の制定と最初の適用事例(1)(2)

- 商事法務
商事法務ポータル「アジア法務情報」
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

『反外国制裁法』の制定と最初の適用事例(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2021年8月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国:輸出管理法と信頼できないエンティティリスト規定について(1)~(5)

- 商事法務
商事法務ポータル「アジア法務情報」
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

輸出管理法と信頼できないエンティティリスト規定について(下)(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2020年12月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

輸出管理法と信頼できないエンティティリスト規定について(上)(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2020年11月)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

(速報)中国:技術輸出入管理条例の改正

- 商事法務
商事法務ポータル「アジア法務情報」
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
講演/セミナー
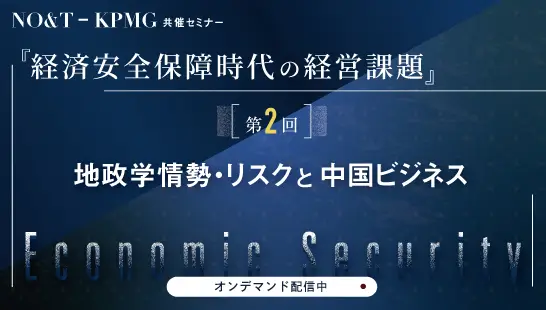
『経済安全保障時代の経営課題』第2回「地政学情勢・リスクと中国ビジネス」
オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国輸出関連制度の全体像
- JEITA中国委員会
電子情報技術産業協会(JEITA)
- コーポレート
- 一般企業法務
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

設備調達の国産優先戦略の動き(中国)
- The NO&T Podcast - JP
長島・大野・常松法律事務所
- M&A
- M&A/企業再編
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
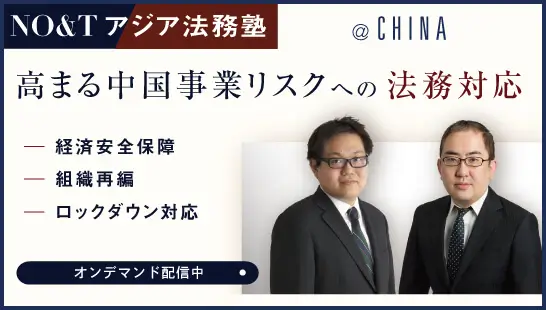
高まる中国事業リスクへの法務対応(経済安全保障、組織再編、ロックダウン対応)
- アジア法務塾
長島・大野・常松法律事務所
- コーポレート
- 一般企業法務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国最新動向のアップデート~米中関係、輸出管理法、海南自由貿易港~
- 三菱UFJ銀行グローバル経営支援セミナー
三菱UFJ銀行、Japan Digital Design株式会社
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国

中国法務最新情報セミナー2020(第2回)
- NO&T―中倫 共催セミナー
長島・大野・常松法律事務所
中倫律師事務所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
04欧州
欧州においては、欧州委員会が、近年の中国との関係等を背景として、2021年5月にEUの新産業戦略を改訂し、戦略物資の域外依存を軽減するためのサプライチェーンの強靱化を図るなどの施策を行っており、EU加盟国においても、2023年1月にドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法が施行予定であるなど、企業に対してサプライチェーンのリスク管理体制の整備が求められるようになりつつあります。また、近年、英国・ドイツ等をはじめとする欧州主要国において、投資規制法の導入・改正が行われ、EUにおいても外国直接投資の審査の枠組みに関するEU規則が発効するなど、安全保障の観点からの外国投資の規制強化が図られています。さらに、ロシアのウクライナ侵攻に関連しては、EU・英国において、米国や日本と協調した金融制裁等の経済制裁もなされています。
これらの欧州の動きについては、欧州に拠点を有する企業だけでなく、欧州企業と取引を行う企業や欧州においてM&Aや新規投資を検討する企業にとっても大きな影響が生じます。当事務所では、欧州における投資審査、輸出入取引に関連する諸規制、デュー・ディリジェンスを含むコンプライアンス体制の見直し等、様々な側面においてアドバイスを提供しております。
著書/論文/ニュースレター

EUの外国補助金調査の近況と中国の関税法改正(中国)

- NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2024年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- ヨーロッパ

Final Order事例からみる英国国家安全保障・投資法の現在地

- NO&T Europe Legal Update ~欧州最新法律情報~
- NO&T Corporate Legal Update ~コーポレートニュースレター~
長島・大野・常松法律事務所(2023年3月)
- M&A
- M&A/企業再編
- 海外業務
- ヨーロッパ
国際危機/経済制裁対応
操業国において国際危機が生じた、取引先の企業が制裁対象の指定を受けた、輸出製品のサプライチェーンに規制原材料が含まれていることが判明したなど、各国の経済安全保障政策を背景とした有事対応については、時に一企業において解決できない政策的問題を含むとともに、複数法域の制裁法や制裁対象国における対抗措置などを含む、複数法域の規制を考慮したうえで判断する必要があります。当事務所は、海外オフィスや世界各国との幅広いネットワークを活用して、このような有事の場面において、柔軟かつ充実したアドバイスを提供できる体制を整えております。また、当事務所は、訴訟のみならず調停や仲裁等による紛争解決についても豊富な実績を有しております。
さらに、このような有事に備えた「守りの戦略」としての、不可抗力条項やいわゆる制裁条項を含む契約上の手当てや、BCPプランの策定、経済制裁によるサプライチェーン断絶を見据えたサプライチェーンのデュー・ディリジェンス、サイバーセキュリティ体制の見直し等についても豊富なアドバイスを提供しております。
著書/論文/ニュースレター

ウクライナ危機アップデート 日本・米国における対ロシア制裁の厳格化

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年5月)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ
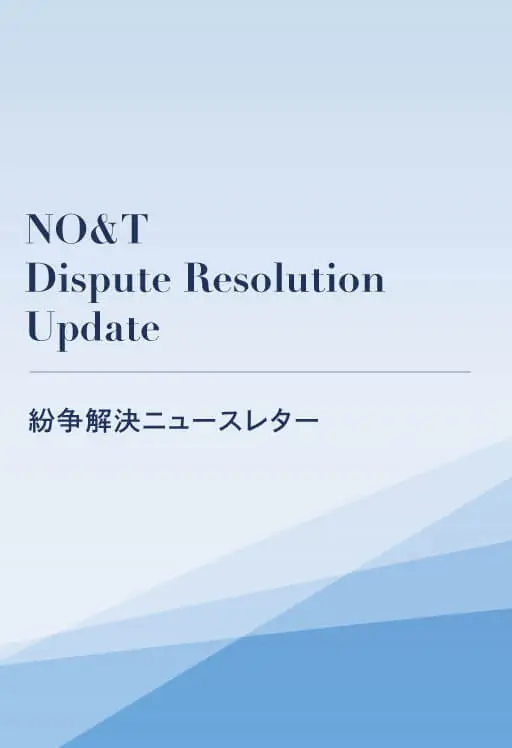
海外投資のリスクマネジメント – 投資協定による保護とより迅速な紛争解決 – ICSID規則改正と新調停規則の紹介
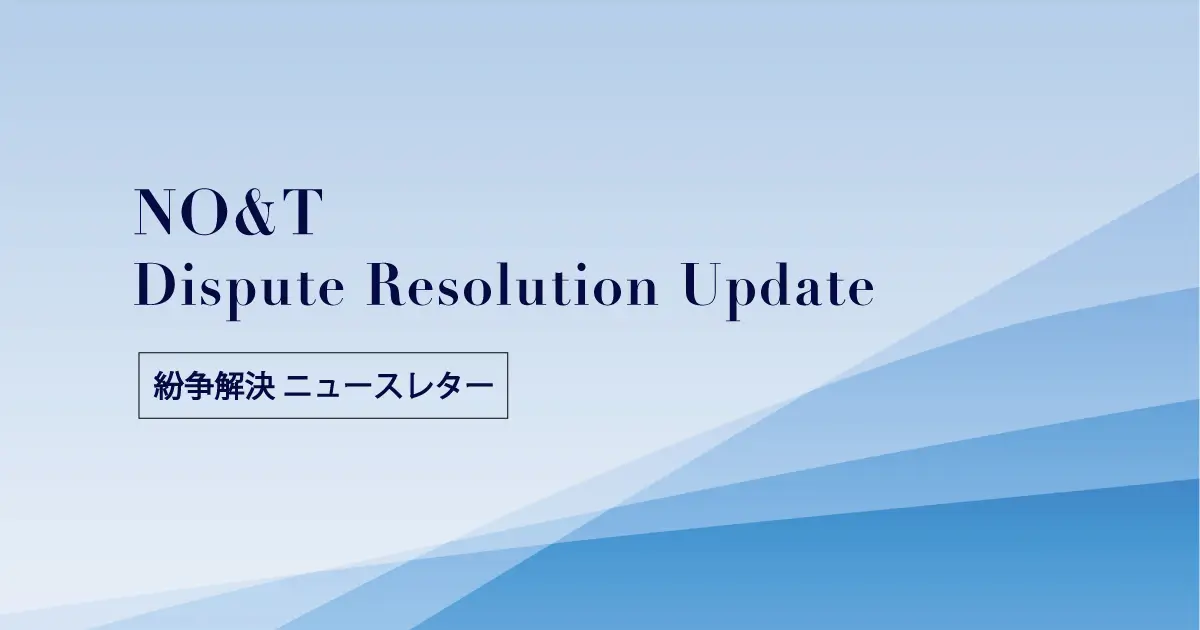
- NO&T Dispute Resolution Update ~紛争解決ニュースレター~
長島・大野・常松法律事務所(2022年4月)
- 国際仲裁
- 国際調停
- 紛争解決
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス

ウクライナ危機アップデート EUにおける対ロシア制裁の厳格化

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年4月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

ウクライナ危機アップデート ロシアによる対抗措置から日本企業のロシア投資を護る投資協定

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年3月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ
- 紛争解決
- 国際仲裁
- 国際調停

ウクライナ危機アップデート ロシアによる経済制裁への対抗措置

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年3月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

ウクライナ危機アップデート 米国輸出管理規則改正による対ロシア輸出規制の厳格化

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年3月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

対ロシア制裁の最新動向(日本・米国・EU)

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年3月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ

ウクライナ情勢を踏まえた米国・EU・英国における対ロシア制裁の最新動向

- NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
- NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
長島・大野・常松法律事務所(2022年2月)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ
講演/セミナー
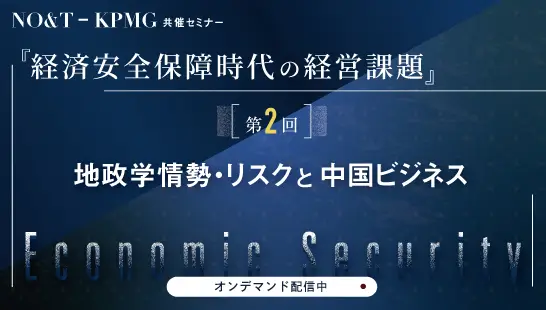
『経済安全保障時代の経営課題』第2回「地政学情勢・リスクと中国ビジネス」
オンライン(オンデマンド配信)
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
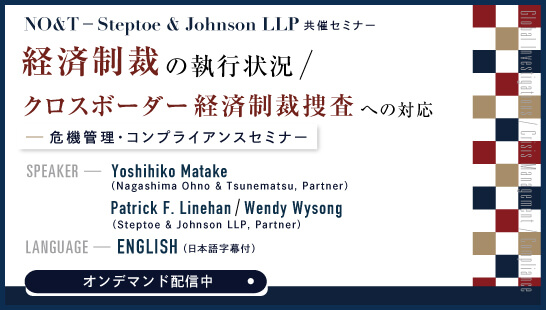
経済制裁の執行状況/クロスボーダー経済制裁捜査への対応
- 危機管理・コンプライアンスセミナー
長島・大野・常松法律事務所
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 海外業務
- 南北アメリカ
- 米国

国際紛争に備える法務対応 チェックポイント〔第2回〕危機管理と紛争解決
- 経営法友会月例会
経営法友会
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 紛争解決
- 海外紛争(争訟)対応
- 国際仲裁

国際紛争に備える法務対応 チェックポイント〔第1回〕法的課題の整理と取引関係の備え
- 経営法友会月例会
経営法友会
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- 紛争解決
- 海外紛争(争訟)対応
経済安全保障政策とWTO協定等の国際ルール
日本、米国、中国及び欧州等の各国・地域による経済安全保障政策は、輸出入規制などの貿易管理、補助金の供給による生産拠点の整備や内製化、外国産品の調達制限、機微な情報や重要技術の移転防止など、非常に様々な政策手段の形で展開し、物品事業であるかサービス事業であるかにかかわらず、企業の事業活動に大きな影響を及ぼします。場合によっては、安全保障以外の経済目的や効果も企図している場合も想定されます。
そうした様々な政策を分析する際には、自由で公正な貿易をめざし、各国・地域の企業・産業が公正に競争しあえる様に定められたWTO協定その他の国際経済上の原則・例外ルールに適合するものであるかどうかといった観点も重要となります。
当事務所では、こうした国際ルールも的確に踏まえながら、政策立案対応、平時のコンプライアンス、個々の取引の実行、有事対応、そして中長期的な事業戦略といた事業活動のそれぞれの局面に即して、事業の国際競争力を高めるためのアドバイスを行っています。
著書/論文/ニュースレター
講演/セミナー

第4回 独占禁止法の域外適用
- 国際通商法基礎講座(全4回)
国際商事法研究所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 独占禁止法/競争法
- 独禁争訟
- 企業結合規制対応
- 独占禁止法/競争法アドバイス
- 紛争解決

第3回 国家法の域外適用の諸問題
- 国際通商法基礎講座(全4回)
国際商事法研究所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 独占禁止法/競争法
- 独禁争訟
- 企業結合規制対応
- 独占禁止法/競争法アドバイス
- 紛争解決

第2回 実務的テーマ各論
- 国際通商法基礎講座(全4回)
国際商事法研究所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理

第1回 国際通商/WTO/EPA総論
- 国際通商法基礎講座(全4回)
国際商事法研究所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
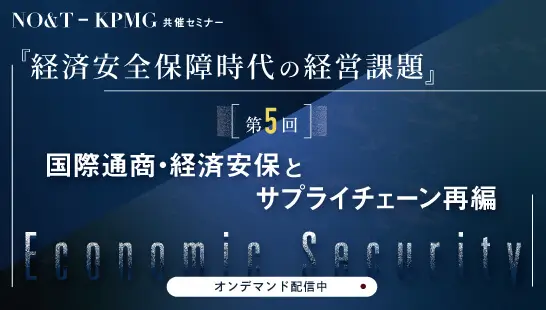
『経済安全保障時代の経営課題』第5回「国際通商・経済安保とサプライチェーン再編」
オンライン(オンデマンド配信)
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- コーポレート
- 一般企業法務
- 海外業務
- ヨーロッパ

『半歩先』を見る国際通商セミナー ~各国の重要施策・措置と戦略的に向き合うための考え方~
- ADVANCE企業法セミナー
長島・大野・常松法律事務所
- 国際通商・経済制裁法・貿易管理
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- 中国
- 南北アメリカ
- 米国
- ヨーロッパ
当該業務分野に関連する弁護士等

服部薫
Kaoru Hattori
- パートナー
- 東京

東崎賢治
Kenji Tosaki
- パートナー
- 東京

塚本宏達
Hironobu Tsukamoto
- パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
- ニューヨーク・オフィス

大久保涼
Ryo Okubo
- パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
- ニューヨーク・オフィス

若江悠
Yu Wakae
- パートナー/オフィス首席代表
- 上海オフィス

眞武慶彦
Yoshihiko Matake
- パートナー
- 東京

川合正倫
Masanori Kawai
- パートナー
- 東京

濱口耕輔
Kosuke Hamaguchi
- パートナー
- 東京

殿村桂司
Keiji Tonomura
- パートナー
- 東京

福原あゆみ
Ayumi Fukuhara
- パートナー
- 東京

大沼真
Makoto Ohnuma
- パートナー
- 東京

逵本麻佑子
Mayuko Tsujimoto
- パートナー(NO&T NY LLP)
- ニューヨーク・オフィス

鹿はせる
Haseru Roku
- パートナー
- 東京

大澤大
Oki Osawa
- パートナー
- 東京
Legal Lounge
会員向けコンテンツ
ホットなトピックスやウェビナーのアーカイブはこちらよりご覧いただけます。
最新情報をリリースしましたらすぐにメールでお届けします。