
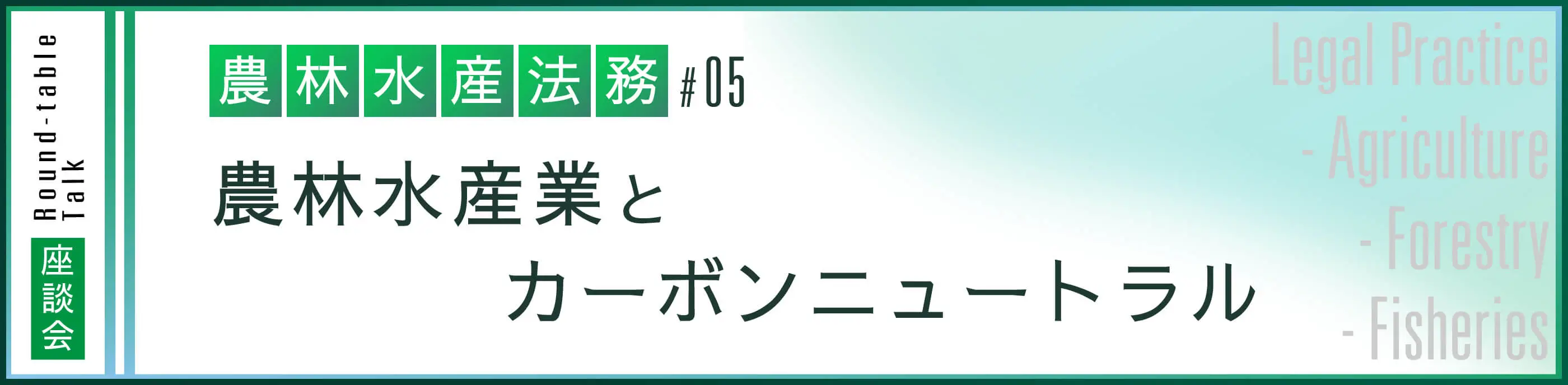
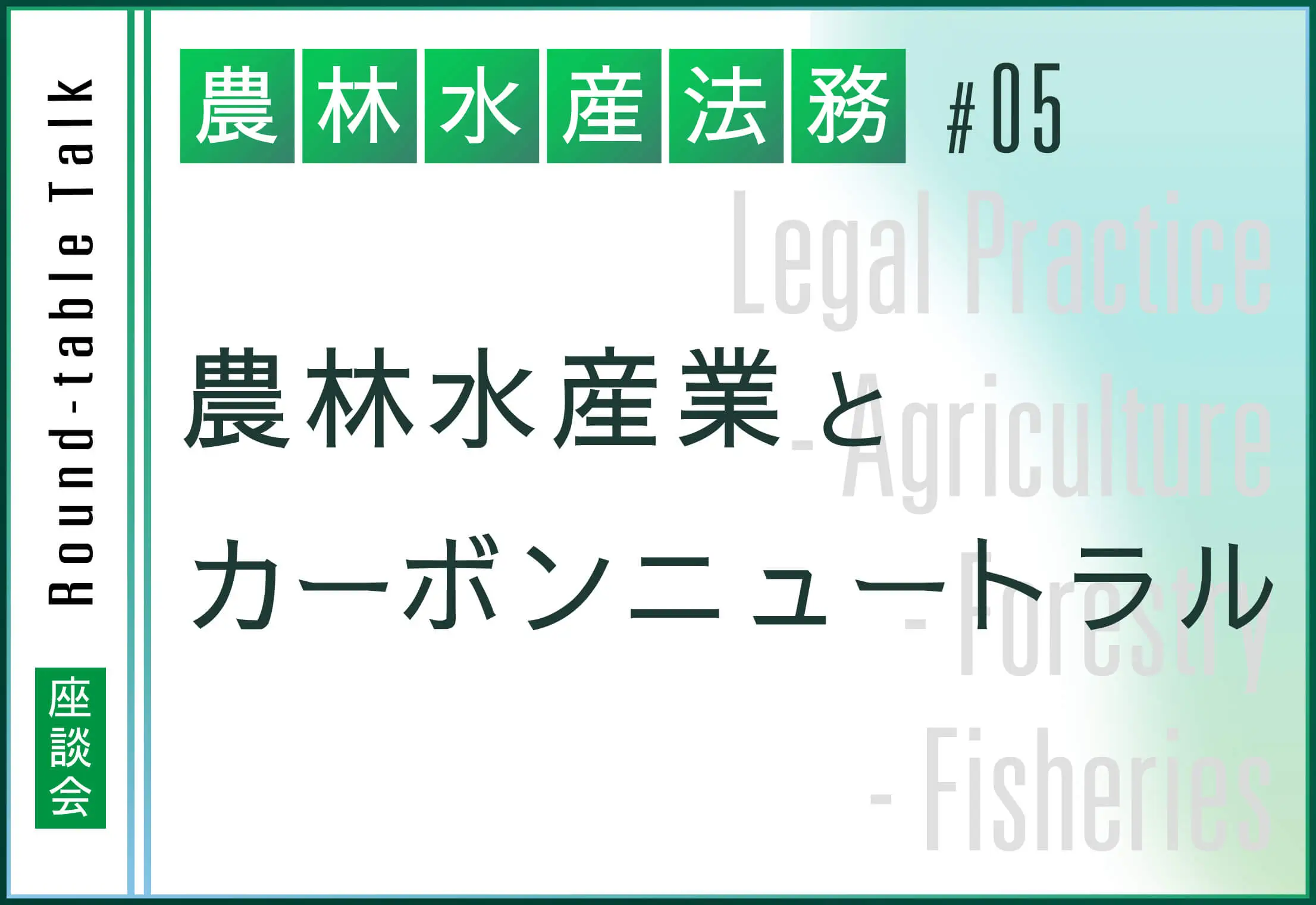
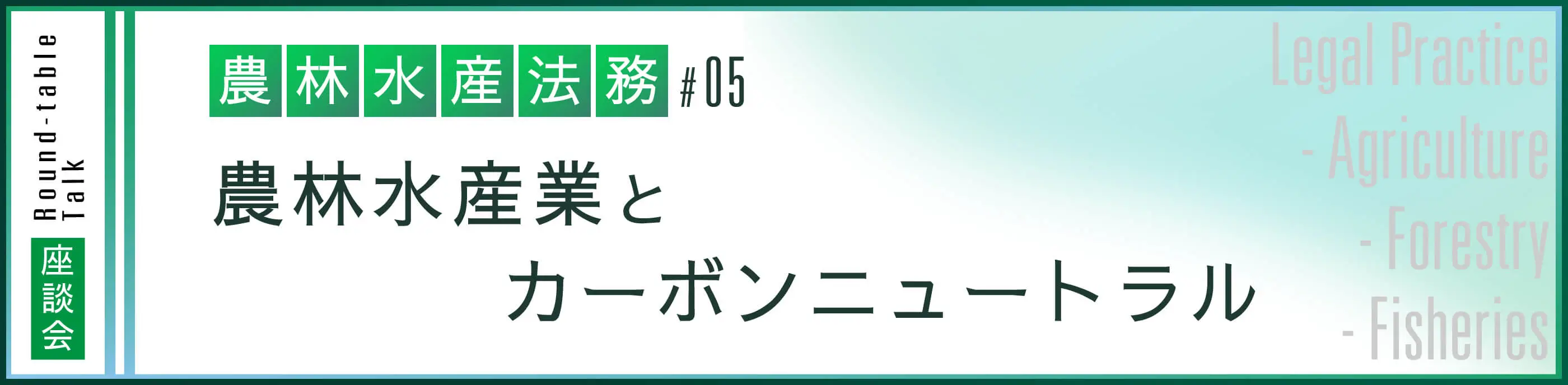
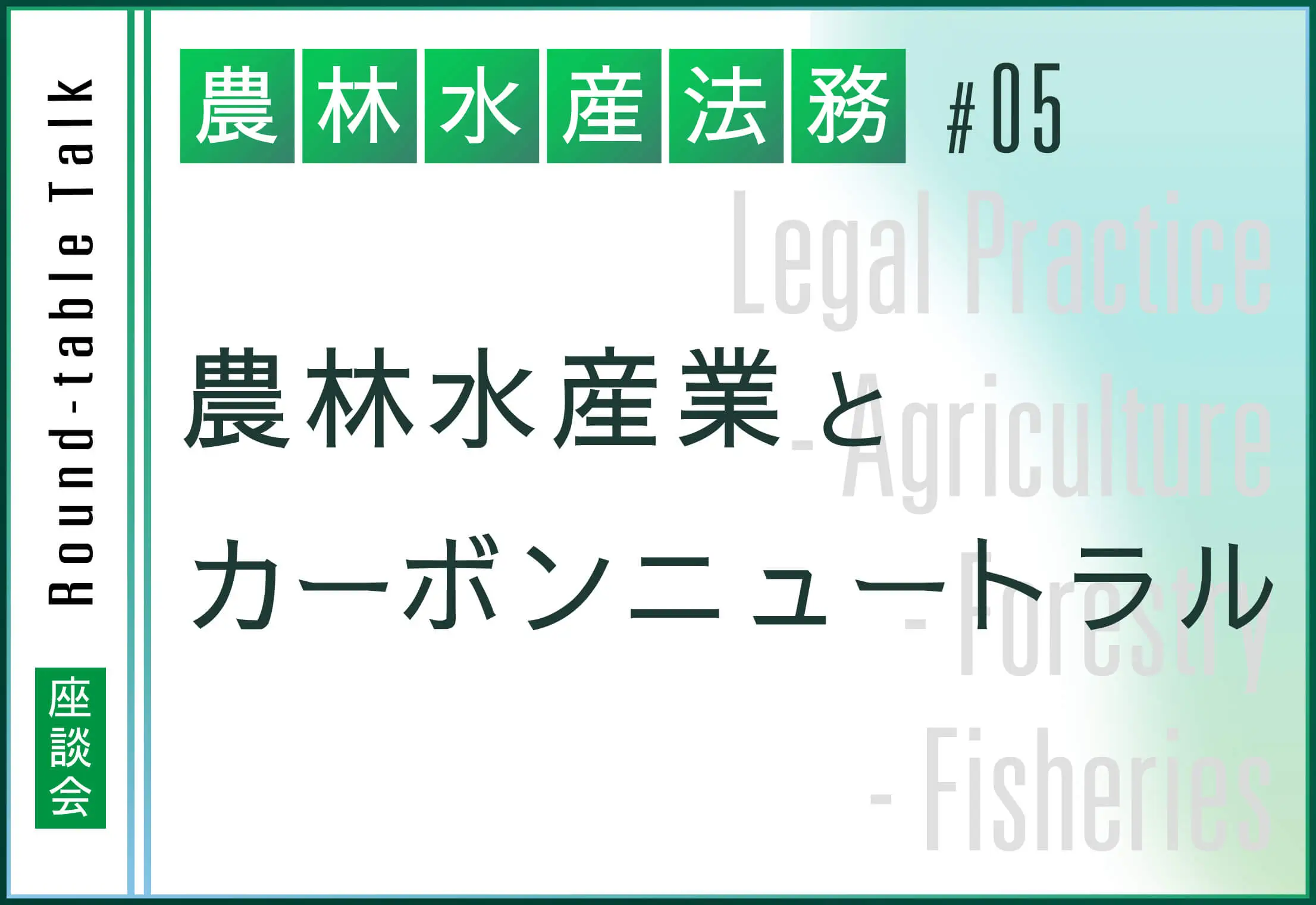

資源・環境・エネルギー、建設・インフラ、プロジェクトファイナンス、証券化・ストラクチャードファイナンス、不動産取引を中心として一般企業法務全般を取り扱うほか、気候変動問題、海洋資源保護や生物多様性保全に関連する法務問題に取り組む。

資源・エネルギー、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス、J-REIT及び私募ファンドの組成・運営等を含むインフラ・不動産取引全般、その他一般企業法務を取り扱う。近時は、テクノロジー、カーボンニュートラル、農林水産分野等に関する法律問題にも取り組んでいる。

再生可能エネルギー分野に関するアドバイスを中心に、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、不動産取引その他企業法務について幅広く取り扱っている。近時は農林水産業に関係する法律問題にも取り組んでいる。

M&A、コーポレートをはじめとした企業法務全般についてアドバイスを提供している。また、農林水産分野に関連する法律問題にも取り組んでいる。
第5回では、農林水産業とカーボンニュートラルというテーマで、主にみどりの食料システム戦略とバイオマス産業、農林水産業と再生可能エネルギーの共生、木造建築物の増加と林業のあり方について議論したいと思います。

渡邉

宮城

水野


稗田

渡邉

宮城

水野

宮城

稗田

渡邉

宮城

稗田

渡邉



渡邉

水野

宮城

稗田

渡邉

宮城

渡邉

水野

稗田

宮城

水野

渡邉



水野

稗田

宮城

渡邉

水野

宮城

渡邉

稗田

第6回 「ブルーエコノミーと自然資本・生物多様性」
(宮下優一弁護士、渡邉啓久弁護士、星野慶史弁護士、田澤拓海弁護士、室憲之介弁護士)
※次回は、2月22日の公開を予定しています。
本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。