
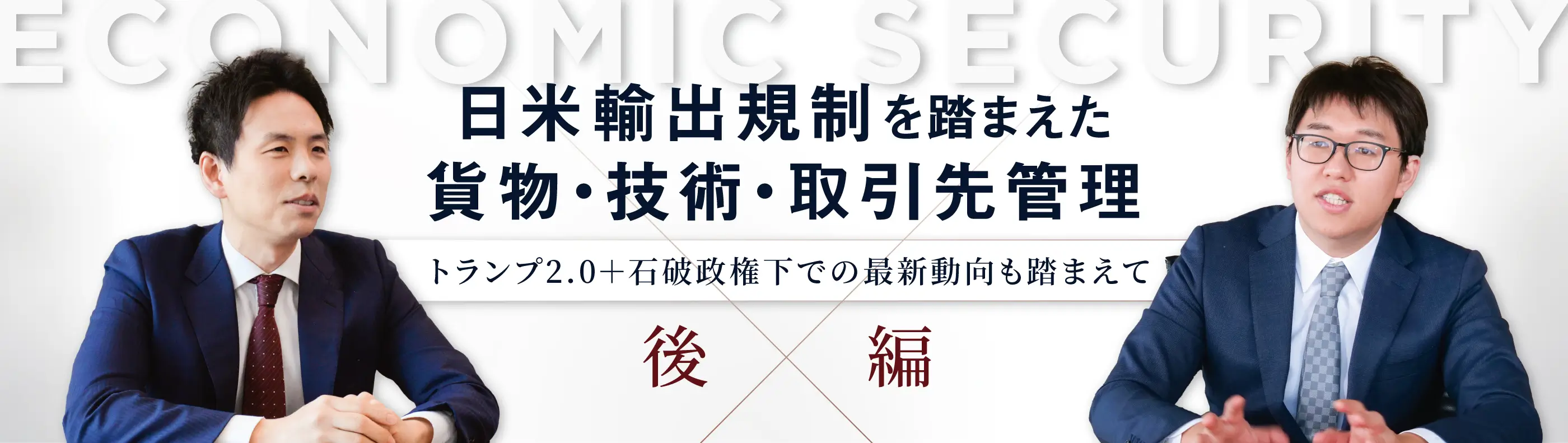
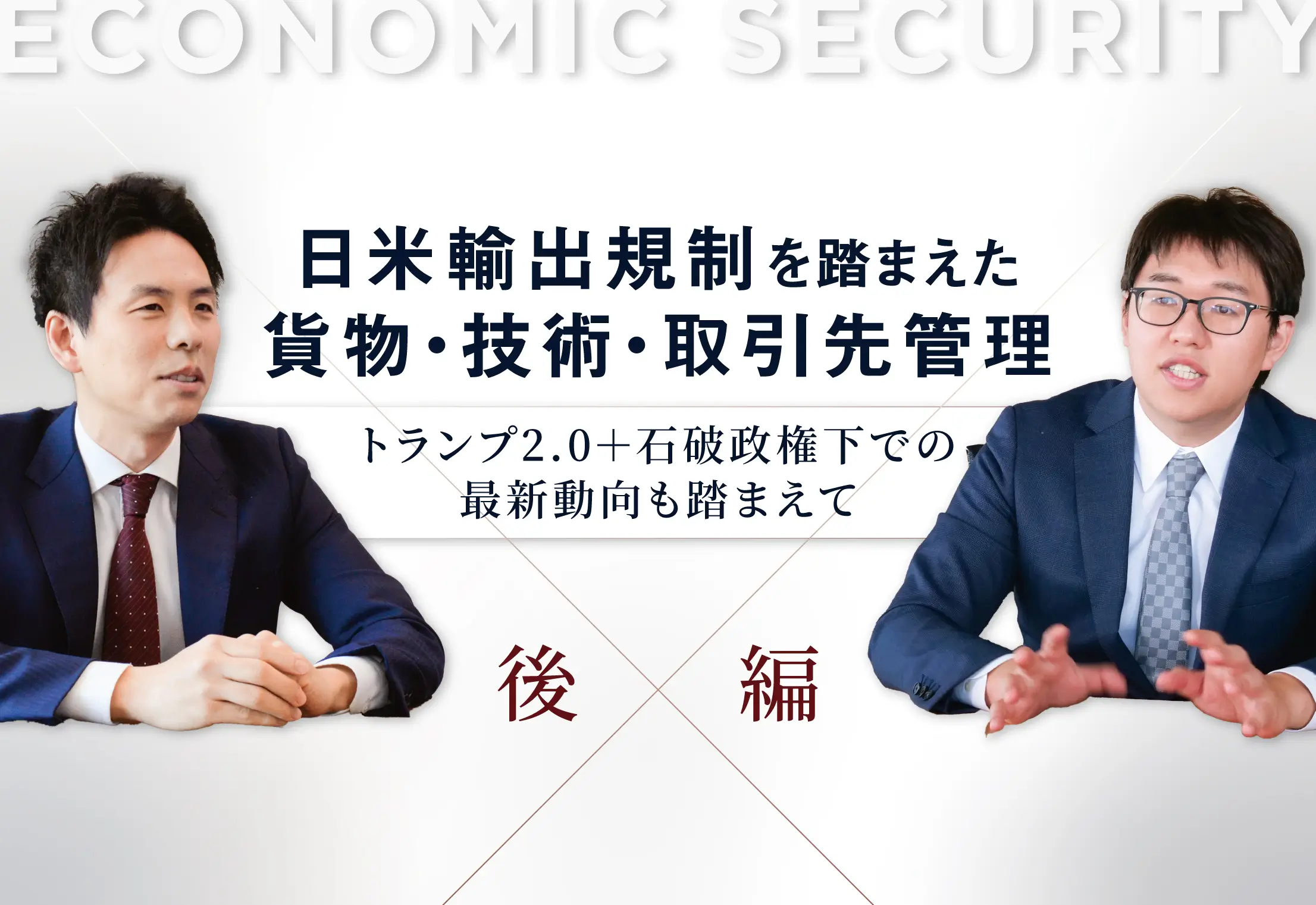
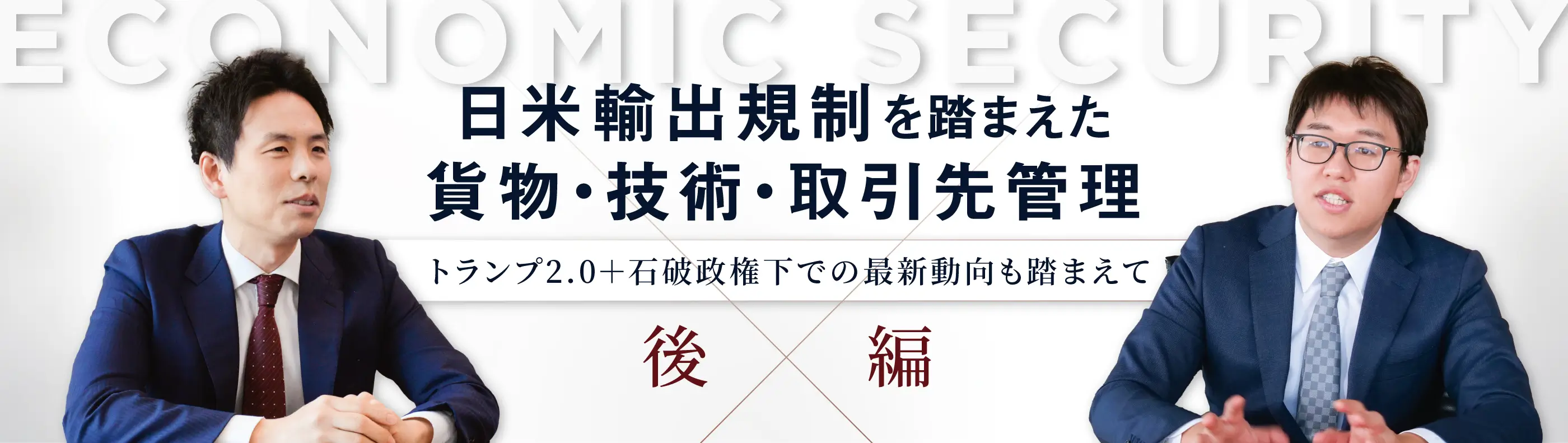
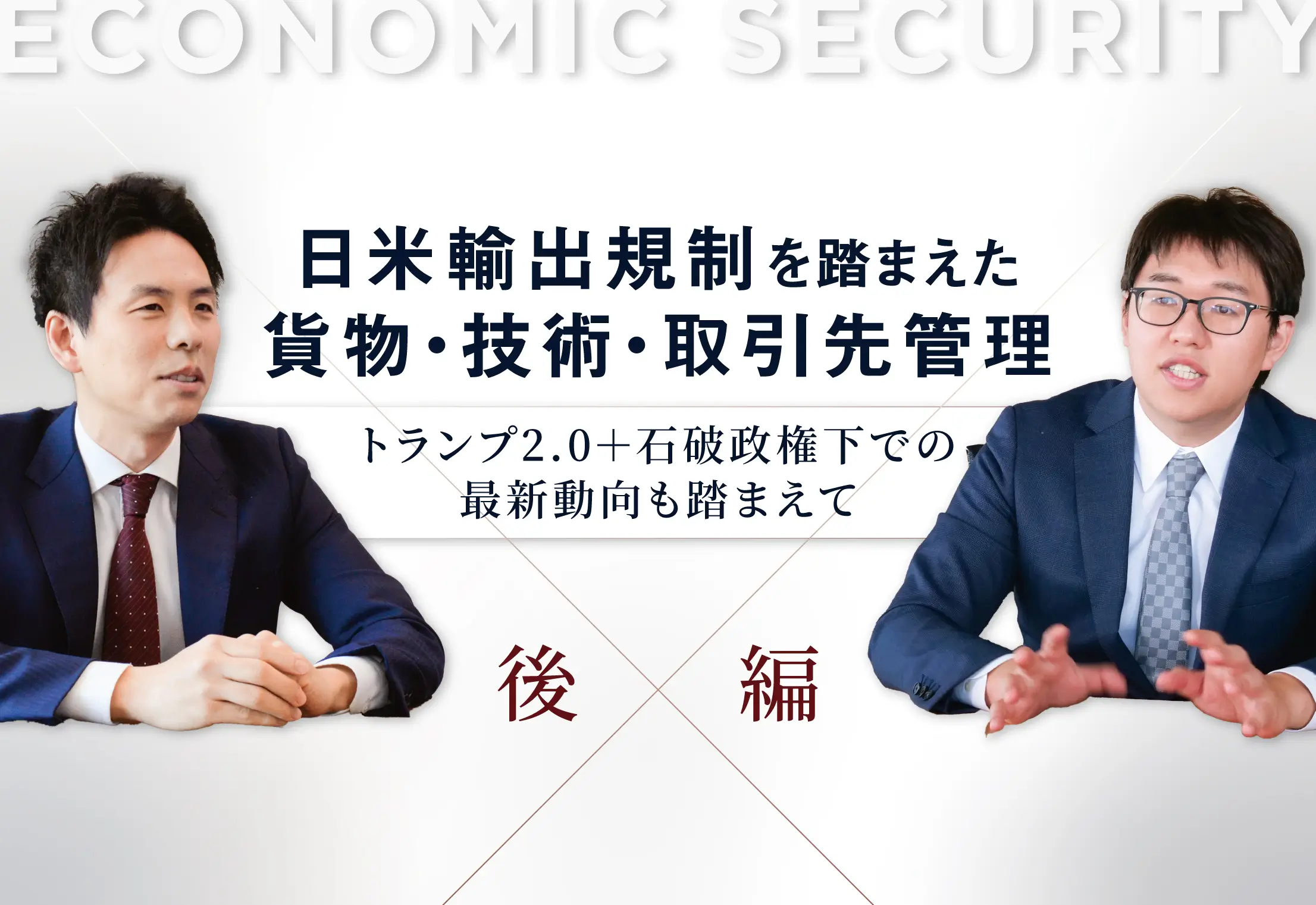
近年、経済安全保障の強化を主たる目的として各国が輸出管理規制を累次強化するとともに、ロシアによるウクライナ侵攻に対する対抗措置として対露制裁が発動されるなど、経済制裁の一環という形でも輸出規制が強化されています。このような状況の下、「自由で開かれた経済」を前提に国際分業が進展し、多くの日本企業が構築・発展させてきた国際的な商流やサプライチェーンが経済制裁を含む各国の輸出規制によって影響を受けるリスクがこれまで以上に増大しています。また、輸出規制の違反者に対する当局のサンクションや措置も年々厳格化しており、その観点からも適切な規制遵守の重要性がより一層高まっています。経済産業省貿易管理部に出向した経験を持ち、輸出管理や経済制裁を含む経済安全保障に関わる案件を幅広く担当している大澤弁護士と、NO&Tニューヨーク・オフィスで米国の輸出管理及び制裁法に関わる案件を数多く扱っている伊佐次弁護士は、日頃から協働してリーガルサービスを提供していますが、本対談では、そのような経験も踏まえて、日米輸出規制や近時の実務動向、それらを踏まえた輸出管理体制や取引先管理等について議論します。

M&A・コーポレートを中心に企業法務全般の助言を提供するほか、経済産業省にて外為法等に関わる立案、審査、規制執行、各国との連携強化等に関与した経験を活かして、経済安全保障全般のサポートを行う。近年ではサプライチェーンの分析や強靱化の支援も行う。

日米間のM&A、米国の輸出管理・投資規制・制裁法関連、TMT(Technology, Media and Telecoms)分野の取引・紛争を中心に、現在はニューヨークを拠点として企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

大澤

伊佐次

大澤

伊佐次
また、輸出管理の社内体制を構築する上で、米国法との関係では、違反を認識した場合に速やかにそれを開示するか否かを検討する体制、すなわち、本社において、本社のみならず、グループ会社の違反を検知し、速やかに対応策において検討を進めることができるような内部統制手続を構築することが求められています。例えば、グループ会社がEAR違反に関する可能性を認識した場合、問題となる行為を速やかに特定・把握して、親会社である日本の経営陣に対して報告する権限が与えられているか否かがポイントとなります。

大澤

伊佐次

大澤

伊佐次


大澤

伊佐次

大澤

伊佐次

大澤

伊佐次

大澤

伊佐次



大澤

伊佐次

大澤

伊佐次

大澤

伊佐次

大澤

本対談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。