
鐘ヶ江洋祐 Yosuke Kanegae
パートナー
東京

NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター
本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。
1 FTXトレーディングの破綻
2 本稿で検討する問題
3 国内交換業者の顧客が有する権利
4 米国チャプター・イレブン手続における国内交換業者の資産管理
5 国内交換業者の顧客が米国チャプター・イレブン手続から離脱する手段
6 国内交換業者の顧客による米国チャプター・イレブン手続への参加
7 米国チャプター・イレブン手続に基づく国内交換業者の顧客への弁済
8 国内交換業者に対する日本の民事再生手続申立ての可能性
9 まとめ
暗号資産交換業の大手であるFTXトレーディングは、グループ法人約130社のグループ会社が経営破綻したとして、本年11月11日、米国連邦倒産法11章(いわゆる米国チャプター・イレブン手続)を申請した。
日本ではFTX Japan株式会社(以下「FTXJ」という)が暗号資産交換業者としての登録を受けていわゆる取引所事業を行っており、多数の顧客が暗号資産や法定通貨を預託している。同社については、現時点(2022年11月17日現在)、取引に係る証拠金の出金等を停止しているようであるが、同社の発表によると、預かり資産の分別管理は適切になされているとのことである(11月14日公表資料)。
他方、FTXJに対しては、本年11月10日付で、金融商品取引法及び資金決済法に基づく業務停止命令と業務改善命令に加えて、金融商品取引法56条の3に基づく「資産の国内保有命令」(居住者に対する支払債務に相当する資産を1か月の間、国内で保有すべきという行政処分)が発出されている。
日本に所在する暗号資産交換業者(以下「国内交換業者」という)を含む企業グループが経営危機に陥った事案を前提として、国内交換業者が日本法に基づき適切に分別管理等を行っており、かつ、国内交換業者に対して金融商品取引法に基づく資産の国内保有命令が発令されているという状況の下で、当該企業グループ全体が米国でチャプター・イレブン手続を申し立てた場合に、国内交換業者に暗号資産等を預託する顧客が有する権利はどのように保護されるか。
より具体的には、顧客保護のための分別管理等の義務や上記行政処分により国内に確保されている国内交換業者の資産が米国チャプター・イレブン手続を通じて適切に顧客に弁済されるために、どのような法的論点があり得るか。
なお、実際のFTXトレーディングの事案については、具体的な法律関係や今後の事件処理の方針が公開されておらず、事態も極めて流動的であるため、本稿の検討内容がそのまま適用されることは保証されないという点には十分留意されたい。
検討の前提として、日本では、暗号資産を預託している顧客が暗号資産交換業者に対してもつ権利は、預託している資産の返還を取引所に請求することができる債権的な返還請求権であると説明されることが多い(東京地裁平成27年8月5日判決参照)。
また、日本で事業を行う暗号資産交換業者は、財務状況が悪化した場合でも間違いなく顧客からの返還請求権に応じられるよう、金融商品取引法及び資金決済法に基づき、預かり金を金銭信託の形で管理して(資金決済法63条の11第1項)受益権は顧客が保有するものとされており、また暗号資産は基本的にいわゆるコールドウォレットで管理することとされている(同法63条の11第2項)。
さらに、資金決済法上、顧客の暗号資産返還請求権に優先弁済権を認めるという特別の規定が置かれている(同法63条の19の2第1項)。この優先弁済権は暗号資産交換業者に対する先取特権の一種であると説明されることが多い。
このように、日本法の下で顧客が保有している金銭信託の受益権と、優先弁済権があるとされている顧客の暗号資産返還請求権とが、米国チャプター・イレブン手続においてどのように取り扱われるかが問題となる。
まず、金銭信託については、信託された財産は受託者の名義となり(いわゆる信託の倒産隔離機能)、暗号資産交換業者が米国チャプター・イレブンを申し立てた場合でも、顧客の権利に基本的に影響はないと思われる。
ただし、後述するように、米国チャプター・イレブン手続における広範なオートマティック・ステイの影響を受けて返還請求権の行使が制限されることや、システムの状況等により事実上返還を受けられないことはあり得る。
次に、優先弁済権がある暗号資産返還請求権については、上記東京地裁判決を踏まえれば、あくまで債権的な権利に対して暗号資産から優先的に弁済を受ける権利が付着しているものと解すべきであり、特定の暗号資産に対する直接の引渡請求権が認められるわけではない(顧客が秘密鍵を自ら管理していない場合には顧客の暗号資産が一義的に特定されているわけではない)。
そのため、米国チャプター・イレブン手続との関係では、上記優先弁済権が米国法上そのまま認められるとした場合でも、一旦、暗号資産そのものは倒産財団に組み入れられ、再生計画上、優先的な弁済を受けられるという取扱いとなるおそれがある(暗号資産そのものがどのように弁済されるのか等の問題もある)。
また、そもそも、資金決済法上定められた優先弁済権は世界に先駆けて日本で取り入れられた顧客保護の仕組みであり、米国に同様の制度は存在しないと思われ、米国チャプター・イレブン手続との関係で、日本法が想定するとおりの効力が認められるかどうかについては、米国法上の議論があり得る。
もちろん、検討の前提となる暗号資産交換業者に対して顧客がどのような権利を有するかという点についてすら、米国では様々な議論があるものと思われる。
国内交換業者が米国チャプター・イレブン手続を申し立てた場合、同社の資産管理は誰が行うことになるか。
この点、米国チャプター・イレブン手続は原則としていわゆるDIP型の手続であり、現経営陣が財産管理を含めて経営を継続することになる。ただし、米国では、法的手続に入る前にCorporate Restructuring Officer(CRO)と呼ばれる企業の再建を専門に行う役員が外部から招聘され、倒産手続との関係ではこのCROが権限を行使するという事案も多い。
そのため、国内交換業者について米国チャプター・イレブン手続が申し立てられても、現経営陣(ないしCRO)が財産管理を含めて経営を継続することになるのが通常である。
なお、管理型の民事再生手続における管財人や破産手続の破産管財人が選任される場合とは異なり、日本において米国チャプター・イレブン手続について外国倒産処理手続の承認手続(外国の倒産手続の効力を日本国内に及ぼすための手続)が申請された場合であっても、裁判所による管理命令(外国倒産処理手続の承認援助法32条)が発令されない限り、日本国内における業務及び財産を管理する承認管財人が選任されることはない。
そして、これまでの裁判所の実務では、外国倒産手続が管理型の手続である場合にのみ、その外国管財人(管理人)の権限を日本国内で認めるために管理命令が発令されるという運用であり、米国チャプター・イレブン手続のように、外国倒産手続がいわゆるDIP型の手続である場合には、債権者の権利行使を禁止する強制執行等禁止命令だけが発令されるというのが通例である(NBL1109号36頁(商事法務、2017))。
日本に所在する顧客は、国内交換業者に対して、米国チャプター・イレブン手続とは別に、直接、法定通貨や暗号資産の返還請求ができるか。
この点、米国チャプター・イレブン手続にはオートマティック・ステイの制度があり(連邦倒産法362条)、米国法上は世界中にある資産に対してステイの効果が及び、債権者による個別の権利行使は制限される。しかしながら、日本法の観点からは、日本国内で顧客による担保権実行手続や強制執行等を制限するために、我が国の裁判所(東京地方裁判所の専属管轄である。外国倒産処理手続の承認援助法4条)において外国倒産処理手続の承認決定及び担保権実行手続等中止命令・強制執行等禁止命令(同法22条、27条及び28条)を得ることが必要になる。
とはいえ、米国法上、弁済が禁じられている資産について、国内交換業者がそれを無視して任意に債権者である顧客に弁済をするということは通常期待できない(米国ではいわゆる法廷侮辱罪のような制裁もある)。
そのため、顧客としては、国内交換業者がステイの効果に妨げられずに返還請求権に応じられるよう、米国チャプター・イレブン手続によるステイからの解放を求めることが考えられる(連邦倒産法362条d項)。これは、多くの事例において、担保権者が担保対象資産に対する権利に対する「適切な保護」がないとして、担保権実行を認める場合に利用される手続である。
金銭信託について受益権を有し、また日本法上の優先弁済権が付着した暗号資産返還請求権を有する顧客について、国内交換業者の預かり資産が法令や行政処分に従って適切に確保されている場合に、このようなステイからの解放が認められるかどうかは、米国法上の検討を要する問題である。
顧客が国内交換業者から任意ではなく強制的に弁済を受ける手段として、上記外国倒産手続の承認決定がない場合に、国内交換業者が保有する何らかの資産に対して仮差押え等の保全手続を行うという手段もないわけではない。
ただし、日本法上、仮差押等の保全手続が認められるためには、当該手続をしなければ将来権利を実行することができなくなるおそれ又は実行するのに著しい困難を生ずるおそれ(いわゆる「保全の必要性」。民事保全法23条1項)が要求される。
国内交換業者の預かり資産が法令や行政処分に従って適切に確保されている場合に、このような保全の必要性が認められるかどうかには議論があり得るところである。
上記のような米国チャプター・イレブン手続からの離脱が功を奏しない場合、国内交換業者の顧客は、当該手続に従って権利行使をせざるを得ない。
この場合、国内交換業者に対する顧客が日本国内に所在する日本人であっても、申し立てられた手続が米国連邦倒産法に基づく手続である以上、当該手続に参加するためには米国法に従った債権届出を求められることになる。また、手続が進捗して再生計画案が米国で提出されればこれに対する賛否を投票し、成立した再生計画に基づく弁済を受けることになる。
当然のことながら、これらの手続は米国法に基づき英語で行われるため、日本の顧客にとっては法制度の理解の問題だけでなく言語の問題がある。
米国チャプター・イレブン手続の下で策定される再生計画に基づく弁済がなされる場合、日本国内に所在する国内交換業者の資産は、そのまま(米国に送られることなく)日本に所在する顧客に弁済されることになるか。
米国チャプター・イレブン手続における債権者への弁済方法として、本件のような債権者が多数となる事案の場合には、清算トラストという機関が設立される場合も多い(連邦倒産法524条g項)。
この清算トラストは、米国チャプター・イレブン手続における債権の調査・確定手続を行い、債権者に対する配当を実行する主体となるものである。
そのため、仮に米国チャプター・イレブン手続において清算トラストが利用される場合には、債権者に対する弁済原資はその管理の下に全て移転され、その弁済事務を行う弁護士等により弁済事務が行われることになるように思われる(例えば、麻布建物やタカタのケースでも米国ではこのような清算トラストが設立された)。
他方で、国内交換業者が自ら顧客への弁済を行う場合、日本に所在する資産を米国に移転させないまま、弁済事務を行うことが可能かどうか、米国法上の検討を要する。
仮に、国内交換業者の顧客に対する弁済が、米国チャプター・イレブン手続における清算トラストにより行われるとすれば、日本で保管されている預かり資産についても、米国で設立された清算トラストに引き渡されるという事態も想定される。そうすると、日本で発令された資産の国内保有命令や監督官庁による監督との関係をどのように整理すべきかという問題が生じるように思われる。
なお、暗号資産交換業者の顧客に対する暗号資産の弁済について、日本では、破産手続に至ると顧客の暗号資産返還請求権は金銭化されるが(破産法103条2項)、民事再生手続であれば、暗号資産のままで弁済することに特段の問題はないと解されている(MtGoxのケース参照)。
この点、米国チャプター・イレブン手続においても、暗号資産返還請求権に対して暗号資産のままで弁済することが可能かどうかについては確認を要する点である。もちろん、弁済に際して、どのようなシステムを利用して暗号資産の移転等を行うかという点も実務的には大きな問題となり得る。
仮に、国内交換業者が日本で民事再生手続を申し立てた場合には、顧客の権利はどのように取り扱われることになるか。
日本国内で国内交換業者の預かり資産が法令や行政処分に従って適切に確保されており、顧客の大多数も国内に所在するという場合、日本で民事再生手続に従って法定通貨や暗号資産の返還処理を行うということもあり得るように思われる。
国内交換業者が管理型の民事再生手続を申し立ててこれが開始され管財人が選任されれば、日本に所在する資産は、日本の裁判所から選任される管財人の管理下に置かれることになる。
また、債権者である顧客は、日本の裁判所において日本語で債権届出を行うことになり、国内で裁判所の監督の下で再生計画に基づく弁済を受けることが可能となる。なお、上記のとおり、民事再生手続であれば、暗号資産を暗号資産のままで弁済を受けることに特段の問題はないと解されている。
さらに、この場合、金融商品取引法に基づく資産の国内保有命令との関係や、資金決済法上の暗号資産返還請求権の優先弁済権との関係でも特段の問題は生じないと考えられる。
しかしながら、国内交換業者の預かり資産が法令や行政処分に従って適切に確保されている場合には、そもそも民事再生手続の申立要件が認められるかについて議論があるように思われる。
すなわち、民事再生法は、債権者が手続開始の申立てをする場合には支払不能又は債務超過の事実を生ずるおそれがあることを要求している(民事再生法21条。債務者自身が申立てをする場合には、これに加えて事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できない場合も含まれる)。この点、米国チャプター・イレブン手続の方が、申立要件が広く認められている。
そのため、国内交換業者が資産超過であり資産の確保の状況から支払能力にも問題がなさそうに見える場合に、これらの申立要件(特に債権者である顧客が申し立てる場合には、支払不能又は債務超過の事実を生ずるおそれ)をどのように解すべきか問題となる。
そして、民事再生手続の申立権者は、債務者である国内交換業者と債権者である顧客ではあるが(民事再生法21条)、国内交換業者がグループ企業から離れて意思決定を行うこと(さらにはコントロール権を手放すことになる管理型の民事再生手続を申し立てること)は困難であるとも考えられ、その場合は債権者である顧客が申立てを主導せざるを得ないことになる。
仮に申立て要件が満たされたとしても、同一法人について複数の国で倒産手続が進行する、いわゆる並行倒産の事例については前例に乏しく(マルコーのケース参照)、民事再生法には日本の管財人等と外国管財人等が相互に必要な協力や情報の提供を行なうといった一定の規定(民事再生法207条等)はあるものの、その手続は相当複雑になることが想定される。
もちろん、国内交換業者を米国チャプター・イレブン手続から外して日本の民事再生手続で処理をするという正式な決定がなされれば、このような並行倒産の問題は生じない。
また、グループ企業について異なる国々で法的倒産手続が申し立てられる場合、それぞれの手続のスケジュールや法的取扱いを調和させて進めるという点には、実務上多大な困難が生じるところである(リーマン・ブラザーズやタカタのケースをはじめ、多数の事例がある)。
特に関係会社間の債権債務関係の整理や、スポンサーを得る場合にはスポンサー契約の交渉やスポンサーからの買収対価の受領及び分配方法等に関して、実務上多くの検討課題が生じることになる。
以上のように、国内交換業者に対する日本の民事再生手続申立ての可能性は検討に値するものの、法的な問題点も実務的な課題も数多く生じるように思われる。
一般に、米国チャプター・イレブン手続では、債権者が自らの権利を主張し、債務者がこれに種々対応する中で妥当な結論が導かれるという側面がある。
本件においては、これまで検討したとおり、国内交換業者の顧客の権利保護を図るための確実な方法があるとは言いにくい状況ではある。そのため、様々な課題があるものの、顧客において債権者の立場から自らの権利を主張し、国内交換業者が債務者としてこれに種々対応する中で、顧客の権利保護のための妥当な結論を探るほかないように思われる。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


(2025年10月)
淺野航平(共著)


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


(2025年10月)
伊藤眞(講演録)


(2025年10月)
淺野航平(共著)


(2025年10月)
淺野航平(共著)


斉藤元樹、大島岳(共著)


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
殿村桂司、滝沢由佳(共著)


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年7月)
清水音輝(インタビュー)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(監修)、糸川貴視、大野一行(共著)
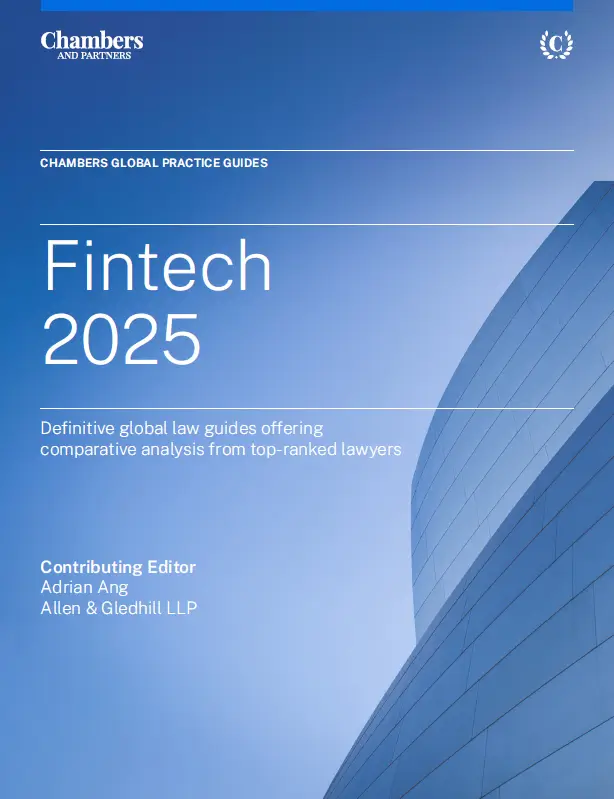
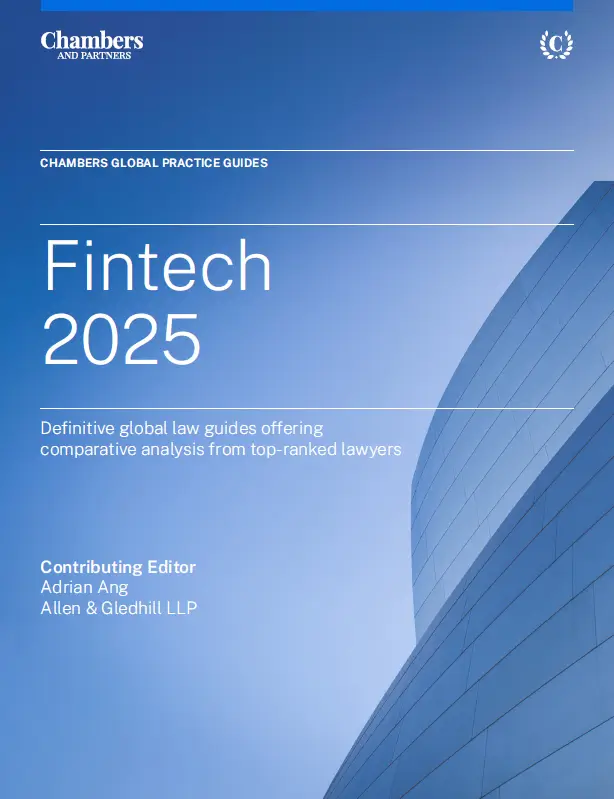
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


工藤靖


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


山本匡


梶原啓


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)


塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)