
佐々木修 Shu Sasaki
パートナー
東京

NO&T FinTech Legal Update FinTechニュースレター
2023年6月1日に施行された「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)(以下「資金決済法」)等が改正され、いわゆるステーブルコインを法制化するものとして、「電子決済手段」が定義されました※1。そして、電子決済手段の1つとして「特定信託受益権」が定められています※2。
ステーブルコインの発行を始め、決済事業への参入に当たっては、収益化の見込みがビジネス上の大きな懸念となり得るところ※3、特定信託受益権においては受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理することが求められている点が特定信託受益権の発行を行う際の支障となり得ます。この点、2024年4月に自由民主党デジタル社会推進本部 web3プロジェクトチームより公表された「web3 ホワイトペーパー 2024 ~新たなテクノロジーが社会基盤となる時代へ~」においても、「web3推進に向けてただちに対処すべき論点」の一つとして、「パーミッションレス型ステーブルコインの流通促進のための措置」についての検討がなされており、この論点に関する提言の一つとして、特定信託受益権について、「国債の組入れを認めることによるプラスの側面(事業継続性(収益性)の向上、裏付資産としての安全性の向上)とマイナスの側面(国債については価格変動や流動性のリスクがあること)の両方の観点を踏まえ、その是非について検討を進めることが望ましい。」※4との提言がなされています。
国債を組み入れた特定信託受益権を認めることは、ステーブルコインの流通促進の1つの有効な方策になるものと考えられますが、他方でその実現に当たっては、現行法の改正が必要となります。そこで、本ニュースレターでは、特定信託受益権に係る現行制度の概要を説明した上で、国債を組み入れた特定信託受益権の実現に当たって、今後、注視すべき論点についてその一部を指摘するに留まりますが、検討してみたいと思います。
「特定信託受益権」は電子決済手段の一つとして定められているところ、電子決済手段の発行・償還は、基本的には、「為替取引」に該当し、銀行業免許又は資金移動業登録が求められると解されていますが※5 、特定信託受益権を発行する信託会社については、銀行業免許及び資金移動業登録を受けずに、特定資金移動業※6を営むことができるとされています※7。
特定信託受益権の具体的な内容は、大要以下のとおりです※8。
そして、特定信託受益権に該当するもので「有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの」は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(以下「金商法」)上の「有価証券」から除外されています※9。現時点の政令・内閣府令の規定を前提とすると、特定信託受益権に該当するものはいずれも「有価証券」に該当しません※10。したがって、特定信託受益権を発行するに当たって、金商法上の開示規制は適用されず、特定信託受益権の売買といった仲介行為それ自体には、金融商品取引業の登録は必要ありません。
以上の現行制度を踏まえますと、国債を組み入れた特定信託受益権の実現に当たっては、少なくとも以下のような論点があると考えられます。
上記①②のとおり、特定信託受益権においては受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理することが求められ、これは法律上の要件となっているため、現行の資金決済法を前提とすると特定信託受益権の信託財産に国債を組み入れることはできません。
そのため、国債を組み入れた特定信託受益権の実現に当たっては、資金決済法及び電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の改正により、特定信託受益権の信託財産として国債をどの程度組み入れることが認められるか(又は上限なく組み入れることが認められるか)、また、国債の他に例えば地方債や政府保証債の組入れが認められるか、等の論点に注視する必要があります。
この点、受託者が引き受けた信託財産をどのように管理するかという点は、特定信託受益権としてのステーブルコインの保有者の償還請求権がどのように保護されるかという点と関連するところ、現行制度上、上記①②のとおり、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を要求払い預金により管理することという要件(以下「要求払い預金管理要件」)が設けられているのは、これまで送金・決済手段として機能してきており、為替取引を行うことができる銀行又は資金移動業者が発行する預金や未達債務を用いたデジタルマネーと同程度に利用者保護を実現することが意識されたものと思われます※11。すなわち、銀行法上の健全性基準や預金保険法上の預金保険により保護される預金を用いた銀行発行のデジタルマネーや供託等の資金決済法上の資産保全義務により保護される未達債務を用いた資金移動業者発行のデジタルマネーと同程度に、利用者の償還請求権の保護を実現するため、特定信託受益権に当たっては、信託契約により受け入れた金銭の全額について要求払い預金管理要件が求められたものと考えられます。
ここで、国債には要求払い性が認められないことから、国債を組み入れた特定信託受益権については流動性リスクが利用者の償還請求権に影響を及ぼすおそれがあります。また、国債には価格変動リスクがある点も要求払い預金とは差異があると考えられます。もっとも、国債は、債務不履行の懸念がないと一般に考えられており、この点からは、要求払い預金よりも安全な資産という評価も可能です。このような評価は、資金決済法上、国債を履行保証金に充てる場合や履行保証金信託契約において国債を信託財産とする場合に、国債の評価がいずれも掛け目なしとなっており、額面金額(履行保証金の場合)又は時価(履行保証金信託契約の場合)の全額を算入できるようになっていることとも整合します※12。他方で、地方債や政府保証債については、掛け目が設定されておりその全額を算入することはできないこととなっており、国債とは異なる取扱いがなされる可能性があります※13。
次に、国債を組み入れた特定信託受益権が、現行の特定信託受益権と異なり、金商法上の「有価証券」から除外されないとすると、原則として、金商法上の開示規制・業規制が及ぶため、事業者の規制・行政手続コストが増加し、事業継続の難易度が上昇します。そのため、国債を組み入れた特定信託受益権が金商法上の「有価証券」から除外されるか等の金商法上の取扱いに注視する必要があります。
この点、資金決済WG報告書24頁・25頁では、「資金決済法において信託財産の全額を円建ての要求払預金で管理することを前提とする等の必要な利用者保護措置がとられること、また、こうした措置により、信用リスク、金利リスク、流動性リスク、為替リスクといったリスクも最小化・明確化され、そうした仕組みも明らかにされること等を前提とすると、投資判断に有益な情報を提供するという金融商品取引法上の開示規制や、投資者保護・資本市場の健全性確保のための諸規制を適用しないこととする制度改正を行うことが考えられる。」という説明がなされており、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を要求払い預金により管理するものであることが、特定信託受益権が「有価証券」から除外されていることの理由の一つになっているように思われます。
他方で、国債は上記「1.資金決済法関係の論点」に記載のとおり、要求払い預金よりも安全な資産という評価も可能であると思われます。また、国債については金商法上の開示規制は適用されないこととなっています※14。これらの事情も踏まえて、国債を組み入れた特定信託受益権についても金商法上の開示規制の対象とされるか、また、金商法上の「有価証券」から除外されるかどうかの検討がなされるものと考えられます。
以上のとおり、本ニュースレターでは国債を組み入れた特定信託受益権の実現のための法的論点について、検討しました※15。以上が、国債を組み入れた特定信託受益権を活用した決済事業の早期の実現に当たっての検討の一助となれば幸いです。
※1
資金決済法第2条第5項
※2
資金決済法第2条第5項第3号・同条第9項
※3
資金移動業の登録申請に当たっても、収支の見通しが審査の留意事項に含まれています(資金決済法第40条第1項第3号・事務ガイドライン「第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係 Ⅸ-2-1(2)④ハ」)。
※4
自由民主党デジタル社会推進本部 web3プロジェクトチーム「web3 ホワイトペーパー 2024 ~新たなテクノロジーが社会基盤となる時代へ~」15頁(2024年)
※5
金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」報告書(2022年1月11日)(以下「資金決済WG報告書」)22頁
※6
「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいい(資金決済法第36条の2第4項)、「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいいます(資金決済法第2条第28項)。
※7
資金決済法第37条の2第1項
※8
資金決済法第2条第9項・電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第3条
※9
金商法第2条第2項柱書き・同項第1号・金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の2第1号・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第4条の2
※10
大野一行・高橋俊介「ステーブルコインを巡る近時の法改正-特定信託受益権に関する制度を中心に」信託フォーラム Vol. 21, 38頁(2024)
※11
資金決済WG報告書23頁でも、利用者保護の要請を満たすステーブルコインを実現する仕組みとして、銀行に対する預金債権や資金移動業者の未達債務と並べて、銀行に対する要求払預金を信託財産とした信託受益権が挙げられています。
※12
資金決済法第43条第3項・資金移動業者に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)(以下「移動業府令」)第13条第1項第1号、資金決済法第45条第3項・移動業府令第21条第1号
※13
資金決済法第43条第3項・移動業府令第13条第1項第2号・第3号、資金決済法第45条第3項・移動業府令第21条第2号・第3号
※14
金商法第3条第1号。地方債、政府保証債も同様(金商法第3条第1号、第4号)。
※15
法務の他にも、会計・税務の観点からの検討についても留意する必要があると思われます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


武蔵野大学出版会 (2025年9月)
井上聡(講演録)


金融財政事情研究会 (2025年9月)
長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)


(2025年10月)
堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)


有斐閣 (2025年10月)
宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


工藤靖


(2025年6月)
吉良宣哉


(2025年5月)
大下慶太郎


(2025年8月)
月岡崇、大野一行(共著)


(2025年8月)
井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)


(2025年5月)
井上聡、大野一行(座談会)


(2025年4月)
松本岳人


(2025年10月)
三笘裕、江坂仁志(共著)


(2025年10月)
関口朋宏(共著)


弘文堂 (2025年9月)
佐藤巴南(共著)


(2025年10月)
犬飼貴之


(2025年7月)
清水音輝(インタビュー)


(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(監修)、糸川貴視、大野一行(共著)
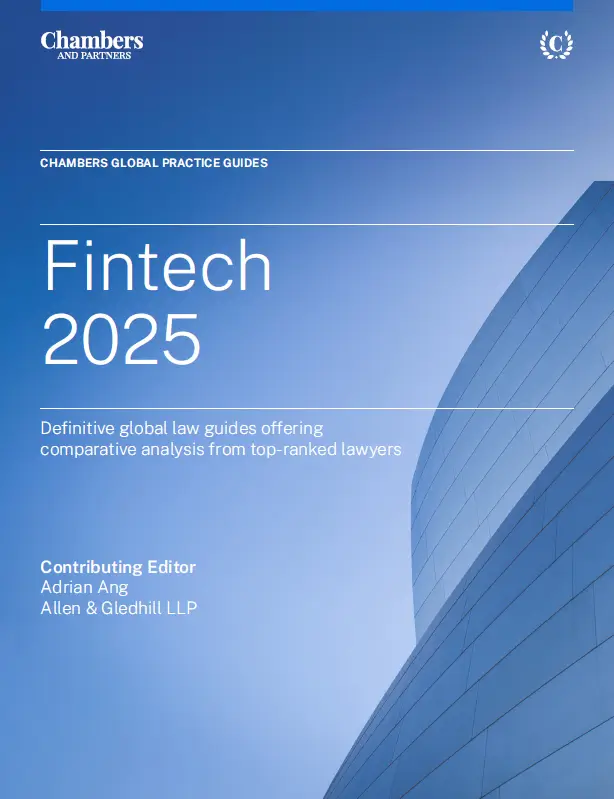
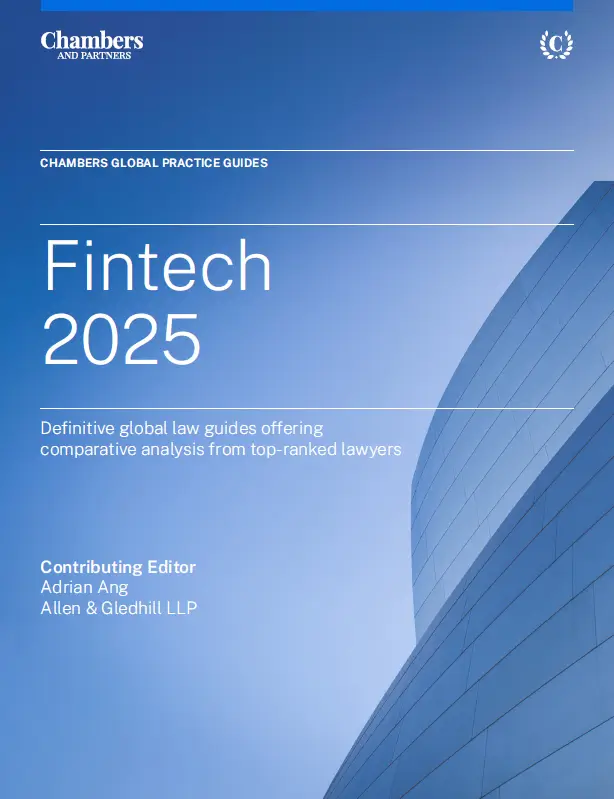
(2025年4月)
殿村桂司、佐々木修、大野一行、清水音輝(共著)


木村聡輔、斉藤元樹、糸川貴視、水越恭平、宮下優一、北川貴広(共著)